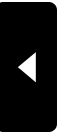特集
ワークの掟【その3】〜社会の仕組みを知って、ブラックを回避せよ〜
私たちが将来、生きがいをもって働くために今しっておきたい社会のルール。デキる社会人の常識、嗜み、後輩への助言(警告を含む)を先取りで学んでいく〈ワークの掟〉シリーズ第3弾です。今回は、一般社団法人ワークルールの理事をつとめている由比藤準治さんに、”ワークルールで見抜く社会の仕組み”を教えてもらいました。「この職場で良かった」と心から思える環境で働くための早道は、自分をとりまく社会や企業の仕組みを知っておくこと。現在、ブラックと言われる企業が表面化してきましたが、その外的要因とは何か、またブラック企業を回避するためには自分がどんな知識をもっていればいいか? 私たちに必要な、社会的モラルも学べます!
(前回記事「ワークルール史の分岐点を探せ!」)→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1474215.html

■由比藤準治(ゆいとうじゅんじ)さん〈写真:左〉
一般社団法人ワークルール理事。
手にもつ「青い本」は、労働法をわかりやすく解説した内容が掲載されている冊子「知っておきたい ワークル—ルの基礎知識」。
10万部発行しており、セミナーや高校や大学などの教育機関で入手することができる。
[聞き手]
■山口奈那子(やまぐちななこ) 〈写真:右〉
常葉大学外国語学部4年。6月1日に発行された静岡時代【最新号】、6月号(vol.39)の編集長。
本人は現在就職活動中!
---------------------------------------
【一般社団法人ワークルール】
2014年4月1日設立。
大学生、専門・専修学校生、高校生などの若者に対し、
社会で働く上で必要な、ワークルールの基礎、多様な働き方の情報を身につける機会を提供している。
県内外問わず、大学、高校生を対象にワークルールの出張講座も開講。
また、労働法がわかりやすく解説した冊子『知っておきたい ワークルールの基礎知識』(通称:青い本)は、現在静岡県版と全国版が発行されている。キャリア支援関係者の他、大学・高校生のあいだで好評を得ている。
http://www.workrule.jp

■「企業は人なり」は変わったのか?
(静岡時代)優良企業やブラック企業はどのように判断できるのですか?
(由比藤さん)「企業は人なり」と言うように、企業の善し悪しの判断基準は、人を大事にしてくれるかどうかだと思います。
リーマンショック以降、企業は余裕をもった採用を控えるようになり、最小限の社員で仕事を回すところが増えました。その結果、一人の社員にかかる負担が多くなり、ブラックと言われるような長時間労働も増えてしまったんですね。
とはいえ、今はネットで見るようにブラック企業が多いのかというと、そうとも言い切れません。残業代を全く支払わないような悪質なケースばかりがニュースで報道されるので誤解を招きがちです。でも、過労死に繋がるような働き方をさせる100%ブラックな会社はごく一部で、いわばグレーといった会社が多いのかもしれません。
静岡労働局の調査によると昨年度、静岡県内を調査した結果、なんらかの労働法違反のあった会社は約6割でした。ただし、この6割の違反の中には、単なる書類ミスなど、直接労働者に関係ないものも含むので、違反=ブラックと決めつけないほうが良いと思います。もちろん法違反はダメなんですが。

(静岡時代)回避するポイントとは?
(由比藤さん) 押さえたいポイントは三つです。一つは、自分がどういう労働条件で働くのかをきちんと確認することです。例えば、求人票に書かれている給料には、残業時間の30〜40時間分が既に入っていることがあります。
二つ目は、離職者数や離職状況を確認することです。今年から大卒向けのハローワーク関連の求人には、過去3年の離職者数を明記することが義務付けられました。離職率の場合、一人が入社して一人辞めたら100%になるので、離職率よりも離職者数や離職状況を把握することが重要です。辞めた理由までは記載されないので真相は分かりませんが、人の定着率が悪い会社は気を付けたほうがいいですね。
三つ目は、相談できる場をもっておくことです。キャリアセンターや家族、社会経験のある人に聞くと、解決も早いでしょう。そして職場の環境を知るには、インターンシップやOB・OG訪問など本音で語り合える場が一番です。説明会で人事の人に、いきなり有給休暇や残業時間数などは聞きにくいと思いますし、実際会社に入ってみなければ分からない部分が多いですから。
働くときの決まり(ワークルール)を知っていれば単なる情報も自分を守るための判断材料になる。労働法令に関わる仕事に約25年携わった由比藤準治さんによると(※ 過去7回の転職経験有)残業代を全く支払わないような悪質な違反を除けば、ブラック企業の定義は人により異なるそうです。ブラック企業回避のためにはどうすればいいか。そのポイントを3つ、ご紹介!
一、
会社のルールは事前に確認することが大切です。お金にかかわることなどトラブルになりやすい内容は書面(労働条件通知書など)で確認することが大事です。
二、
離職率には自己都合で辞めている場合もあり内容まで把握できません。「毎年5人入社して5人が辞める」など離職者数や離職状況を把握する方が現実的。年齢が異常に若い会社は人の定着率が悪い可能性あり。社員構成も確認!
三、
一人で悩んでいても解決はできません。友人やOB・OG・会社の先輩など身近な人、またはキャリアセンター・行政機関などに相談することもできます。早く相談すればするほど、問題解決への早道となります。

■職に就いたのか、会社に就いたのか
ブラック回避といっても、何がブラックなのかは人によって違います。自分の将来のビジョンと働き方がうまくマッチングできれば、もし労働時間が長く、みんなからブラック企業だと思われていても、本人にとっては優良企業なのかもしれません。
今の時代は「就職」ではなく「就社」の風潮があり、いかに大手企業に就職できるかが重要視される時代です。大切なのは、会社の規模・名前にこだわらず、たとえ無名な中小企業でも自分がしたい働き方を選ぶことです。また、自分にまだ経験や技術がないのに、権利ばかりを主張するだけの社会人はどうでしょうか? 私が社会人になった頃、上司から「給料の3倍、いや5倍稼いでこそ一人前」と言われましたが、今ならその言葉も納得できます。自分自身が会社に貢献せず権利だけ主張するのは、ただのワガママです。企業から見れば「ブラック社員」と言われるかもしれません。
ワークルールは一生ものです。働くということは人間にとって切り離せるものではなく、気持ちよく働けないのは非常に不幸なことです。自分が気持ちよく働くためにも、常に変わりゆくワークルールを自分で押さえていくことが大切です。(取材・文/山口奈那子)
〈ワークの掟〉シリーズ記事
(2)ワークルール史の分岐点を探せ!:http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1474215.html
Updated:2015年06月12日
"大学モラトリアム"の歴史とは?〜モラトリアムの男脳、女脳〜【2/4】
たとえば、モラトリアムが「羽化過程のサナギの時代」だとすれば、大学は「繭」といえるのかもしれない。
では、静岡県の大学の「繭」はどのようにかたちづくられたのだろう。昔も今もかわらず、大学時代はモラトリアムでありつづけるのだろうか。歴史学を専門とする静岡英和学院大学の小和田美智子先生に、静岡県の大学の歴史を通して、モラトリアム時代の学生像を紐解いてもらった。

■小和田美智子(おわだみちこ)先生〈写真:左〉
静岡英和学院大学 非常勤講師。専門は日本史。静岡の歴史とその変化、地域とのつながりや現代の男女関係を扱う。暗記科目と思われがちな歴史だが「考える
こと」を通して学べる授業を展開されている。
[聞き手]
■木下莉那(きしたりな)〈写真:右〉
静岡英和学院大学4年(取材当時)。本誌編集長。
大学卒業後、現在は就職先の東京で新しいスタートを切っています。
■澤村優妃(さわむらゆうひ)
静岡大学3年。本記事の執筆担当。

◉いつの時代も学生はモラトリアム真っただ中
(静岡時代)大学のあり方が変わるとともにモラトリアムも変化してきたのでしょうか?静岡県に大学が生まれた歴史的な経緯を教えてください。
(小和田先生)まず静岡県には、現在の大学の前身となった「静岡学問所」という学校があったんですよ。明治のはじめ、江戸幕府崩壊後に駿府に移封された徳川氏を藩主とする駿府藩が、藩の建て直しや人材育成を意図して開設しました。徳川氏の駿府移封とともに、旧幕府の教育機関に所属していた学者も駿府に移住し、旧幕府の蔵書も移されました。
つまり、全国から集めた優秀な学者や文献が、江戸から静岡にやってきたんです。徳川の時代に脈々と受け継いできた知識が静岡に集結し、そこでは、望めばどんな人でも学ぶことができました。国内最高水準の教育が静岡県で展開されたんです。すごいでしょう!
でも、明治5年の学制頒布によって、教授・学生は後にできた東京大学に引き抜かれてしまったから、結局静岡学問所は廃退してしまいました。ちなみに、学問所にあった江戸幕府の旧蔵書は現在「葵文庫」と呼ばれて静岡県立中央図書館に保管されています。
▲静岡大学に建つ〈静岡学問所〉跡の石碑。
▲国学の他にも、伊、仏、独などの洋学も教授されていた。明治時代、文明開化のさきがけとなる学び舎でした。
(静岡時代)大学の基礎となる学問所が静岡に存在したなんて驚きです。時代も背負っているものも違うとは思いますが、約150年も前の学生にもモラトリアムはあったのでしょうか?
(小和田先生)どうかしら?当時は分からないけれど、少なくともモラトリアムという言葉は、私の学生時代にはなかったんです。とはいえ、私が大学生の頃は学生運動が盛んな時代で、みんなでよく意見を出し合って真剣な話し合いをしていました。サークル活動でも人生について考える機会は頻繁にありましたね。だから、「モラトリアム」という言葉はなかっただけで、当時の学生も同じだと思います。
私も本当にたくさん悩んで挫けて、それでも挑戦しました。当時、女性が大学に通うことは今のように当たり前ではなかったし、戦後だったから、金銭的な問題も大きかった。なんとか両親を説得して行かせてもらっていましたし、必死でしたよ。

(静岡時代)確かに学生運動はモラトリアムです。でも今はありません。なぜでしょうか?
(小和田先生)静岡の学生に限らず学生全体に言えることですが、「考える」ことをしなくなってきていると思います。なぜなら大学の制度が変わったからです。昔は、大学受験は試験が二回行われていて、一期校がだめだったら二期校、というようにチャンスが二回ありました。それが共通一次試験になり、今では全国統一のセンター試験一本に絞られた結果、どれだけ考えられるかよりも、どれだけ良い点が取れるかで比べられてしまいます。いろんな知識が暗記になって、考えさせる問題が少なくなりました。でも、はっきりと伝えておきたいのは、それがモラトリアムにおいても重要な「考える力」を低下させてしまうことです。歴史だって暗記ではないですよ。これは声を大にしていいたいです。そもそもなぜ歴史を勉強すると思いますか?
(静岡時代)過去を知ってこれからの未来に活かすため、ですかね。
(小和田先生)そう。今、自分たちが生きている世の中を知るために、歴史の中から事象と、そこに関わった人の「考え方」を学ぶ必要があるんです。そもそも大学はこういうことを学ぶ場でなくてはならないと思うけど、今はそこも変わってきていると感じます。「何年に何があって、誰がどんな政治をした」ではなく「何故そうしたか、なぜそう考えたのか、誰が関わってどんな過程を経て、その結果になったのか」を知ることが重要です。
大学は能動的に自由に、自分の望むことを学ぶ場です。そういう意味で、サークル活動などはみんなで意見を出したり、考えたりする良い機会だけど、今はそうやって友達同士で意見を出し合うことって少ないでしょう?

(静岡時代)大学だけでなく、学外や家でもほとんどないですね。だから、将来や自分について、一人で悩んでしまう人もいれば、逆に全く考えない人もいます。
(小和田先生)原因は少子化だと思います。一人の子供に対する親や周りの大人の数が増えましたよね。昔は兄弟も多いから、自分から主張しないとほとんど何も実現しなかったし、なんでも一人で考えていたものです。
私自身、5人兄弟の末っ子だったので、上の人たちの様子をみて、先まわりして危険が及ばないようにし、生きる力が知らず知らず身についていたんです。逆に、今は大切にされすぎて、自分から何かを発信しようとする子がいなくなっている気がします。
モラトリアムの時期に悩んで、親との対立を経験する子は将来困らないと思いますよ。なぜなら、衝突の中で次を、次をと考えて主張するからです。その親に認められたり、理解されようと必死になる経験は、社会に適応するために必要な力になるでしょう。
(静岡時代)親との対決、私もしました!では大学というモラトリアムは、今後どのような場になっていくのでしょうか?
(小和田先生)大学は自分自身の人間性を深める場です。では、どう深めるかだけど、一つは「恋愛」です。みんな恋愛してるでしょう?恋愛は自分を見つめる意味でも良い経験になります。相手の理想に応えるために自分を抑えて苦しくなったりしてね。自分が大きく変わるタイミングになりやすいと思うし、私はそうでした。私の場合、結婚しても続けられる教師を進路に選んだから、特に社会に出ることに対して壁はなかったの。仕事を続け、男性との関係も、いい関係とはどうあるべきか、など考えました。

少し話は逸れるけど、どの大学でも学生全体に目を向けると、男性と女性が持つ気質はかなり違うんです。面白いですよ。男性は、アンテナがいろいろなところに張られているけど、女性は一つのことしか見れない。あちこちに意識を飛ばして、一見すると不真面目に思える男性は、実は多面的に物事を捉えているんです。生きていくうえで大切な力ですよね。一方、女性はこれと決めたら一点集中型だから、授業中もノートを写すことに夢中になりがちです。真面目には見えるけど、学びとしてはプラスαが中々ないんですね。だから成績は女性の方がいい気がするけど、全体を見た時に、やはり男性の方が視野が広いところはあると思います。両方の側面が重要だから、やっぱり恋愛も大事よね。
本当の自分を見つけるために、勉強して恋愛して、社会にふれて困難を乗り越えていく。一見無駄なように思える4年間だけど、人間的に成長できる貴重な時間、それがモラトリアムです。それは今も昔も、これからも変わらないでしょう(了)(取材・文/澤村優妃)
・小和田美智子 .『 地域と女性の社会史̶駿遠地方を中心に』. 岩田書院. 2012
モラトリアムの男脳、女脳シリーズ
Updated:2015年06月04日
モラトリアムって一体なんだ? 〜モラトリアムの男脳、女脳(1)〜
多くの学生にとって大学は、学生であることを許された最後の猶予期間だ。少なくとも社会に出る前よりは、社会的(責任)にも経済的にも追われることはない。しかし将来や人間関係など、大学生がもがき迷うときは大学生活中に何度も訪れる。その時期を、"モラトリアム"と言われることがあるけれど、そもそも私たち大学生を悩ませるモラトリアムとは一体何なのだろうか? また、大学で同じようにモラトリアム時期を過ごす大学生の男女に違いはあるのか。今回は、静岡大学で近代文学を専門とする酒井英行先生に、モラトリアムの歴史と概念を伺いました。

■酒井英行(さかいひでゆき)先生 /〈写真:右〉
静岡大学人文社会科学部言語文化学科 教授。
専門は日本近代文学。主に夏目漱石、内田百閒、村上春樹など。高校生の頃、加山雄三に強い憧れを抱いていたそう。
研究室には文学作品について議論した学生との対談本が置かれている。学生に愛される優しい先生。
[聞き手]
■木下莉那(きしたりな)/ 〈写真:中央〉
静岡英和学院大学4年(取材当時)。現在は同大学を卒業し、就職先の東京で新しいスタートを切りました。
■漆畑友紀(うるしばたゆき)/ 〈写真:左〉
静岡英和学院大学2年(取材当時)。本記事の取材・執筆を担当。

▲研究室の書棚には、先生の専門である村上春樹、夏名漱石ほか、関連書籍や資料がぎっしり置かれていました。
◉文学作品の数だけ、モラトリアムがある
(静岡時代)モラトリアムはいつ、どのように生まれた概念なのでしょうか?文学ではどのように扱われてきましたか?
(酒井先生)モラトリアムとは、大人でも子どもでもない、いわゆる青年期のことを言います。
一般的に14歳、15歳から大学を卒業するまでの間とされ、社会に出ることや大人になることを待ってもらっている猶予期間のことです。
「モラトリアム」という言葉が当たり前に使われるようになったのはこの数十年のことです。
文学の中で、作中で「モラトリアム」という言葉そのものを扱った作品は知りません。ですが、青年を主人公にした作品は、青年期特有の葛藤や成長が描かれていることが多いです。例えば、村上春樹の『ノルウェイの森』は、要約するならば、青年が自分が何者であるかを知るために、旅をしている物語です。まさにモラトリアムですよね。
面白いのは、作家または作家になろうと思う人自身が「モラトリアム人間」だということです。一般的には大学を卒業したら職に就くことになりますが、作家を目指す人は、職に就かず部屋に閉じこもって、小説を書いています。夏目漱石は明治の男でしたから、大学卒業後に職に就きましたが、村上春樹は会社で働いてはいないでしょう。基本的に「作家」という人間は「社会に出たくない」という思いから小説家になるのだと思います。つまり、作家自身が「モラトリアム人間」なのだから、作中で描かれる登場人物も基本的には「モラトリアム人間」になります。
(静岡時代)だとすれば文学作品の数だけモラトリアムがあるのですね。具体的にどのように描かれているのでしょうか?
(酒井先生)明治時代に出版された夏目漱石の小説はまさにそうです。漱石は『それから』『彼岸過迄』など自身の小説の中で、「遊民」、「高等遊民」という言葉を用いています。遊民は「遊ぶ民」。本来ならば働かなければならないのに、遊んでいるように見えることからそう呼ばれています。これってモラトリアムですよね?
明治42年に書かれた漱石の小説『それから』を例に挙げましょう。当時の日本では、大学卒業者は大変なエリートでした。主人公の代助は裕福な家の出で、東京帝国大学を卒業しました。にもかかわらず、一軒家を借りて、親から仕送りをもらいながら、働かず好きに生きている青年です。ちなみに、『こゝろ』の主人公「私」も、大学を卒業しても職につかず、父親に嘘をついてまでして働こうとしません。そういう青年を漱石は、大正3年に書いています。だから今に始まったことじゃないんです。自分が何者か、何のために生きているか解決できていないという問題が、時代の背景と共に小説で表現されていることがわかりますよね。

◉「自分」という世界でただ一人の存在との対決
(静岡時代)今も昔も自分が何者であるかという問いかけは、避けては通れないのですね。でもそんな大きな問題、答えは見つかるのでしょうか……?
(酒井先生)自分が何者であるかという問いかけの答えは、大学四年間で解決できる問題とは思えませんよね。大学時代は人生最大のモラトリアム期間だと言われます。今までの中学と高校は決められたレールの上を走っている状態です。自分が何者で、何のために生きているのかを考える暇さえありません。
人は青年期に入っていくと、突如「自分」という世界でただ一人の存在に気付くことになります。思春期における「自我の目覚め」です。その時に自分は一体何者で、何のために生まれてきたのかという根本的な問いにぶつかります。それをモラトリアムの期間に解決しなければならないのは、就職活動よりも大仕事ですよね。そのことをアメリカの有名なエリクソン.E.Hは、自我同一性、つまりアイデンティティの確立として提唱しました。
また『青年期の心』という本には、モラトリアム期間に二つの側面を解決しなければならないと書かれています。一つは「現在の自分と過去の自分を有機的な連続性をもった同一のものとして受け入れることができ、しかもそれが未来に向かって開かれた存在として、現在いきいきと生きている実感があるという実存的な感覚」。もう一つは「自分と自分の所属する社会との間に内的な一体感があって、社会から受け入れられているという感覚」。
これを「社会的同一性」と言います。これらを上手く統合することで、自分のアイデンティティを確立することができます。これがエリクソンの言うモラトリアム期間の重要な仕事なのです。つまり「私は私」といった思い込みだけでは、満足なアイデンティティは得られないという訳です。

(静岡時代)具体的にどうしたらいいのでしょうか?何もせずに素通りしたらどうなるのでしょうか?
(酒井先生)例えるなら、恋愛が一番わかりやすいのではないでしょうか。一概には言えませんが、一人の異性として自分以外の他者に受け入れられることは、社会に受け入れられることと似たようなものです。自分を受け入れてもらうために、自分と向き合い葛藤することで、自分を鍛えられると思いますよ。
私は高校の頃、ある女性に一目惚れしてね、振り向いてもらうにはどうしようかと思った時、音楽・スポーツの才能も顔もスタイルも抜群な加山雄三が目に入ったんですよ。自分が彼に勝てるものを見つけられれば、自分の存在が見出せるのではないかと思って大変悩みましたね。そうして「人間性を磨こう」という結論に至って、大学ではそのおかげで割とモテましたよ。

▲〈さかじい〉の愛称で親しまれている酒井先生。現在も変わらず、学生から非常に人気のある先生です。
自分のアイデンティティについて悩むのは今も昔も変わりません。私が学生だった頃は、大学の進学率が十数%だった時代です。でもその中にいる私は、何をしようという具体的な目標はなく「東京に行きたい」「大学に行けばどうにかなるだろう」という漠然とした考えで進学しました。大学へ入った理由が分からなくなり、大学を辞めてしまう人も沢山見ました。ただ、今より当時の学生の方がアイデンティティについて悩んでいたと思います。
傷ついたり、悩んだりせずにそこを通過してしまったら、後々とても大変なことになると思います。そこが上手くいかなければ、社会に適応できない人間になってしまいます。深く考えずに妥協して社会に出たものの、就職してすぐに挫折をして会社を辞めてしまうのはそこに起因しているのでしょう。なかには、自分で自分が分からなくなり、傷つき、心が壊れてしまう人も多くいます。それだけ大変な期間を学生は通るのです。自分が何者で何をすべきなのかを考えることは、いわゆる私達に課せられた宿題のようなものですからね。傷ついても恐れずに悩むことが大事です(了)
(取材・文/漆畑友紀)
・村上春樹.『ノルウェイの森』. 講談社. 2004.
・福島章.『 青年期の心』.講談社. 1992
Updated:2015年05月29日
ワークの掟【その2】〜ワークルール史の分岐点を探せ!〜
デキる社会人の常識、嗜み、後輩への助言(警告)、愛され社会人になるメソッドなど、私の「働きたい」をもっと大事にできる『ワークの掟』シリーズ。第二弾は、静岡大学 人文社会科学部法学科の本庄淳志先生に、”経済から紐解くワークルールの歴史”を伺いました。「もしも経済が右肩上がりだったら、ワークルールは△△になる」。実は、ワークルールは経済や社会の移り変わりと密接に連動しているようです。産業革命期から現代までの約100年余り、ワークルールはどのように変わってきたのでしょうか?(文中、ピンク字表記はワークルールを考える上での要チェックポイント)歴史の知恵には、実は社会の荒波を生きるヒントが隠されていました!!
◉前回記事/「先輩に学ぶルールの必要性」→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1474140.html
■本庄淳志(ほんじょうあつし)先生 〈写真:左〉
静岡大学 人文社会科学部法学科准教授。専門は労働法。また一般社団法人ワークルール代表もつとめています。
写真内、本庄先生と学生がもっている冊子は『知っておきたい ワークルールの基礎知識』(通称:青い本)。
本庄先生のゼミ生が制作協力しており、労働法や保険制度についてわかりやすい解説が特徴で、キャリア支援関係者の他、大学・高校生のあいだで好評を得ている。
[聞き手]
■三好景子(三好景子) 〈写真:右〉
静岡大学 教育学部美術専修3年(取材当時)。
就活も無事に終わり、現在は卒制・展示にむけて邁進中!!
【一般社団法人ワークルール】
2014年4月1日設立。
大学生、専門・専修学校生、高校生などの若者に対し、
社会で働く上で必要な、ワークルールの基礎、多様な働き方の情報を身につける機会を提供している。
県内外問わず、大学、高校生を対象にワークルールの出張講座も開講。
http://www.workrule.jp
http://www.rengo-shizuoka.jp/mate/event/#event
2015年5月から、静岡県、東・中・西部の各地域で、ワークルールの基礎講座を開講。社会人の方も参加可能です。
講座の詳細は、上記URLよりご確認ください。
■ワークルールのはじまりは、産業革命にあり。
(静岡時代)ワークルールの発祥は?
(本庄先生)一般的には一八八〇年代の産業革命以来と言われています。農業社会から工業社会へと社会構造が変化したことにより、資産や土地を持たず、都市部に出て働く人が大量に出てきた時期です。はじめは女性や年少者を対象に始まりました。当時は戦争を前提としていましたから、国の競争力を下げることが問題とされたんです。例えば女性が働きすぎて身体を壊してしまうと次の世代が産まれません。戦後、一般の労働者へ拡大していきました。
今でこそ男女同じ基準でワークルールが整備されていますが、当初は女性は特別に保護するものでした。工業社会からサービス社会へと変わり、深夜に働いても長時間働いてもそれほど大変ではない・女性の社会進出という働き方や社会構造が変わるにつれて、男女同じ基準であることが重要視されるようになりました。産業構造の変化もワークルールの変化に関係しているんです。
(静岡時代)経済や社会の移り変わりによってワークルールはどのように変わってきたのでしょう?
(本庄先生)分岐点として大きいのは政権交代です。でもそれだけではなく、例えば少子高齢化の問題はどこの政党が与党になろうとも避けられないものですよね。今後少なくとも二〇年は想定されている問題です。長期的なスパンの問題を想定し、どのようなワークルールが必要とされるかを考えます。また現在、短期的なことで問題とされているのは労働時間です。働き方が多様化し、美術家など高度の専門知識や経験がある人に関しては時間の規制はあまり意味がないのではないかと。そうした人を対象に労働時間の規制を外していくことも議論になります。ワークルールの変わる背景はその時々のニーズによっても違いますので一概には言えません。政治的な事情で変わることもありますし、長らく懸案されているような問題もある。
さらに今は「賃金が少なくても良いから短時間で働きたい」という人もいれば、「長時間でも構わないからたくさん稼ぎたい」という人もいるように、働き方が多様化している時代です。常にワークルールもアップデートされ、非常に複雑になっています。同時に基本ルールを知らないままに紛争が増えてきている傾向もあるので、それは問題ですよね。
(静岡時代)どういうことでしょうか?
(本庄先生)ある意味いまは豊かなんですよ。これまで右肩上がりの時代で、会社も無茶はしませんし給料が下がることはありませんから、それほど紛争は起きない。ルールを知らなくとも問題はなかったわけです。ただ今のように経済が右肩上がりでなくなった場合、あるいは下がる時も想定しなくてはなりません。給料が下がる、場合によっては失業者も増えるでしょう。そうなった時、一番困るのは働いている人です。少なくとも、雇用の社会に出て行く人が知っておく必要があります。近年は比較的早い段階で転職や離職をする方が増えているので、尚更ワークルールの知識が必要です。
(静岡時代)知らずに損するのは私達ですね。今後のワークルールのあり方とは?
(本庄先生)本来、労働教育は学校教育で一律に勉強することが望ましいです。海外では学生の間に一定の職業訓練を受けるなど学校教育と職業教育が密接にリンクしています。しかし、日本ではこれまでワークルールに関する教育はほぼ行われてきませんでした。情報が氾濫している今、自分の働き方におけるワークルールの基準を押さえることが重要です。昔は職場の皆が同じ労働条件で働いていたので、情報共有も比較的しやすかったのですが、今は職場でのルールの共有が難しいこともあります。働き方が多様化しているということを前提にワークルールを準備していく、同時に広く浸透させていくシステムも必要です。
また、ワークルールや労働法は「大人の世界」です。理屈はもちろん重要ですが、結果の妥当性やモラルの問題などバランスを見ていくことが大事。理屈で割り切れないところがワークルールの難しいところでもあり、面白いところ。越えてはいけない一線があり、その判断の基準は法治国家の日本の場合は法です。ただ仮に守っていなかったとしても、どの程度の乖離があるのかが重要です。守っているか・いないかの二択ではなく、その乖離を知るために、このラインは知っておく必要があるでしょう。(取材・文/三好景子)
http://www.rengo-shizuoka.jp/mate/event/#event
2015年5月から、静岡県、東・中・西部の各地域で、ワークルールの基礎講座を開講。社会人の方も参加可能です。
講座の詳細は、上記URLよりご確認ください。
〈ワークの掟〉シリーズ記事
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
【PR】2015年度就活シーズンも最盛期!
働く掟を知って、曇りなき眼で自分の将来を見定めよ!!
〜静岡時代推薦の働く入り口特集〜
◉「静岡就職net」
静岡県の就職サイト。県が運営する就活サイトだから安心・安全!
http://www.koyou.pref.shizuoka.jp/
◉「就コン〜社員と交流できる合同企業説明会」(働く先輩に直接仕事の裏側を聞ける!)
https://job.tsunoru.jp/shushoku/shukon/
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Updated:2015年05月08日
ワークの掟【その1】〜先輩に学ぶルールの必要性〜
「働く」には、自己欲求・社会欲求・生存欲求といわれる人間の三大欲求が集約されている。
自分を成長させたい、社会の役に立ちたい、親に恩返しをしたい、むしろ家から出たい、大学を卒業したら就職するのが当然だ、生きていくために……。働く理由はそれぞれありますが、「働く」ことで満たされるものは、”自分が何者であるのかを知りたい”、”誰かに認められたい”、という欲求なのではないでしょうか。人間は社会のなかで生きているからこそ、みんな、拠り所を求めるのだと思います。だから、わたしは「働きたい」。
つながりの希薄化も叫ばれているいま、「働きたい」がスタンダードな時代です。
わたしの「働きたい」という気持ちを、よりうまく社会へ循環させるためにはどうしたらいいだろう。誰かを傷つけることなく、喜んでもらうために、わたしが社会に疲弊するのではなく、生きがいをもってはたらくために、いま知りたい『ワークの掟』。
『ワークの掟』シリーズでは、そもそも働くとは何か、経済から紐解くワークルール史、デキる社会人の常識や嗜み、後輩への助言(警告含む)を先取りで学びます(静岡県内外で若者の労働教育普及を行う一般社団法人ワークルールさんが全面協力!)。
シリーズ第一弾は、一般社団法人ワークルールの理事 由比藤準治さんに、「働く上での基本的なルール(ワークルール)と、それが必要とされるワケ」を伺いました。実は、学生アルバイトも超必須な知識とモラルが詰まってました。
■由比藤準治(ゆいとうじゅんじ)さん
一般社団法人ワークルール理事。労働法令に関わる仕事に25年勤務。
写真の中でふたりが持っている青い冊子は一般社団法人ワークルール発行の『知っておきたい ワークルールの基礎知識』(通称:青い本)。働くことと直に関わる労働法が、イラスト付きでわかりやすく解説されています。新社会人、就活中のみなさん必読の一冊です!(大学のキャリア支援関係室に設置されているか、もしくは会社のホームページまでお問い合わせください)
[聞き手]
■渡邊なみほ(わたなべなみほ)
静岡大学教育学部4年。現在、公務員試験にむけて猛勉強中!
------------------------------------------------------------------
【一般社団法人ワークルール】
2014年4月1日設立。
大学生、専門・専修学校生、高校生などの若者に対し、
社会で働く上で必要な、ワークルールの基礎、多様な働き方の情報を身につける機会を提供している。
県内外問わず、大学、高校生を対象にワークルールの出張講座も開講。
また、労働法がわかりやすく解説されている冊子『知っておきたい ワークルールの基礎知識』は、キャリア支援関係者の他、大学・高校生のあいだで好評を得ている。
http://www.workrule.jp
http://www.rengo-shizuoka.jp/mate/event/#event
2015年5月から、静岡県、東・中・西部の各地域で、ワークルールの基礎講座を開講。社会人の方も参加可能です。
講座の詳細は、上記URLよりご確認ください。

▲就職先の先輩達も驚いた! はたらく上でのトホホなお話。身に覚えのある方もいるのでは?
ワークルールを身につけておけば、就業時のトラブルや不安も回避できます!
■「おかしいな」と気づけることの大切さ
(渡邊)働くうえで必要とされるワークルール。なぜ今、大切なのでしょうか?
(由比藤さん)そもそもワークルールとは、働くうえで必要な労働法などの法律だけではなく、社会人として必要なマナーやモラル、会社の規則を一通りまとめたもの、社会で働く上でのルールのことを言います。ルールの中には義務と権利(法律)という関係がありますが、法律だけでは足りないんです。自分の権利を行使するには、まずは自分に与えられた義務を果たさなくてはなりません。しかし、時代の流れからか社会人としてのマナーやモラルが欠けているという人は少なくありません。最近は権利だけを主張するという人も増えています。義務を果たしてこそ、権利を主張することができるということを念頭に置いてもらいたいですね。
(渡邊)義務と権利のバランスの取り方が大切なんですね。もっと早く知っておきたかったです!
(由比藤さん)学校教育の現場では、働くうえで必要なワークルールについて学ぶ機会があまりないのが現状です。今は社会全体に人を育てる余裕がないのかもしれません。知識がないまま社会に出て、損をしてしまう人も多くいます。社会に出てから「知らなかった」では済まないということもあるんです。自分自身を守るためにも、「おかしいな」と気づけることが大切です。
(渡邊)実は、私もアルバイトを辞める時に揉めてしまったことがあって。今すぐにでも辞めたい! と思った時にネットで調べたんです。そうしたら「14日前までに申し出れば法律上は大丈夫」と書いてあったので、期限ギリギリではあったけれど辞めたいということを申し出ました。でも、相手には「そんな直前で辞めさせてくれと言うのは非常識だ」と言われてしまったんです。法律上ではよしと思っても、社会ではNGとなってしまうことを痛感して、今も後悔しています。
(由比藤さん)そうですね、ネットで調べた知識だけでOKだと思っても、社会のルールとしては「どうなの?」と言われてしまうケースもあります。なので、一般社団法人ワークルールとしても、社会に出る前の学生が、法律だけではなく様々なルールを学ぶことの出来る場を全国的に広げることを目指しています。今年は県内外の100の大学や高校で講座を開催する予定ですよ。ワークルールについて知ることで、働くことに対する不安が少しでも解消でき、いざという時に守ってくれる法律があるということを知ってもらいたいですね。
(渡邊)全国的に注目されているんですね。さっそく今から学生に心がけてほしいことはありますか?
(由比藤さん)自分がどのような労働条件で働くかということを理解して働いてほしいです。ただ給与が良いからという理由だけで会社を決めてしまうと、自分の予想に反することも多くあります。アルバイトを選ぶ際も同じです。条件を確認する癖をつけておくと社会に出たときに役立つと思いますよ。あとはやはり、自分の義務をしっかり果たす人になること。義務を果たしてこそ、権利を主張できます。そうしたらきっといい方向へ向かっていくはずです。
(取材・文/渡邉なみほ)
ワークの掟【その1】〜先輩に学ぶルールの必要性〜
■由比藤準治(ゆいとうじゅんじ)さん
一般社団法人ワークルール理事。
労働法令に関わる仕事に25年勤務。就職への不安も悩み事も(もちろん働いている社会人の方も)、一人で悩まずにまずは相談するのが一番。
〈聞き手〉
■渡邊なみほ(わたなべなみほ)
静岡大学教育学部4年
現在、公務員試験にむけて猛勉強中!
------------------------------------------------------------------
【一般社団法人ワークルール】
2014年4月1日設立。
大学生、専門・専修学校生、高校生などの若者に対し、
社会で働く上で必要な、ワークルールの基礎、多様な働き方の情報を身につける機会を提供している。
県内外問わず、大学、高校生を対象にワークルールの出張講座も開講。
また、労働法がわかりやすく解説されている冊子『知っておきたい ワークルールの基礎知識』(通称:青い本)の発行も行っており、キャリア支援関係者の他、大学・高校生のあいだで好評を得ている。
http://www.workrule.jp
http://www.rengo-shizuoka.jp/mate/event/#event
2015年5月から、静岡県、東・中・西部の各地域で、ワークルールの基礎講座を開講。社会人の方も参加可能です。
講座の詳細は、上記URLよりご確認ください。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
【PR】2015年度就活シーズンも最盛期!
働く掟を知って、曇りなき眼で自分の将来を見定めよ!!
〜静岡時代推薦の働く入り口特集〜
◉「静岡就職net」
静岡県の就職サイト。県が運営する就活サイトだから安心・安全!
http://www.koyou.pref.shizuoka.jp/
◉「就コン〜社員と交流できる合同企業説明会」(働く先輩に直接仕事の裏側を聞ける!)
https://job.tsunoru.jp/shushoku/shukon/
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
Updated:2015年04月18日
卒業論文、その後の物語〜静岡県の卒業論文からみる、大学生の姿〜
卒業論文(制作)は、大学時代の集大成だ。しかし、大学全入時代が訪れ、いつのまにか卒論は、卒業するためだけ(=こなすもの)のもになってはいないだろうか……? 今の私と同じ年代の先輩たちは、一体どのような考えで卒論に向かっていたのだろう。今回は、論文が学会誌に掲載され、卒業後も研究が続いているという、静岡文化芸術大学卒の福嶋成美さんにお話を伺った。福嶋さんの卒論エピソード、そして、論文を書く前と後で何か変わることはあったのか。教えてください!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉福嶋成美(ふくしまなるみ)さん〈写真:左〉
静岡文化芸術大学 文化政策学部 文化芸術学科2011年卒業。
卒業論文のテーマは「子どもの生きる力を育む為のワークショップ型授業実施には何が必要か」。
自身の卒業論文が学会誌に掲載され、現在は(公財)浜松市文化振興財団の文化事業課に勤務。
[聞き手]
◉鈴木理那(すずきりな)〈写真:右〉
静岡大学教育学部4年。本特集の編集長。
普段は穏やかな人柄だが、場をしめなければいけないときはハッキリとものを言う頼れる編集長。
2015年3月、無事に論文を終え、同大学を卒業。
◉見好景子(みよしけいこ)
静岡大学教育学部3年。本記事の執筆担当。
筆者は美術コース専攻のため、今後、卒業制作が控えている。
★「伝説の卒業論文」シリーズ/記事
(1)そもそも卒論って何?→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1388029.html
(2)卒論の天敵「誘惑」の本質とは?→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1464051.html
(3)静岡県の大学生200人に聞きました みんなの卒論・卒制、のぞき。→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1368556.html
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■卒業論文は、ただ書いておわりじゃない

本誌編集長鈴木(以下鈴木):福嶋さんの卒業論文は査読付き論文として学会誌に掲載されたそうですね。どのような卒論を書かれたんですか?
福嶋さん:卒業研究では「子どもの生きる力を育む為のワークショップ型授業を実施するには何が必要か」をテーマに、全国2万校以上ある学校から、350校の小学校を抽出し、各校2名の先生にアンケートをお送りして「芸術教育における意識調査」を行いました。もともと音楽が好きで、音楽に関わる仕事に就きたかったので、大学ではアートマネジメントを専攻していたんです。その中でも芸術教育に関心がありましたね。
大学3年生の時に、子どもたちのひきこもりやいじめが深刻な社会問題とされているなかで、生きていくうえで必要な「自己表現力」が低下しているのではないかという問題意識を持つようになったんです。私の研究テーマにもある「ワークショップ型授業」の定義は、①アーティストを招いていること、②子どもたちが鑑賞だけでなく創造の過程に加われるもの、③個人が活かされて創造性の伸長が期待できるもののこと。楽しく表現できればどれも正解です。私も学生時代にNPOの開催するワークショップのお手伝いをする機会がありましたが、子ども達は自由に表現を楽しんでいましたね。芸術を通して、表現する過程自体が楽しいと体感できれば、生きる力を育むことができるのではないかと思ったのが、そもそものきっかけです。
鈴木:アートコミュニケーションと言われるものですね。ちなみに、「査読付き論文」「学会誌に掲載」と聞くと「すごい卒論」というイメージですが、どのような講評があったのでしょうか?
福嶋さん:私のようにワークショップ型授業に焦点をあて全国的にアンケートをとった事例が今までになかったので「広く周知していかなければいけない」と指導教員の片山先生が推薦してくださったんです。学会で発表したことがきっかけで、学会誌に掲載していただきました。私自身も、先生やアンケートに協力してくださった先生方の思いを受け継いで出来た卒論だったので、思い切って挑戦しました。


私の卒論は査読付きなのですが、査読とは、学術誌に投稿された学術論文を専門家が読んで内容を査定することです。卒業後に査読が通ったので、働きながら査読を受けるのは大変でした。でも、学会誌に掲載していただいたことにより、小学校の先生や教授にお会いした時に「卒業論文を読んだよ」と声をかけていただくことがあります。研究として形にすることで、知らないところで誰か(の研究)の役に立っている、というような繋がりが広がっていくことが凄いと思いました。先生からも大学のゼミで卒論を教材にして勉強していると伺い、卒論はただ書いて終わりじゃないのだなと思いました。
鈴木:学会誌に掲載されるということはオリジナリティがあって「学術論文」として、「学者」として学会から認められたということだと思います。「書いて終わり」ではなく、卒論が誰かのもとに届いて、自分に返ってくるというのは羨ましいです。私は理系なのですが、今「水とイオン液体の相互作用」を研究しています。私の研究室では、卒論というと先輩から後輩へ引き継ぐイメージが強いです。私自身、先輩や先生から教えてもらうことが多く、教えてくださる方々は勿論、私から研究を引き継ぐだろう後輩の為に研究しています。卒論に取り組むうえで、福嶋さんはどんな卒論を、誰の為につくりたいと思っていましたか?
福嶋さん:私の場合は、子ども達が充実した芸術教育を受けられるきっかけになればと思って研究していました。それに、アンケートの回答に学校の取り組みの新聞記事のコピーを同封してくださったり、「大変だと思いますががんばってくださいね」や「何かあれば連絡ください」などと応援や励ましの言葉が添えられていたりして、心が温まりました。卒論は自分のものですが、そうやって協力してくれる人達がいることで「自分だけのものじゃない」と感じ、ちゃんとやらなくては、とやる気がでました。
鈴木:そのような言葉掛けは、確かにやる気につながりますね。とはいえ私は、いま卒業論文や卒業制作が「こなす」ものへと変わってきているのではないか、と思っています。就活に気をとられて、みんなそこまで必死じゃないのかな、と。福嶋さんは2011年卒業ということで、私と世代は大きく変わらないと思います。大学時代における卒論のことを、どう捉えていましたか?
福嶋さん:私の場合、知らない人にアンケートをとったりインタビューをしたりしました。それは、卒論があったからできたことで、卒論がないと会えない人や話を聞けない人がいると思います。いろんなことができる機会なので、自分の好きなものをどんどん追究してほしいです。
■卒論と向き合うことが自信や糧につながる

鈴木:本誌制作に当たり、今までいろんな人にインタビューをしてきて、
「卒論は大学時代の学びの集大成」とよく言われました。でも、私はまだ本格的に卒論を書き始めていないので、自分の中で「乗り切らなきゃいけない」みたいな、強要されているような感じがあるんです。福嶋さんは卒論に取り組む前と、やり遂げた後でなにか心境に変化はありましたか?
福嶋さん:はじめは研究テーマである「なぜ芸術教育は大事なのか」という理由は主観でしかなくて、研究する前は論証立てて言えませんでした。卒論に取り組むにあたり先行研究を整理していく中で、自分の中で曖昧だったことがちゃんと言語化できるようになったということは、すごく大きいなと思います。学ぶということの本質を学んだ気がしますね。
卒論とどう関わったかによって得られるものは違うと思います。大学4年間の学びの集大成として自分の考えをまとめることは、振り返るとこんなことをやったんだなって自信や糧になると思います。課題をクリアすること、課題をどうやって乗り越えるかということは、自分が生きていく上で必要になること。プロセスを学んでおけば、研究だけでなく、全てに通ずる部分があると思います。
鈴木:でも、卒論や卒制が将来何につながるのかと思うと、卒論に消極的になってしまいます。福嶋さんは将来に、どのようにつながりましたか?
福嶋さん:研究の分野により違うかもしれませんが、私が卒論に取り組む前、先生や先輩に「時間をかけて一緒にいるものだから、自分が本当に思いを掛けてできるものにしなさい」と言われました。大学のときじゃないと、長い時間を費やして何かを研究する事はできない。やりたいことは全部やりたいと思っていました。負けず嫌いなところがあって、自分の好きなことをやっていたからできなかったと思われるのは嫌だし、自分だって好きなことを言い訳にしたくない。好きなことをやっているからこそ、逆に頑張れていました。
卒論という機会を活かして、自分の好きなものを、自分が知りたくて追究しているんだってポジティブにとらえるといいと思います。私は、ありがたいことに、卒論が仕事と結びついています。学校教育と深く関わる事業にも携わる中で、小規模校だと外部から先生を招く予算が厳しい、芸術教育に割く時間がとれないといった、現場でしか分からない問題もみえてきます。働くことにより研究がさらに深まっているようで、今の仕事はとてもやりがいがあります。卒業してからもずっと研究が続いている感じですね。
(取材・文/三好景子)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
◉連続特集:静岡時代10月号(vol.36)『伝説の卒業論文』(4)
【卒業論文、その後の物語〜静岡県の卒業論文からみる、大学生の姿〜】

◉福嶋成美(ふくしまなるみ)さん〈写真:左〉
静岡文化芸術大学 文化政策学部 文化芸術学科2011年卒業。
卒業論文のテーマは「子どもの生きる力を育む為のワークショップ型授業実施には何が必要か」。
自身の卒業論文が学会誌に掲載され、現在は(公財)浜松市文化振興財団の文化事業課に勤務。
[聞き手]
◉鈴木理那(すずきりな)〈写真:右〉
静岡大学教育学部4年。本特集の編集長。
普段は穏やかな人柄だが、場をしめなければいけないときはハッキリとものを言う頼れる編集長。
2015年3月、無事に論文を終え、同大学を卒業。
◉見好景子(みよしけいこ)
静岡大学教育学部3年。本記事の執筆担当。
筆者は美術コース専攻のため、今後、卒業制作が控えている。
★「伝説の卒業論文」シリーズ/記事
(1)そもそも卒論って何?→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1388029.html
(2)卒論の天敵「誘惑」の本質とは?→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1464051.html
(3)静岡県の大学生200人に聞きました みんなの卒論・卒制、のぞき。→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1368556.html
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Updated:2015年03月31日
卒論の天敵「誘惑」の本質とは?〜静岡県の卒業論文からみる、大学生の姿〜
卒業論文は持久戦だ。しかし、大学生についてまわるのが、"飲み会"、"卒業旅行"、などといった娯楽や余暇の類。誘惑はいたるところに転がっているのだ。卒業論文を控えている私たち大学生は、目の前にある誘惑をどうくぐり抜けていったら良いのだろう? 人間の動機付けやモチベーションの研究をされている静岡理工科大学の今野勝幸先生に、卒論の環境を切り口にお話を伺った。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉今野勝幸(こんのかつゆき)先生
静岡理工科大学 総合情報学部 人間情報デザイン学科講師。
研究分野は英語学習者の心理的要因と人間の動機付け。教育心理学や社会心理学の知識を習得し、主に英語学習者のモチベーションを研究されている。趣味のギターは研究室で弾くこともあるそう。
[聞き手]
◉鈴木理那(すずきりな)
静岡大学教育学部4年。本特集の編集長。
普段は穏やかな人柄だが、場をしめなければいけないときはハッキリとものを言う頼れる編集長。
自身が現在卒業論文制作のまっただ中!
◉塚本みゆき(つかもとみゆき)
静岡英和学院大学1年。本記事の執筆担当。
数年後、卒業論文を書く身として、取材中は先生のお話を真剣に拝聴していた。
★「伝説の卒業論文」シリーズ/記事
(1)そもそも卒論って何?〜卒論史にみる、静岡県大学生の姿〜→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1388029.html
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■誘惑ではなく選択? 私は自律性を求めている。

——私たちは卒論や卒制に取り組むにあたり、常に誘惑と隣り合わせです。そもそも誘惑とはどのような存在なのでしょうか?
(今野先生)ここでの「誘惑」は、卒論をやらなければならないのにゲームをやってしまったり、勉強しなければならないのに飲み会に行ってしまったり、というときのゲームや飲み会のことですよね。これまで心理学を研究してきた私の視点でいうと、それらは誘惑ではなく、その時々の「選択」だと思います。誘惑にかられるというよりは、「卒論や勉強をやりたくないからゲームをやろう!」みたいな感覚ですね。
おそらく皆さんは物事をするにあたって、自律性を求めているのではないでしょうか?その自律性が阻害されているから、誘惑にかられていると思い悩んでしまうと思うんです。ですから、人はいかにして自律的になれるのか、について考えてみましょう。私はいま、教育心理学の観点からモチベーションを研究しています。その理論では、行動に対して内発的に動機づけすることができれば、人は自律的になれると考えられています。内発的動機づけとは、行動そのものが自分の行動の理由になっていることを指します。たとえば、趣味はなんですか?それをなぜしますか?
——読書です。本を読みたいからです。
(今野先生)そうですよね。つまり、読書をする理由は読書が好きだから、本を読みたいから。読書をすることに意味があり、それが理由になって行動しているんです。このような動機を「内発的動機づけ」といいます。一方で「外発的動機づけ」もあります。動機そのものは人間の行動にはないケースです。では、なぜ勉強しますか?
——うーん……。将来のためです。
(今野先生)そう。勉強をすること自体が理由ではなくて、勉強して得られる将来、これこそが行動の理由になっています。これが「外発的動機づけ」です。長い目で見れば卒論や卒制も内発的動機づけで取り組むことが理想型ですよね。心理学でいうと、人間はより楽しいもの、興味のあるもの、好奇心の向くものに目がいくので、基本的には内発的に動機づけられた行動をとるようになっています。誘惑に負けて行動が阻害されるというよりは、より楽しい方、より欲求が湧く方を選択しているんです。これが人間の本来もっている心情で、誘惑のメカニズムだと思います。
■卒論・卒制の理想型は、動機を「好き」に置くこと

——卒論・卒制の理想型は動機を自分の「好き」に置くことなんですね。とはいえ、実際なにをしたらいいか分からない人も多いと思います。さらに卒論は長い時間をかけて取り組む持久戦。卒論に対するモチベーションを上げるにはどうしたらいいでしょうか?モチベーションを上げ下げする卒論ならではの心理的要因はありますか?
(今野先生):本来、卒論・卒制は大学4年間の研究の集大成です。みんな、卒論に対しては「やらなきゃいけない」という気持ちを持っていると思います。今、静岡県だけでなく全国的に見ても大学進学率は約51%と高いのですが、中には大学に来たけど何かをしたいわけじゃない、という人もいると思います。そうした風潮から、卒論の位置づけが曖昧になっていると思います。卒論でやりたいことがわからない、何をしたらいいかわからないなど、やりたいと思っていても出来ない人も多いですよね。
卒論で何をやるのか、テーマを決めることが実は一番難しいものです。入りたい研究室に入っても、先生に興味はあるけど学問には興味がない学生も今は多いでしょうし。そうした卒論事情のなかでモチベーションをあげるには、卒論・卒制を自分自身の内発的動機づけに結びつけていくことです。つまり、卒論自体を楽しくすること。卒論のテーマを興味のあるものにしたり、友達と勉強会を開いてみたりするとかね。
人間が自律的になれない理由は、「やらなきゃいけないことが楽しくない」とか「自分は何をしたいのかわからない」というところにあるんです。やることや目標が明確で、自己効力感(自信)さえあれば人は動くんです。みなさんも日常の生活の中で思い当たる節があるはずですよ。また、小刻みに自分ができる範囲の目標を立てることも大切です。短いゴールですね。大きなゴールが1つあるより、短いゴールがたくさんあるほうが人は頑張れるんです。
——ちなみに、今野先生は卒論にどのように取り組まれたのでしょうか。
(今野先生):私の卒論は大失敗でしたね。実は大学4年生の時に大恋愛をしてしまいまして、好きな子に気をとられてしまったんです。彼女とお付き合いしたくて頑張っている間に、他にも大学院の試験やバンドの練習などやることがあり、優先順位の中で卒論が一番最後になってしまいました。提出2〜3か月前になって、ようやく彼女とお付き合いすることができたのですが、今度は彼女の家に入り浸るようになってしまって、卒論に手を付けず。でも、今更先生に「何をやったらいいのかわかりません」なんて言えないから、最終的には苦し紛れになんとか書いて提出したところ、「なんだこれは!」と怒られました。尻を叩いてくれる先生ではなかったので、それに甘えてしまいましたね。結局、彼女とは付き合うまでに1年かけて、9か月で別れたんです。大恋愛をしても続くわけではない、と学びました。

■友だちと研究会など、卒論をやる過程・環境を面白いものに
——今の大学生も色恋がらみの誘惑に悩まされている人が結構多かったです。最後に、万が一「卒論が楽しくない」と思えてしまったり、大恋愛をしてしまった場合に備えて(笑)、卒論の天敵・誘惑にどうしたら勝てるのでしょうか?
(今野先生):私は大学受験を控えているとき、勉強に集中するために大好きなギターをしまいました。でも、ギターを弾かなくなったからといって勉強がはかどったかというと、そうでもなかったです。今思うと、自分を一番勉強に集中させたのは、先生からのポジティブな言葉掛けでした。だから私は、誘惑に勝たなくてもいいんじゃないかなって思います。もちろん、誘惑に負けてしまって締め切りを守らなかったり、何もやらなくなったりしてしまうのはよくないですけどね。
たとえば、締め切りまで1週間あって、5日間遊んでしまったから残りの2日間を徹夜で仕上げたとしても、最終的に他の人と同じように提出できたならそれでいいんじゃないかな。誘惑に勝ったとか負けたとかは、最終的な結果を見て判断すればいいと思います。
個人的なアドバイスとしては、早めにSOSを出すことですね。何をやるのかしっかり決めて行動している人には、頑張れとしか言えませんが、テーマが全然決まっていなくて何をしたいのかわからない人は早めに助けを求めることが必要です。あとはやはり内発的動機づけをするために、卒論をやる過程、環境を面白く、楽しくすることです。そのためにも、やはり友達作りは大切だと思いますよ。
(取材・文/塚本みゆき)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
◉連続特集:静岡時代10月号(vol.36)『伝説の卒業論文』(2)
【卒論の天敵「誘惑」の本質とは?〜静岡県の卒業論文からみる、大学生の姿〜】

◉今野勝幸(こんのかつゆき)先生
静岡理工科大学 総合情報学部 人間情報デザイン学科講師。
研究分野は英語学習者の心理的要因と人間の動機付け。教育心理学や社会心理学の知識を習得し、主に英語学習者のモチベーションを研究されている。趣味のギターは研究室で弾くこともあるそう。
■このお話をもっと深く掘り下げたいひとへ今野勝幸先生からのオススメ本!
パオロ・マッツァリーノ 『反社会学講座』. イースト・プレス. 2004
[聞き手]
◉鈴木理那(すずきりな)
静岡大学教育学部4年。本特集の編集長。
普段は穏やかな人柄だが、場をしめなければいけないときはハッキリとものを言う頼れる編集長。
自身が現在卒業論文制作のまっただ中!
◉塚本みゆき(つかもとみゆき)
静岡英和学院大学1年。本記事の執筆担当。
数年後、卒業論文を書く身として、取材中は先生のお話を真剣に拝聴していた。
★「伝説の卒業論文」シリーズ/記事
(1)そもそも卒論って何?〜卒論史にみる、静岡県大学生の姿〜→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1388029.html
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Updated:2015年03月28日
【特別対談】“誰もが幸せ”になる、真の介護とは?(2/2)
人と人が向き合う“介護”。その人間同士の関係性は、外から見てわかりやすい「介護される側」「介護する側」という世界なんだろうか。介護職の人材不足だからというわけでなく、いま本当に必要な介護とは何かを考える上で、誰かに幸せを与えたり、与えられたり、またその幸せに寄り添う仕事として、介護や介護職を捉えてみたい。今後、静岡県内地域でどんな介護を私たち世代も一緒になってつくっていければいいんだろう……?
今回は静岡英和学院大学 人間社会学部コミュニティ福祉学科教授の見平隆(みひら たかし)先生(コミュニティ福祉学科・学科長も務められています)と、静岡県介護の未来ナビゲーターの野中一臣さん・小林正子さんと一緒に、大学生がいま知るべき介護のこれからの展望について伺いました。
取材・文:小泉夏葉(静岡時代編集部・静岡大学 理学部地球科学科2年) [写真右]
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■見平隆(みひら たかし)先生 [写真中央]
静岡英和学院大学 人間社会学部コミュニティ福祉学科教授。専門分野は、地域福祉、政策、福祉社会学。
コミュニティの一員として、誰もが幸せである介護とは何なのか、先生の実体験をもとにしたお話を伺いました。
《介護の未来ナビゲーター》
■野中一臣(のなかかずおみ)さん [写真中右]
社会福祉法人・松風
特別養護老人ホーム 「みずうみ」勤務。
■小林正子(こばやしまさこ)さん [写真中左]
社会福祉法人・春風会
特別養護老人ホーム 「みはるの丘 浮島」勤務
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■大学生世代と介護の関わりが、家族を支える肝になる
(静岡時代):お話を伺ううちに、介護職にものすごく可能性を感じるようになったのですが、たとえば働き手の立場から、これからの介護や介護職の展望で期待していることはありますか?
(小林さん):今、施設として地域に関わっていく活動に意識を向けています。介護施設って、みずから行くようなところではないじゃないですか。家族が入居していれば行くかもしれないですが、何もない人が行くようなところではない。
だから、誰でもおとずれることができるフラットな場所、地域にとってオープンな場所になったら、介護自体も身近に感じてもらえるのではないかと思います。
(見平先生):日本の老人ホームって、靴をぬぐスタイルでしょ。これって、私反対なんです。重篤な患者さんがいる病院もみんな土足ですよ。なんで老人ホームでは靴脱いで入らなければいけないんだと。それは、老人ホームがひとつの家だからという日本の感覚がありますね。一般の人たちが、自由に出入りできるかといったらできないです。だったら、施設の中に喫茶コーナーでもつくって、中からも外からも自由に行けるようにするとか。実際にそういう風につくっている施設もありますよね。
小林さんの言うように、これからは、“まちの住民として施設職員”がいる状況をつくらなければならない。お茶会などをやったとして、最初は人がこなくても、月一回でもずっと続ければ、だんだんと広がるはず。やがてそれが公園のような機能も持つでしょう。そこからまた人が来始めるんです。あとはやっぱり若い人たちが、「今の時代これですよ」ってアイデアを出して、業界や施設をどんどん変えていってほしいなあ。
(静岡時代):そういう環境、風土を育てていく時期にあるのかもしれませんね。若手職員のみなさんの腕にかかっていると。
(野中さん):僕たちは毎週毎日、ケアの仕方だけでなく、どちらかと言えば、“どうやったら笑わせられるか”に頭を悩ませてますよ。次はどんなことをしようかって。生活は生モノだから、今日やったことを来週やれるかといったら同じことはできないですし。ウケも良いときや鈍いときがありますし。そう考えると、本当に創造性高くておもしろいんですけどね。
あとはこの頭の使い方を、もっと仕事自体が面白くなるように、自分たちに向けても活かさないとって思います。単純ですけど、やっぱり面白いと思われる仕事には人は集まりますし。どこまで介護そのものを面白くするのかが、僕たちの勝負だと思っています。
(見平先生):だから吉本新喜劇でないけども、計算された笑いは緻密なものですよ。施設にはいった瞬間から職員の方はパフォーマンスが始まっていると考えてもいいくらいです。すると確かに疲れはするけど、心地よい疲れだと思います。3Kとかも、義務感でやるからキツく感じるし、排泄物はきれいにすれば済む話。給料も、決して安い訳ではない。日本の平均的な賃金からいけば、介護職の給料は決して悪くなくて、ある程度の水準なんです。
高額所得者をとびぬけて問題視させないように操作するからね。これから、介護の施設のありかたももっと変わっていきます。そうしたら、今の民間企業でも会社が自分の社員を独立させて一緒にやるというスタイルもあるでしょ?それを、介護の世界でもできるようにしていこうというのが、20年前に考えられたことなんですよ。だからチャンスや可能性を広げていくことができる職場なんです。
それを逆にマスコミが、人手が足りないとか、悪いイメージを植え付けてる気がします。自分にふさわしい仕事があるのではないかと皆思いますよね。それはそうなんですが、でも自分にふさわしい仕事は何かというときに、じゃあ自分は何したいのよ。誰かが、何かが提示するのをまっているのという。結局、カタログ・マニュアル人間なんです。自分がつくる楽しさを感じれば、全然違う。作る楽しさをしると、見方が変わってくる。だから何かいいものないか、何が私にあっているのかを探している人は、ずっとそればかりにとらわれてしまう。自分が人生をつくる楽しさを今の若い人たちに考えてほしい。どん欲さが大事だと思います。これをやるともっと変わるのではないか。介護の世界に限らずね。だから仕事で伸びるんですよね。
(野中さん):僕もこの仕事をはじめてから10年しかたっていないですが。やはり、楽しい仕事をやって、今33歳なんですが、ちゃんと結婚できて子どももいて、親の援助もうけずに一戸建てを買って暮らしています。車もあるし、ちゃんとした収入ってあるんですよね、介護の現場でも。自分たちで楽しい仕事をつくっていけるかどうかっていうのが大事で、僕はすごく楽しくやらせてもらっています。それはたくさんの人に伝えていかなければいけないなと感じましたね。
(静岡時代):私は介護について全然知識がなくて。給料が安いとかもテレビやインターネットなどからの情報しかなくて。実際に介護職の方がどういう生活をしているのか、どういうことを感じて仕事をやっているのかも、こういう機会で初めて知って、自分がいつの間にかつくっていた固定概念が変わってきました。
(野中さん):給料が安いとか、シフト勤務で土日が休めない、とかいうのは、考えようによってはどうにかなりますよ。同じような条件のお仕事だって他にもあるでしょ? 介護職だけじゃないんです。僕らは新たに介護のプロになってくれる方をいつも探し続けているんですが、学生さんたちはどんなところに興味を持ってくれるんですかね。
(静岡時代):そもそも現場で働いている方とも接点がないですよね。でもこうしてお話を聞いて、みなさんがそれぞれ想いを注いでいる様子を見聞きできるのは、体験として大きいと思います。あと気になるのは、みなさんが今の仕事に就こうと思ったきっかけでしょうか。
(小林さん):私は元々、小さい頃から祖父母と一緒に暮らしていたんです。お年寄りの存在を身近に感じていたんですね。中学か高校のときに、夏休みを使って短期間のボランティアに参加して、あまり意識もせずに介護施設に行ってみたんです。そうしたら、すごく大変そうなのもわかったんですが、何も知らない素人の私に利用者のみなさんが笑顔で「ありがとね」って言ってくれて。それにすごく感動して、素敵な現場だなと思ったのが始まりでした。
(野中さん):僕も同じような経験をして、この世界に入りました。20歳そこそこで、そんなに福祉の意味や価値がわからなかったですが、どうやって楽しく過ごせるかということは考え続けてきました。面白いこと、楽しいことって、体使って、大変な部分があってもそれを乗り越えるのが楽しいものです。
(静岡時代):私は昨年、祖父を亡くしたのですが、そのときになって介護についてもう少し知っておけば良かったなと思いました。というのも、私の両親が北海道出身で、実家が群馬。祖父は北海道でしたから、どうしても傍にいてあげられなかったんですね。自分ができることを全然見つけられなかったんです。また、祖父のことだけでなく、両親の心配や不安だってあったと思うので、私は他にどう向き合うことができたかな、というのは今一度考えてみようと思っています。これって、個人がどう動くか、という面と、今後の教育を考えることにもつながりそうなんですが。
(見平先生):大体20歳前後の学生さんたちは、自分が年をとるイメージってないでしょ? だから介護の世界とは無縁だと思っている人が多いのかもしれない。最近は、おじいちゃんおばあちゃんと同居している人たちも随分減っているしね。
私は自分の学生には、おじいちゃんおばあちゃんがもしも寝たきりになったらどうしますか、と聞くんです。たちまち慌ててしまうよって。あなたは自分のことだけ考えていればいいけれど、両親はおじいちゃんおばあちゃんのことを考えなきゃいけなくなる。そのうえでお仕事もあなたのことも。だから、今から心の準備しておこうよ、って伝えるんです。
自分の問題であるとしたときに、直接は関わらないからと思いがちだけど、結局は間接的にでも自分に影響があるとわかっていてほしい。
あまり会えないおじいちゃんおばあちゃんであっても、最後は安らかにしてもらいたいでしょって言っています。心に余裕がなくなってくると、ぎすぎすしちゃうでしょ。だから、どんなことすればいいか、どこに相談すればいいか。最低限の知識は持っておいた方がよいと思います。知識をもっていれば、職業として選ばなくても、どこかで役に立つことにつながるんですよ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
いままさに現場で働く、県内指折りの若手介護職員が日々情報発信を行っています。静岡県の介護の現場について、詳しく知りたい人は、以下のリンク先も要チェック!
・HP:http://kaigonavigator-shizuoka.jp/
・Facebook:「介護の未来ナビゲーター」で検索!
Updated:2015年03月27日
【特別対談】“誰もが幸せ”になる、真の介護とは?(1/2)
人と人が向き合う“介護”。その人間同士の関係性は、外から見てわかりやすい「介護される側」「介護する側」という世界なんだろうか。介護職の人材不足だからというわけでなく、いま本当に必要な介護とは何かを考える上で、誰かに幸せを与えたり、与えられたり、またその幸せに寄り添う仕事として、介護や介護職を捉えてみたい。今後、静岡県内地域でどんな介護を私たち世代も一緒になってつくっていければいいんだろう……?
今回は静岡英和学院大学 人間社会学部コミュニティ福祉学科教授の見平隆(みひら たかし)先生(コミュニティ福祉学科・学科長も務められています)と、静岡県介護の未来ナビゲーターの野中一臣さん・小林正子さんと一緒に、大学生がいま知るべき介護のこれからの展望について伺いました。
取材・文:小泉夏葉(静岡時代編集部・静岡大学 理学部地球科学科2年) [写真右]
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■見平隆(みひら たかし)先生 [写真中央]
静岡英和学院大学 人間社会学部コミュニティ福祉学科教授。専門分野は、地域福祉、政策、福祉社会学。
コミュニティの一員として、誰もが幸せである介護とは何なのか、先生の実体験をもとにしたお話を伺いました。
《介護の未来ナビゲーター》
■野中一臣(のなかかずおみ)さん [写真中右]
社会福祉法人・松風
特別養護老人ホーム 「みずうみ」勤務。
■小林正子(こばやしまさこ)さん [写真中左]
社会福祉法人・春風会
特別養護老人ホーム 「みはるの丘 浮島」勤務
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■介護の本当の姿を、わたしたちはまだ知らない
(静岡時代):今の介護・介護職について考えるとき、見平先生が重要だと思われている考え方、「介護の捉え方について教えてください。
(見平先生):学問的な話も大切ですが、まずは私の体験からお話させてください。
40年も前のことですが、私が心理や福祉分野の勉強をしていた大学生のときに、自分の父親が脳卒中で倒れたんです。一命はとりとめたものの、一家の大黒柱が寝たきりの状態になってしまった。そこで家族としてどうしていこうか、と当時の私なりに考えましたね。
当時はハンドルで回すベッドもなかなか手に入らないですし、ホームヘルパーだって、低所得で家族の居ない人しか市町村が派遣しない時代でした。ちなみに昔の介護用ベッドって三畳くらいのスペースを使ってしまうんですよ、今は一畳分くらいですよね。
特別養護老人ホームも数えるほどしかなかったし、いまほど介護に関する制度がまったくといっていいほど整っていなかったんです。そういうなかで、私は学生ながら介護という問題に直面しました。
(静岡時代):大学生で自分の親の介護をする……。私はそういうシチュエーションを想像したことがなかったです。
(見平先生):そうですよね。今では恥ずかしい話ですが、父が倒れて寝たきりになった頃、意識は戻ったので、当時の私はリハビリをすれば治るんじゃないかと思っていたんです。でも、一応専門的な勉強をする身としては、現実的に考えると回復できる程度のものじゃないとわかってきました。
そこで、さあどうしようかと思ったんですが、私たちは家族として、家で父を介護することにしたんです。いつも身近にいられる状態にね。それなり大変でしたし。当時私は大学を辞めることも考えましたけど、そこはなんとか通い続けることができました。
自分自身が専門の勉強をして社会人となっていくうえで、最終的には家を離れましたが、親子関係大事にしなきゃだめだということが常に頭の中にあったんです。当時の私の研究テーマが“家族”だったのもリンクしたのでしょう。結果的に、父は倒れてから10年自宅で暮らし続け、しかも最期は私の腕の中で息を引き取りました。
その期間に気づいたことがありました。家族での父の介護を支えたのは、身内だけでなく近所のお医者さんや地域の人たちでした。そうした人たちのおかげで、自分の父が“この地域で必要な存在”ということを肌で感じられたんです。だからこそ余計に、私は「家族の中での介護」が大切だと思うようになりました。
(静岡時代):“介護”というと、もう自然と「施設に入る」ことが普通だと思ってしまっていました。でも考えてみれば……。
(見平先生):そう、自宅にいても施設にいても家族なんだから、家族として人生を全うさせてあげたいと思うのが自然なんじゃないかな。介護する側もされる側もどういう生き方、暮らし方をしていきたいかを明確にさせておかないとだめなんだということが、父の介護を通じてわかったんです。今もその考えが根底にあります。
たとえば食事介助だったら、“食べさせてあげる”という発想ではなく、かつてのように“一緒に食事を楽しむ”をいう考えです。所謂食べさせる部分は増えるけれど、その時間をどういうものだと捉えるかで意味合いは大きく異なります。介護全体を通じて、「本人の代わりに」という発想になってしまうといけないと思うんです。
職業として介護をやっている人たちになると、家族以上に「代わりに」という意識になってしまうかもしれません。これは誰が悪いではなく、忙しない社会の空気が仕向けていってしまっている面もあるでしょう。でも、義務感で動かされる状態になったとき、仕事って楽しくなくなっちゃいますよね。
私はまだまだ、介護する側もされる側も、家族も、昔の一心に背負わなければならないイメージを引きずってしまっているなあと感じています。今はだんだんと、介護される側の方が、自分でやろうと思えば自分でできる環境をつくりましょう、という風になってきてはいますけど。まだまだです。
(静岡時代):実際に介護の現場で働いてらっしゃる、野中さんはいかがですか?
(野中さん):僕は現場で働きながら、職員の管理もするような仕事に就いているのですが、僕は何より現場が好きですね。よく3Kとか言われますけど、できることなら、利用者さんの排泄物などを“汚い”と思う人にこの業界に入ってもらいたくないとすら思います。
気持ちよく排泄できるというのは「喜び」です。それは本人だけでなく、私たち職員として関わらせてもらう側としても嬉しい気持ちになれることなんです。もしそういう考え方に結びつかないのであれば、先生のおっしゃったように、全部が作業になってしまうんだろうなといつも感じていますね。
(見平先生):いいですね。私が普段接する介護関係職のみなさんには、『歌って踊れる介護職員、社会福祉士になりましょう』と言っています。
自分たちからパフォーマンスをする、古いスタイルの介護ではなく、これをやると楽しい、充実しますよ、ということを自ら利用者さんに示していくんです。そういうことを堂々とやっていいはずなんですけど、なぜか未だ遠慮があるようにも感じちゃいますね。いかに充実した介護ができるか、要はその気になって、その人が充実した人生を送れるように、また本人がそうしていこうと思えるように、どうあの手この手を使えるかですよね。
(静岡時代):……歌って踊れる。介護職ってものすごくクリエイティブな仕事なんだなと思えてきました。
(野中さん):毎日がライブのようですよ!
(小林さん)私も仕事をしていると、本当に楽しいなと思うことが多いですね。人と話しながら仕事をして、この人にはこうしたら良いのではないかとか、もちろん職員同士でも話し合います。話していた内容が実現した時には、本当によかったね、と私たちも利用者さんもみんな一緒になって喜べて、本当に幸せな仕事だなって
(見平先生):介護は、そのときそのときをつくる面白さや難しさがあって、芸術と一緒ではないかと。どれだけ喜びや感動を与えられるかなんです。
芸術家の場合は作品を通してだけど、介護の場合は、対人援助ですから直接的に受け手に触れるもの。ダイレクトに、人が人と喜びを伝え合えるものですから、そんなことは他の仕事では、なかなかないですよ。お年寄りひとりひとりに、自分の自由な表現を出して、関われる。この世界の特権ですね。
http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1460196.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
いままさに現場で働く、県内指折りの若手介護職員が日々情報発信を行っています。静岡県の介護の現場について、詳しく知りたい人は、以下のリンク先も要チェック!
・HP:http://kaigonavigator-shizuoka.jp/
・Facebook:「介護の未来ナビゲーター」で検索!
Updated:2015年03月27日
体感! 大学生の介護の現場訪問録(3)—きじの里編
静岡県の大学生が、いま・これからの“介護”を考える本特集。
これまでの静大フューチャーセンターでのセッションや、英和学院大・見平先生との対談を通じて、介護に関して普段から抱いているイメージが知らず知らずに定着しているものだと気づかされました。また静岡県介護の未来ナビゲーターの介護職員のみなさんには、介護現場で“はたらく人”として自身の仕事の魅力についても教えてもらいましたが、まだまだ大学生にとって現場のイメージを具体的に持つことは難しいのでは。
そこで大学生が実際の介護の現場に赴き、話だけではわからなかった介護の本当の魅力や大変さ、イメージとは違う(?)現場の空気を感じてきました。今回は、大学生がつくる情報誌の編集を行うわたしたち『静岡時代』編集部が、浜松市にある「きじの里」を訪問。最先端の施設について学んできました。

◉訪問先:総合福祉施設「きじの里」
スタッフ・山口隼司さん(静岡県から委嘱された介護の未来ナビゲーター、写真左)
総合福祉施設「きじの里」のケアワーカー。
自身のお父さんが高齢者施設で働いていた影響もあり、「自然な流れで自分もケアワーカーになるんだと思っていました」と山口さん。
◉訪問したのは:静岡時代編集部(計2名)
静岡県で学び尽くしたい人におくる、大学生による大学生のための雑誌『静岡時代』をつくる編集部。
静岡県の介護×大学のコラボで静大FCとのセッションなども企画。“介護”と大学生とがどのように関わっていけるか、今後の情報発信も模索中。
(過去記事)静岡県の大学生が介護の未来を考える〜静大FC特別セッション〜
→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1415512.html
■多世代間交流がうまれる場。
介護施設=コミュニティ・カフェ!?
静岡時代編集部の一行が向かったのは、浜松市にある総合福祉施設「きじの里」。静かで小高い場所に建てられた施設には、なんと高齢者施設だけでなく、保育園や障害を持つ人が暮らす居住スペースも並行で運営されているのです。この日施設の案内をしてくださったのは、同施設ケアワーカーで介護の未来ナビゲーターの山口さん。平成23年に設立された比較的新しい「きじの里」のヒミツをたっぷりと教えてもらいました。


▲晴れた日は眺めも気持ちいい3階のデッキ。下を眺めれば子どもたちが元気いっぱい園内を駆け回る様子もみられます。
「きじの里」の基本方針は「0歳から100歳まで地域で共に暮らし続ける施設を目指して」。
施設の1階を保育園スペース、2・3階は高齢者施設の機能として、基本方針に沿った世代間交流が日常的に行われています。
お年寄りにとって子どもは元気の源に。子どもにとってお年寄りは、交流の中でおもいやりの心を学ぶきっかけになったりと、先生のような存在でもあるそうです。

▲きじの里のとっておきスペース(本格的なステンドグラスできじが描かれてます!)。もともとこの地域にはきじがいたそうで、施設のシンボルになっています。実は、右端の木の遊具で下に降りることができ、保育園スペースとつながっています。

▲先述した木の遊具に、大学生も入ってみました。つくりが精巧!
施設内では、放課後近所の小学生があつまる放課後児童クラブも実施されたり、周辺自治会と防災に関する連携を取っていたりと、この施設自体が地域の人にとって“なくてはならない存在”に。人口減少社会、こうした多機能的な高齢者施設はこれからも増えていきそうです。「きじの里」はまさに静岡県の未来の高齢者施設の形を表しているトップランナーとも言えそうです。
ちなみに、誰でも立ち寄れるカフェスペースも併設しており、近所の方が散歩のついでに利用する姿も定着してきているとのことでした。

▲施設訪問に参加した静岡時代編集部の河田弥歩(左)、小泉夏葉(右)。

▲「きじの里」ではたらく山口さんと、生活相談員の袴田さん(右)に、仕事の醍醐味を伺いました。
「きじの里」は、本当に明るくてゆとりある構造が印象的でした。(むしろ「私たちも住みたい」と思えるくらい雰囲気も良かったです)
こちらでケアワーカーとして働く、今回案内をしてくれた山口さんと、生活相談員として働く袴田さんに、いまのお仕事のやりがいや苦労について伺ったところ、「自分がやったさりげないケアを利用者さんが覚えていてくれて、ありがとうと声をかけてもらえた時は格別」「亡くなった利用者さんのご家族に感謝の言葉をいただき、自分だけでなく他の職員とも共有するときは感慨深い」と、人の人生に関わる仕事の喜びを教えてくださいました。一方で、「もちろん肉体的につかれることはあります」と率直なお話も。介護は利用者さんだけでなく、その家族との関わりもあったり、気を使う場面の多い仕事。たしかに大変さもありますが、でも仕事って、ラクしてできるものではないのではないでしょうか。気の使いどころは仕事の種類によっても違う気もしますし、一概に介護だから大変、というわけではないはず。
最後に、職員の山口さんから、わたしたち大学生向けにメッセージもいただきました。
「ぜひ若いうちから、福祉やお年寄りに対するイメージを具体的に持ってもらえたら嬉しいです。一緒に暮らしている人も少なくなってきているので、なかなか接点を探すのは難しいかもしれませんが、年のうんと離れた方から学ぶことは多いですよ。きじの里では、普段から見学に来てくれる方も受け入れていますので、気軽に声をかけてください」。
介護は誰しもがなんらかの形で関わる道です。静岡県の介護の現場をまずは体感し学んでみたいという方は、ぜひ手を上げて、少しでも自分ごととして関わる機会をつくってみてはいかがでしょうか?
・HP:http://kaigonavigator-shizuoka.jp/
・Facebook:「介護の未来ナビゲーター」で検索!
「介護の未来ナビゲーター」HPでは、介護人材に関する現状や介護のしごとをより詳しく知ることができます。
「人生の必修科目。大学生のための"さきどり介護学"」シリーズ
(2) 大学生の介護の現場訪問録〈晃の園編〉→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1460297.html
(3) 大学生の介護の現場訪問録〈ぬまづホーム編〉→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1461741.html
Updated:2015年03月25日
体感! 大学生の介護の現場訪問録(2)—ぬまづホーム編
静岡県の大学生が、いま・これからの“介護”を考える本特集。
これまでの静大フューチャーセンターでのセッションや、英和学院大・見平先生との対談を通じて、介護に関して普段から抱いているイメージが知らず知らずに定着しているものだと気づかされた。
また静岡県介護の未来ナビゲーターの介護職員のみなさんには、介護現場で“はたらく人”として自身の仕事の魅力についても教えてもらった。
そこで大学生が実際の介護の現場に赴き、話だけではわからなかった介護の本当の魅力や大変さ、イメージとは違う(?)現場の空気を感じてきました。
前回に引き続き、静岡大学教育サークル「飛翔」メンバーが、静岡県沼津市にある「ぬまづホーム」を訪問。交流では脳の前頭野・ワーキングメモリを鍛える絵本『ドコドコ』を用いて、お年寄りとの交流もはかりました。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

■訪問先:特別養護老人ホーム「ぬまづホーム」
スタッフ・小森優太さん(静岡県から委嘱された介護の未来ナビゲーター、写真左)
特別養護老人ホーム「ぬまづホーム」ではたらく。
大のおじいちゃん・おばあちゃん子だったという小森さん。大好きだった祖父母の介護経験から介護職に関心を持ち、20歳の頃、専門学校に入り直し勉強を重ねこの業界へ。
■訪問したのは:静岡大学教育サークル『飛翔』のみなさん(計4名)
将来、教員志望の学生が集まって、普段は“子どもにとって価値ある授業、“ふれあい”を研究・実践している。
介護施設訪問は、前回の「晃の園」に続き2回目。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■生活のなかにとけ込んだ“ケア”の実践
今回飛翔のみなさんが向かったのは、沼津市にある『ぬまづホーム』。施設自体は平成元年に建築され、当時は回廊式(廊下をぐるっと一周する形の施設構造)でしたが、平成12年から増改築を重ね、現在はユニット式のケアを行っています(ユニット式は、小さな区分けごとにケアを行うので、お年寄りと職員がより密に関わり合えるそうです)。まずは、職員で介護の未来ナビゲーターの小森さんに連れられて、広い施設をざっと見学へ。今回も随所に光る現場の“心づかい”を発見できました。


▲お風呂を見せてもらいました。明るい場所につくられ、中も広々とし、お年寄りが座る椅子や浴槽まわりにはたくさんの取手やバーが。

▲介護職員をサポートする器具もありました。よく聞く介護の3Kのうちの“キツい”も今は様々な工夫で軽減できるようになっています。

▲お年寄りが集まる場所には献立表が。季節に合わせた料理だけでなく、デザートのメニューにもこだわりが!(バレンタインが近いとチョコレート系のものだったり)
リハビリスペースやお風呂場に続く廊下で見かけたのは赤と青の足あとマーク。これは廊下を行き来する機会に足腰をしっかりと使った動きをして、自然とトレーニングができてしまうようにと貼られたもの。大学生だって、今から足腰を意識して歩かないとです……。


▲行きも帰りもながらトレーニングできちゃいます。やってみると結構しっかり足を踏み出す感覚が。
施設を一周したら、いよいよ大学生×お年寄りの交流会! 今回の飛翔メンバーは“とっておき”の道具を持ってきていました。それは『アタマげんき どこどこ』という絵本です(写真の学生が持っているもの)。『アタマげんき どこどこ』は、ページごとに指定したキャラクターを絵の中から探し出すなど、記憶する作業をたのしく行うための本。人間がものを記憶する際に使う脳の部分(ワーキングメモリ)を鍛える教材でもあるのです。



▲『どこどこ』を使ったレクリエーションははじめてだったという飛翔メンバーもいましたが、お年寄りのみなさんと一緒に熱中。またお年寄りだけでなく職員の方からも「この本いいね、うちにも欲しい」という声もあり大好評でした。

▲大盛り上がりだった交流時間。飛翔のみなさん、お年寄りのみなさんからもモテモテでした。(「また来てね!」のラブコールも)

改めて小森さんや職員の方と意見を交わしました。早朝勤務や夜勤も必須な介護職。
「正直なところ大変ではないですか?」とストレートな質問を投げかけた飛翔メンバーに対して「それが仕事でもあるし、何より利用者さんたちの笑顔が見れるのが嬉しいので、特別つらいということはない」と小森さん。
お給料事情を聞いても、特別高いわけでもなければ特別低いわけでもない。実際のところ生活は困っていないというお話でした。

▲ぬまづホームの一日が載っているパンフレット。季節ごとのレクリエーションも大切にされていました。
職員の方からは「介護の仕事って、こんなに知られていなかったんだなと感じました」という声も。現場からの情報発信に加え、外からも介護の現実とイメージのギャップを埋めていくことが必要なのではないでしょうか。
「信頼関係で成り立つ仕事」ともお話いただいた介護職には、きっと潜在的なファン、就職希望者もいるはず。大学生自身がその距離をどう埋めていったら良いのか、今後も様々なアイデアが必要かもしれません。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
◉特別養護老人ホーム「ぬまづホーム」
〒410-0822 静岡県沼津市下香貫猪沼981-2
TEL:055-934-1821
◉『介護の未来ナビゲーター』は静岡県内の若手介護職員が結集し、日々介護職にまつわる情報発信中。
今回お世話になった小森さんもそのおひとり。
静岡県の介護の現場について、もっと知りたいと思ったら、以下のリンク先も要チェックです!
静岡県『介護の未来ナビゲーター』
・HP:http://kaigonavigator-shizuoka.jp/
・Facebook:「介護の未来ナビゲーター」で検索!
Updated:2015年03月25日
体感! 大学生の介護の現場訪問録(1)—晃の園編
静岡県の大学生が、いま・これからの“介護”を考える本特集。
これまでの静大フューチャーセンターでのセッションや、英和学院大・見平先生との対談を通じて、介護に関して普段から抱いているイメージが知らず知らずに定着しているものだと気づかされた。
また静岡県介護の未来ナビゲーターの介護職員のみなさんには、介護現場で“はたらく人”として自身の仕事の魅力についても教えてもらった。
そこで大学生が実際の介護の現場に赴き、話だけではわからなかった介護の本当の魅力や大変さ、イメージとは違う(?)現場の空気を感じてきました。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■訪問先:特別養護老人ホーム『晃の園』
スタッフ・佐野貴之さん(静岡県から委嘱された介護の未来ナビゲーター、写真右から2人目)
特別養護老人ホーム「晃の園」ではたらく。
佐野さんのように、晃の園の職員のみなさんは決まったユニフォーム(制服)を着ていない。
これは、介護は特別視されるものではなくて、身近な生活の中にあるものとして捉えてもらい、利用者さんにも気持ちよく過ごしてもらうための工夫なんです。
■訪問したのは:静岡大学教育サークル『飛翔』のみなさん(計4名)
将来、教員志望の学生が集まって、普段は“子どもにとって価値ある授業、ふれあい”を研究・実践している。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■暗い? いや、むしろ明るい『暮らしの場』
飛翔のみなさんが向かったのは、静岡市葵区富沢にある『晃の園』。飛翔メンバーは教育学部の学生が中心となっており、介護実習経験者もいますが、介護の現場についてじっくり見学するのは初めてということでした。
まずは職員で介護の未来ナビゲーターの佐野さんに、施設を案内してもらいます。
▲ここは入居されている高齢者ひとりひとりの部屋が並ぶ廊下です。清潔感がありあたたかみのある雰囲気に訪れたこちらもほっとします。
▲施設の所々に、自由に使える休憩スペースが。利用者間や、職員とのコミュニケーションも弾みそうです。
『晃の園』は、入居型だけでなく、ショートステイ、デイサービスも展開。それぞれの利用者が過ごしやすいよう施設をエリアで区切っています。
施設の基本理念は、“尊厳を守り、ゆとりある生活をともにおくる”。
明るくゆったりとした施設内の雰囲気は、利用者視点にたった工夫によってつくられています。(季節ごとの飾り付けなど、手作りのあたたかみも感じられました)
▲伺ったのはクリスマス前。みなさんが行き交うスペースにも心づかいが。
今回せっかくの訪問ということで、飛翔メンバーと利用者とで折り紙を使った交流も実施。「鶴」をみんなで折りました。(大学生も鶴を折るのは久しぶり……)。「昔折ったけど、忘れちゃったわ」という方にも、大学生が一緒になって折るうちに完成。時間があっという間に過ぎてしまうほど、楽しい時間になりました。
▲初対面の大学生を笑顔で迎えてくれた利用者のみなさん。飛翔メンバーもすぐにとけ込み、折り紙交流も大盛況。
お年寄りとの交流後には、職員の佐野さんと栄養士の方も交えてのプチ座談会。施設訪問の感想や、職員への質問が交わされました。
▲「人の人生に関わり、必要としてもらえる仕事。利用者さんひとりひとりに対して丁寧に対応するためにも、職種をまたいだコミュニケーションも大切」と佐野さん。
今回の施設訪問を通じて、飛翔の岡山晃一郎さんは「利用者の方への微細な配慮に感動しました。入居者の個室スペースでは、利用者ごとに部屋がわかりやすいよう取っ手の質感を変えてあったり、目印になる飾りだったり、パッと見ただけでは気づかない工夫がたくさんあるんですね。あと何より、利用者さんも職員さんも笑顔の絶えない場所になっていて、仕事をする環境としても素敵な現場だなと思いました」。
将来、子どもたちに社会生活を教えていく立場となる飛翔メンバー。介護の現場やこれからについて、自らも当事者として考え、教えていきたいと話していました。静岡県の介護の未来をつくる種が、彼らから蒔かれることにも期待です。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
◉特別養護老人ホーム「晃の園」
〒421-1311
静岡県静岡市葵区富沢1542番地の39
TEL:054-270-1210
『介護の未来ナビゲーター』は静岡県内の若手介護職員が結集し、日々介護職にまつわる情報発信中。
今回お世話になった佐野さんもそのおひとり。
静岡県の介護の現場について、もっと知りたいと思ったら、以下のリンク先も要チェックです!
・HP:http://kaigonavigator-shizuoka.jp/
・Facebook:「介護の未来ナビゲーター」で検索!
Updated:2015年03月25日
静岡県の大学生が介護の未来を考える〜静大FC特別セッション〜
超高齢化社会に突入した日本。静岡県も例外ではなく、全県民に対する高齢者層の人口が比率が年々高まっている。高齢化の事実にともなって、介護の担い手不足が、ここ静岡県でも叫ばれています。しかし、介護の世界は「きつい・汚い・給料が安い=3K」というイメージがある。しかし、そのイメージは果たして本当なのでしょうか? 実際の介護職の現場をじっくり目にしたことはありますか? 現場で働く職員のみなさんが、日々、どんな思いでお年寄りと接しているかを知っていますか?
将来の国や地域の運営を考える上で、"介護"は重要なトピック。自分のそばにいる大切な人のため、誰もがいつかはむかえる老いについて考えてみませんか。
今回は、静岡大学FC(フューチャーセンター)に所属しているみなさんと、「10年後、静岡の介護の未来は明るいか」をテーマにセッションを行いました。介護知識ゼロからはじめる、大学生の介護学、開講です。

▲静岡大学FC:年代、職種も様々な人たちが対等な立場で対話し、地域課題について未来思考する場。
今回のファシリテーターは、静大人文社会科学部3年 古川美帆さんです(下段左から2人目)。
■自分が当事者になったとき、明るく介護に向き合いたい
介護のイメージはネガティブなもの? 介護は誰もが将来関わるだろうことも、大切な職業であることも分かります。でも、どうしてもネガティブイメージが先行してしまう……。そんな現状を変えようと静大FCで特別セッションを行いました。テーマは「静岡県の介護の未来」。大学生、一般参加者、介護職員の中村瑠美子さん・篠田徹也さん、県関係部局の方も参戦。白熱議論をお届けします!
■介護は3K? 楽しい?
それではセッションをはじめます! まず参加者の介護に対するイメージを聞いてみると、「大変そう」「低賃金」などやはりマイナスイメージばかり。一方、介護職員の中村さん・篠田さんは「やりがいがある」といった肯定的なご意見。「会話を重ねるごとに、段々とお年寄りの気持ちを理解できるようになるのが楽しいです」と中村さん。現場のリアルな声によると、介護職は「やりがいのある仕事」であり、大変だけど「楽しい仕事」なのだそうです。
■10年で2万人増やす? 静岡県の介護職事情をのぞいてみましょう!
静岡県の試算では、2025年には、現在の約1.5倍、約5万人の介護職員が必要になると予測されています。高齢化や平均寿命の延びにより、今後、介護需要が増加するのは明らかです。介護の担い手不足の対策として、県は「介護の未来ナビゲーター」を結成。県内介護施設で働く若手職員27名が介護職の魅力を発信します。主に若い世代に介護の仕事について関心を持ってもらうことが目的です。就職ガイダンスへも出展。中村さんと篠田さんもそのメンバーです。
介護の魅力をまず伝えたい対象は、大学生をはじめとした若い世代です。ただ、若い世代が現時点で介護にどう関与できるか分からないことも事実。参加学生の中には「曾祖母が離れた土地で要介護になった時、結局自分では何もできなかった」と語る人もいました。介護の必要最低限の知識を持っていれば、もっと何か出来たかもしれない。そう考えると現時点で既に、誰にとっても他人事ではないですよね。
▲介護の未来ナビゲーターのひとり、中村留美子さん。現場からのリアルな声で、私たちも介護の今をイメージしやすくなりました
・介護需要はさらに増加
・現在の静岡県の高齢化率は、約25.9%
・2025年までに、あと約2万人の介護職員が必要
・2035年には、およそ3人にひとりが高齢者と予測
▲セッション開始前は、「きつい」「汚い」「給料が安い」の3Kのイメージが濃厚。しかし、話し合いを進めていくうちに、
親の身体のことを考え、就職先を親元の近くに決めた学生もいました。
■10年後の静岡県の介護。どうなっていてほしい?
セッション開始から40分程、議論は10年後の静岡の「未来予想」に。まず介護職員が現状から増えなければ、10年後、約2万人もの人手不足になってしまう。いかに介護職への興味や就職率をあげるかが重要です。課題は「どんな介護事情だったら、介護の仕事をしたいか」。介護を明るく捉えられるのでしょうか?
議論に挙ったのは「職場の空気」の問題でした。例えば、介護食が美味しい・入居者はいつでも出かけることが出来る・毎日お風呂に入れる。入居者に関わることですが、清潔感や日常の贅沢感は働く人の気持ちを前向きにさせるはずです。
そして県民全員が介護サポーターになること。介護は家族内の問題になりがちですが、必要不可欠なのは地域コミュニティの理解と支えです。介護職の中でもホームヘルパーとして働く中村さんの「お年寄りの家にかかっている鍵をなくしたい。そのためにはもっと支える人が必要」という発言が印象的でした。地域コミュニティ全体が介護の担い手となったら、実現できるかもしれません。そうなれば介護職のイメージも変わり、さらなる就職率向上が期待できるはず。 静岡県に明るい介護を実現するためには、地域コミュニティの再編が必要不可欠ですね。
■より身近になっていく介護を先取りしていく
セッション終盤、参加学生からは「介護を明るく考えられるようになった」「介護FCを大学や企業、地域で定期的に行いたい」と前向きな声多数!
10年後、私達にとって介護はより身近になっていきます。今、どれだけ介護の実情や知識を先取りできるかが静岡の介護の未来の要となることを実感させられました。
それではいよいよ、セッション後の発表です。
(1)求めるものは「静岡らしさ」
静岡県の美味しい食材を使った介護食の開発や介護施設をオクシズなど静岡の自然あふれる場所につくります。過ごして楽しい・家族も会いに行きたい環境になること間違いなし!
(2)やるからには目指すはNo.1
介護は、遅かれ早かれ将来の自分自身や家族、大切な人たちに密接に関わってくることです。幸せに過ごしたいし、過ごしてもらいたい。静岡から始まる理想のモデルを目指す!
(3) ポイントその1「人づくり」
介護体験などを通し、中学生や高校生、大学生など10代、20代のうちから介護を自分事と捉えられるような人づくり。その積み重ねが明るい介護のコミュニティをつくります。
(4)ポイントその2「企業育成」
とにかく介護の世界は人手不足! 企業との介護食コラボ・企業のビジネスプランコンテストなど、県内企業の介護業への進出を促進。「介護職を目指す人を増やす」という狙いも!
(5) 3776人の介護サポーター
富士山にちなみ、3776人の介護サポーター(県民)・3776社の介護サポーター企業がいる静岡県を目指します。そうなれば県全体が施設そのもの! 地域コミュニティが変わる!
(6)大学生にできること現在/未来
介護の現状を知ることが第一歩。静岡らしさをいかに見出せるか、介護FCを大学・企業で展開! 大学生の短期インターンシップを全大学で必須に。介護職の3Kのイメージを払拭!
(7) 静岡の介護とは日常の贅沢である
「毎日お風呂に入れる」「お酒を飲める」「自由に出かけられる」「みんなに見守られて死ねる」。介護に求めるものは、ごく普通の日常です。鍵は⑤の見守りコミュニティ!
(8) 最終的には静岡の技術を世界へ!
最終目標は「静岡の介護を世界へ売る」ということ。県民全員が介護サポーター、若者の介護職への就職率向上、明るい地域コミュニティの再編、このノウハウを全世界へ届けます。
私たちの発表はいかがだったでしょうか?
静岡県の介護を家庭内の問題から地域ぐるみで支えられるものになったら、安心だし嬉しいですよね。介護・介護職についてもっと深く知りたい人は、以下のリンク先へ飛んでみてください!!
・Facebook:「介護の未来ナビゲーター」で検索!
「介護の未来ナビゲーター」HPでは、介護人材に関する現状や介護のしごとをより詳しく知ることができます。
「人生の必修科目。大学生のための"さきどり介護学"」シリーズ
(2) 大学生の介護の現場訪問録〈ぬまづホーム編〉→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1461741.html
(3) 大学生の介護の現場訪問録〈きじの里編〉→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1462111.html
Updated:2015年03月16日
伝説の卒業論文〜静岡県の卒論論文からみる、大学生の姿〜
大学時代とは「卒業論文」である。4年間の集大成である卒業論文には、大学生が何をどう問い、導きだしたが集約されているのだ。過去、同じように大学生であった人たちは、私とどこか違うのだろうか? 卒論をどう捉えていたんだろう? そもそも卒業論文ってなんだ?まさに今、卒業論文制作のまっただ中にいる本特集の編集長が、「卒業論文」の根本に迫る企画。今回は、静岡大学名誉教授・日本史の専門家の本多先生に、大学時代における卒論とその醍醐味を聞いた。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●本多隆成(ほんだたかしげ)先生
静岡大学 名誉教授。文学博士。専門は日本史。地域に根付いた歴史を研究され、主な研究テーマは東海地域史や徳川家康。1973年から静岡大学に勤務され、以後35年間多くの学生に教鞭を執ってきた。目標は「自分にしか書けない歴史の概説書を書くこと」。
■このお話をもっと深く掘り下げたいひとへ
本多隆成先生からのオススメ本!
有光友學『今川義元』吉川弘文館. 2008
本多隆成『定本徳川家康』吉川弘文館. 2010
【聞き手】
●鈴木りな
静岡大学教育学部4年。本特集の編集長。
普段は穏やかな人柄だが、場をしめなければいけないときは ハッキリとものを言う頼れる編集長。
自身が現在卒業論文制作のまっただ中!
●野村和輝
静岡大学経済学部4年。
静岡時代編集部の中でも古参の人。そして編集部唯一の貴重な男子部員。
(ときどき羽目を外すが)フォローがうまく、多くの取材をこなしている。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■今も昔も卒論へのひたむきな姿は変わらない
――私にとって卒業論文は、乗り越えなくてはならない大学時代の最終関門です。でも、そもそも卒論とは大学生にとってどんな存在なのでしょうか?
まず普段の講義で提出するレポートと卒業論文は、密度の点で大きく違いますよね。レポートが講義のまとめなどであるなら、卒論は学生が大学で学んだことの集大成です。大学の授業は、一年生のときは基礎的なものから始まり、二年生、三年生になるにつれて専門性が増していきます。その全部が卒論に反映されるというわけですから、卒論が勉強の積み重ねの末にあることがわかるでしょう。
やはり卒論に真面目に取り組めば、そのときのノウハウはどんな分野にも応用が利くものです。それは専門分野とは関係ない会社に就職した時もそうです。たとえば何かをリサーチするとき、調べ方は卒論を書くときに使った方法とそう変わらないことが多いです。私は静岡大学に勤めるようになってから35年間、合わせて455本の卒論を読んできました。
それでも、卒論の口頭試問で学生と向き合うと、毎回こっちまで緊張してしまいましたね。口頭試問が終わると、三年生までとは違って一段突き抜けたような、この子も一皮むけたなぁと感じていました。本人にも達成感がありますし、大学としても学生の成長を期待して卒論を課しているのではないかと思います。


——455本の卒論……。本多先生だけでも、それだけの数の卒論が静岡の大学社会に積み上げられてきたんですね。時代とともに、大学のあり方も変わってきましたが、静岡県の大学生や卒論に挑む姿勢にも変化があるのでしょうか? 大学の歴史や時代背景とともに教えてください。
1960~1970年代は学生運動が活発で、ベトナム戦争など大きな事件が世界各地で起こっていたこともあり、学生は社会情勢に対して大きな関心がありました。ですから、日本史の卒論も、百姓一揆をテーマにするなど闘争に関わるものがかなりみられたように感じます。今は学会などでも政治的なテーマは少なくなり、個人が好きなテーマで卒論を書き進めるようになりましたね。
学生そのものも、今と昔では違いがあります。センター試験(共通一次試験)導入前は、旧帝大をはじめとする一期校と、それ以外の二期校に国立大学の受験時期が分かれていました。静大は二期校だったのですが、当時、人文学部人文学科のような哲学・史学・文学がある学部は二期校では珍しく、一期校の文学部に落ちた学生が全国から静大人文学部に入学してきました。センター試験導入後は、一期校・二期校制が廃止され、学生に地域的な偏りが出て、静大も東海地域出身の学生が多数を占めるようになりました。
ただ、時代によって卒論のテーマや学生の様相が変わっても、卒論の意義に真剣に向き合っていく学生がいるのは、今も昔も変わりません。おかげで、論点や問題意識がしっかり認識された質の高い卒論に毎年のように出会うことができました。卒業後に研究者になり、私と同じ大学教員の道に進んだ学生も何人かいます。それは嬉しいことですね。

■後輩に引き継がれる卒業論文。それは、自身の成長の糧になる。
ーーいいお話ですね。私は大学の在り方が変わっていくなかで、卒論の在り方も変わってきているのではと思っていました。来年から就職活動が四年の春スタートになるなど、研究と就活との両立が大変になって、卒論が「こなす」ものに変わりつつあるのかなと。大学生の卒論・卒制から得られるものを、学生自身や社会が期待していないんじゃないかと思ってしまいます。
昔の就活も、春からスタートしていたんです。それでも学生はきちんと卒論と向き合っていました。当時のようになるだけで、心配いらないと思います。むしろ今は就活の時期が早いために、三年の後半から浮足立っている学生が多数見受けられますが、私はこれには感心しません。三年生は一番勉強しなければならない時期だと思っています。三年生は特に専門性の高いことを学びますから、そこを疎かにすると良い卒業論文は書けません。
これからの大学は、学生の数が減ることは避けられないでしょう。これは静岡に限らず全国的な現象ですね。このままいけば、私立の大学を中心につぶれるところも出てくるでしょう。学生が減ることで、選びさえしなければどこでも入れるような、大学全入時代にすでに突入しているのです。そうなると、学生自身の能力の低下につながり、卒論を満足に書けないような学生が実際に出てきていると思います。すると大学でも、卒業するのに卒論を課すところが少なくなっていくかもしれません。

――卒業論文の意義を考えると、あまり良いことではないかもしれませんね。どうしたら卒業論文・卒業制作に必死になる風習がこれからも残り続けるのでしょうか。
そうしたいのであれば、各大学で行わなければいけないのは、キャリア教育のような社会に出てから使えるような実践的な講義よりも、学部ごとの基礎・基本となる授業を丁寧に行っていくことです。活字の資料や論文などを読む訓練なども必要でしょう。
あとは、学生一人一人が、卒業論文や卒業制作を自身の成長のチャンスだという風に捉えられるかどうかですね。その姿を研究室などで後輩が目にして、憧れたり、刺激を受けたりすることで、卒論を書く意義を見出してくれれば、それが一番素晴らしいことでしょう。卒業論文は大学四年間の集大成で、完成までにはたくさんの過程があります。私の専門である日本史の場合、必要になれば古文書・原本などの史料を探さなければいけないこともあり、その点数はかなりの数になるでしょう。一つ一つの工程は地道で大変なものですが、それをくぐり抜けた学生はそれまでの学生とは一味違うわけです。私としては、ぜひ皆さんには卒論に挑戦してほしいですね。
(取材・文/野村和輝)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◉連続特集:静岡時代10月号(vol.36)『伝説の卒業論文』(1)
【伝説の卒業論文〜卒論史にみる、静岡県大学生史〜】
●本多隆成先生
静岡大学 名誉教授。文学博士。専門は日本史。地域に根付いた歴史を研究され、主な研究テーマは東海地域史や徳川家康。1973年から静岡大学に勤務され、以後35年間多くの学生に教鞭を執ってきた。目標は「自分にしか書けない歴史の概説書を書くこと」。
■このお話をもっと深く掘り下げたいひとへ
本多隆成先生からのオススメ本!
有光友學『今川義元』吉川弘文館. 2008
本多隆成『定本徳川家康』吉川弘文館. 2010
【聞き手】
●鈴木りな
静岡大学教育学部4年。本特集の編集長。
普段は穏やかな人柄だが、場をしめなければいけないときは ハッキリとものを言う頼れる編集長。
自身が現在卒業論文制作のまっただ中!
●野村和輝
静岡大学経済学部4年。
静岡時代編集部の中でも古参の人。そして編集部唯一の貴重な男子部員。
(ときどき羽目を外すが)フォローがうまく、多くの取材をこなしている。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Updated:2015年03月03日
「短所・長所を掘り返せ! 熱海市発・地のもの勝負の地域活性論」【後編】
ロケ支援によって地元を盛り上げ話題を呼ぶ、熱海市役所職員・山田久貴さんに学ぶ“これからの地域のつくり方”。
後編は、山田さんが職員になり始めから抱えていたまちの課題からその解決にいたるまでと、静岡県全体の地域活性化についてをお送りします。最初は思うようにいかず(もちろん何ごともそうですが)、頭を抱えていた山田さんがとったのは、短所を長所に転換する逆転の発想法でした。静岡県に暮らす私たちも、改めて自分のいる地域のこと・まちのことを振り返ってみませんか?
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●山田久貴(やまだひさたか)さん
熱海市役所 観光推進室 ロケ支援担当。熱海生まれ、熱海育ちで地元を知り尽くしているロケ誘致のスペシャリスト。
熱海市のHP内にあるWebページ「ADさん、いらっしゃい!」には“365日、24時間連絡OK”を大々的に掲げており、文字どおり昼夜問わず撮影関係者の問い合わせに応え、今年度は対応ロケ数100件を超える予定。
単にロケ地探し、ロケ地で必要な撮影交渉、申請だけでなく、ロケ隊の宿泊施設や打ち上げの下準備までスピーディーに行われるため、業界関係者からの信頼も厚く、親しみをこめて『現地のAD』と讃えられている。現職に就いて今年4年目を迎える。
・熱海市「ADさん、いらっしゃい!」
http://www.city.atami.shizuoka.jp/page.php?p_id=970
【聞き手】
●渡邊なみほ(わたなべなみほ)
静岡大学・教育学部美術専修3年。
取材前から「神対応の秘訣って何!?」と、山田さんの業務が気になって仕方がなかった。自身も公務員志望のせいか実際のインタビューでは、まちづくり、仕事への姿勢など、勉強になったところがたくさんあったのだとか。
・Facebook静岡未来
https://www.facebook.com/shizuoka.mirai
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
◉「短所・長所を掘り返せ! 熱海市発・地のもの勝負の地域活性論」【前編】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1435454.html
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■「短所も活かし尽くす、地域活性化」
――山田さんが今のお仕事をこなしていく上で、感じている課題はありますか。
(山田さん):大きな課題というのは特に感じてはいませんね。
しかし、強いてあげるのであれば熱海市は駅前の中心街ばかりが賑わっているという点です。だから、熱海市全体を活性化させるためにはそれぞれの地域の持つポテンシャルを引き出す必要があると考えているんです。そこが案外難しいところなんですよ。
この仕事が成功したのは、さきほども言ったように熱海市が元々もっている特性が良かったことが理由のひとつにあります。東京からのアクセスが良いし、多種多様なロケ地がある。山あり海あり島ありで。ホテル群や廃墟みたいなものもある。
——熱海には何度か行ったことがありますが、無造作なまちのつくりが印象に残りましたね。
そのごちゃごちゃ感が悪かったんですけど、逆の発想でね。おもちゃ箱をひっくり返したようないろいろなものがあるという様にとらえたんです。ディズニーランドもそうじゃないですか。いろんなものがごちゃごちゃあるから行っていて飽きないっていう。
熱海が元から持つ特性を活かしながら、どこに行っても賑わいがあるよう町全体を活性化することができたら、と考えていますね。

▲ロケ地案内2ヶ所目は、現在は廃校となっている市内の中学校に行きました。こちらの場所も、撮影にはよく使われるそうです。

▲この学校にある教室のいくつかは、山田さん自身でリフォーム(!)されたそうです。スゴイ!

▲教室内にある机は山田さんが新しく用意したもの。廃材として捨てられるものを修理して活用しています。
――なるほど。では今後、山田さんが挑戦していきたことはありますか?
(山田さん):最終目標としては、熱海市をハリウッドみたいな街にしたいんです!
そもそも、熱海市は”観光地”と言われているんですけど、本来は”保養地”だったんです。でもいつしか観光地として認識されるようになってしまって。熱海を訪れたお客様と、認識のすれ違いが発生してしまうんですよね。
「観光地」となると必然的に観るものを要求されます。しかし元々保養地だった熱海を訪れたお客様は「何も観るもの無いじゃん!」という状況になってしまうんです。
だから、解決策として熱海市にロケ隊をじゃんじゃん呼ぼうってなりました。ロケを増やすことによってハリウッドみたいな、いつもどこかでロケが行われているという街にしたいんですよ。キーポイントは都内で撮れない風景。例えば、アメリカのカントリーウエスタン時代の町並みとかって絶対都内には無いですからね。都内にないものを見に多くのお客様が熱海にきてくれるはずですし。熱海独自に出せる風景を生み出していきたいと考えています。
ロケが増えると、観光客のみなさんにとって観る対象が撮影の風景となっていく。そうすると自然と街も賑わうじゃないですか。
芸能人・有名人の方が見られるというだけで、熱海に対するイメージが確実にぐーんと上がりますし。そのプラスのイメージがどんどん口コミで広がっていくことで、地域活性化につながるんじゃないかなと思いますね。
■まちのもつイメージを、市民に強く焼きつける
(山田さん):また、まちの中でロケが行われる風景は、熱海市の住民のみなさんにとっても誇りになると思っています。「自分の住んでいる街はいつも撮影が行われている」って。
昔は「自分たちの街は何も無い」っていうネガティブな気持ちを住民のみなさんは持っていたんじゃないかと思うんです。でも、こうしてロケが頻繁に行われることでその気持ちがポジティブな気持ちに変化してきますよね。
最近は、住民の方の雰囲気も良くなってきたんじゃないかなと感じます。私がやっていることに対しての市民の方々のご理解も高まってきているし。理解が得られると、協力体制が出来てきますよね。もともと協力的な街ではあったんですけど。良い方へ進んでいるなと実感します。
■「どれぐらい相手にインパクトを与えられるかが勝負」

(山田さん):全国各地でフィルムコミッショナーといった所は多々あるんですけど、こういった活動やるとなると、市の職員がやるのが一番強いんですよ。
まずは無償で動けるという事。他のところに依頼をすると時間単位で有償になってしまいます。
もうひとつは、申請が通りやすいところです。ロケでは公共の施設を使うことがかなり多くなります。しかし私(市の職員)がトップへ伝えて、各部局に広まれば申請がさっと済むんですよ。
またロケを行う際には、必ず現場周辺に暮らすお宅にロケについての文書を投函します(ポスティング)。地域の町内会長や警察へ挨拶に行き周囲に了承をもらう目的がありますが、その際に「市役所」となると信用がありますよね。
だからこそ、市の職員が一番適職なのではないかなと思います。やり始めた当初は意識していなかったんですけど、やっていくうちに段々と感じてきましたね。
一番重要なのは、意外性を突くということです。
私自身、24時間対応できるのは苦ではないんですが、「役所の職員が24時間年中無休で対応できる」という点で結構注目を浴びるんですよね。
公務員がやるからインパクトがより強く残るんですよ。意外性が大切ですね。
——確かに。私もはじめて山田さんの紹介文を拝見したときに、「24時間対応ってどういうことなの?」と良い意味でのひっかかりがありました。また山田さん自身、生まれも育ちも熱海という経歴があるので、市の職員として地域のことは熟知していそうですね。
(山田さん)そうですね。この土地に精通しているから出来ることもたくさんあります。それも私の強みですし。仕事のようで仕事でない、仕事を上回っていくような感じですね。ライフワークみたいなものなので、お金もあまり関係ありません。
最初は自分の子どもも小さく、なかなか思うように活動ができなかったんですけど。最近は子どもの手が離れたので、自由にやらせてもらっています(笑)

――市民のみなさんの理解はもちろんですが、職場のみなさんの理解も大切ですよね。
(山田さん):正直、動き始めた当初の周囲の反応は無関心というか、「よくやるなぁ」といった感じだったんです。しかし今では実績も出てきましたし、市民のみなさんの良い反応も得られました。ですので、トップも応援をしてくれています。認められたって感じですね。
やはり、職場の理解が無いと仕事はやりづらいじゃないですか。そのためには実績を上げることが大切ですよね。実績が信頼につながっていくこともありますし。
――これから未来をつくっていく私たち世代に対して何かヒントというか、こうしたら良いという山田さんからのご意見はありますか?
(山田さん):それは、コミュニケーション能力ですね。
人に話しかけたりするのはもちろん、指導を受けたり、叱られたりすること等、どんな方からも様々な形でコミュニケーションをとってもらえる関係性を、築き上げられるようになってほしいです。

コミュニケーション能力を培うためには、色々なことに積極的に携わっていくことが重要です。学生だけで集うのではなくて、社会の現場で働く人たちと接していってもらいたいですね。いろんなところに顔を出して、様々な年代、背景をもった人と顔を合わせて対話することで育まれるのではないかなと思います。
また、「コスト意識」は重要になってきますね。
コスト意識とは、いわゆる自分が企業からもらったお給料を何倍にして返すことができるのかなということです。自分が民間企業に勤めていた頃、ずっと考えさせられてきた経験で、そう思います。
年齢関係なく、やろうと思えばなんだって出来ますからね。物怖じせず、常に大きい気持ちでいると良いですよ。
「将来、何々になろう」ってゴールを定めてしまったらそこで終了してしまいます。ですので色々な物事を体験、経験して、自分にあった適正っていうのをしっかり見定めてほしいですね。転職だってどんどんしたって良いし。むしろ転職できるバイタリティがあった方が良いと思いますね。将来どうなるかは、誰にもわかりません。だからこそ広い意味で「自分はなんだってできる!」という気持ちを持ち続けてほしいです。
■「新しいものを、むやみにつくらない」
――今後、熱海市の活性化が他の地域にも派生していくと良いですよね。山田さんは、県内の地域活性化について考えることはありますか?
(山田さん):やはり「もともと地域の持っているポテンシャルを活かすこと」。これに尽きるんじゃないでしょうか。実際に熱海市が観光地として成功したのも、まちが持つ豊富な素材を活かすことができているからなのではないかと思っています。
うまく活かすことができれば、情報は口コミで全国へと広まっていき、各地から人が訪れるようになりますよね。そこから人口が増えていくことだって望めます。
ただ、どこもかしこも観光地にするっていうのは大きな間違いだと私は考えています。
主幹産業=ポテンシャルだと考えているんですが、観光地なら観光地、農業なら農業など、その土地の持つ魅力を土台にした上で、盛り上げることが大事だと思います。そもそも、その土地に合っているから産業地帯になっていたりしますしね。必然的に雇用も高まりますし、観光客も増えていく。
余談ですが、私たちもそうですよね。人それぞれ性格は違いますし、チャームポイントや欠点があったりする。その中で長所を引き立たせたり、もっと魅力的になろうと思ったときには、自分の素材が必ず元となっていますもんね。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
◉シリーズ第2弾:静岡「未来の教科書」
「短所・長所を掘り返せ! 熱海市発・地のもの勝負の地域活性論」
【前編】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1435454.html
●山田久貴(やまだひさたか)さん
熱海市役所 観光推進室 ロケ支援担当。熱海生まれ、熱海育ちで地元を知り尽くしているロケ誘致のスペシャリスト。
熱海市のHP内にあるWebページ「ADさん、いらっしゃい!」には“365日、24時間連絡OK”を大々的に掲げており、文字どおり昼夜問わず撮影関係者の問い合わせに応え、今年度は対応ロケ数100件を超える予定。
単にロケ地探し、ロケ地で必要な撮影交渉、申請だけでなく、ロケ隊の宿泊施設や打ち上げの下準備までスピーディーに行われるため、業界関係者からの信頼も厚く、親しみをこめて『現地のAD』と讃えられている。現職に就いて今年4年目を迎える。
・熱海市「ADさん、いらっしゃい!」
http://www.city.atami.shizuoka.jp/page.php?p_id=970
【聞き手】
●渡邊なみほ(わたなべなみほ)
静岡大学・教育学部美術専修3年。
取材前から「神対応の秘訣って何!?」と、山田さんの業務が気になって仕方がなかった。自身も公務員志望のせいか実際のインタビューでは、まちづくり、仕事への姿勢など、勉強になったところがたくさんあったのだとか。
・Facebook静岡未来
https://www.facebook.com/shizuoka.mirai
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
こちらもどうぞ!
◉静岡「未来の教科書」シリーズ第1弾
【実践! 静岡ブランドの実力 ~アメーラ・トマト】
一年中、高価格&高品質で、その味と甘みが注目・支持されている「アメーラ・トマト」。
そのブランディング戦略に迫ったインタビューです。トマト生産者の稲吉正博さんと、アメーラのブランドづくりを行う静岡県立大学経営情報学部の岩崎邦彦教授らのチームのお話をお聞きしました。
・前編: http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1380415.html
・中編: http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1381066.html
・後編: http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1381082.html
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Updated:2015年01月30日
「短所・長所を掘り返せ! 熱海市発・地のもの勝負の地域活性論」【前編】
静岡大学・教育学部美術専修3年の渡邉なみほです。
静岡県内の様々な事例から、地域のこれからを考えるためのヒントを学ぶ『静岡「未来の教科書」』企画。今回は、現在“ロケ地のメッカ”として新たなまちの盛り上がりを作り出している熱海市に注目しました。お話を伺ったのは、熱海市役所職員にしてロケ誘致・支援のスペシャリスト・山田久貴(やまだひさたか)さん。
熱海市のシティプロモーションの一環として立ち上がったプロジェクト『ADさん、いらっしゃい!』をひとりで担当する山田さんは、ここ数年、同市のロケ実績を飛躍的にのばす原動力となってきました。市民が誇れる“いつもどこかでロケが行われているまち”は、一体どのように生み出されているのでしょうか? そのヒミツに迫ります。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●山田久貴(やまだひさたか)さん
熱海市役所 観光推進室 ロケ支援担当。熱海生まれ、熱海育ちで地元を知り尽くしているロケ誘致のスペシャリスト。
熱海市のHP内にあるWebページ「ADさん、いらっしゃい!」には“365日、24時間連絡OK”を大々的に掲げており、文字どおり昼夜問わず撮影関係者の問い合わせに応え、今年度は対応ロケ数100件を超える予定。
単にロケ地探し、ロケ地で必要な撮影交渉、申請だけでなく、ロケ隊の宿泊施設や打ち上げの下準備までスピーディーに行われるため、業界関係者からの信頼も厚く、親しみをこめて『現地のAD』と讃えられている。現職に就いて今年4年目を迎える。
・熱海市「ADさん、いらっしゃい!」
http://www.city.atami.shizuoka.jp/page.php?p_id=970
【聞き手】
●渡邊なみほ
静岡大学・教育学部美術専修3年。
取材前から「神対応の秘訣って何!?」と、山田さんの業務が気になって仕方がなかった。自身も公務員志望のせいか実際のインタビューでは、まちづくり、仕事への姿勢など、勉強になったところがたくさんあったのだとか。
◉Facebook静岡未来
https://www.facebook.com/shizuoka.mirai
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■地元に眠っていた十数億円の可能性。
――熱海市のいち職員である山田さんが、熱海市内でのロケ誘致、サポートを専門業務として行う最初のきっかけは何だったんでしょうか?
(山田さん):熱海独自の誘致活動をはじめたきっかけは、一本のテレビ番組でした。平成23年5月のことです。
私は元々民間企業に勤めていて、中途採用枠で35歳の時に熱海市役所に入りました。当時は「イベント業務担当」ということで観光課に配属され、熱海市に関するイベントの企画や運営、PR活動をしていたんですが、業務を続けていく内に、”大都市圏以外の地方でイベントをしても、広報活動が上手くできない”ということに気が付いて。広報イベントに関しては若干限界を感じていました。
その後、商工業系の課へ配属されたときに、一本のバラエティ番組のオファーがあったんです。私は、番組の担当ディレクターさんや制作部の方たちとロケハンをしました。ロケ地の良さや自分にできることを必死に伝えていく中で、逆にこちらから提案もしたりして。先方の要望を聞いているだけではなくて、むしろ、やや入り込んでやりとりをしていたと思います。でもね、そうしていたら、なんと熱海紹介の撮影枠が増えたんですよ。
——嬉しいことですね。
そうなんです。そこで私は気が付いんたんです。ロケにやってくる方々の撮影しやすい環境を整えたり、また熱海を選んでもらうための売り込みを行えば、やってくるロケ隊の数は増えるはずって。私自身熱海市生まれ熱海育ちでして、長い間、どうやったら熱海市にたくさんのお客さんが来てくれるかな、魅力が伝わるのかな、という課題意識があったのですが、テレビ番組はその点、うってつけの広報素材となりました。
テレビコマーシャルを流すとなると莫大な費用がかかりますが、番組サイドから紹介をしていただく形なら、お金は全くかからないんですよね。それでも広告効果として、年間トータルすれば十数億円になるので、これくらい効率のいい広報って無いんです。
■「一番目立たなくて、一番大変な人のパートナー」として、
“ロケ地・熱海”の価値を高める

――撮影関係者からは「現地のAD(アシスタント・ディレクター)」とも呼ばれていますよね。具体的には、どういったサポートをされているんでしょうか?
(山田さん):ドラマやバラエティなどのテレビ番組や映画、CM、ミュージックビデオ撮影のサポートをしています。また、撮影隊の方々に要求されるロケーションの提案や撮影に使えそうな場所の開拓など。私1人で、年中無休、24時間いつでも電話やメールで対応していますよ。
先方がこちらの提案したロケ地に興味を持って下されば、次はロケハン(ロケーションハンティング)と呼ばれる下見をします。撮影をされる方が現場を実際に見て、使えるかどうかを判断するんです。電話や写真だけでは伝わらない状況もたくさんありますしね。その際も私は撮影隊の方々に同行して、ロケ地の案内をします。
ロケハンの際には、撮影隊の方に細々とした説明もしていきます。例えば、廃校がロケ地となった場合。その敷地に大きなマイクロバスが通ることはできるのか、演者さんが着替えたりメイクしたりできる部屋の準備はできるのか、電源はしっかり確保できるのか。などの説明ですね。
ロケ地の情報を先方が持ち帰っていざ決定となったら、最後にメインロケハンが行われます。監督やカメラマン、装飾担当の方やメイクさんなど、メイン関係者の方たちが数十人ほどでいらっしゃるので、引き続き同行・ご案内します。メインロケハンを終えると、撮影はほぼ決定されますね。
また私は同時進行で、実際に撮影をするとなった時の下準備をします。例えば、ロケ地との交渉や時間調整、車両の数に応じた駐車場の確保、さらには昼食や夕食のロケ弁の手配もします。
そういった現場のコーディネートというか、調整ですね。ロケ当日には、離れた場所から撮影の様子を見守って、急な変更やトラブルに対応できるようにしています。
――まるでADが本職かのような、そんな細かいところまで携わっているんですね…!驚きです。想像していたより何倍もハードな仕事で大変なんじゃないでしょうか。
(山田さん):そうなんです。意外とハードですよ(笑)
でも実際は、撮影現場のADさんや制作部のみなさんがやっていることなんですよね。その方々の方がずっと大変だと思います。
撮影スタッフやキャストの皆さんは、日本全国を休み無し移動しっぱなしなわけですからね。撮影関係者の皆さんに比べたら、自分なんてまだまだ楽な方です。
私の仕事は、ADさんや制作担当さんの一番大変な、いわゆる影の部分の調整役の方のサポートなんです。あまり目立たないし光の当たらない、でも一番大変な仕事をする。
そんな方たちのパートナーとして動くことで、より現場が活発になるような気がするんですよね。全体が上手くいくような良い雰囲気を感じることがあるんです。

■ロケ隊対応の先には、最大顧客の熱海市民がいる
(山田さん):おかげさまで2014年度は、4月~11月の間で約70本のロケが熱海市で行われました。今年度3月までに、おそらく100本超えも見えてきました。個人的にも、そのくらいの仕事をこなせるくらいが丁度いいんですよね。受け身よりは攻める方がはるかに面白いですし。
結構せっかちなところもあって、仕事を溜めたくはないので、どんどん片付けていく方が合っていて。先方が「えっ!もう出来たんですか!?」と驚かれるぐらいを心がけてます。「なるべく早く」が自分のモットーです。
相手のニーズにスピーディーに、100%に近い形で応えていくこと。例えどんな困難な要求であっても決してできないとは言いません。「こうすればできますよ」といった感じで違う角度からの視点で提案をさせていただくようにしています。
相手に提案をしたり、自ら開拓したりするような、能動的に動いていくことが好きな性格なんですね。そうすることで、次の仕事に繋がっていくこともありますし、受けより攻めの方が面白いんです。
――自分から能動的に動き、相手の要求を先回りして考え対応していくんですね。山田さんはもともと、相手を気遣ったりサポートするのが得意だったのでしょうか?
(山田さん):実は、最初はこういった仕事は得意ではなかったんです。ロケの経験も皆無でしたし。でも経験が無いなりに、お客様のニーズを考慮して常にアンテナを張っていくように努力はしました。現在も相手の気持ちを察知して、臨機応変に対応をしていくようにしています。また私は熱海市職員なので、最終的なお客様は熱海市民のみなさんです。その最終的なお客様をしあわせにするための前段的なお客様は、ADさんとか制作担当の方になるんですよね。だからこそ、そのお客様が求めるものをどれだけこちらが提供していけるかが、この仕事の肝になってくるのだと思います。
――そもそも、どうして山田さんは一人でこの活動をしているのですか?もっと人数がいた方が効率は良さそうなのに…。
(山田さん):私はあえて、一人でこの仕事をやっているんですよね。理由は、一人だけのコストでどれだけの効果が生み出せるかにかけているからです。
みんなで意見を出し合ってやるっていうのも良いですけれど、提案だけで終わってしまうこともしばしばあるじゃないですか。意見は多く出たけれど、じゃあ次に誰が実行するの?となってしまう。実行できない状況をなるべく作らないために、自分だけでやってみようと思ったんです。

▲取材当日は、山田さんの案内でロケに使われた現場を訪れました。写真は、後楽園ホテル地下にある旧・下水処理場。

▲取材前には、とある番組のロケが実際に行われたそうです。非日常的な世界観をだす撮影には重宝されているのだとか。

■「“神対応”の秘訣は相手のニーズにとことん応えていくこと」
――ひとりでの活動にはそのような考えが基づいていたんですね。でも、大変で困ったこと、立ち止まってしまったこともあったのではないでしょうか?
(山田さん)そうですね。たくさんあります。常に何らかの問題がありますが、それを解決することが相手(制作側、市民、事業者)への信頼を深めるこになっています。一言で言えば「顧客重視」ですね。
お客様が求めるものにはとことん対応しますが、反対に好まない物・嫌がるものは避けていく。自分の生活のための仕事じゃなくて、まずはお客様重視の仕事という感じです。みなさんいろいろな仕事をされていると思いますが、それはどの仕事も共通しているのではないでしょうか。

→「短所・長所を掘り返せ! 熱海市発・地のもの勝負の地域活性論」【後編】へつづきます。
http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1435457.html
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
こちらもどうぞ!
◉静岡「未来の教科書」シリーズ第1弾
【実践! 静岡ブランドの実力 ~アメーラ・トマト】
一年中、高価格&高品質で、その味と甘みが注目・支持されている「アメーラ・トマト」。
そのブランディング戦略に迫ったインタビューです。トマト生産者の稲吉正博さんと、アメーラのブランドづくりを行う静岡県立大学経営情報学部の岩崎邦彦教授らのチームのお話をお聞きしました。
・前編: http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1380415.html
・中編: http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1381066.html
・後編: http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1381082.html
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Updated:2015年01月30日
10年後、静岡の介護の未来は明るいか?【特別編】〜ただものでないお年寄りたち〜
静岡県の試算によると、2025年には約5万人(現在の約1.5倍)もの介護職員が必要になると予測されている。超高齢社会に突入し、介護需要はさらに増加。一方で介護のイメージは「大変そう」「低賃金」などマイナスイメージがつきまとう。正直、きっとそれは仕事の内容じゃなくて、お年寄りと向き合うのが怖くて不安なんだと思う。
「お年寄りは単なるお年寄りではなく、人生財産」。そう語るのは清水区三保にある特別養護老人ホーム 羽衣の園 室長 市川さん。介護の仕事を通して、施設のお年寄りから多くの学びややりがいをもらっていると言う。毎年冬、羽衣の園が行う「はぴはぴサンタプロジェクト」は、そんな「お年寄りのファンをつくりたい」という気持ちからはじまったものだ。
羽衣の園・生活相談室室長の市川晃さん、ケアマネージャー・伊藤直子さん、ぬいぐるみ作家 金森美也子さんに聞く、介護のリアル。お年寄りとの関わり方はもちろん、介護の現場を深く掘り下げていく中で、三保の土地の歴史と介護のつながりが見えてきた。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
◉市川晃(いちかわあきら)さん(写真左奥)
特別養護老人ホーム【羽衣の園】生活相談室・室長。
「お年寄りが生活しやすい、暮らしやすい環境とは何か」を常に考えて行動する方。福祉・介護に限らず、
幅広くアンテナをはり、”これだ!”と思えば、熱いアプローチで人や情報を取り入れます。
◉伊藤直子(いとうなおこ)さん(写真左)
特別養護老人ホーム 羽衣の園 ケアマネージャー。
ケアマネ—ジャー8年目。住み心地の良い空間で、お年寄りの方が自分らしく生活できるような環境づくりを目指している。
◉金森美也子(かなもりみやこ)さん
ぬいぐるみ作家。
大学卒業後、生活雑貨やぬいぐるみの商品企画の仕事に携わる。1998年よりフリーの活動を始め、
定期的に個展やワークショップを開く。はぴはぴサンタプロジェクトには毎年参加し、
お年寄りたちのぬいぐるみ制作を手伝っている。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■私たちは、お年寄りのファンをつくりたい!
——羽衣の園では施設のお年寄りのことを「人生財産」と呼んでいるそうですね。
「人生財産」とはどういうことですか?
(市川晃さん:以下 市川さん)個人や団体の持っているモノ・技術・知識・情報・経験・ノウハウ・考え方・哲学といったものを指します。もともとこれまで日本には、自身の資本や財産を提供し、将来に渡って次世代を支援するという美しい文化がありました。代表的なのは能楽での継承方法です。能楽師は、先人達から芸の技や所作といった具体的な実践方法、使用する道具類、そして考え方や思考、哲学といった自身のあらゆる経験や人生の財産を次の世代へ伝達していくといった文化を何百年も実践してきました。その考え方や継承方法は、いまもなお次世代へ受け継がれています。
羽衣の園をはじめ施設で生活されているご高齢の方は、本当に様々な経験をされています。戦争や戦後の体験、これまでの生涯……その経験・知見の一つひとつが「人生財産」であって、お年寄りもまた「人生財産」なんですよ。羽衣の園では、これまで様々な経験をされてきたお年寄りが次世代へ伝えていきたいことを伝え、地域で次世代を育てていく・お年寄りの生きがいをつくることが大事だと考えています。施設のお年寄りの生涯を「人生財産」として展示するといった取り組みもしています。実際に介護の仕事をしていても、お年寄りから教えてもらうことは本当に多いですよ。
——例えばどんなことですか?
(市川さん)仕事を通して、私たちは目に見えない色々なプレゼントをもらっているんです。介護の仕事は「休みがなくて大変そう」と言われるけれど、実際に現場で働いている自分にとっては、お年寄りのみなさんと楽しく接していられるんです。私自身、それは何故だろう?と考えたとき、理由はお年寄りのみなさんからの「ありがとう」という言葉でした。「自分が必要とされている」と感じます。同時に日々、自分が成長していると実感するので、一般の方たちにもお年寄りと接する機会を増やしていきたいですね。
今月23日に行う「はぴはぴサンタプロジェクト」は、そういった日々感じるお年寄りへの感謝の気持ちと「お年寄りのファンをつくりたい」「もっと好きになってもらいたい」という願いからはじまったものなんです。
——もうすでに市川さんたちはお年寄りのファンなんですね。“はぴはぴサンタプロジェクト”は、お年寄りが地域の力になったり人との交流も視野に入っている印象を受けたのですが、具体的にどんなプロジェクトなのでしょうか?
(市川さん)施設のお年寄りが、「ありがとう」と言ってもらえるようないいことをした地域の子どもたちにクリスマスプレゼントを届けにいくというものです。今年で3回目になります。コンセプトは「良いことをしたら、良いことが返ってくる」。つまり、ペイ・フォワード(=恩送り)です。
子どもたちは家族やお友達から「ありがとう」と言われたエピソードをハガキに書いて、はぴはぴサンタ(羽衣の園で生活するお年寄り)に報告します。そのエピソードを受けとった「おばあちゃんサンタ」がプレゼントとなるシロクマのぬいぐるみをつくります。全て手作りです。そうして12月23日に「おじいちゃんサンタ」が子どもたちのお家にプレゼントを届けにいくんですよ。
——子どもたちとお年寄りとの間に、「ペイ・フォワード」が生まれる仕組みなんですね。
ところで、ぬいぐるみ作家の金森さんは去年から実際にワークショップに参加し、おばあちゃんサンタのぬいぐるみ制作を手伝っているそうですね。携わりはじめたきっかけは何ですか?
(金森美也子さん:以下、金森さん)はい。市川さんに誘われて参加をしました。プロジェクトのコンセプトや活動自体、素晴らしいなあと思ったんです。
初めてのワークショップでは、お寝間着をきて参加しているおばあちゃんたちに驚いてしまいました。正直、この状況でうまく教えられるのかな、と心配になったんです。でも、実際手を動かすと「実は昔(縫い物を)やっていたのよね」というおばあちゃんたちが意外に多くて。みなさん、割とさっさか作業をしていました。
——お年寄りの方と接する中で、金森さんが感じたことや得られたものはありましたか?
(金森さん)たくさんありました。初めてぬいぐるみを作る人は、やはり首が曲がったり手が左右非対称になったりするんです。でも、実際に完成したものはそれぞれ味があるんですよね。
私はぬいぐるみを作り慣れているので、きれいになってしまうのが逆につまらないなと思っているのですが、お年寄りのみなさんが作るぬいぐるみは、目の付け所や雰囲気などが逆に面白みがあって良いんです。だから今では、もうみなさんの自由に作ってもらっています。
そうそう。逆に私が縫い方を教えてもらうこともあって、得したなあとか、嬉しい気持ちになりました。なにより作業を終えたあとの充実感を得られるのが、良い経験になっていますよ。他の仕事を断っても「これはやりたい」と思えるほど、楽しいお仕事なんです。
■多世代交流の広がる環境づくりを。
——年齢も背景も違う人たちが交流しながら、同じ思いのもとに集まって何か行うというのは素敵ですね。子どもたちに何を伝えたいですか?
(市川さん)まずは喜んでもらえると嬉しいです。ぜひ、お年寄りのファンになってほしいなあ。でも実際問題、現在は少子高齢化が深刻になっていて、「自分だけがよければいい」という風潮があるじゃないですか。その中で、自分が何かして「ありがとう」と言ってもらえることにより、「ありがとう」が返ってくる。幸せの連鎖が地域に生まれれば、結果的に自分が住みやすかったり、豊かな地域になっていくと思いますし、その連鎖に自分が関わっているんだよ、ということを子どもたちに感じてもらいたいですね。
また、子どもたちがプロジェクトに参加することそのものが「施設のお年寄りを支えている」ということを伝えたいですね。そして、私たち介護スタッフのやりがいにも繋げられたら良いなと思います。施設にいる私たちはどうしても、「支援する人」「支援される人」という意識に偏ってしまいます。 でも、はぴはぴサンタプロジェクトは地域や子どもたちにも幸せの連鎖を生むものです。 施設のお年寄りだけではなく、地域や子どもたちを支えている一員だということを、スタッフ同士共有することができたらと考えています。
(伊藤直子さん:以下、伊藤さん)ぬいぐるみを作っているときも、プロジェクトメンバー以外のスタッフが「何やっているんだろう」とのぞきにきてくれたりして、そういう小さな積み重ねがどんどん大きくなっていったら良いですね。
実は、このプロジェクトには皆さんと同じ世代の医療専門学校の学生さんも来てくれているんですよ。その中で、お年寄りと一緒にぬいぐるみだけではなく、他のものも作りたいねって話していて、古い着物をリメイクしたコースターも作りました。
(市川さん)イベントに限らず、他にも施設を改修するときに、静岡福祉大学のゼミ生に参加してもらったことがありました。僕たちは社会福祉法人なので、介護サービスだけを提供するのではなく、社会や地域の課題を解決していきたいと思っています。そのためには「よそ者、若者、馬鹿者」という3要素が必要だとよく言われるんですが。若い人たちが世の中や地域を変えていく力をもっているんだよということで、施設の中にも新しい発想や表現の仕方が欲しいなと感じます。ただ楽器を演奏しにくるだけでも良いし、本を読みにくるだけでも良いと思います。
(伊藤さん)きっかけは小さなことでいいです。別にボランティアではなくても、今回のプロジェクトのような「何か楽しいことやっているな」という視点で来てもらえるとよいと思います。例えば参加したワークショップの過程で、お年寄りのみなさんと触れ合ってもらって、金森先生もおっしゃっていた「感じてもらう」というのが一番良いかなと。たぶん話してみたら、「うちのおばあちゃん・おじいちゃんと全然変わらないじゃん」という感覚もあると思うんですよね。私たちスタッフも、一般の方が気軽に訪れられるような施設だということを発信し続けていきたいと思います。
——お年寄りや子どもたちとの多世代交流の輪に大学生も気軽に入っていける仕組みをつくりたいですね。市川さんはさきほど「地域の課題」とおっしゃいましたが、羽衣の園さんの捉える地域の課題は何なのでしょうか?
(市川さん)羽衣の園のある三保半島は昔から造船業で栄えてきた歴史があるんです。造船で流れてきた人には、地縁や血縁、社縁のない人がたくさんいます。羽衣の園にも、無縁で来られる方がたくさんいるんですね。これは、つながりの希薄化につながってくるんですよ。私たちは、その無縁社会が一番課題だと考えています。ですので、ゆるやかなつながる場所として「学老所」を園内と地域につくらせてもらいました。おそらく、三保半島以外にも同じような課題をもっている地域はたくさんあるのではないでしょうか?
——だからこそ、このプロジェクトだけではなく施設全体、地域全体で掲げている「支え合いの連鎖」につながるんですね。
(市川さん)はい。小さいことでも「ありがとう」という思い合いが「あたり前」という環境にしたい。そういう環境で子どもが育てば、自分らしく生きていけるし、生きていくなかで自分だけがいいというのではなく、人との繋がりのなかで生きていける。
今、入居されているお年寄りのみなさんはそういう時代の中で生きてきました。お互いに協力し合わなくては、生きて来られなかった人たちです。だからこそ、お年寄りの持っている貴重な人生財産を後世に伝えていきたいですね。壮大な目標ですが、まずは「小さなありがとう」を繰り返し、段々と増えていってくれたらなと思っています(了)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
◉はぴはぴサンタプロジェクト
2014年12月23日(火) 10:00〜 スタート
→ http://www.hagoromono-sono.jp/ssk_wp/?p=93
多世代交流、また地域交流の一環として2年前よりスタートしました。
おじいちゃん・おばあちゃんがサンタクロースとなり、地域の子どもたちに手作りのぬいぐるみ(クリスマスプレゼント)を届けにいく、この季節にピッタリな素敵なイベントです。当日は静岡福祉医療専門学校、常葉学園橘高等学校、清水国際高等学校の生徒さんたちもお手伝いにきてくれます。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
◉特別養護老人ホーム「羽衣の園」
〒424-0902
静岡県静岡市清水区折戸5丁目18-36
TEL:054-335-3353
◉HP:http://www.hagoromono-sono.jp
◉市川晃(いちかわあきら)さん
特別養護老人ホーム【羽衣の園】生活相談室・室長。
「お年寄りが生活しやすい、暮らしやすい環境とは何か」を常に考えて行動する方。福祉・介護に限らず、
幅広くアンテナをはり、”これだ!”と思えば、熱いアプローチで人や情報を取り入れます。
◉伊藤直子(いとうなおこ)さん
特別養護老人ホーム 羽衣の園 ケアマネージャー。
ケアマネ—ジャー8年目。住み心地の良い空間で、お年寄りの方が自分らしく生活できるような環境づくりを目指している。
◉金森美也子(かなもりみやこ)さん
ぬいぐるみ作家。
大学卒業後、生活雑貨やぬいぐるみの商品企画の仕事に携わる。1998年よりフリーの活動を始め、
定期的に個展やワークショップを開く。はぴはぴサンタプロジェクトには毎年参加し、
お年寄りたちのぬいぐるみ制作を手伝っている。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Updated:2014年12月22日
実践! 静岡ブランドの実力 ~アメーラ・トマト【後編】〜
わたしたちと静岡県の未来のつくり方=教科書をつくる連載企画第三回。
「つくれば売れる」という高糖度トマト、"アメーラ"。その鍵となったのは、トマト生産者の稲吉正博さんとアメーラのブランドづくりを行う静岡県立大学経営情報学部の岩崎邦彦教授らのチームでした。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●岩崎邦彦(いわさきくにひこ)先生
1964年生まれ。静岡県立大学経営情報学部教授・地域経営研究センター長・学長補佐。
●稲吉正博(いなよしまさひろ)さん
トマト生産者。「アメーラ」「アメーラ・ルビンズ」のブランド管理、生産支援、指導管理を行う株式会社サン・ファーマーズ代表取締役。
【聞き手】
●山田瑞己(やまだみずき)さん
静岡県立大学食品栄養科学部栄養生命科学科3年生
●服部由実(はっとりゆみ)
静岡時代所属。本記事エディター。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■弱点? それとも強み?
(岩崎先生)ルビンズには事前のマーケットリサーチで「皮がかたい」というご意見があった。では、皮がかたいというのは弱点か? と。ちょっと視点を変えて、「歯ごたえがある」という風に考えると、「歯ごたえがある」というのは日本人にとってプラスじゃないですか。だから、ルビンズのキャッチコピーは「パキッという歯ごたえが新しい」。歯ごたえを「売り」にしようと考えたんです。商品とマーケティングの表現の両輪で進めている。「歯ごたえがある」ということで認識すると、誰も「皮がかたい」と言わない。逆に「歯ごたえが魅力的」となる。そういった伝え方とか捉え方を考えながらやっています。
(山田さん)ここでも着眼点が野菜としてのトマトとは違いますね。フルーツだと「歯ごたえがある」というのはプラスになりますよね。
(岩崎先生)中小企業に多いのは、景気が悪いとか、農業はだめだとか、外のせいにしてしまって、自分がチャレンジしないことが多いんですよね。稲吉さんみたいに、実際に着実に行動されているのが魅力でもありますし、本当に教わることも多いですね。だから、アメーラのブランドづくりについて書いたこの本(岩崎邦彦著『小さな会社を強くするブランドづくりの教科書(日本経済新聞社刊)』)でも稲吉さんの言葉というのは鍵かっこ付きで出てきたりしますので。そういう意味でもいい連携をさせていただいています。
■学生の活動にもブランディングの発想を
(岩崎先生)静岡時代の雑誌のブランディングというのもあると思うんですよ。共通するところもあるかもしれないし。「静岡時代」と聞いて、どんな絵が浮かんでくるかとか、どんなコンテンツが浮かんでくるかとか。イメージが浮かんでくれば勝ちですよ。ターゲットとなる人とね。私は静岡産業大学に非常勤講師として行っているんですけど、静岡時代、置いてあるのを見つけましたよ。この(最新号35号のSNAPに登場している)戸田書店の長澤さんにも以前お会いしました。
(静岡時代)ありがとうございます。静岡時代のイメージについてアンケートを取ると結構はっきり出るのは、……これ自分たちで言うとちょっとアレなんですけど、「知的」「デキる大学生の読み物」みたいなもので。これは「とんがり」といえるかもしれません。実はこれは創刊当時からやや狙っていたことで、全国的に見てみても、学生雑誌で「エリート感」みたいなものを前面に出したものって、大学の機関誌くらいしかない。逆に大学生活の「楽しさ」とか、あとはまちづくりやキャリア系みたいなものは多いんですが。だとしたら、そこがPRを考える上でのフックになるかな、とお話聞きながら自己分析してました。どういうコピーでやろうかな……。

(静岡時代)ところで、こちらの山田さんは、おとなりの山梨県出身で、先ほど述べた通り大学生ですけど、山梨県のワインを静岡で紹介する「ROUTE52」というワインバーを経営されています。日々、山梨県・静岡県とは、とか、静岡県の学生とは何かとか、そういう問いに触れてると思うんです。だから、静岡時代と山田さんはこうして一緒に記事をつくったり共同作業することが最近多いんですけど、いろいろ自分たちのことが見えてくるね、という話をよくしてるんです。
(岩崎先生)すごいですよね。
(稲吉さん)学生さんなんですよね。社会人をやって、もう一度大学へ来たという感じ? それとも、そもそも学生?
(山田さん)私は今、静岡県立大学に通っているんですけど、その前に3年くらい静岡大学に通っている時期がありまして。静大を途中でやめて、県大を大学入試で入って、いま栄養学を学んでいます。
(稲吉さん)頭いいね。
(山田さん)いえいえ……。ちなみに、「ROUTE52」の名前は、静岡市の清水区と山梨県の甲府市を結ぶ国道52号線からとりました。52号線はもとを辿ればいわゆる甲州道です。武田信玄とかの時代から静岡と山梨をふるくからつないできた道ですね。静岡の塩を山梨に送り、山梨の産品を静岡に送った。そういうストーリーと、ワインバーを通して静岡山梨両県をつなぎたいという店のあり方を重ねています。
(岩崎先生)いいですね。
(稲吉さん)すごいな~。
■一生離れない客をどれだけ掴むか
(静岡時代)ちょうど、富士山世界遺産登録ということもあって、静岡県と山梨県がひとつの地域としてコラボレーションしていきましょうよ、という時期なので、山田さんって、そういう中で両県の架け橋の象徴的なキャラクターになんじゃないか、と。そこで今、静岡時代のウェブ版や静岡県庁のソーシャルメディアで連載などしていただいていて、そこから話を広げていこうかと、今回の取材もお願いしたんです。
(山田さん)わたしとしても、自分の店の今後の戦略を勉強してしまおうと……。何かアドバイスをいただけませんか?
(岩崎先生)山田さん自身のブランディングでもあり、お店のブランディングでもあると。10人中10人のお客さんを惹きつけることを考えないで、一人ひとりを大切に、リピートしてもらう。一生離れない客をどれだけ掴むかですよね。お客さんがいない時に、「買ってください」とワインを半額にしたりしてしまうと、半額のときは来るけど、それ以外は来ないお客さんが増えるので。いかに好き嫌いの勝負をするか。好きな人を増やす。先ほども言ったように、一本のものさしで測るような、価格の安さで勝負をするのではなくて、好きな人(ファン)を増やしていくことが大切になってくるだろうなと思いますね。
ルビンズを稲吉さんがやられたときは、東京のホテルのお洒落なバーとかで使ってもらう、そんな利用シーンを頭にイメージしていました。
(山田さん)そうですよね。ルビンズって利用シーンがすぐに見えるんですよね。どんなシチュエーションで食べているかとか、子供に食べさせるとかもちょっとお洒落なお母さんが食べさせているイメージがありますもんね。
(岩崎先生)是非、食べてくださいね。独自性がある。卸値を生産者の方が決めているトマトは多分世の中にないと思います。
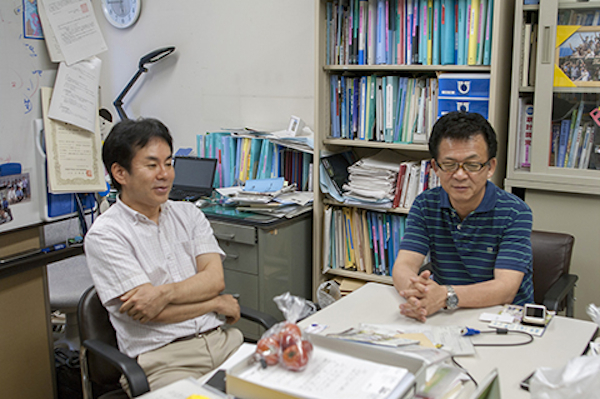
■絶対に安売りしない
(稲吉さん)ルビンズは市場へ価格を設定して、卸しているんですよ。量が多い時も少ない時も。普通だと取引される量が多いと市場の価格は下がるでしょう? 逆に少ないと上がるじゃないですか。それをやらないってことが、ひとつ市場の方は受け入れがたい点がひとつ。
もうひとつあって、ヘタの話なんですが、「このヘタのないトマトを売るのか?」と。最初は、市場のプロの方から、「こんなもの、売れないだろ。クズだろ」と言われたんです。そこで「ヘタってなんで必要なんでしょうかね?」と、そういうところからスタートしていって。でも相手もヘタは「鮮度感」なのだという。「じゃあ、ヘタがついていないと鮮度が分からないんですかね?」という話をしていたら、新宿の伊勢丹のバイヤーの方が「やってみますよ。全部うちに売ってください」と言われて。そう言われた瞬間に市場の人が途端に態度を変えて「いや、全部は無理です。他にも販売します」って。
(静岡時代)一触即発?
(稲吉さん)全部持ってかれて、約束してしまうと、他に売れなくなるじゃないですか。市場の人も「自分じゃ売れないな」と思っていたら「全部持ってく」と言われたら……。その辺がやっぱり市場の人とプロのバイヤーとの駆け引きなんだなと目の当りにみていて。
(山田さん)常識がひっくりかえった瞬間なのは確かですね。
(稲吉さん)結局、今はルビンズが全部で2億円弱の売り上げなんですね。市場の人が言うには、ルビンズゴールドが少なすぎると。今は5パーセントしかないですね。何パーセントくらい要るんでしょうか、と聞くと2割だと。ゴールドを増やすだけで四千万の売り上げになる可能性がある。そうするとビジネスがまた大きくなっていく。ただ、ゴールドを増やすとなると栽培面積を増やさなくてはならないので、ゴールドを増やすとルビンズが減ってしまう。それは市場としては困る。ということは、ゴールドを増やす分だけまともに売り上げが伸びていくということじゃないですか。やっぱりそのブランドができて、マーケティングがうまく機能すれば、値段を下げなくても売れていくんですよ。
(山田さん)そうか。ブランドづくりは「農業」を“続ける”ためにも必要なことなのかもしれない。
■「買っていただかなくて結構です」
(稲吉さん)まあそれはやっぱり農家の側もね、ビジネスに長けないといけない。例えば「(商品が)この辺の地域ですごく人気があるんだけど」というと他の業者さんが来て、「いや、うちはこちらの方でもっとたくさんお客をかかえているので、ぜひ直接取引をお願いします」と。そういうのにみんな飛びついて行ってしまうと、お客さん同士が競合したりしてしまう。お客さんを選ぶというのは相当やっぱり「買わなくて結構です」という言い方をしなくちゃいけないわけだから、こちら側も大変ですよね。ただ、それをやっていかないと、ブランドを維持できないのかなと。
(山田さん)どのように「売ってくれるか」で商品のイメージは大きく変わりますからね。
(稲吉さん)よくあるんですよ。「たくさん売れます」って。よくよく聞いていくと安売りスーパーだったり。「そこじゃあ、結構です」と。「市場で買ってください」と。正規で買ってもらって、安く売ってもらっている分には文句いえませんけどね。やっぱり先生が「安く売っちゃいけない。安売りは絶対だめ」と言われているので、自分たちのためにもね、やっぱり安く売らないように。
(岩崎先生)安い価格でなく、高い「価値」を提供する。これがマーケティングの発想です。アメーラトマトだけじゃなくてね。安さで競争すると、勝つ人もいますけど、結局ほとんどが「負けて」しまう。勝ち負けの勝負になって、消耗戦になってしまう。いいものを、それぞれ個性的なものをつくると。それが多様性につながっていく。だから、いまいろんなトマトが出来ている。単なる価格の勝負だけだったら、カゴメのこくみトマトしかないとか、消費者にとってもよくないですよね。競争でなく、共存です。
(稲吉さん)僕らも、なかなか最近、新しい品目が出てこないんですよ。美味しくなくてはいけないので。世界中のトマトをいろいろと試しているんですよ。
■ブランドは"継続"でつくられる

(山田さん)そうやって、品質や安売りじゃない価値の継続的な追求が積み重なって「歴史」ができてゆくんでしょうね。わたしは山梨のワインを静岡で紹介しているわけですけど、山梨のワインは、ブドウの品種やワインの品質を改良し続けると同時に、古くからワイナリーに川端康成みたいな文豪や文化人を招聘、あるいはパトロンになったりして権威化やイメージ戦略を行い、長い時間をかけてブランディングしてきたものです。
それを今、静岡でなんとか広げたいというところで。ただ、いずれは静岡の食べ物やいいところを自分の出身の山梨に持ち帰って広げたいというのが最終的な目標なんです。わたし、静岡も好きなので。
(岩崎先生)山田くん、いいですね。わたしはお酒弱いので、ワインはあまり飲まないんですけど、ただ山梨に行って、グレイスだったかな、美味しい、いいワインを飲んだらあまり酔わなくて、びっくりして、いいなと思いましたよ。ぜひ広めていただきたいですね。
(山田さん)本当ですか。嬉しいです。がんばります。
(静岡時代)きょうのお話はこの静岡県庁と一緒に運営している「静岡未来」のプロジェクトの戦略としてもすごく参考になりました。
(岩崎先生)アメーラの戦略を100パーセント真似するということでなく、自分なりに創意工夫して、アレンジしていけば参考になるところはたくさんあると思います。実際に、このアメーラの話は全国各地でお話をさせていただく機会があって、全然違う業種の方とかが参考になると言ってくださるので。
山田くんのお店については、特に食に関するところなので、ヒントはあると思います。あとはそれを実行していけば、いいと思います。
(山田さん・静岡時代)ありがとうございました。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
——編集後記——
アメーラの社外ブレーンについてのお話がありましたが、社外ブレーンのとのコラボレーションにおいて大事なポイントは5つあるのだそうです(岩崎邦彦著『小さな会社を強くするブランドづくりの教科書(日本経済新聞社刊)』より)。
①企業内に連携のハブとなる人材がいること
②ブレーンと生産者の間に信頼関係があること
③ブレーンと生産者の間にWIN-WINの関係が構築できること
④ブレーンにまかせっきりにせずともに考える姿勢があること
⑤商品そのものや組織自体にブレーンを惹きつける魅力があること
見てゆくと、①~⑤がうまいこと手順になっているんですね。①プロジェクトは多岐に渡るので、ハブの人材がいないとブレーンもバラバラになってしまいがちです。②信頼関係はハブとなる「誰か」を介して涵養される。③お互いの信頼関係があれば相互にいいことがあるように考えるようになる。④信頼関係は自立した大人同士でなければ維持できない。ブレーンに頼りっきりにならずに専門の違うお互いがアイデアを出しあうと、それは刺激になって飽きずに楽しい。⑤楽しいとどんどんのめり込んでゆく……。
かのマルセル・モースは社会学の古典である「贈与論」のなかで、「交換」が人間の社会を構築していると述べています。交換は誰かから誰かへの「贈与」によって開始されるということ、贈与を受けた者は贈与者に「負債感」を感じ、それは贈与を受けた者が誰かに対して「別の贈与」を行うことでしか解消できないのだと。
静岡県は、本文中でもふれられているように、ちゃんといいものをもっていると思います。ものづくりも、環境も。もちろん、大学社会にもいいものはたくさんあると思います。モースの論に従うなら、そういう「いいもの」をしっかりと社会的な文脈にあてはめて有用性や魅力をプレゼンテーションして、ちゃんと他所の誰かに贈与していかないと、交換の社会に「タダ乗り」している事実と直面して負債感に押しつぶされてしまうか、社会の外側に押しやられてしまう。
昨今の静岡県の人口流出の問題も、あるいは「静岡県が社会の外側に押しやられつつある」ことを示しているのかもしれません。ブランディングの戦略や技法とは、そういうふうにならないためのガイドラインのようなものなんだなと思いました。自分が持っているものや価値を誰かに「プレゼント」したいと考えた時に、その意思が、届けたい人に届くようにするために押さえておく手続き。
わたしたちにもできるでしょうか。少なくとも、稲吉さんたちは積極的に外に出て、自分たちが知らないけれど「必要」とかんがえる知識を集めて、実践して、成果を出した上で、そのメソッドを外部に「輸出」して、それも成果を出している。このような繰り返しが、いずれ周囲の「静岡県を見る目」を変えるのだと思います。わたしたちも静岡未来などを通してそういうことをしたいと思ったのです。「先輩」につづこう! ということです。
さて、岩崎先生と稲吉さんのアメーラトマトの話はこれでおしまいですが、これを機会に、静岡県の未来未来のつくり方=教科書をつくる本連載は続きます。
次回のインタビューもぜひ、お楽しみに。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
◉静岡「未来の教科書」
《実践! 静岡ブランドの実力 ~アメーラ・トマト》
●岩崎邦彦(いわさきくにひこ)先生
1964年生まれ。静岡県立大学経営情報学部教授・地域経営研究センター長・学長補佐。
上智大学経済学部卒業、上智大学大学院経済学研究科後期課程単位取得。
国民金融公庫、東京都庁、長崎大学経済学部助教授などを経て現職。
主な著書に『小さな会社を強くするブランドづくりの教科書』(日本経済新聞社刊)※、『小が大を超えるマーケティングの法則』(日本経済新聞社刊)、『スモールビジネス・マーケティング-小規模を強みに変えるマーケティング・プログラム』(中央経済社)、『緑茶のマーケティング-“緑茶ビジネス”から“リラックス・ビジネス”へ』(農文協)など。
※『小さな会社を強くするブランドづくりの教科書』(日本経済新聞社刊)はアメーラを題材に、小さな組織が大きなブランドをつくるための実践理論がわかりやすく書かれています。さらに詳しく知りたい方はこちらへ → http://www.amazon.co.jp/dp/4532319056/ref=cm_sw_r_tw_dp_53g0tb187CEGA
●稲吉正博(いなよしまさひろ)さん
トマト生産者。「アメーラ」「アメーラ・ルビンズ」のブランド管理、生産支援、指導管理を行う株式会社サン・ファーマーズ代表取締役。アメーラは日経MJ「ブランド評価」第1位(2009)や、ベジフルサミット「おいしいトマト」第1位(2007)に輝くなど高い評価を得ている。
アメーラは公式通販ショップで購入することも可能 → https://www.amela-shop.com/
【聞き手】
●山田瑞己(やまだみずき)さん
静岡県立大学食品栄養科学部栄養生命科学科3年生
1989年、母の実家がある静岡県沼津市に生まれ、父の実家がある山梨県塩山市で育ち、現在、静岡県で食品栄養学を学ぶ。近年静岡にワインバーが増えているが、山梨県産ワインが飲める場所が少ないことを悲しく思い、「山梨県産ワインが飲める店をつくろう」と一念発起。Wine Cafe ROUTE52を出店する。
住所:静岡県藤枝市大東町442
☎:054-637-0670
●服部由実(はっとりゆみ)
静岡時代編集部。本企画・記事のエディター。現在、静岡時代10月号(最新号)が発行中です!
静岡県内の大学、書店、図書館などで配布しています(PDFでも読めます)→ http://www.shizuokajidai.net
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Updated:2014年12月12日
実践! 静岡ブランドの実力 ~アメーラ・トマト【中編】〜
わたしたちと静岡県の未来のつくり方=教科書をつくる連載企画第二回。
「つくれば売れる」という高糖度トマト、"アメーラ"。その鍵となったのは、トマト生産者の稲吉正博さんとアメーラのブランドづくりを行う静岡県立大学経営情報学部の岩崎邦彦教授らのチームでした。第二回目より稲吉さんも合流。アメーラの非常に精緻なブランディング戦略を、より深く掘り下げていきます。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
●岩崎邦彦(いわさきくにひこ)先生
静岡県立大学経営情報学部教授・地域経営研究センター長・学長補佐。
●稲吉正博(いなよしまさひろ)さん
トマト生産者。「アメーラ」「アメーラ・ルビンズ」のブランド管理、生産支援、指導管理を行う株式会社サン・ファーマーズ代表取締役。
【聞き手】
●山田瑞己(やまだみずき)さん
静岡県立大学食品栄養科学部栄養生命科学科3年生。
●服部由実(はっとりゆみ)
静岡時代所属。本記事エディター。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

▲サンファーマーズ・稲吉さんがここから合流です。おみやげにアメーラをいただきました。おいしかった!
(後日、調理していただきました https://twitter.com/shizuokajidai/status/486144943849607168 )
■静岡県から輸出される“ブランドづくりのメソッド”
(岩崎先生)アメーラで実践していることそのものは、トマト以外でもイチゴもそうですし、地域のマーケティングにも利用できます。最近は、東日本大震災被災地域の水産物が苦戦していますが、その地域のブランドづくりでも、アメーラの事例を発信しています。被災地の気仙沼市役所と連携したり、キリンの「絆プロジェクト」という復興地域の再生活動の一端として、ブランドづくりを生産者の方々と一緒に考えたりしている。ですから、稲吉さんをはじめサンファーマーズのみなさんがされていることは、単にトマトだけでなくて、いろいろな分野のブランドづくりに活用できるわけですね。
昔はブランドというと、宣伝費がなくてはできない、テレビCMがないとできないと思われていた。ただ、強いブランドというのは、口コミ(※1)で広がっていくし、パブリシティとかね、記事で広がっていく。口コミにしても、新聞記事にしてもお金がかかりませんよね。口コミは人から人へ伝わっていくもので、非常に強いメディアなんです。実際、稲吉さん、あまり広告宣伝費の予算というのはほとんど使っていないですよね(アメーラの売上高に占める広告宣伝費率は0.01% 岩崎邦彦著『小さな会社を強くするブランドづくりの教科書(日本経済新聞社刊)』・218ページ)。デザインとかパッケージとかは力を入れてやっていますけど。いわゆるテレビCMとかラジオCMとかはやっていませんよね。ただ全国に知られるようになってきて、高い評価をもらっているというのは、小さい企業でも戦略性をもってやれば、大手に匹敵するような強いブランドをつくることができる。大手と同じではなくて、完全に逆張りをいくようなブランドをね。
(※1)口コミでのブランドづくりにおいては、口コミのタネ(=ネタ)があると、消費者は自分の気に入ったブランドを他者に伝えやすい。「アメーラ」では、名前の由来が静岡弁の「甘いでしょ」であることや、アメーラが糖度や栄養度が凝縮しているため水に沈むこと、木村拓哉さんが紅白歌合戦の舞台袖でルビンズを食べたことなどは口コミのネタになっている。〈小さな会社を強くするブランドづくりの教科書・227p〉
■私自身がアメーラファン
(岩崎先生)私がアメーラのマーケティングをやらせていただいているのも、子どもの頃からトマトが大好きで。トマトパスタが大好きなんですけど、アメーラトマトでつくるパスタはめちゃくちゃ美味いんですね。稲吉さんの周りにはいろいろなブレーンがいて、マーケィングは私がやらせていただいていますけど、デザイナーのブレーンとか食の専門家とか弁護士とかいっらしゃるんですけど、みんなアメーラが好きな人。やっぱり美味しいし、本物ですよね。ですから、最高品質を目指すというアメーラの方向性に共感してやっているので、ビジネスでやっているわけではないし、単に研究材料としてやっているのではない。私はトマト、毎日トマト食べても平気ですね。アメーラルビンズも静鉄ストアで買っていますからね。私は「アメーラファン」ですから、そのいいものをつくる生産者のトップが稲吉さんで、稲吉さんの前向きなチャレンジがこういったブランドをつくっていると。
■ブランド力があるから、大ブランドに選ばれる
(岩崎先生)もう販売終了してしまいましたけど、ローソンの今年(2014年)の夏コレクションでアメーラトマトをトッピングしたトマトとチーズのスイーツを販売したんです。
□ローソン2014夏コレクション・トマトとチーズのスイーツ(アメーラトマトトッピング)
http://www.lawson.co.jp/recommend/uchicafe/column/0049.html
(稲吉さん)食べました?
(岩崎先生)食べましたよ。
(稲吉さん)僕も食べましたけど、美味しかったですよね。
だんだんよくなってきてますね(笑)。値段も高くなったけど。
(岩崎先生)コンビニで400円をこえるスイーツですよ?アメーラが目指しているのは最高品質。ブランドづくりにおいても高級感を大事にしていますからね。
(稲吉さん)でも、確か最初は安かったですよね。300円ぐらいで、イチゴに負けてたんですよ。とうとう400円こえたんだな、と。値段に僕も「やった」と思いましたね。最初は3切れとかすごく少なかったアメーラも、5切れになりましたしね(昨年2013年のローソン夏コレクション「アメーラトマトとチーズのスイーツ」は280円)。
(岩崎先生)信じられないのが、ムースのうえに生のトマトがのっているんですよ? そんなデザート信じられないでしょ? ローソンがアメーラというブランドを使ってくれるというのは、アメーラのブランド力を認めていただいたということだと思いますし。
ヤマザキのランチパックでもアメーラを使ってくれるのも、ブランド力を評価してくれたからだろうと。単に美味しいだけでは使わないですよね。ブランドを現在進行形でどんどん磨いていこうと努力してきた。そういう意味で、ある程度成果はでていると思いますし、消費者や市場の評価は高まっていると感じています。
■“アメーラのパスタ”っておしゃれな感じ
(山田さん)どこのスーパーでも、アメーラトマトはちょっと高級なトマトとして売られていますもんね。
(稲吉さん)5、6年前は、松屋にはあったけど、松坂屋にはないね、とかあったけど、今は銀座の高島屋とか三越にも置いてあります。
(山田さん)京都のレストランでアメーラトマトの入った冷製パスタを食べました。
(稲吉さん)京都にも出てますよね。
(岩崎先生)アメーラにはブランド力があるので、シェフの方もメニューに使ってくださるんですよ。アメーラのパスタってなんとなくお洒落な感じもするじゃないですか。語源はね、静岡弁の「甘えーら」ですけど。カタカナで書いているのは、イタリアっぽい響きがするとか、お洒落なイメージがあるとか。外国人の方もお洒落なイメージを持たれて、音もいいので。ネーミングは、ブランドをつくるうえで品質ともに重要になってきますからね。「アメーラ」という個性的な名前で、且つ高級感のある名前は非常にブランドづくりにおいて力になっていると思います。

■口コミにしやすい言い回しを考えてカタログを作っている
(稲吉さん)ただ、デザイナーさんにお金を払ってつけていただいたものですからね。それを言っておかないと。農家のダジャレで出来ている名前ってたくさんあるじゃないですか(笑)。実はアメーラもそう思われがちですけど、ちゃんとこう、科学的にね、プロがコピーライティングをしているんです。岩崎先生の影響もあって、口コミにしやすい言い回しを考えながらカタログなどをつくっているので、割と口コミしやすいです。「一言でいうとなに?」と聞かれたときに、答えるものはもう既にカタログとかそういうものに書いておく。それで覚えてしまえば、すっとしゃれべれる。答えやすいということでね。それもすごくマーケィング的に考えられている。
(岩崎先生)マーケティングにここまで力を入れている生産者の方は非常に少ないですよね。農業をされている方も、みんな言葉ではブランドは大切だと言います。では具体的になにをやっているかというと、何もやってないことも多いんですよ。ただ、稲吉さんやサンファーマーズの場合には、そのためにこういうパッケージをつくりましょう、ラベルにこだわりましょうとか、口コミを生み出すカタログを作りましょうとか、実際やっているということですよね。行動して成果を出しているというところがすごい。
■「野菜ではない、フルーツである。アメーラ・ルビンズ」

(岩崎先生)頭の中に絵が描けないとか、イメージが浮かばないとだめで、例えば、このアメーラ・ルビンズはとても個性的な形で、これを一回見ると二度と忘れないと思うんですよ。ネーミングも、「ルビー」と「ビーンズ」ということで「ルビンズ」と分かりやすいですよね。四文字の短い名前で覚えやすい。長い名前ですと、口コミしにくいということもありますので、固有名詞で、且つ覚えやすくて、お洒落なイメージということで、ネーミングにもこだわっています。まあ、「アメーラ」にしても、「ルビンズ」にしても、覚えてもらいやすい名前だと思いますね。
(山田さん)「ルビンズ」ありきの「ゴールド」ですよね。「ゴールド」だけだとちょっとよく分からないですけど、「ルビンズ」がまずありきで「宝石」のようでもある。
(岩崎先生)この話だけでも、30分くらい話せますよ(笑)。最初ね、黄色のルビンズだからね、「キビンズ」って話になったんですよ。「ルビンズ」「キビンズ」ってね、お笑いコンビみたいじゃないですか。それで「キビンズ」は却下になって、次は黄色だから「イエロー」とかね。「イエロー」はなんか高級感がないじゃない。次は、「ソレイユ」がいいと。
(山田さん)ひまわり、ですね。
(岩崎先生)「ソレイユ」で「ひまわり」が出てくる人、珍しいですよ? ソレイユはまさに「ひまわり」なんですけど、ただソレイユって言っても、「美容室ソレイユ」とかね「シルク・ドゥ・ソレイユ」とかね、あるじゃないですか。やっぱり固有名詞でいくべきだと。じゃあ「ルビンズ」を使って、高級感がある「ルビンズゴールド」と。これが出来たのは3、4年前ですけど、最近は「セブンゴールド」とかね、まさに広がってきているので。ですから、やり方としてはしっかりと考えてネーミングをすると。
ルビンズという傘の中にゴールドがあるので。広げるときに、さっき洋服が受けたからといってスリッパをつくると失敗するという話をしましたけど、広げ方は赤があるからゴールドがあるということで、非常にお互いがお互いを高めるような広げ方をやっている。そういう意味でも全体的にハーモニーを重要視しています。だから、パンフレットを見ていただいても、調和がとれているんですよ。
多いのは、前回は洋風だから、今回は和風にしようとかね。何が何でもゆるキャラを使うとかね。例えば、高級でやるなら、ゆるキャラは合わないじゃないですか。そういう意味で、アメーラのいろいろな商材を見ていただくと、非常にシンプルなんですよ。色も赤と白しか使っていないんですけど、できるだけ洗練されるように、デザインにもこだわっています。
■“大人のイメージ”なはずなのにゆるキャラが……!?
(静岡時代)アメーラの箱はシンプルな一色刷。赤の特色もただ単にトマトの赤じゃなくてフレッシュな感じのする色を指定してるんですね(特色とは、通常のカラー印刷に仕様するインクとは異なった特別な指定色のこと。現物の印刷の色は彩度が高くて独特の色合いです)。でもぜんぜん安っぽくなくてかっこいいです。

(稲吉さん)アメーラってね、市場でものすごく目立つんですよ。遠くから見ても。できるだけコストをかけないというのもありますし。贈答品のようなカラーのいい綺麗な箱もあるんですよ。でも、それはお金がかかってしまう。とは言え、デザイン性だけでかっこよくしないといけない。そうそう、今これ(アメーラちゃん)消えたんですよ。
(静岡時代)消えちゃったんですか? この子、もういないんですか?
(岩崎先生)アメーラちゃんはね、消えてもらうしかないってね(笑)。高級感でいこうということで、カゴメだったら親しみがあってこれでいいだろうけど、アメーラはそうじゃありませんよね。なので、高級感でいくんだったらこれはないほうがいいだろうと。どんどん進化というか、ハーモニーが合うように、ゆるキャラは使わずに「大人の女性」のイメージを持ってやっています。とはいっても、アメーラは甘いので、子供もルビンズとか大好きでパクパク食べてくれるんですよ、事前のテストマーケティングでもね。ただ、我々の頭にあるターゲットというのは、子供に好かれようというのではなく、大人の女性とか、洗練とか、お洒落とか、情緒に訴えるということでやっています。ルビンズは赤が綺麗で、本当にルビーのような感じで、光があたると輝くようなイメージで。
■発想をひっくり返した。トマトにヘタって本当に必要?

(稲吉さん)日持ちもいいんですよね。これ(写真のアメーラ・ルビンズ)は先週の経営戦略会議のときのものですから、もう一週間くらい経っています。
(岩崎先生)そうですね。日持ちもいいですし、あとルビンズを稲吉さんがつくったとき、ヘタが取れてしまうと。ヘタが取れるトマトというのは、今まで市場ではクズで商品にならないと言われていたんですね。
(山田さん)たしかに、真っ赤な実に緑のヘタありきのトマトのイメージですもんね。
(岩崎先生)そう。ただ、じゃあお客さんはヘタがあるからトマトを買うのか、というとそうじゃありませんよね。そこで稲吉さんと言ったのは、ヘタを取っちゃえと。ヘタを取ることによって、ルビンズも綺麗な形になりますし、ごみも出ないし、お洒落なイメージにもなるので、消費者にとってはそっちの方がいいかもしれないと。
(山田さん)確かにトマトイメージが刷新された感じします。フルーツみたいですもんね。
(岩崎先生)リーフレットにも「ルビーのようなフルーツ」ということで、「ルビーのようなトマト」と書いていないということがひとつデザイナーの方のこだわりかなと。「ルビーのようなトマト」と書いてもよかったと思うんですけどね、ただそれをやらないというのは、お客さんの情緒に訴えるという戦略になっている。
(稲吉さん)最初は、「キャンディタイプの」とか、そういう言い方もしたりしたんですけど、とにかくさっき先生が言ったように、野菜っぽいイメージではないですよね。
(静岡時代)野菜軸だったらカゴメと同じものさしの上の勝負になってしまう……。
(岩崎先生)アメーラ・ルビンズは独自性がありますよね。強いブランドは独自性が必要ということで、そういう意味で、さきほどブランドのとんがりの話をしましたけど、とんがりがある。ただ、不味いとだめなんです。すごく美味しいし、品質の管理もしっかりとされている。生産の仕組みもしっかりされていて、技術とかの土台があるからこれが出来るんです。
■ブレーンになっていただけませんか?
(山田さん)ところで、岩崎先生と稲吉さんはどんな経緯でお知り合いになって、今に至るんですか?
(稲吉さん)農業法人協会で僕が役員をやっていたときに、もう10年近く経っているんですけど、総会で先生が講師で見えられたんですよ。そこで初めてお会いして「面白い話だな」と。
当時、先生は40歳くらいでしたかね。すぐに先生の本を買いにいったのね。先生が最初に出された本『スモールビジネス・マーケティング』を買ったんですよ。それを読んで。あれは教科書っぽいですよね。分からない単語を調べながら読んで、やっぱり面白いなーと。それで、農業法人協会のAMP(Agree Marketing Project)のサポートをしてもらえませんか、と頼みにいったんです。トマトをお土産に持ってね。そしたら先生が「わたしトマト好きなんですよ」と言うものだから、「じゃあ、ついでにアメーラの外部ブレーンになっていただけませんか?」とお願いしたんです。そしたら「いいですよ」って。
(静岡時代)結構、簡単に(笑)。でもそれがタイミングだったのかもしれませんね。
(稲吉さん)もう7、8年経ちますね。ちょうど僕たちがサンファーマーズをつくって、軽井沢に農場をつくって、一気に出荷量が倍で動くような時期にタイミングよくこういうことになった。それまでデザイナーさんとずっとやってきたことがブラッシュアップされたり、デザイナーさんにとっても勉強になったと思う。先生もイメージで言うものをデザイナーさんが形にしていくじゃないですか。先生はデザイナーじゃないから「こういうイメージだよね」とデザイナーに伝える。すると、どんどん先生の方へデザイナーからデザインが送られてくるんですよ。それでA案・B案・C案どれがいいとなって、学生に聞いてみます、主婦に聞いてみます、という風に決めていって、やってきたんですよね。すごく我々も面白い。
よく先生の実験材料じゃないか、とかそういう見方をされる場合もあるんですけど全然違って、一緒になって面白く、何十億というトマトをつくっている。まあ先生はそういう人を育てる職業じゃないですか。さすがに我々みたいな小さな会社が先生の研究材料になっていいかとは話が別ですけどね。ただ、近くにそういう農家もなかなかいない。そういう意味では運よくコラボレーションできたなと思いますね。
(岩崎先生)非常にいい関係でコラボレーションさせていただいて。たまに、トマトももらえますしね(笑)
■マーケティングでものをつくれるか?

(山田さん)岩崎先生のマーケティングのロジックが、実際に生産するトマトの品質に影響していったとして、例えば、アメーラルビンズもマーケティングありきで品種改良をされていったとかはあるんですか?
(岩崎先生)まず稲吉さんが独自の種を入手されたんですね。
(稲吉さん)まずこちら側にアイデアがないと、「じゃあ先生、何かつくってください」という話ではないので。だから、先ほども先生が話されてましたけど、「こういうトマトがあって、ヘタが取れちゃうんだよね」「じゃあ、取ってしまいましょうか」と。例えば、同じミニトマトで丸くて、ヘタがついているものだったら、ものすごく美味しくても、次に買うときに「あれはなんだっけ?」と思うじゃないですか。だけど、ヘタもないし、長いし。今「アイコ」というトマトが人気が出てきていますけど、当時こういう長いトマトはあまりなかったんですよ。
形も違うし、ちょうど収量が取れないので、高く売るにはどの程度の量が妥当かみたいなこともやったんですよね。まあそうすると、デザイナーさんなんかも、試しに買うとすると、300円くらいまでじゃないかと。500円だと試しに買わないんじゃないかと。300円で売れる単価というと、我々は卸しで200円くらいだねと。200円なら何粒いれるなら我々は採算があうの? となって、大きさやパッケージが決まっていく。その間に、先生に食べてもらったり、欠点をみてもらったり、そうして最終的に出来上がったものがこちらなんですね。ちなみに、こちらは蓋が閉じないからシールを貼っているんですけど、何枚もシールを貼ると手間がかかってしまうので、長いシールで両側から貼ると。
(岩崎先生)この貼り方も重要で、ずれないように真ん中にくるように貼らないといけない。デザイナーさんがね、お店にいくと「ずれているものがある」ってね、チェックしてくれる。
(稲吉さん)そういう個々の専門家の人たちがいっぱいいるということが大事ですよね。気が付かないですよね? 曲がっていても。
(岩崎先生)つくる人と買い手のギャップがあるので、それを上手く縮めていくことがマーケティングの作業になってきますよね。消費者の目線で。ですから、これをつくるときも、最初、消費者に食べてもらって、意見をもらって。みんな「おいしい」って言ってっくれた。香りもいちごみたいな香りで評判がいいんです。
(山田さん)ここでもう甘い香りしますもんね。
→ 《実践! 静岡ブランドの実力 ~アメーラ・トマト【後編】〜》へ
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
——編集後記——
イメージに合わないから「ゆるキャラ(アメーラちゃん)には消えていただいた」というエピソードを聞いて、あらためて、ブランディングの戦略とはコミュニケーションの文法そのもので、アート・創作の技法なんだなぁと思いました。
伝わることを重視した創作の基本は、導入では扱うものの全容がおおまかにつかめるようにしておくこと。わかりやすいフレーズをつくる際は、省略にするわけではなくて象徴化する。文脈には一貫性がないといけない。作り手は扱う素材や方法のひとつひとつや意味を全部分析して把握して、それを場面場面で、使用することの意味や意図を全部説明できる状態でいる必要がある。広げた風呂敷は作り手の「メッセージ」によってまとめる。
それって、大学での勉強にも通じる部分があるのではないかと。
大学では、自分の知らないものを自覚してどのように知るか。場合によっては、何に応用できるのかを考えなければならない。そして、自らが発信者(作り手)となって、対大勢に自分の考えを伝える場面もある。ブランドと大学生。一見すると離れたようなものではあるけれど、実は私たちも参考にするべきことや大学生活のヒントがたくさん潜んでいそう。
次回は、現役大学生の山田さんにもスポットを当てて、お話を進めていきます。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Updated:2014年12月05日
"土"を愛する女子大生が、"土"の歴史を読み解く。〜土とわたしのつながりって?〜
これまでの取材を通してわかったことは、どうやら私たちは「土によって生かされている」らしい。土は緑を育み、水を豊かにし、その恩恵でもって私たちの生きる根底が守られている。では、その連鎖は一体どこから始まったのだろうか。『静岡の土を舐めたい』連続特集の最終回は、発掘調査員・小牧直久さんと静岡の古墳を訪れました。日本の草創期まで遡ることでみえてくる、私たちと土の縁。古代の痕跡が映し出すのは、自分自身の知られざるルーツなのかもしれません。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●古牧直久(ふるまきなおひさ)さん〈写真左〉
静岡市文化財課 職員。発掘調査員として、日々発掘をし遺跡に眠っている謎を解き明かしている。静岡大学人文学部卒業。学生時代は剣道部に所属し、今も大学時代の恩師に会うために大学へ足を運ぶこともあるという。
■このお話をもっと深く掘り下げたいひとへ古牧 直久さんからのオススメ本!
『静岡清水平野の古墳時代 新出土品にみるまつりとくらし』静岡市登呂博物館.1990
【聞き手】
●樫田那美紀(かしだなみき)〈写真右〉
静岡大学人文社会科学部3年。静岡時代6月号(本連続特集企画)編集長。
特集企画立案の段階から、自身の土考を熱心に語る。目標は「この特集を通して"土の愛し方"を知る!」とのこと。
そして念願叶い、"自らの舌で土を味わった"。
→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1297872.html(知ることは舐めること。「静岡の土、いただきます」)
●漆畑友紀(うるしばたゆき)〈取材・執筆〉
静岡英学院大学社会学部2年。静岡時代6月号副編集長。
樫田編集長の右腕として編集長を支え、編集部メンバーをサポートしてきた。本取材では編集長・副編集長によるタッグを組み、特集企画の最後を飾る。普段は淡々と発言するが、キメるべきところはしっかりと声を大にして言う「静かな内に情熱」を抱くメンバー。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■わたしのルーツは、土に在り?
本誌編集長 樫田(以下 樫田):現代を生きる私たちは、農家さんが作った農作物を食べ、アスファルトの上を歩く、大半の人は土に触らなくても生活していけます。それに対して太古の人々は、土器の制作や農耕など、土と触れ合わないと生きていけなかったのではと思うのです。古牧さんは静岡県で古代の遺跡の発掘調査をされていますが、土やその出土品から当時の人の社会と土の繋がりにおいてどのようなことがわかるのでしょうか?
古牧さん:まず重要なのが土器です。縄文時代では、土器は食物を貯蔵や煮炊きに使用するなど、生活に必要不可欠な道具だったと言えますね。その一方、火焔土器という沢山の紋様が彩られている土器は、本当に実用品目的かと目を疑うほどの装飾が施されています。当時土器は生活の道具としてだけじゃなくて、祭祀に使われる目的も担っていた可能性があるわけです。この古墳は午王堂古墳といって、清水ICの北側に三つ並んだ古墳の三号墳。ほら、このように土器の破片も出土したんですよ。

樫田:こんな小さな破片となって出てくるんですね! 縄文時代や弥生時代に、人はどのように土器を作り上げていたのでしょうか?
古牧さん:まず縄文時代や弥生時代は、まだ土器を高温で焼くための技術が発達していなくて、その頃は粘土で形作った土器の上に木くずなどの燃えるものを土器に覆いかぶせ、周りで火を焚く、「野焼き」と呼ばれる方法で焼かれていました。土器はオレンジっぽい褐色系になります。古墳時代に窯の技術が大陸から伝わったことで土器の焼成温度が上がり、「須恵器」と呼ばれる土器が作られます。高温で焼かれた「須恵器」は、より強度が保たれて丈夫で、土器の色が鼠色なんです。
樫田:この小さな破片からこんなにもたくさんの情報が紡ぎ出されるとは。その変遷は考古学においてどのように解明されてきたのですか?
古牧さん:集落や墓、土器を造った窯などが発掘されると、その土器の粒子や形で作られた時代がわかるんです。地域や時代によって様々な特徴があって、それらを比べることによって土器の変遷がわかります。土の粒子とか材質って重要で、静岡の土器と他の地域の土器をみると形は同じでも材質は全然違うことがわかる。地域ごとに土が含む鉱物も違うから、触っただけで「これは静岡の土器だ」ってわかることもあるんですよ。

樫田:同じ土器でも地域性が出るなんて、改めて土の多様性に驚かされます。
古牧さん:ある窯の拠点では、沢山作られた土器を他の地域へ流通させていたこともわかったんです。例えば静岡県では、古墳時代に浜松の湖西に窯があったので、その窯で作られたであろう須恵器が静岡市の方で発掘されました。静岡県では瓦を焼いていた窯も見つかっているんです。窯が発掘されるってことは、近くにいい粘土がとれる場所があるってことなんです。
樫田:山がちな静岡県で採れる土は火山灰など不純物が多く、焼くとすぐ粘土が溶けてしまって静岡は陶芸に不向きだと言う声もありますが、土器にいい粘土が採れる地なんですね。縄文から弥生、古墳時代へと土器を焼く技術の進歩を受け継いだことが今の陶芸の技術を生んでいるような気がします。その他、太古の人々の土にまつわる生活の手がかりはありますか?
古牧さん:土に埋もれた水田などの農業の跡も考古学的に重要な昔の遺跡の痕跡です。昔安倍川の洪水で流れてきた堆積物、つまり土によって、高い所と低い所ができたんです。高い所は水捌けが良く生活するのに適し、低い所は水が豊かなので、人々はそこで田んぼや農業を始めたと言われています。
樫田:天災で地形が形成される中で人は農業地帯を整えていったんですね。
古牧さん:そう。洪水が治まった後も人々は生活するのですが、土が積もって地形が変わり、かつて住んでいた集落は埋もれしまいます。静岡で有名な登呂遺跡は、集落と田んぼが近くにある状態で発掘されたんです。何千年も前に起こった安倍川の洪水で積もった土に埋もれた、家の柱の穴や、生活水を流していた溝などごく一部が出土しました。僕らは土によってパックされたかつての住民の痕跡を発掘し、調査によって当時の生活を解明していきます。時には泥だらけになりながらね。

▲全長77.6メートルもある午王堂山古墳。写真は発掘現場の一部です。

▲古牧さんに案内していただきながら、古墳にまつわる貴重なお話を聞くことができました。
■本来は語らないはずの土が雄弁に語る。
耳を傾けることで伝わる、当時の時代背景や歴史。
樫田:治水されていない当時の安倍川が人民の生活に与える影響は絶大だったのですね。そんな人の営みの最後にあるのが死だと思うんです。かつてはお墓である古墳自体が土で作られ、人は土の中に埋葬される、この事から人は土に還るものなんじゃないかと思ったんです。そんな土と人の密接な間柄を感じるからこそ、今土と私の間に距離感があることが苦しいのです。
古牧さん:でも僕は結局今と縄文、弥生などはるか昔とは、そんなにかけ離れたものじゃないと思うんですよ。今使われている技術や物は昔から使われていたりするわけだし、アスファルトの下にも土は確かにあるんだから。
樫田:私にはその想像力がないのかもしれません! 昔は古墳を使いどんな埋葬方法をとっていたのですか?
古牧さん:弥生時代の代表的な墳墓である方形周溝墓は穴を掘って土の中に遺体を埋めていたようです。仏教が入ってくる以前は土葬が一般的でした。そのまま土の中に遺体を入れる方式や、土の中に一度亡くなった人の遺体を入れ、骨になったものを取り出して再葬する、このどちらかが行なわれていたようです。このような面を総合すると、土に還るといえるかもしれませんね。
樫田:なるほど。発掘調査員として土に触れていらっしゃる古牧さんは、これから土とどう向き合いたいとお考えですか?
古牧さん:そうですね、埋没した土も、同じ土なのに酸化した部分だけ色が変わっていたりしています。そんなどんどん堆積した土の中にある遺物は真空状態だから、腐食せずに保存できるんです。僕らが発掘調査で掘り起こすことで酸化や腐食を進ませてしまうのも事実。土を掘り起こすことで分かること、失われるもの、両方あるんです。だからこそ少しの発掘で最大限の情報を得たい。洪水で流れてきた土の埋没過程のストーリーや、土の中に含まれている土器をみてその時代の背景や歴史といった物語を探るのは楽しいし、その時まで謎になっていたものが明らかになるのにはロマンを感じますよ。
樫田:はるか昔の人々の土との関わりが私たちに影響を与えるように、私たちの土との関わりも遠い未来の人たちに繋がっていくのかもしれませんね。
古牧さん:土を観察し昔の人の生活を想像することで自分のルーツが見える。それが発掘の面白いところです。発掘帰りに「今日も土で泥だらけだな」って自分の爪をしみじみ見てしまいますね。
(取材・文/漆畑友紀)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
◉連続特集:静岡時代6月号(vol.35)『静岡の土を舐めたい』(5)
【"土"を愛する女子大生が、"土"の歴史を読み解く。〜土とわたしのつながりって?〜】
●古牧直久(ふるまきなおひさ)さん〈写真左〉
静岡市文化財課 職員。発掘調査員として、日々発掘をし遺跡に眠っている謎を解き明かしている。静岡大学人文学部卒業。学生時代は剣道部に所属し、今も大学時代の恩師に会うために大学へ足を運ぶこともあるという。
■このお話をもっと深く掘り下げたいひとへ古牧 直久さんからのオススメ本!
『静岡清水平野の古墳時代 新出土品にみるまつりとくらし』静岡市登呂博物館.1990
【聞き手】
●樫田那美紀(かしだなみき)〈写真右〉
静岡大学人文社会科学部3年。静岡時代6月号(本連続特集企画)編集長。
特集企画立案の段階から、自身の土考を熱心に語る。目標は「この特集を通して"土の愛し方"を知る!」とのこと。
そして念願叶い、"自らの舌で土を味わった"。
→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1297872.html(知ることは舐めること。「静岡の土、いただきます」)
●漆畑友紀(うるしばたゆき)〈取材・執筆〉
静岡英学院大学社会学部2年。静岡時代6月号副編集長。
樫田編集長の右腕として編集長を支え、編集部メンバーをサポートしてきた。本取材では編集長・副編集長によるタッグを組み、特集企画の最後を飾る。普段は淡々と発言するが、キメるべきところはしっかりと声を大にして言う「静かな内に情熱」を抱くメンバー。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
・静岡時代6月号(vol.35)『静岡の土を舐めたい』バックナンバー
(1)【そもそも土って何ですか?】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1384374.html
(2)【知ることは舐めること。「静岡の土、いただきます」】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1297872.html
(3)【土と人が共にある原風景】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1384419.html
(4)【土がある生活を創る、陶芸家の土論】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1387583.html
・静岡時代6月号制作の舞台裏〜『静岡時代』はこうしてつくられている〜
(1)【静岡時代6月号制作、始動!】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1277696.html
(2)【静岡時代編集部の毎日】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1297245.html
(3)【怒濤の編集ラッシュを終えて……】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1305953.html
(4)【静岡時代6月号が発行されました!】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1309006.html
(5)【より質の高い静岡時代をつくるために〜次号へのバトンタッチ〜】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1324506.html
(6)【静岡時代6月号、配送キャラバン】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1323878.html
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Updated:2014年11月17日
実践! 静岡ブランドの実力 ~アメーラ・トマト【前編】〜
市場での流通量が増えても卸値が下がることがない「つくれば売れる」すごいトマトがあります。一年中、高価格&高品質。銀座のデパートや全国の高級レストランで取り扱われ、ローソンやヤマザキなどの大企業からコラボレーションのオファーも舞い込む。高糖度トマト「アメーラ」です。
「アメーラ」の成功は、もちろんそれ自体の品質あってのことではあるのですが、同時に非常に精緻なブランディング戦略によってでもあります。プロジェクトのキーマンは、トマト生産者の稲吉正博さんとアメーラのブランドづくりを行う静岡県立大学経営情報学部の岩崎邦彦教授らのチーム。
わたしたちと静岡県の未来のつくり方=教科書をつくる新連載の第一回。静岡未来でもしばしば登場してもらっている静岡県立大学食品栄養学部生にしてワインバー店主・山田瑞己さんとともに、県立大の岩崎研究室を訪ねました。
静岡未来→ https://www.facebook.com/shizuoka.mirai

◉「アメーラトマト」
静岡県で開発された高糖度トマト。大きさは一般的なトマトの1/3程度で、糖度は7~8度以上と、フルーツ並の糖度をほこる。名前の由来は静岡弁の「甘えらー」(あめえらー:「甘いでしょ」という意味)から。公式HPではアメーラを使った料理レシピなど情報満載→ http://www.amela.jp/
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●岩崎邦彦(いわさきくにひこ)先生〈写真中央〉
1964年生まれ。静岡県立大学経営情報学部教授・地域経営研究センター長・学長補佐。
上智大学経済学部卒業、上智大学大学院経済学研究科後期課程単位取得。
国民金融公庫、東京都庁、長崎大学経済学部助教授などを経て現職。
主な著書に『小さな会社を強くするブランドづくりの教科書』(日本経済新聞社刊)※、『小が大を超えるマーケティングの法則』(日本経済新聞社刊)、『スモールビジネス・マーケティング-小規模を強みに変えるマーケティング・プログラム』(中央経済社)、『緑茶のマーケティング-“緑茶ビジネス”から“リラックス・ビジネス”へ』(農文協)など。
※『小さな会社を強くするブランドづくりの教科書』(日本経済新聞社刊)はアメーラを題材に、小さな組織が大きなブランドをつくるための実践理論がわかりやすく書かれています。さらに詳しく知りたい方はこちらへ → http://www.amazon.co.jp/dp/4532319056/ref=cm_sw_r_tw_dp_53g0tb187CEGA
●稲吉正博(いなよしまさひろ)さん〈写真左〉
トマト生産者。「アメーラ」「アメーラ・ルビンズ」のブランド管理、生産支援、指導管理を行う株式会社サン・ファーマーズ代表取締役。アメーラは日経MJ「ブランド評価」第1位(2009)や、ベジフルサミット「おいしいトマト」第1位(2007)に輝くなど高い評価を得ている。アメーラは公式通販ショップで購入することも可能 → https://www.amela-shop.com/
【聞き手】
●山田瑞己(やまだみずき)さん〈写真右〉
静岡県立大学食品栄養科学部栄養生命科学科3年生
1989年、母の実家がある静岡県沼津市に生まれ、父の実家がある山梨県塩山市で育ち、現在、静岡県で食品栄養学を学ぶ。近年静岡にワインバーが増えているが、山梨県産ワインが飲める場所が少ないことを悲しく思い、「山梨県産ワインが飲める店をつくろう」と一念発起。Wine Cafe ROUTE52を出店する。
住所:静岡県藤枝市大東町442
☎:054-637-0670
●服部由実(はっとりゆみ)
静岡時代所属。本記事エディター。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■「いいもの」をつくるだけでは選ばれない
(静岡県立大学経営情報学部・岩崎邦彦先生)まず、いきなりアメーラの話から
外れるんですけど、静岡の「牛肉」ってすごいレベルが高いことを知っていましたか?
静岡牛は品評会においてはナンバーワンをとることも多いんですよ。とても美味しいんです。
ただ、高く売れるのは何かというと、静岡牛ではなくて「松坂牛」です。
実際にある品評会の話ですが、静岡牛が一番になりました。そのあとにすぐ競りが
あったわけです。いまさっき「美味しい」と評価されたばかりなのに、競りになると
静岡牛は、品質ほどは高く買われないんですよ。ということは、良いものをつくるだけでは選ばれないと。ブランドづくりが必要です。
静岡はご存知のとおり、ものづくり県で、非常にいいものをつくるんですよ。
美味しい鶏肉もあるし、美味しい豚肉もある。ものづくりはすごい。ただ、ブランドづくりのことを考えると、ものづくりとブランドづくりはイコールではない。
選ばれるためにはブランドを強くしていきましょうと、10年ほど前から、生産者の稲吉正博さんを中心としたサンファーマーズという生産者グループと産学連携で力を合わせて「アメーラ」のブランドづくりを行っています。
■ブランドとは"とんがり"である
(山田瑞己さん:以下/山田)「アメーラ」というと、わたしはイメージとしてもあたらしい時代のトマトという感じがします。で、実際食べてみるとびっくりするくらい甘くておいしい。普通のトマトよりもすこし小ぶりなルックスも、印象を補強する感じです。野菜なんだけど、これまでの野菜のイメージとずいぶん違います。
(岩崎先生)イメージづくりはとても大事です。例えばブランドを「人」に例えてイメージしたり、トマトが食べられるシチュエーションを具体化したり。実際どういうふうに、お客さんに認識されているか、マーケットのリサーチもしています。羅針盤を持って、戦略的に進めています。パッケージやリーフレットにもこだわってみたりね、それこそ、本が装丁にこだわってみたりするのと同じですよ。トマトみたいな野菜でもそういうことが大切になってくる。
「ブランドづくり」というと、言葉だけがひとり歩きしがちです。しかし、そもそもの土台は「おいしい」という品質。ただ、おいしいトマトっていうだけなら結構あるんですよ。つまり、おいしいとか、栄養価が高いというだけでは埋もれてしまう。なんらかの「とんがり」をつくりましょうと、こういう発想でやっています。
(静岡時代)先ほどの静岡牛と松阪牛の話みたいにですね。静岡牛は品質はいいのに、残念ながら埋もれてしまったというわけですね。
(岩崎先生)そうです。同じように、例えば、リコピンで勝負すると「カゴメ」には敵わない。価格の安さで勝負してもカゴメには敵わない。じゃあ勝つところはどこかというと、価格の安さではなくて「高い価値」を売るということ。ただ、価値といっても目に見えないじゃないですか。
トマトのイメージを「人間」に例えて考えてみる。おそらく、性別は男性か女性かというと女性ですよね? そこに年齢や性格を加えて例えてもらうと、一般的な普通のトマトは「20歳くらいの可愛い女の子」、元気のある可愛い女性というイメージがあります。カゴメのトマトがまさにこの辺のイメージだと思います。
ということは、今更それと同じようなトマトをつくっても絶対にカゴメに敵わない。じゃあ、我々のアメーラはこの逆張りで「大人のトマト」でいこうと。且つ「明るい」のではなく、「しっとり系」。おとなしいイメージでやろうという戦略でやっています。ブランド・パーソナリティを明確にするということです。

■品質を超えたポジティブなイメージをお客さんの頭に植えつける
(岩崎先生)ブランドってなにか、結構みんな知っているようで分からないですよね。辞書でひくと、ブランドというのは「名前」と書いてあります。商標。ただ、名前であれば、すべての商品に名前はついているじゃないですか。
もともとブランドというのは、「焼印」を押す=名前をつけるということです。しかし、ただ単に名前というだけでは、今の時代のブランドとは違うだろうと。よく言うのは、品質をよくすることがブランドづくりだということです。でも、先ほども言ったように、品質がよくても選ばれない。ということは、ブランドというのは、「品質を越えた何かしら」をつくっていくことなんですね。それをお客さんの頭の中のイメージとして植え付けていくことだと。そのためにはどうすべきか、戦略が大事になってくる。
(静岡時代)岩崎先生は、著書『小さな会社を強くするブランドづくりの教科書』(日本経済新聞社刊)のなかで、「ブランドづくりとは顧客の心のなかに品質を超えたポジティブなイメージを形成し、顧客との感情的な“絆”をつくること」と述べられていますよね。
(岩崎先生)強いブランドの法則を調べてみると、いくつか共通点があります。ひとつは明快なイメージがあること。すでにほかにあるものの真似をしてもダメですね。二番手、三番手ではダメ。高糖度の高級トマトは、当時はほとんどなかった。 お洒落なトマトも今までなかったわけです。そういう方向性でやれば、頭の中で明快なイメージができる。
ちなみに、いま全国各地で地域産品をつかったワインをつくりましょう、という動きがあるけど、他で行っていることと同じだと、ブランドになるのは難しい。
二つ目は、感性に訴求するということ。単に機能がいいだけだと、例えばリコピンの含まれる量だけだと、もう勝ち負けの世界じゃないですか。片方は10含まれている、もう片方は5しか含まれていないという具合に。

▲"アメーラ"を題材に、小さな組織が大きなブランドをつくるための実践理論がわかりやすく書かれています。
(静岡時代)スペックの指標という勝ち負けのルール自体が自分ではどうにもならないですしね。感性に訴えれば「自分の土俵」を戦えます。
(岩崎先生)そう、一本のものさしでは測れないようなもので勝負をしようということです。それは美味しさかもしれないし、デザインかもしれない。私が好きなデザインは、みなさん好きじゃないかもしれませんよね。そういったお客さんの感性に訴えると。
■情感に訴えよ!
(岩崎先生)強いブランドの特徴をみてみると、機能だけではなくて、お客さんの情緒とか感性に訴えています。例えば、スターバックス。コーヒーの美味しさだけだったら、僕はドトールの方が好きなんだけど(笑)、じゃあなんでスタバがいいかっていうと、お洒落な雰囲気や空間とかね、単に機能だけを売っているわけではない。パソコンにしても、機能性だけだったら日本製の方がいいと思うんですよ。でも、アップルが去年の世界のブランド競争でナンバーワンになったんですね。アップルがコンピュータの機能だけでナンバーワンになったのかというと、そうじゃないですよね。機能だけだったら、多分NECとか、東芝とかの方がいいと思うんですよ。なぜアップルがいいのかというと、お客さんの感性に訴えているからなんですね。
じゃあ、農産物も単に美味しいとか、お茶だったらカテキンが豊富とかだけではなくて、お客さんの情緒とか心に訴えようと。頭だけではなくてね。栄養性とか機能は、お客さんの頭に訴えるもの。それはもちろん重要です。美味しいのは当たり前で、機能性は当然あるという前提で、我々はそれプラス、情緒性に力を入れています。
■一番でなければ埋もれてしまう
(岩崎先生)3つ目は独自性。どこかの真似をしていないこと。二番手、三番手だと強いブランドにはなりません。よく多いのは、「これが売れたから、私もつくろう」ということ。後追いだと強いブランドはできないということで、独自性です。これは本にも書いてある例えですけど、日本で一番高い山はどこですか?
(山田)富士山です。
(岩崎先生)じゃあ、二番目は?
(静岡時代)八ヶ岳ですか?
(岩崎先生)違うんですよ。二番目は北岳なんです。じゃあ、一番大きい湖は?
(山田)琵琶湖。
(岩崎先生)じゃあ、二番目は?
(山田)あ、うーん…… 分からないです。

(岩崎先生)でしょう? トップは頭に浮かぶんですよ。二番目は浮かばない。イメージが浮かばないと、選ばれないんです。ちなみに、二番目に大きい湖は茨城県の霞ケ浦。我々は、高さの勝負では富士山には敵わないでしょう? 北岳も敵わないわけですよ。それから、NHKの世論調査によると、日本人が一番好きな山は富士山なんですけど、二番目に好きな山は阿蘇山なんですよ。カルデラ火山のね。イメージが浮かぶじゃないですか。阿蘇山って、高さではベスト100にも入らないですよ。低い山なんです。ただ、「カルデラ火山」というカテゴリーだと一番なんです。だから、我々のやり方も、トマトで一番になるというよりも、あるカテゴリーでトップになろうという発想なんですね。
お洒落なトマトでトップになろう、高糖度トマトでトップになろうと、二番目を狙わないということで独自性が三つめの方向性になっている。あとは価格の安さではないということ。安さで引きつけたお客さんは、安さに逃げていきますからね。別のトマトが割引になったら、みんなそっちに行ってしまうじゃないですか。
(山田)たしかに。
(岩崎先生)安さではないところで引きつける、好き嫌いで引きつけるような考えで一貫性をもってやってきている。明快なイメージを持とうと。ところで、私たちはアメーラのアイデンティティ、ブランドのあるべき姿を明快に文章化しているんです。「最高品質の高糖度トマトで、おいしさの感動をお届けします」。これです。生産者の方にも、経営戦略会議の際に毎回一番最初に伝えています。
■アメーラは“トマト”でしか勝負しない
(岩崎先生)「最高品質」ということは、アメーラトマトは常に最高品質を狙いますよ、つまり常にレベルアップしますよ、ということ。次に、「アメーラ」という名前が有名になってきたんですが、アメーラは「高糖度トマト」ということでやっているので、「アメーラのイチゴ」とかは絶対につくらない。「アメーラのキャベツ」もつくらないし、「アメーラのにんじん」もつくらない。よくブランドが有名になると、その名前を他に使うということがあるじゃないですか。昔、あるアパレル企業が洋服をつくっていて一流ブランドだった。それで、今後はスリッパをつくりましょう、タオルをつくりましょう、と商品を広げていった。何が起こるかというとブランドイメージが薄まってしまって、頭にイメージが浮かばなくなってしまう。
(静岡時代)静岡時代も、そういう迷走をしたことがあります……。
(岩崎先生)アメーラの場合はトマトでしか勝負しない。商品を広げる場合も、赤色(アメーラルビンズ)があるから黄色(ルビンズゴールド)があるというように、ハーモニーのある広げ方はしますけど、足し算の広げ方というのはやらない。ソニーが今弱くなっているのは、昔は「ソニーといえばウォークマン」という明快なイメージがあったけれど、今は、保険事業もやっているし、ソフト事業もいろいろやっているし、非常に幅広くやっています。広さゆえに、イメージが薄まってしまっているのではないかと思います。そうするとブランドイメージも薄まる。アメーラはトマトのブランド。トマトだけでいこうと。
最後は、「最高品質の高糖度トマトで、「おいしさの感動」をお届けします」ということで、稲吉さんをはじめ生産者の方は、単にトマトをつくっているのではなくて、「おいしさの感動」をつくっているんだという発想です。
→ 《実践! 静岡ブランドの実力 ~アメーラ・トマト【中編】〜》へ
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
——編集後記——
岩崎先生の著書によれば、消費者1000人への調査したところ、1回辺りの「トマトの購入」に支払ってもいいと考える金額の平均は335円。しかし、問いを「おいしいさの感動に対していくらまで支払えるか」と替えると、8939円と27倍に上昇したそうです。同様の問いを、例えば「化粧品」に対して行うと、平均は5696円。しかし「美しくなるため」と問いを替えると平均は2万3749円になったとのこと。(岩崎邦彦著『小さな会社を強くするブランドづくりの教科書(日本経済新聞社刊)』90-91ページ)
モノが世の中に溢れていて、よく言われるように、わたしたちに“これ”というような「物欲」がどんどん少なくなっているのかもしれないとは思います。でも「欲求がない」わけでは全然なくて、その矛先が「体験・経験」に向かっていることも理解している。
だからこそ、これからの時代自分はどのように生きて行こうかとか、どうやったら誰かの役にたてるかだとか、そのためにどうやって自分のことを知ってもらおうかとか。岩崎先生のインタビューが、そういうこと全般の大きなヒントになればなあと思います。
次回はアメーラ生産者の稲吉さんにもご登場いただきます。アメーラ、ブランドづくり話をさらに掘り下げた内容になっています。お楽しみに。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Updated:2014年11月07日
"土"を愛する女子大生と、静岡県の陶芸作家。〜土がある生活を創る、陶芸家の土論〜
前回の記事で私たちは、菊川市上倉沢の棚田を訪れて"土"と"水"の深い関係を目の当たりにしてきました。今回は、"土"と"火"が出会うことで生まれる陶器をキーポイントに、静岡県の陶芸家・小國さんにお話を聞きました。土の潜在能力を引き出す陶芸家はどのような想いで土と向き合っているのか。「静岡の土でしか作れないものを作りたい」という小國さんにとって"土"とは何なのか、その魅力に迫ります。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●小國加奈(おぐにかな)さん〈写真中央〉
陶芸家。普段の器からランプまで、生活に寄り添う多種多様な作品を制作。静岡市内のカフェや料亭などでも小國さんの作る器が多く使われている。静岡市清水区の陶工房「KANa」では、小國さんの作品や器を実際に購入できるほか、陶芸体験もできるそう。
■小國加奈さんの陶工房「KANa」
住所:静岡市清水区有度坂5-16/☎054-347-7781
毎月1日~15日開店。16日~月末は作陶につき休業。静鉄電車「狐ケ崎駅」より徒歩で約12分。
【聞き手】
●樫田那美紀(かしだなみき)〈写真右〉
静岡大学人文社会科学部3年。静岡時代6月号(本連続特集企画)編集長。
特集企画立案の段階から、自身の土考を熱心に語る。目標は「この特集を通して"土の愛し方"を知る!」とのこと。
そして念願叶い、"自らの舌で土を味わった"。
→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1297872.html(知ることは舐めること。「静岡の土、いただきます」)
●三好景子(みよしけいこ)〈写真左〉
静岡大学教育学部3年。小國さんへの取材にむけて、樫田編集長とともに企画を練りに練ったメンバーのひとり。自身が教育学部で美術を専攻しているため、本取材内で吸収するものや共感できたものが多々あったそう。これまでの経験をふまえ、静岡時代10月号(vol.36)では副編集長をつとめた。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■実は主役級? 奥深い土の世界。
――小國さんの作られる器からはどれも土の暖かみが感じられる、柔らかい印象を受けます。そもそも陶芸において土とはどのような役目をもっているのでしょうか? 小國さんの土へのこだわりも含めて教えてください。
私が普段使う粘土は、お付き合いのある粘土屋さんから、自分の出したい色や手触りに合ったものを選んで仕入れています。例えば粒子の細かい粘土はなめらかな手触りになりますし、程よい重みが出るんですよ。私が今使っている窯でうまく丈夫に焼き締まる土を選ぶことも大事ですし、毎日気を遣わずに使えるタフな器にしたいですね。あとは、器を焼く前に釉薬(ゆうやく)という薬をかけてコーティングをしますが、この釉薬の種類によって、手触りも変わるんですよ。
また、日本の食卓では、他の国よりも器を持って食べるという文化が強く根付いていますよね。「器を触る」という機会が多いからこそ、触り心地や重すぎず軽すぎない重さを大事に作っています。縁の下の力持ちのような、皆さんの生活を引き立てる、毎日使っていても飽きのこない器作りを心がけています。


▲こちらの器が、静岡県の土を混ぜて作ったもの。静岡の土は高温に弱く早く溶け出すため、
黒い斑点のような模様が自然と浮き出るのだそう。
――器の手触りの土台となる土選びから、繊細な工夫を重ねていらっしゃるんですね。では、出身地である静岡の土を使って陶芸はされていますか?
私もまだ研究途中で100%静岡の土で作る、ということはあまり出来ていないのですが、普段使う粘土にすこし混ぜてみたり試行錯誤はしています。というのも、市販の粘土で陶芸をしていたとき「せっかく清水という地で陶芸をしているんだからこの地で採れた土で作りたい」と思ったんです。静岡で陶芸をする意味を考えるようになったんですよね。
静岡の土を使うきっかけとなったのが、静岡の様々な土を使って器を実験した成果をまとめた『やきもの実験 静岡の土(芳村俊一・宮本森立編)』という本。釉薬を使わずに静岡の土が出してくれる色を活かす陶芸のやり方、静岡の様々な土を使って実験的に焼いているその姿がとても衝撃的で。その本に刺激を受けて以来、私ももらえる土があればとにかくもらって研究しています。
山と海を持つ静岡県の土は、火山灰や海成土が多く含まれています。そのため焼いたとき、含まれる成分が相互作用して早く溶け、形を留めておくことができません。不純物が多い粘土を高温で焼くとぶくぶくと泡立ったり溶ける一方で、純度の高い磁器土などは高温で固く引き締まります。焼いて固まって溶けるまでの温度の幅が土の成分によって違うんですよ。でも不純物があるからこそ釉薬を使わなくても、予想外に混ざった金属の作用で、土が色を出してくれたりするんです。また、同じ釉薬を使っても、土によって焼き終わった時の色も全然違うんですよ。


――土の中の成分がそんなに強く器に影響を与えているなんて驚きです。
陶芸って、土はもちろん、火の力も使うし、水の力も使うでしょう? つまり、自分の力というよりも自然の力を借りて焼き物はできているんです。そう思うと謙虚な気持ちになれるんですよね。静岡の土でできた器に、静岡で採れた野菜やお米をのせて静岡の人がそれを食べる、そんな今は薄れてしまった「土の地産地消」の実現が私の理想ですね。
――土の地産地消! 確かにせっかく自然豊かな静岡に住んでいるんだから、その魅力を五感で感じたいです!
実現したらすごく贅沢ですよね! 私自身、大学生活を石川県の金沢市という伝統的に焼き物が根付いている街で送ったことで、静岡に陶芸が根付いていないことを実感したんです。静岡に帰ってきた理由の一つに、静岡の人にもっと身近に気軽に陶器を使って欲しい、という想いもありました。私に限らず静岡県はあまり陶芸が盛んじゃないイメージを持つ人が多いかもしれないけれど、私の工房のある清水区の辺りは古墳時代には窯がいっぱいあって、昔は日本有数の窯業産地だったそうなんですよ。窯があるということはその土地の土を使った陶芸も行われていたということ。つまり、今静岡の土があまり陶芸に向いていないと思われているのも、陶器を焼く今の一般的な温度が静岡の土に適していないからなんです。だから、土に思いやりを持って寄り添って、その土地の土に適した温度で焼けばどんな土でも焼き物になると芳村俊一さんはおっしゃっています。
同じく印象的だったのが、大学で本格的に陶芸を始めた時の先生の「土を使う事の意味を考えなさい」という言葉。土を生かし、土じゃないと作れないものを作りなさいという意味です。手で触れることで、私も土の特性の生かし方や土を使う意味を感じ、見つけていきたいです。

■「奥が深すぎて、一生やってもやり尽くせないかも(笑)」
――土の力でその器の個性を出す、難しそうですが、陶芸だからこその表現方法だなと感じます。
やっぱり土が主役なんですよね。そんな土は、実は何千年~何百万年というものすごく長い年月をかけて作られているんです。もしかすると人間がいつか使い尽くしてしまうかもしれない、限りある資源の一つなんですよ。陶芸家としてその問題に取り組むために、割れて使えなくなってしまった焼き物を粉砕して、もう一度粘土に戻された「リサイクル粘土」を使った器作りもしています。埋め立て処分するしかなかった焼き物を違う形に生まれ変わらせることができるんです。
――土は限りある資源。だからこそ土の存在を日常の中で想う時間を持てたらいいですよね。最後に、小國さんにとって土とは何か教えてください。
私にとって土は「生かしてもらっているもの」ですね。自分の職業としても、自分が食べる野菜やお米などすべての食べ物を育む点でも。そんな土を扱う陶芸は、知れば知るほど本当に奥が深い。芸術の表現方法ってたくさんあるけれど、私はこれからも土一本にしぼりたいし、奥が深すぎて一生やってもやり尽くせないかも(笑)。好きが根底にあるから、今、土と触れることが一番楽しいんですよ。
(取材・文/三好景子)

▲小國さんの作業場は、ガラス張りになっているため、外からもろくろを回す姿をみることができます。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
◉連続特集:静岡時代6月号(vol.35)『静岡の土を舐めたい』(4)
【"土"を愛する女子大生と、静岡県の陶芸作家。〜土がある生活を創る、陶芸家の土論〜】
●小國加奈(おぐにかな)さん〈写真中央〉
陶芸家。普段の器からランプまで、生活に寄り添う多種多様な作品を制作。静岡市内のカフェや料亭などでも小國さんの作る器が多く使われている。静岡市清水区の陶工房「KANa」では、小國さんの作品や器を実際に購入できるほか、陶芸体験もできるそう。
■小國加奈さんの陶工房「KANa」
住所:静岡市清水区有度坂5-16/☎054-347-7781
毎月1日~15日開店。16日~月末は作陶につき休業。静鉄電車「狐ケ崎駅」より徒歩で約12分。
【聞き手】
●樫田那美紀(かしだなみき)〈写真右〉
静岡大学人文社会科学部3年。静岡時代6月号(本連続特集企画)編集長。
特集企画立案の段階から、自身の土考を熱心に語る。目標は「この特集を通して"土の愛し方"を知る!」とのこと。
そして念願叶い、"自らの舌で土を味わった"。
→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1297872.html(知ることは舐めること。「静岡の土、いただきます」)
●三好景子(みよしけいこ)〈写真左〉
静岡大学教育学部3年。小國さんへの取材にむけて、樫田編集長とともに企画を練りに練ったメンバーのひとり。自身が教育学部で美術を専攻しているため、本取材内で吸収するものや共感できたものが多々あったそう。これまでの経験をふまえ、静岡時代10月号(vol.36)では副編集長をつとめた。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
・静岡時代6月号(vol.35)『静岡の土を舐めたい』バックナンバー
(1)【そもそも土って何ですか?】http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1384374.html
(2)【知ることは舐めること「静岡の土、いただきます」】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1297872.html
(3)【土と人が共にある原風景】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1384419.html
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Updated:2014年11月02日
"土"を愛する女子大生がみた、人と土のともにある風景〜書を捨てて、棚田に行こう〜
"土"に魅了された女子大生、樫田那美紀編集長(静岡大学3年)は今回、実地調査に向かいました。訪問先は土が生きる現場、菊川市にある【上倉沢の棚田】です。"農業"と"土"は相関関係。思い立った樫田は、案内人にNPOせんがまち棚田倶楽部事務局長の堀さんと静大棚田研究会の山本部長を迎え、世界農業遺産にも登録された田園風景を歩きました。もちろん、自らの五感すべてを使って静岡県の"土"の力を徹底調査。そこからみえてくる、私たちと土壌の切っても切り離せない関係とは!?
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

【案内】
●堀延広(ほりのぶひろ)さん〈写真左〉
NPO法人せんがまち棚田倶楽部 事務局長。生きものがにぎわう美しい棚田を目指し、棚田の回復と保存・維持の活動を行っている。菊川市北東部に位置する千框は、総面積10.1ha、3000枚以上の棚田で構成された風景が広がる。
→ http://www.tanada1504.net(棚田いこうよ.net)
■ 日本の田園風景・千框へ行こう!
静岡県菊川市倉沢1121-1(東名相良牧之原ICから約10分。東名菊川ICから約15分。新東名島田金谷ICから約15分)
●山本達郎(やまもとたつろう)さん〈写真中央〉
静岡大学理学部3年。棚田研究会(通称:棚けん) 部長。棚けんは2009年12月に設立。NPO法人せんがまち棚田倶楽部と連携して田植え、草刈などの棚田保全活動を行っている。また、シズオカガクセイ的新聞では月イチで、団体の活動や棚田の風景を伝えるレポートを連載中!
→ www.tanada1504.net/tanaken/(「しず大棚けん」ブログ)
【聞き手】
●樫田那美紀(かしだなみき)〈写真右〉
静岡大学人文社会科学部3年。静岡時代6月号(本連続特集企画)編集長。
特集企画立案の段階から、自身の土考を熱心に語る。目標は「この特集を通して"土の愛し方"を知る!」とのこと。
そして念願叶い、"自らの舌で土を味わった"。
→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1297872.html(知ることは舐めること。「静岡の土、いただきます」)
●亀山春佳(かめやまはるか)〈取材・執筆〉
静岡英和学院大学人間社会学部3年。静岡時代入部時より企画、取材、執筆など精力的に取り組む。自衛隊が好きで、『静岡時代』12月号(vol.37)の連載企画【ハタチの社会見学】では、念願の自衛隊取材へ赴く予定。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

▲取材の舞台となった、上倉沢の千框(せんがまち)棚田。かつては、廃田の危機に瀕したことがある。しかしNPOせんがまち棚田倶楽部・山本理事長の「先祖が汗水流して築いた棚田が滅んでしまうと、すぐ横のお墓の先祖が泣くぞ」という一声で、復田がはじまった。
■昔のものを守る。土の力って凄い。
――菊川市上倉沢にある千框の棚田は今も多様な生き物が集う日本の原風景。植物を育む土台となる「土」は、農業やそこに棲まう生き物たちにとってどのような存在なのでしょう。千框の棚田について教えてください。
静岡大学棚田研究会 山本さん(以下:山本さん):ここ上倉沢には江戸時代の中期に10ヘクタールもの立派な棚田があり、年に五百俵ものお米がとれたようです。今はかつての棚田面積のうち3分の1が復田しています。僕は棚田研究会で上倉沢の廃田でお芋や古代米をつくっています。大学祭などで、棚田でとれた古代米の販売や古代米を使ったたい焼きも販売しているんですよ。
――古代米のたい焼き! 美味しそうです。それにしても棚田が折り重なる風景は圧巻ですね。
せんがまち棚田倶楽部 堀さん(以下:堀さん):上倉沢周辺は地面に平らなところがなく、食べていくためには山を切り開いて棚田を作るしかなかったんです。昔は家族が一人増えるごとに一枚田を増やすなど、棚田は人々の生活と共にありました。せんがまち棚田倶楽部では、そんな棚田の保全活動をしています。山をそのまま切り開いたため、一枚として同じ形はありません。だから今の農業機械を使わず、棚田が作られた頃と同じで全て手作業。土に農薬などの化学肥料も使っていないので、土を舐めても問題ないぐらいです!

――そのくらい健康的な土壌なのですね! 農薬を一切使わない、千框の棚田は、土の力が大きいように思います。
堀さん:土に農薬をまかないことは、四百年前の戦国時代にこの棚田が切り開かれた頃から変わっていません。昭和50年代の減反政策によって、棚田は40年余り手付かずで放置されてしまうのですが、私たちが復田をすると「シャジクモ」という絶滅危惧種の藻が出てきたんです。昔のものを守る土の力は凄い。無農薬だから人が手入れしなくても、土や田が生きていたんです。僕たちが復田した時に、土が長い眠りからぱっと覚めた、そんな気がします。
山本さん:この棚田はそういった絶滅危惧種が多くいるんです。僕も今、必死に覚えようとしているのですが、種類が多くてなかなか厳しいです(笑)。
――何百年も前の人々が見ていた景色と動植物に触れられる。初めてこの棚田を見たときに感じた「懐かしさ」の所以が分かった気がします。
山本さん:僕も棚けんに入って、千框の棚田を初めて見たとき「すごい綺麗だな。なんだか好きだ」って思いましたね。時々お昼にこの棚田でとれた棚田米を食べさせてもらうのですが、これがまた美味しいんですよ。
堀さん:本当に美味しそうにバクバク食べてくれるよね。とはいえ、僕らはお米作りのためだけに千框の棚田を守っているんじゃないんです。「ニホンアカガエル」や「キキョウ」などの貴重な生き物や植物、そしてこの景観を守り残していくのが仕事だと考えています。ほら、今の時期だと日本在来種「シュレーゲルアオガエル」がちょうど産卵の時期を迎えていて、今も鳴き声がしていますよね。この声を聴くためだけに来る人もいるんですよ。
山本さん:棚けんで、お茶畑から棚田にかけて水を取り込む場所にビオトープを作ろうと試みているのですが、まだ成功したことがないんです。こんなに生き物がいるのにその場所だけには生き物は棲みついてくれないんです。
堀さん:そうなんだよね。僕のお茶畑は棚田のすぐ近くにあって、良質な茶葉にする為に窒素を多くする化学肥料をまきます。その結果、溶け出した肥料成分を含んだ水が棚田に流れ込み、水を取り込む場所に生き物は棲まなくなる。そんな茶畑から出た生き物に良くない水は、棚田を一枚通ると、土が余分な窒素を吸って生き物が棲みつく綺麗な水になるんです。この棚田が一つの大きな浄化装置なんですよね。



■人と土がともにある静岡県の原風景
――土と水は強く関係し合っているんですね。山本さんは棚けんに所属していて、私を含めた大半の学生よりも土に触れ合っている大学生ですよね。
山本さん:そうですね、僕も大学にいると不意に「最近棚田に行ってないな、行きたいな」と思うことがあります。慣れない作業を全て自力で行うのは大変ですが、どの作業も楽しいんです。
堀さん:一生懸命どろんこになりながらやってくれています。みんな全く土に抵抗ないしびっくりですよ(笑) 。
――この手と土で何かを育めるということを忘れてはいけませんね。堀さんにとって棚田の魅力とはなんですか?
堀さん:今の世の中には何でもあるけれど、この棚田には、何もないけど何かがあるんですよね。貴重な生き物だったり日本の原風景だったり、日本人が失くした大切なものがある。ここの棚田の目的はお米を売って僕らが生活をたてることでないからこそ、僕らも土と自由に交わえるんです。
山本さん:僕らも思いっきりわいわい騒いで楽しく作業できるし、部員のみんなも、この棚田が大好きなんです。
――お二人を見ていると、棚田が人を繋げているんだと実感します。私もまた棚田に遊びにきていいですか?
堀さん・山本さん:ぜひ! 棚田で待ってます!
(取材・文/亀山春佳)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
◉連続特集:静岡時代6月号(vol.35)『静岡の土を舐めたい』(3)
【"土"を愛する女子大生がみた、人と土のともにある風景〜書を捨てて、棚田に行こう〜】
【案内】
●堀延広(ほりのぶひろ)さん〈写真左〉
NPO法人せんがまち棚田倶楽部 事務局長。生きものがにぎわう美しい棚田を目指し、棚田の回復と保存・維持の活動を行っている。菊川市北東部に位置する千框は、総面積10.1ha、3000枚以上の棚田で構成された風景が広がる。
→ http://www.tanada1504.net(棚田いこうよ.net)
■ 日本の田園風景・千框へ行こう!
静岡県菊川市倉沢1121-1(東名相良牧之原ICから約10分。東名菊川ICから約15分。新東名島田金谷ICから約15分)
●山本達郎(やまもとたつろう)さん〈写真中央〉
静岡大学理学部3年。棚田研究会(通称:棚けん) 部長。棚けんは2009年12月に設立。NPO法人せんがまち棚田倶楽部と連携して田植え、草刈などの棚田保全活動を行っている。また、シズオカガクセイ的新聞では月イチで、団体の活動や棚田の風景を伝えるレポートを連載中!
→ www.tanada1504.net/tanaken/(「しず大棚けん」ブログ)
【聞き手】
●樫田那美紀(かしだなみき)〈写真右〉
静岡大学人文社会科学部3年。静岡時代6月号(本連続特集企画)編集長。
特集企画立案の段階から、自身の土考を熱心に語る。目標は「この特集を通して"土の愛し方"を知る!」とのこと。
そして念願叶い、"自らの舌で土を味わった"。
→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1297872.html(知ることは舐めること。「静岡の土、いただきます」)
●亀山春佳(かめやまはるか)〈取材・執筆〉
静岡英和学院大学人間社会学部3年。静岡時代入部時より企画、取材、執筆など精力的に取り組む。自衛隊が好きで、『静岡時代』12月号(vol.37)の連載企画【ハタチの社会見学】では、念願の自衛隊取材へ赴く予定。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
・静岡時代6月号(vol.35)『静岡の土を舐めたい』バックナンバー
(1)【そもそも土って何ですか?】http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1384374.html
(2)【知ることは舐めること「静岡の土、いただきます」】→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1297872.html
Updated:2014年10月27日
"土"を愛する女子大生と、静岡県の土壌学。〜そもそも土って何ですか?〜
突然ですがみなさん、最近「いつ土に触りましたか」? 雄大な山々に豊かな海。県内外から高い評価を受ける農産物。これらはすべて土によって作られ、育まれています。しかし、至極当然のことであるが故に、私たちは"土"そのものを軽視しがちなのではないでしょうか? 一見、地味な土だけど、「母なる大地」と呼ばれるほどの秘めたるパワーを持っている。まずは、「そもそも土って何なのか」、土壌学のスペシャリスト・静岡大学の南雲先生に聞いてみました。さらに、インタビューでは「静岡の土」にもスポットをあてて、"静岡県"と"土"の関係を探ってみました。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
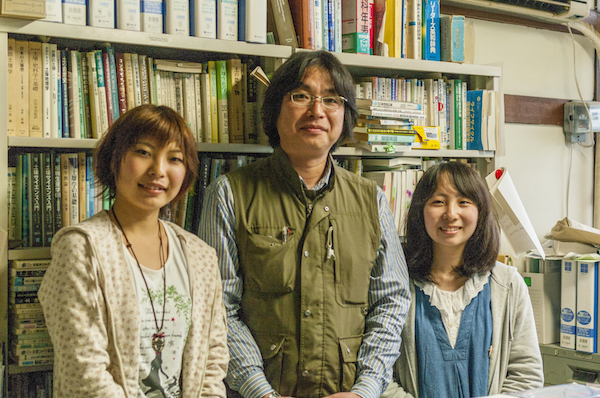
●南雲俊之(なぐもとしゆき)先生〈写真中央〉
静岡大学 農学部 共生バイオサイエンス学科 准教授。
研究分野は土壌肥学と持続可能型農業科学。土壌保全を目的とし、水田土壌に集積したリンの有効利用について主に研究されている。藤枝市にある農学部の所有する研究農場も研究拠点の一つだそう。
■このお話をもっと深く掘り下げたいひとへ〜南雲俊之先生からのオススメ本!〜
『土とはなんだろうか?』久馬一剛. 京都大学学術出版会.2005.
【聞き手】
●樫田那美紀(かしだなみき)〈写真右〉
静岡大学人文社会科学部3年。静岡時代6月号(本連続特集企画)編集長。
特集企画立案の段階から、自身の土考を熱心に語る。目標は「この特集を通して"土の愛し方"を知る!」とのこと。
そして念願叶い、"自らの舌で土を味わった"。
→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1297872.html(知ることは舐めること。「静岡の土、いただきます」)
※後日、静岡時代本誌の実舐ページが、農文協プロダクションの『図解でよくわかる土・肥料のきほん(誠文堂新光社)』に掲載されました!
●杉野花菜(すぎのかな)〈写真左〉
静岡大学人文社会科学部3年。冷静に、時に鋭いツッコミで企画・取材を滞りなく進めてくれるメンバーのひとり。
取材準備や取材メモはノートに見やすくまとめてあり(ちなみに字も綺麗)、編集部員のお手本になることも。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■自然物であり、植物が生育可能。それが土。
――南雲先生の専門分野である土壌学的にいうと「土」とはそもそもどういったものを指すのですか?
土壌学的にいうと「自然物であること」と「植物が生育している、もしくは生育可能である」という二つの条件を同時に満たすものを「土」と定義しています。
"自然物"というのは、水があり、植物がいる自然のなかでできたということ。たまたまそこにあった岩石の上、川の氾濫や火山の噴火などで堆積物が積もったところで、風化が生じ、また植物が侵入して植生が発達していく。このとき、雨が多いとか、植物の違いによって土に様々な変化が起こり、固有の土壌が作られます。
――では、砂場の砂は「砂」であって「土」とは呼べないのでしょうか?
砂場の砂は植物が生育可能なので土に分類できます。ただ、定義を厳密に適用しようとすると「植木鉢にいれた砂」というのは判断に困ることもあります。例えば、月の表面にあるものは土といえるか、考えてみてください。地球に持って帰って植木鉢に入れて、肥料をまいて種を植えたら植物が育ちそうな気がしませんか。しかし、月にある限り植物がいないので、残念ながら「植物が生育可能か」という定義によって土壌学でいうと月には土が存在しないことになります。

――植物が土の定義には必要不可欠なんですね。なんの変哲もないような土から植物が立派に育つことは不思議なことであり、目に見えずとも生命のうごめきのようなものを感じます。土の中で何が起きているのですか?
まず、土壌の岩石など「一次鉱物」の集合体が、雨風や岩石自身に含まれる水分の膨張などの影響を受けて風化され、鉱物自体に含まれている鉄、リン、カリウムが少しずつ溶け出します。これらの元素の多くは植物の栄養になります。土はこれらの栄養を蓄えて植物に与え、生育を助けています。
ただし、窒素は植物の生育において三大栄養素の一つで、大気中にたくさん存在しますが、植物はこの大気中に存在する窒素を自力で取り込むことはできない。ですが土の中に、大気中の窒素ガスを植物と共生しながら取り込むことのできる、ある種の微生物がいます。そのおかげで、植物は大気中の窒素を利用できるようになります。この微生物の働きを生物的窒素固定といいます。
土の性質としてもう一つ上手くできているのが排水の機能。雨が降ると土に水がしみ込んでいきますが、大雨でしみ込みきれなくなると、表面にあふれます。これは雨のとき川が茶色の濁流になる原因にもなります。でもいったん雨がやめば、すぐに重力の働きで余分な水を排水し、排水した分だけ酸素を含んだ新鮮な空気が土に入り根に届けられます。このとき全部の水を排水しないで、植物が使う分の水を残してくれる。これが土の働きです。
土は植物に水と栄養を届ける台所なのです。


■静岡県の土壌を豊かにする、"土"の恩恵。
――植物が育つコンディションを自然に整えてくれているんですね。では、静岡県の土の中で違いはありますか?
静岡県にしか存在しない土というのはありません。例えば、静岡県には、山地に「褐色森林土」、丘陵地には「黒ボク土」、「赤黄色土」、川沿いの低地には「グライ土」などが分布していますが、これは全国共通です。でも見たことないでしょうけど、この四つは色も形も異なるんですよ。その中でも「黒ボク土」は、世界遺産にも登録された富士山や観光名所が多い伊豆という静岡県東部に広がっていて、象徴的な土ですね。「黒ボク土」地帯は大規模な露地野菜産地になっていることが多く、静岡でも根菜類など多くの野菜が栽培されます。静岡県のものは主に穴の開いたボールのような形をしたアロフェンという鉱物が多いタイプのものです。
土に含まれる水(液相)、空気(気相)、鉱物と有機物(固相)の容積割合を百分率で示したものを「三相分布」と呼びます。一般的な土は、固相が約半分、残り半分は気相と液相で構成されています。それに対して黒ボク土は、鉱物の割合が全体の四分の一程度と少ないのが特徴。残り四分の三は液相と気相です。つまり、隙間が多いということ。粘土質の土壌だとべちゃべちゃするんだけど、黒ボク土は手触りも軽くてホクっとした感じになることが多い。おかげで植物の根が入りやすく伸びやすい。隙間がある分、排水もしやすい。こういった性質が野菜栽培に適しているんだと思います。
――黒ボク土、なかなかやりますね。土が含む物質により質感も植物の生育も大きく左右されているなんて驚きです。では、静岡県の土はどのように変化してきたのでしょうか。
県内の川で水質調査をしていると、お茶畑が多いほど川の水の硝酸濃度が高い。静岡県の特産品であるお茶畑には、窒素肥料が大量にまかれています。「土」にまいた肥料の一部が水質汚染の原因となるのです。
もう一つはリンの問題。日本の土は酸性土壌があったり、火山国のため火山灰の影響を強く受けたりしています。そうした土壌ではリンが土壌中のアルミニウムや鉄と完全に結合して、植物は利用できなくなります。そこで農作物の収穫量を上げる目的で、過去約50年間にわたりリン肥料がまかれてきました。しかし実際は、肥料として100まかれたもののうち90は土壌粒子と結合してしまい植物にとって利用不可能なものとなる。植物の成長に役立つのは残りの10だけ。一割の効果を得るために、何十年も肥料として大量にリンがまかれ続けたわけです。その結果、現在では、土壌に沢山のリンが溜まってきました。この溜まったリンから、ごく僅かずつではあるけれども、溶け出すリンが植物だけでなく環境にとっても無視できなくなってきている。この問題を、僕は水田土壌を対象に研究しています。
僕の研究は、お茶畑で使われる肥料と川の水質汚染の関係や、リンの溜まった水田ではこれ以上リンをまく必要がないということを、現地でのモニタリングやいろんな実験によりきちんとデータとして示し、土壌管理の正しい方向を見つけていくことを目標としています。

――お茶畑が水質汚染と関わっているとは思いもしませんでした。最後に、以前と比べ私たちが土と関わる機会は減っていると感じます。土と私たちの繋がりはどうなっていくのでしょうか。
僕が子どもの頃に比べ道路や工場は増えて、あぜ道や緑や土が減ったと感じます。ただ、いったんコンクリートの下に埋めたてられてしまった土はしょうがないでしょう。もとは田んぼが広がっていた場所も、田んぼを続けられなくなった理由があって埋め立てられたのだろうから。そういう場所を田んぼだった頃の状態に戻してまで、もう一度田んぼをやる人がいるだろうか。その変化はどうしようもないことだから、受け入れるしかない。今ある農地もいずれは埋め立てられるかもしれない。そんな今だから、残った田んぼや畑で、いかに上手く土壌を育てて管理するのかを考えていく。そのために、土壌学の視点から環境への負荷を少なくしつつ、土壌保全を行うことが僕の担っている役目だと感じますね。
(取材・文/杉野花菜)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
◉連続特集:静岡時代6月号(vol.35)『静岡の土を舐めたい』(1)
【"土"を愛する女子大生と、静岡県の土壌学。〜そもそも土って何ですか?〜】
●南雲俊之(なぐもとしゆき)先生〈写真中央〉
静岡大学 農学部 共生バイオサイエンス学科 准教授。
研究分野は土壌肥学と持続可能型農業科学。土壌保全を目的とし、水田土壌に集積したリンの有効利用について主に研究されている。藤枝市にある農学部の所有する研究農場も研究拠点の一つだそう。
■このお話をもっと深く掘り下げたいひとへ〜南雲俊之先生からのオススメ本!〜
『土とはなんだろうか?』久馬一剛. 京都大学学術出版会.2005.
【聞き手】
●樫田那美紀(かしだなみき)〈写真右〉
静岡大学人文社会科学部3年。静岡時代6月号(本連続特集企画)編集長。
特集企画立案の段階から、自身の土考を熱心に語る。目標は「この特集を通して"土の愛し方"を知る!」とのこと。
そして念願叶い、"自らの舌で土を味わった"。
→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1297872.html(知ることは舐めること。「静岡の土、いただきます」)
※後日、静岡時代本誌の実舐ページが、農文協プロダクションの『図解でよくわかる土・肥料のきほん(誠文堂新光社)』に掲載されました!
●杉野花菜(すぎのかな)〈写真左〉
静岡大学人文社会科学部3年。冷静に、時に鋭いツッコミで企画・取材を滞りなく進めてくれるメンバーのひとり。
取材準備や取材メモはノートに見やすくまとめてあり(ちなみに字も綺麗)、編集部員のお手本になることも。
■静岡時代6月号本誌内、【知ることは舐めること、「静岡の土いただきます」】ページ掲載書籍。
『図解でよくわかる 土・肥料のきほん(誠文堂新光社)』
http://www.seibundo-shinkosha.net/products/detail.php?product_id=4259
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Updated:2014年10月21日
静岡県の大学生200人に聞きました みんなの卒論・卒制、のぞき。
大学時代とは「卒業論文」である。大学生にとって、卒論・卒制は避けては通れない大学時代の最終関門であり、集大成。静岡県は23の大学・約180もの学科があるけれど、大学や学部ごとで学んでいることは全く異なる(だから面白い!)。大学ならではの卒論事情は?隣の大学のアイツも、同じ大学のコイツも実は「静かな闘志」を抱いてた?2014年の夏休み、静岡時代編集部があらゆる人脈を駆使し、大学生の卒論事情を徹底調査!アンケートの回答者、その数202人!学生のリアル、大公開(高校生も、先生方も必見です)![※回答は4年生から卒業後2年に限定。現役大学生148人と卒業生54人にご協力いただきました。
ご協力くださった皆様、ありがとうございました!!]
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
▲200人アンケート達成!
■そもそも卒論・卒制は「必須」ではない!?
大学に卒論・卒制の文化を残すには?
今号(静岡時代36号)の巻頭特集で「大学時代は卒業論文である」と豪語してきた編集部。しかし、実際のところ「必須ではない」大学・学部もあるのだそう。アンケートにご協力いただいた人たちの中でも、必須ではないと答えた人が35人、全体の17%でした。
例えば、常葉大学の外国語学部・教育学部、静岡文化芸術大学文化政策学部、日本大学国際関係学部、静岡大学人文社会科学部法学科など一部では卒論は必須ではないとのこと。でも、必須ではない学部学科でも卒論や卒制に取り組む学生もいます。
かつて、卒論・卒制は大学生の青春そのものでした。大学生にとって卒論・卒制とはなんなのか?大学に卒論・卒制の文化を残すには?本誌10月号巻頭特集に登場いただいた本多先生のインタビューは必読です!
★「伝説の卒業論文」シリーズ/記事
(1)そもそも卒論って何?(本多先生インタビュー)→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1388029.html
(2)卒論の天敵「誘惑」の本質とは?→ http://gakuseinews.eshizuoka.jp/e1464051.html
★静岡時代10月号は10月1日より順次、大学構内にて配布
配布場所一覧はこちら http://www.shizuokajidai.net/大学生の雑誌-静岡時代/
■気になる調査結果、発表!
9割が「静かな闘志」を抱いている

Q1 卒業論文・卒業制作へのモチベーションは?
A 9割が静かな闘志を抱いている
・実は心底はりきっている……16%
・どうせならいいものを……72%
・卒業できればなんだっていい……13%
Q2 高校生・入学時の卒論・卒制に対するイメージは?
・大変そう(多数)
・自分の好きなことを、思う存分に研究するって楽しそう(静岡大学教育学部・女・YW)
・大学に入学する頃から卒論で書きたいと思う内容があり、大学での4年間のうちにそれに関する知識を身につけたいと思っていた(静岡英和学院大学人間社会学部2014卒・女・IK)
・一生の思い出になるもの(静岡大学情報学部・2014年卒・女・わーこ)
・今まで誰も考えなかった合成方法を実験を通して発見して、自分でまとめることにとても憧れを持っていた(静岡理工科大学理工学部2014年卒・女・YKR)
・「追究する」ってかっこいい(静岡大学人文社会科学部2013年卒・女・あ)
・難しそうだが、やりがいがありそう(静岡大学工学部2014卒・男・TK)
・様々なところにアンケートを依頼して、分析することにかっこよさを感じてた(静岡大学教育学部2014卒・男・Y)
・あることも知らなかった(静岡大学理学部・女・A)
・美大の卒業制作展に対してすごそうなイメージを持っていた(静岡文化芸術大学デザイン学部4年・女・ぴこ)(静岡文化芸術大学デザイン学部4年・男・PINO)
・大学生活の集大成(多数)
・ハチクロの影響でとにかく輝かしいイメージ(静大教育学部芸術文化課程・男・MA)
・作文苦手(静岡文化芸術大学文化政策学部4年・女・しろやま)(静岡大学人文社会科学部4年・男・じじい)
・大きな場での発表があるためわくわくした(静岡大学教育学部2014年卒・女・森の海藻)
・連日の徹夜といういかにもな研究姿勢に憧れ(静岡大学工学部2014卒・男・みよかつ)
・卒業した証(静岡大学人文社会科学部・女・ちろ)
・ドラマにでてくる修羅場な感じに憧れ(静大教育学部・女・タックル)
・通過儀礼(静岡大学教育学部4年・男・FH)
・「論文」という言葉の響きが大人のようで憧れ(静岡英和学院大学人間社会学部4年・女・るい)
・正直そこまで考えていませんでした(静岡大学情報学部4年・男)
・卒業よりも就職のほうが大事(静岡大学人文社会科学部4年・男・N)
・4年間の成果を目に見える形で後世に残せる(静岡大学工学部院2・男・ムークン)
・登竜門(静岡県立大学経営情報学部・女・スズ)
・「論文=かっこいい」(静岡県立大学国際関係学部・女・YH)
・やらなければいけないもの(日本大学国際関係学部4年・女・みか)
・「卒業論文執筆してるんだよね」って言って遊びを一回断りたかった(静岡大学教育学部2013卒・男・リョコヒキ)
・大学生といえば、研究!研究=かっこいい!(静大情報学部4年・女・N)
Q3 卒論・卒制を真っ最中(もしくは終えた)いま、卒業論文・卒業制作に対するイメージは?
・大変だけどやりがいのあるもの。人生で一度きりだと思うから(静岡大学教育学部4年・男・KY)
・就活のためというイメージ。たかが学部4年間だから集大成も何もない(静岡大学人文社会科学部4年・男・らおう)
・悩み悩み悩み悩み悩んでうちこんでやるもの(静岡大学人文社会科学部2013年卒・女・あ)
・自分の考えたことを周りに伝えることができる手段(静岡大学人文社会科学部2014卒・男・YN)
・自分の興味ある分野について追究できる(静岡大学人文社会科学部2013卒・女・AY)
・4年間の集大成(多数)
・手を抜くことも全力で取り組むこともできるもの。その人の大学生活での学業に対しての姿勢がわかりやすい形となって表れる(静岡県立大学経営情報学部・女・ST)
・卒業論文はあって当然のもの。大学が研究機関であり、その中で自分が籍を置いている。ということは、当たり前ながらそこでの成果を自分なりに表現するべきだと思う(日本大学国際関係学部・男・いいんちょ!)
・研究室に缶詰して、狂ったように書くもの(静岡大学情報学部4年・女・N)
・大学に入れば、かっこいい作品をつくる技術が自然に身に付くと思っていた(静岡産業大学情報学部2013卒・女・CK)
・どうせやるのなら、自分のためにも、協力してくださった人のためにも役に立つものにしたかった(静岡大学教育学部2013卒・女・MS)
・膨大な資料と書籍をかき集めて自分の課題に対して提言するもの。人生で最も文章をかく瞬間(静岡県立大学国際関係学部4年・女・りん太郎)
・大学生活4年間だけでなく、今までの人生で学んで培ってきたものの集大成であり、けじめをつけ今後社会人としての自分の新たな出発地点となるもの(常葉大学造形学部4年・女・TS)
・成果がないと論文は書けない(静岡県立大学食品栄養科学部4年・男・おおちゃん)
・卒論=研究。大学に入学してからの授業はなんだか教養科目的で驚いた。内心もっと研究というか専門的なことばかりだと思っていたので。なのでその分卒論は教授や仲間と共に探求する「研究」でありたい(静岡大学人文社会科学部・女・もくもく)
・しんどい(日本大学国際関係学部・男・K)
・何かしらの壁に気づくためのもの。自分の知識と語彙力不足、今までの勉強の不真面目さ、体系的にものを考えられない頭、などなど(静岡大学人文社会科学部2013卒・男・RK)
・論文=誰もがかっこよくなれる瞬間(静岡県立大学国際関係学部・女・YH)
・大卒の言い訳(常葉大学造形学部2013卒・女・YS)
Q4 卒業論文・卒業制作を通して、あなたの「なりたい自分」を教えてください(スローガンっぽく!)
マイノリティスト(日本大学国際関係学部4年・男・づめ)/目指せ!世界レベル(静岡大学工学部修士2年・男・大谷翔平)/物事の全体を見通す余裕のある自分(静岡大学教育学部4年・女・あ)/研究に費やした時間よ、社蓄をも凌げ!!!(静岡大学教育学部修士2年・男・みたらしだんご)/カリスマくそやろう(静岡大学教育学部2013卒・男・リョコヒキ)/芯のある人(静岡大学教育学部・女・こじゃ)(静岡大学人文社会科学部4年・女・みやむー)(静岡文化芸術大学文化政策学部・女・DS)/今までに無い新しい発見をする(静岡大学理学部修士2年・女・A)/どこまで本気になれるか。結果を出すことで自信につなげる(静岡大学農学部2013卒・男・たんぽぽ)/完全燃焼(静岡大学教育学部教修士1年・女・た)/童謡のスペシャリスト(静岡文化芸術大学文化政策学部4年・女・KM)/研究者の卵!(笑)(静岡県立大学食品栄養科学部4年・男・SH)/卒業できる身分!(静岡大学人文社会科学部2013卒・女・むらせ)/要領のよい人間に!(多数)/春からの仕事に繋げる!(静岡文化芸術大学文化政策学部4年・女・さくさくぱんだ)/やるなら徹底的に(日本大学国際関係学部・女・YH)/一流のエンジニアに!(静岡大学工学部4年・男・SE)/「大好き」を追っていきたい(静岡英和学院大学人間社会学部4年・女・るい)/クリエイティブな理科専科教師(静岡大学教育学部4年・男・あああ)/学んできたことがはっきり言える私(静岡文化芸術大学文化政策学部4年・女・しろやま)/先生が「この子が入ってくれて良かった」って思うような人(静岡大学教育学部4年・RS)/イマを生きるかっこいい大人(静岡大学教育学部2014卒・女・みぃみ)/塞翁が馬!!(静岡大学工学部院2・男・ムークン)/静岡大学にいた証をつくる!(静岡大学教育学部4年・男・KO)/胸を張って学生を卒業する(日本大学国際関係学部4年・女・みか)/学ばされる心意気から、自ら問う心意気へ(東海大学海洋学部4年・男・MT)/静岡のアインシュタインになる!(静岡大学工学部2014卒・男・もろこしタロー)/論理的に考えることのできる自分!(静岡県立大学看護学部4年・女・MA)/地獄からの帰還(静岡大学人文社会科学部2013卒・男・HT)/先生を怒らせない(常葉大学造形学部2013卒・女・YS)/感じろ、己の小宇宙(静岡大学教育学部・女・NW)/研究し、突き詰めることにより人生は輝きを増す!(静岡英和学院大学人間社会学部・男・TO)
◉編集部のひとこと
入学時は7割の学生が「卒論のイメージが湧かない」と答えていたが、大学生活を送る中で卒論がプラスに転換していくみたい。ちなみに、デザイン学部や美術専攻の学生は、卒業制作展を見に行った経験がある人が多く、先輩の姿や制作そのものに憧れを抱いている人が多数!
■マニアック?なんかすごそうな卒論
静岡時代編集部の思う、「なんかすごそう!」10選

▲「夏休みで大学の空調とまったから、カエルのコンディション最悪だよ……」(静大・YO)
Q5 卒業論文・卒業制作のテーマは?
・食の歴史(食歴)を履歴書形式で追う「食の履歴書」(静岡産業大学情報学部 ・女・CK)
・文献は最低100!「アフリカツメガエルの初期発生における 老化制御因子の解析(静岡大学大学院農学研究科・男・ YO)
・八千万の機材を操る男「カーボンナノチューブを用いた複合材料について」(静岡大学工学部機械工学科2014卒・TK)
・風をよむ男「北半球中緯度海域における海上気象要素の長期変動」(東海大学海洋学部・男・MY)
・温度受容体から皮膚病の予防や治療を「hTRPV3、hTRPV4の活性、阻害成分の探索」(静岡県立大学食品栄養科学部・男・SH)
・古代ギリシャ哲学者から紐解く「愛の区別」(静岡大学人文社会科学部・女・れんれん)
・日本人はホントに無宗教?「日本の宗教看守と無宗教について」(浜松学院大学現代コミュニケーション学部・女・RH)
・「近代クラシック演奏会文化における諸課題と、それを打破する寛容で、創造的な音楽ワークショップの可能性 〜マイケル・スペンサーの実践を事例に〜」(静岡大学教育学部・男・KO)
・実は期限に間に合わなかった……orz「図書館内サイン計画の見直し」(常葉大学造形学部2013卒・女・YS)
・岩石から地球を知るロマン「オマーンオフィオライトヒルチかんらん岩体ハルツバージャイトの結晶方位ファブリックの特徴について」(静岡大学理学部地球科学科・女・A)
Q6 ……ウソだろ?テーマのきっかけとなった出来事や人は?
A 「○○学を学ぶうちに」「先生にすすめられて」「先輩に憧れて」が多い。
そんななか度肝を抜かれた(「へえー!」含む)回答がこちら!
・実習中にアロマテラピーをしているところを見て、服薬以外に苦痛を取り除くことができることに興味を持ったから(静岡県立大学看護学部4年・女・MA)
・これから期待される液体「磁性流体」に魅力が湧いた(静岡大学工学部機械工学科2014卒・男・もろこしタロー)
・利き足と非利き足の違いが気になった(常葉大学保健医療学部2014卒・女・SK)
・「どんなに熱しても蒸発しない液体」と聞いて興味を持った(静岡大学教育学部教育学研究科教育研究専攻理科教育専修修士2年・男・みたらしだんご)
・たまたま筆がなくて、その辺にあるものでキャンパスに下地を塗ったら面白かった(静岡大学教育学部美術教育専修2014卒・女・O)
・先輩から「頭が悪くてもできるテーマ、体を使えば良い」と言われたため(静岡大学工学部機械工学科2014卒・TK)
・軽い不眠症になった時にふと聞いたラジオ(浜松学院大学現代コミュニケーション学部・女・KK)
・恋愛と友愛は分けられないのだろうか……?(静岡大学人文社会科学部・女・れんれん)
・司書にむかついた(常葉大学造形学部2013卒・女・YS)
・就職活動が嫌で、でも向き合わなくてはいけなくて、「食の履歴書」(卒制)を書くところから始めようと思った(静岡産業大学情報学部 ・女・CK)
Q6 あなたの卒論・卒制、ハウマッチ?
A 最高額は八千万!(研究機材です)
何十万、何千万もかかる研究費や制作費、背負っているものがあるから「必死」という声もある。
Q7 どのくらい文献読みますか?
A 30冊。中には100冊が最低ライン!という人も。
◉編集部のひとこと
当たり前のことだけど、理系や文系、美術で全く異なる卒論・卒制のテーマや着眼点。「まずテーマを決めることが難しい(けどテーマを決めるところから、卒論ははじまっている!)」と先生や先輩は言うけれど、普段の生活や世の中の社会現象を絡めてテーマに結びつけていくことが王道っぽい。理系の研究室のなかには先行研究を引き継いでいくケースも。
▶合わせて読みたい。編集部イチオシ記事!
「静岡県のすべての學コンシャスに捧ぐ「良い論文とは“とんがり”」をつくること」(静岡時代10月号特集インタビュー:p.10)
■卒論の赤本。傾向と対策は?
絶対ルールは2万字以上。「彼氏・彼女・美人」に注意せよ!

▲「オレ、彼女にフラれた」(多数)「
Q8 絶対ルールは?
A 三大常識。コピペ禁止・締切厳守・2万字以上!
・最低4万字の字数制限(静岡大学教育学部4年・男・TM)
・統計的手法を使うこと(静岡大学人文社会学部2014卒・女・むらせ)
・教授が好きなフォーマットが決まっており、必ずそれに合わせる(静岡大学農学部2013卒・男・たんぽぽ)
・ゴーストライター禁止(静岡大学人文社会学部4年・男・らおう)
・現地調査をするにあたって対象者に失礼のないようにすること(浜松学院大学現代コミュニケーション学部・男・YN)
・研究室内で物を食べない(静岡大学教育学部修士2年・男・みたらしだんご)
・仮説を立て、実際に足を運んで調査する(静岡県立大学経営情報学部2012卒・女・スズ)
・危ないことはしない(静岡大学教育学部4年・男・gerugeru)
・論文が書けたら、同期→直属の先輩→指導教員の順に添削して貰う(静岡大学教育学部4年・男・FH)
・英語で書く(常葉大学外国語学部4年・女・おらたん)
・先生に逆らわない(静岡大学教育学部2013卒・男・ヒョコリキ)
・調査地点の環境保護のため無駄な殺生の禁止(東海大学海洋学部4年・男・MT)
Q9 卒論・卒制にまつわる学部学科・研究室・ゼミのあるあるや信条、御法度は?
A「むむ、このレッドブルの量。この研究室やりおる」(静岡大学工学部生談)
・教授からの指摘は「刺される」と表現する(静岡県立大学経営情報学部2013卒・男・RH)
・同じゼミの仲間と日々進行状況を確認しあい、サボる時はみんなで同時にサボる(静岡産業大学情報学部2013卒・女・CK)
・提出前は徹夜続きでアトリエにこもる。後輩と仲良いほうが有利!手伝って貰える(静岡文化芸術大学デザイン学部4年・女・ぴこ)
・卒論前は培地の減りが半端ない(静岡大学農学部4年・女・RM)
・先生の所在表が「食事中」となってるときは、不可侵、たとえ3時間以上「食事中」のままであっても(静岡大学教育学部修士2年・男・みたらしだんご)
・ゼミのPC周りの私物化。資料、食料等が置いたままになっている(常葉大学造形学部4年・女・澤田)
・学部生が卒論のフィールド調査のために、海外まで足を運ぶこともある。ワイン好きの教授のため、ワイン片手に卒論の方針について話し合ったことも(静岡県立大学経営情報学部2012卒・女・ST)
・ゼミの初めに発表する人は大概フルボッコ。最後の人は時間が足りなかったり、教授も疲れたりで適当になる(静岡大学工学部2013卒・男・たんぽぽ)
・研究室には常に味噌汁と春雨が常備(静岡大学教育学部4年・女・WS)
・研究室には常にカップ麺が常備(東海大学海洋学部2014卒・男・MY)
・基本的に文献は英語で書かれているもののみ(日本大学国際関係学部・男・A)
・卒論が終わる頃 には教授のものまねが上手くなっている.(静岡大学工学部2014卒・男・TK)
・のりちゃん(ゼミの先生)と対立する意見は避けろ(静岡大学人文社会学部・女・ちろ)
・先生が海外出張帰りにくれる中国のお土産のこの上ないまずさ(静岡県立大学国際関係学部2013卒・女・YH)
・ゼミ室にあるプーさんの人形は大事にすべし(静岡大学教育学部2013卒・女・M)
・自作した機材がショート(静岡大学教育学部4年・男・あああ)
・卒論提出期限は1月。でも国家試験受験者は試験勉強に集中するため、10月完成を目指す(静岡英和学院大学人間社会学部4年・女・RO)
・ゼミ担がなかなか捕まらない。予告なしで前日などにいきなりゼミが入る(常葉大学教育学部4年・女・えつこ)
・「卒制やってる?」「制作進んでる?」等の話題を出すと皆静かになる(静岡大学教育学部4年・女・フトアゴ)
・土日深夜問わず基本誰かが研究室にいる(静岡大学工学部2014卒・男・みよかつ)
・ゴミ箱にレッドブルの空き缶がいっぱいあるゼミ室はワークの量が多い(静岡大学工学部2014卒・男・ムークン)
Q10 卒論・卒制における仲間はどんな人?
一位「ゼミ仲間」……40人
・どうしても方向性が決まらなくて精神的に追い込まれていたときに、時間をかけて話をきいてくれた(静岡大学教育学部2013卒・女・M)
・装置の使い方や,論文の内容などわからないことをすぐ、気兼ねなく聞けるゼミ室の仲間(静岡大学工学部2014卒・男・ムークン)
・課題がゼミの日までにできていなくて、さりげなく順番を後回しにしてくれた神様、ゼミ長(静岡県立大学国際関係学部2013卒・女・YH)
・毎週ゼミでの進捗状況の報告は大変だが、いい刺激になっている。お互いに気持ちを分かち合ったり、アドバイスしたり、仲間の存在は大きい。皆が頑張っているなら、自分も頑張らなくては…という気持ちになる(静岡英和学院大学人間社会学部4年・女・RO)
・会う度に持っている資料の量が増えていった子がいて、それを見て焦る自分がいました。仲間であり、ライバルでもありました(静岡文化芸術大学デザイン学部2014卒・女・AU)
二位「先輩」……8人
・23時ぐらいまで測定をしていて、サンプルの処理をどうすればよいか先輩に連絡したときに、わざわざ自宅から学校まで大量の差し入れを持って来てくれた(静岡大学教育学部4年・女・つん)
・無口な先輩だが、とてもプレゼンがうまかった。あとで聞いたら二日で作ったらしく、その才能に感動した(静岡大学工学部4年・男・ガル)
・1年スロバキアへ留学に行っていた1つ上の先輩。尊敬してない先輩に敬語を使う必要はないと言われたことは印象的だった(静岡大学教育学部4年・女・AH)
三位「ゼミの教授」……7人
・他大学に異動された元ゼミの先生。その先生が勤めている沖縄の大学まで会いに行き、その夜サシで居酒屋に行き、泡盛を飲みながら卒論について熱く相談にのってもらった(静岡大学教育学部4年・男・KO)
・一人で研究していたので基本は教授。深夜まで一緒にやってくれたこともありました(静岡大学工学部2014卒・男・みよかつ)
・テーマ設定から資料探しまで、いろいろなことで相談に乗っていただいています(静岡文化芸術大学文化政策学部4年・女・しろやま)
Q11 「宿敵」はいますか?
一位「自分」……28人
・適当に仕上げようと思えばそうできてしまえる分、自分がいかに怠け心を出さずに卒論に向き合えるかが鍵になると思う(静岡大学人文社会科学部4年・女・MS)
・あとでやればいいや…などと思ってしまう弱い自分がすぐ出てくる(静岡英和学院大学人間社会学部4年・女・RO)
・強いて言うなら自分。実験に失敗してもめげずに続けていくことが大事です(静岡県立大学食品栄養科学部4年・男・SH)
・自分の甘え。就職が決まるとやってくる安心感。研究や制作はハングリーな状態でないとできないと思う(静岡大学教育学部2014卒・女・みぃみ)
・興味が1〜2ヶ月サイクルで移り変わるのと、日常的に閉め切りギリギリにならないと取りかからないので(静岡県立大学国際関係学部4年・女・CS)
二位「ゼミの教授」……18人
・その道のプロフェッショナルからの指摘・質問が一番怖い。準備不足の発表をした時には、「君はみんなの時間を無駄にした」と言われた(静岡大学教育学部4年・男・FH)
・どんなにやってもダメ出しがくるので「わたしはあんたみたいに頭よくないよ!」と目で訴えてました(常葉大学2014卒・女・ゆか)
・論文の添削をお願いすると真っ赤になって返され、書き直しをたくさんさせられた(静岡大学工学部2014卒・男・もろこしタロー)
・実験レポートを延々と再提出させられた。卒論でボコボコに言われるのが本当に怖い(静岡大学工学部4年・男・ガル)
・12月の一番大変な時期に長期海外出張に出かけてしまい連絡がほとんど取れなくなった(静岡県立大学経営情報学部2012卒・女・ST)
・いつも目が笑っていない笑顔でダメだしされる(静岡文化芸術大学2011卒・女・りか)
・とにかく根拠ある記述しか認めない人。誤字・脱字があるだけでキレる人。文献を100冊以上読まないとキレる人。でも頑張って取り組めば、その分しっかり面倒を見てくれる人。宿敵であり恩師(常葉大学教育学部2013卒・女・SF)
三位「眠気」……4人
・明け方の3時4時が一番辛い。作業したまま気づいたら寝てる(静岡大学教育学部修士1年・女・た)
・ガムやコーヒー、栄養ドリンクにはお世話になりました(静岡大学教育学部2013卒・女・MS)
・眠気とモチベーションの低下。実験は暗室でやったり、単純作業だったりするので(静岡大学工学部2014卒・男・KN)
その他
・強いて言えばイエス様です。日本人なので(文献中で)「キリスト教的な云々」言われると感覚で理解できず苦しかった思い出があります。だからと言ってその深淵には辿り着けないのがつらいとこです(静岡大学人文社会科学部2014卒・男・斉藤)
・期限。時間がねぇ….(静岡大学教育学部4年・男・たくみん)
・同じゼミの元彼女。自分の卒論について辛辣に批判してくれたので、絶対に見返したい(静岡大学教育学部4年・男・KO)
・アルバイト先の店長。卒論に必死な私に、人が足りないから、バイト入ってくれの連絡がしつこい(静岡大学情報学部2014卒・女・わーこ)
・台風。調査を司っている(東海大学海洋学部4年・男・MT)
・卒論・卒制をやらない友達。頻繁に遊びの誘いをしてくる(静岡産業大学情報学部2013卒・女・CK)
Q12 困ったとき、助けてくれた人は誰ですか?
一位「ゼミの教授」……37人
・卒論の方向性に悩んだときに今まで私が読んだ本や引っかかっていた文章、興味を持っていたことを教授がうまくつなげてくれて方向性がすんなり見えてきたのには感動した(静岡大学人文社会科学部4年・女・れんれん)
・卒論制作の課程で何か行き詰まると、必ず相談しに行き、アドバイスを貰う。先生に相談すると新たな視点に気付かせて貰える(静岡英和学院大学経済学部4年・女・SS)
・自宅にも招かれ、たくさんの本をいただき、それを論文に活用した(静岡大学人文社会科学部2013 卒・男・RK)
・助けられたことは多いが、特に心に残っているのは、提出期限ギリギリで印刷をしているときに用紙が足りなくなり、タダでくれたこと。夜なので買いに行けなくてピンチのところを救われた(静岡大学教育学部2013卒・女・MS)
・よくわからない化合物が取れたときに一緒に解明してくれた(静岡県立大学食品栄養科学部4年・女・SC)
・もはや話を聞いてくれるだけで嬉しい(文化芸術大学文化政策学部4年・女・KM)
二位「ゼミ仲間」……32人
・院に通う違う学科の先輩にたまたま食堂で会い、テーマや考え方について多角的なアイディアをいただきました(静岡大学教育学部4年・女・AH)
・落ち込んでいるときにそっと近寄って話を聞いてくれた(静岡福祉大学社会福祉学部4年・男・KS)
・偶然図書館であって与太話したことが一番楽しかった(静岡大学人文社会科学部2014卒・女・むらせ)
・同じ時間に指導を受けていた為、互いの進捗状況を伝え合い、フォローやアドバイスをして乗り切っていた(常葉大学教育学部2013卒・女・SF)
三位「先輩」……16人
・二人の先輩。一人は、簡単には答えを言わず、自分自身で考えるよう導いてくれた。もう一人は、自分の弱音を最後まで聞いてくれた(静岡大学教育学部4年・男・FH)
・となりの席にいた同学年だけど3歳年上の研究室の長老。研究が嫌になった時の気分転換に付き合ってくれた(静岡大学工学部2013卒・男・もろこしタロー)
・操作途中ですぐに止めて正してくれる。そのおかげで大きな失敗はしていない(静岡大学農学部4年・男・かい)
・院生。効率の良いデータ処理方法を教えてもらった(東海大学海洋学部4年・男・MT)
・実験を始めたころは右も左もわからず、一つ一つの実験操作の意味がわかりませんでしたが、研究室の先輩が丁寧に教えてくれたことで理解できました(静岡県立大学食品栄養科学部4年・男・SH)
その他
・大学外のその専門の職の方たち。「君の卒論で救われる人はたくさんいる」と言ってくれた(静岡大学教育学部4年・男・KO)
・たまに来る母からの電話。ちょっとうるさいけど息抜きになる(静岡県立大学2013卒・女・SH)
・中間発表でデータがクラッシュした時に、(私が即席で資料を鬼作成しているところを)何も言わず見守ってくれていた同年代と後輩たち。そのとき私は静岡時代の編集長で締切前でした(静岡県立大学国際関係学部2013卒・女・YH)
・学校の図書館の事務員さんが私のテーマに合ったおすすめの文献を教えてくれた(静岡英和学院大学人間社会学部2014卒・女・IK)
・姉。寝てると起こしてくれる(静岡産業大学情報学部2013卒・女・CK)
・実験の時間が合わないとき、先輩や後輩、そして同期で作業を交代した事がありました。困った時はお互い様と皆で協力し合う事で時間的問題を解決しました(静岡大学農学部博士4年・男・YO)
Q13 卒論・卒制の闘いのなか一緒にいてくれた人(癒しの存在)は誰ですか?
一位「友人」……36人
・これまで大学生活の苦楽をともにしてきた仲間だからとても支えになる(静岡大学教育学部4年・女・リコピン)
・各々がいろんな人をフォローし乗り越えた。特定の人でなく多くの人に癒やされ助けられた(静岡大学教育学部2014卒・女・森の海藻)
・研究室の同期。徹夜も一人だったら耐えられなかった(静岡大学工学部2014卒・男・TK)
・アルバイトの仲間。おしゃべりでスッキリして、おいしいまかないを食べる(静岡大学工学部修士2年・女・な)
・まず、先生の笑顔にいやされます。たぶん、辛い時に一緒にお酒を飲んでくれたりするでしょう。また、研究室は古本の甘い良いにおいがするので、それも癒しポイントです(静岡県立大学国際関係学部4年・女・CS)
・同じ学年の友人。実験が上手く行かなかったーって話を聞くと、自分だけ失敗しているんじゃないと安心できる(静岡県立大学食品栄養科学部4年・男・SH)
二位「ペット」……9人
・ペットの猫。キスしたりお腹を撫でまわしたりするだけで癒された(静岡大学人文社会科学部2013卒・男・RK)
・ミニ卒論のときの癒しは、研究とは関係なく飼われていたイモリとベルツノガエルだった、可愛い。(実験用のカエルはアフリカツメガエル)(静岡大学教育学部4年・女・RS)
・猫(くろべえ)(静岡産業大学情報学部2013卒・女・CK)
三位「ゼミの教授」……8人
・いつもにこにこゼミの教授(静岡大学人文社会科学部4年・女・れんれん)
・かわいい(静岡大学教育学部4年・男・あああ)
その他
・彼氏。励まし合いながらがんばった(静岡大学人文社会科学部2014卒・女・KY)
・図書館で稀に見かけるあの美人。何気無く相席に座る(日本大学国際関係学部4年・男・づめ)
・同じ大学を卒業した年上の彼氏に、なかなか書き進められないイライラを八つ当たりしながら書き上げました。申し訳ないことをしました(英和学院大学人間社会学部2014卒・女・IK)
・研究室の技術補佐官の方。可愛い(静岡大学教育学部4年・女・つん)
・息抜きのおやつ。暑い研究室でも、扇風機の前でアイスを食べてリフレッシュ!(静岡大学教育学部4年・女・フトアゴ)
・母のおいしいごはん(静岡県立大学国際関係学部2013卒・女・YH)
・ミッキーマウスとミニーマウス(静岡文化芸術大学造形学部4年・男・PINO)
・カロリーメイト。すぐに食べられるバランス栄養食ですよ(静岡大学工学部2014卒・男・KN)
・YeYe 京都で活動しているシンガーソングライターですが、毎月11日にUstremを配信していて、月に一度の癒しの時間です(静岡大学教育学部修士2年・男・みたらしだんご)
Q14 逆に妨害した人は誰ですか?
一位「自分自身」……26人
・授業、レポート、テスト、また当時行っていた地域活動等、研究以外のもの全て。元を辿れば、自分自身のスケジュール管理能力の無さが原因だが。(静岡大学教育学部4年生・男・F.H)
・「まだ日はあるし」という怠け心があり、一向に卒論作成が進まず、中間発表が出来ないという事態に…(静岡大学教育学部2014卒・男・Y)
二位「いない」……12人
三位「ゲーム」……6人
・ドラクエ9。プレイ時間が200をこえた(静岡大学工学部4年生・男・ガル)
・PS3とPSP、艦これ。詰まると気分転換に遊びたくなり、ついつい手を伸ばしていました(静岡大学農学部博士4年・男・YO)
同率三位「就活」……6人
その他
・壊れかけのusb。中間発表のデータをusbに入れて、いざ当日印刷しようとしたら、「データが壊れています」と。凍った。後日、普通に開いた。(静岡県立大学国際関係学部・女・yh)
・彼女。デートをしなければならなかったので,研究の時間が減った.(静岡大学工学部2014卒・男・もろこしタロー)
・風邪。卒論発表の直前の土曜日に熱が40度近く出たせいで、発表練習をほとんどできないで、卒論発表をすることになった。(静岡大学教育学部2014卒・男・M.T)
・中華料理店がおいしすぎて週一で通った(常葉大学教育学部2014卒・女・K.O)
Q15 また意味もなく、かき乱していった人(あるいはもの)は誰ですか?
一位「いない」……20人
二位「ゼミの人」……4人
・PPT作成という名の大富豪大会(私が4年生の時のこと)(静岡大学教育学部2013卒・男・みたらしだんご)
・研究室の同期(とその彼女).隣席の友達が彼女と喧嘩し,その愚痴に付き合う(喧嘩は週に 3 回は行われ る).(静岡大学工学部2014卒・男・TK)
三位「ツイッター」……2人
・Twitterで、他大学の友人の「卒論もう終わったから、あとは遊ぶだけ!」アピールが、私の心をかき乱していった。(静岡大学情報学部2014卒・女・わーこ)
その他/記憶にないが多分全ての物体(常葉大学造形学部2014卒・女・ys)
◉編集部のひとこと
絶対ルールとして、中には「先生に逆らわない。待ち受ける口頭試問は地獄」なんて声も(静大人文生談)。対策は先生や友達、ゼミ生などとにかく仲間をつくること。また妨害した人・意味もなくかき乱していった人として、彼氏・彼女・美人という色恋沙汰も。研究に夢中で彼女にフラれたり、研究室の三角関係もリアルにある。色恋は癒しの存在と転落と紙一重です。
▶合わせて読みたい。編集部イチオシ記事!
「卒論の天敵「誘惑」の本質とは?理想の卒論環境学」(静岡時代10月号特集インタビュー:p.11〜13)
■学生の数だけ卒論がある。卒論の数だけドラマがある。
泣ける。先輩の悲喜こもごもエピソード、大公開!

▲「制作費、追いつかない!」(文芸大・PINO)
Q16 卒論・卒制期間中、あなたの研究室・ゼミやあなた自身に起こった事件を教えてください
A 定番は電子磁器による強制終了
カエルがよい卵を産まない/締切間際「結果が足りない」と先生より追加実験を仰せつかる/ネズミ逃亡(研究が四日遅れる)/彼女にフラれ、院を辞めた/ゼミ生があまりにも卒論を書くのが遅いので教授が長文メールでキレた(静岡県立大学国際関係学部・女・SH)/工事のおっちゃんが大事な機械のメモリを誤って触る → 菌死滅/ゼミの子と先生の三人で二泊三日の京都卒論合宿(地獄)/先生の言っていることがわからなくて辛い(静岡大学教育学部・女・た)/周りのリア充化/蛍光測定の機械を壊しそうになった。普段優しい先生がお怒りですごい怖かった。二度としません(静岡大学教育学部4年生・女・つんつん)/自分の研究についてわかったつもりになっていたが、その研究をしている学者達に囲まれて話について行けず、「なるほどー。」「はい!」「たしかにー。」を使いまわしました。(静岡大学教育学部4年生・男・YS)/思い通りの結果など出たことが無い。生物を扱っている以上は理論など通用しない(静岡大学農学部2013年卒・男・たんぽぽ)/新しい発想が生まれなくなったとき。作品の数だけが増えていき、それがただの色違い(バリエーション)に過ぎないことに気づいた(静岡大学教育学部2014卒・女・みぃみ)/一年ぶん6400本のCMをみきれない、、見ても見ても終わらない(笑) (静岡文化芸術大学文化政策学部・女・さくさくぱんだ)/自分の研究の意義が分からなくなった時(静岡大学理学部2014卒・男・サワディ)/半年間続けてきた研究で結果を出せず,卒論提出 1 か月前に教授から研究の変更を言い渡される前代未聞の 事態に。悔しかった (静岡大学工学部2014卒・男・T.K)/毎週ゼミで進捗報告があり、先生から「それ1時間でできるよね」と言われたとき(静岡県立大学経営情報学部2013卒・男・r.h)/搬入一週間前くらいにパネルが倒れて穴が空いた時は泣いた(静岡大学教育学部2014卒・女・森の海藻)/最終締め切りに間に合いませんでした(常葉大学造形学部2014卒・女・ys)
■明るい絶望感とオリーブ色の哀しみ
卒業論文・卒業制作とはなんだったのか?
Q17 あなたの卒論・卒制で得たものと失ったものを教えてください
【得たもの】
執念(常葉大学教育学部・女・ゆか) /自分の無力さ、未熟さを知ったこと。でも同時に自分を支える存在がいてくれることもわかった。(英和学院大学人間社会科学部・女・RO)/ 体重…結構増えました。メンタル…実験が失敗してもそこまでへこまなくなりました。(静岡県立大学食品栄養科学部・男・SH)/ 無理難題に挑む気合い(静岡大学理学部・男・KN)/ ロジカルに物事を考えること。(静岡県立大学経営情報学部・男・SM)/柔軟性(静岡大学情報学部・女・N)/過程では理論的思考(と言いたい)。 結果では今こうして仕事をして、生活をしていること(静岡大学人文社会科学部・男・斉藤) /経験、自信、達成感、子どもが成長していく喜び、知識などなど。得たものは多い。社会に出ても役に立っている。(静岡大学教育学部・女・MS)/「世の中に正解はないんだな」という悟り(静岡大学人文社会科学部・女・むらせ)/行動力(静岡県立大学国際関係学部・男・SH)/ PCの使い方。エクセル、ワードのやり方(常葉大学保健医療学部・女・SK)/大学時代、これやりましたという達成感と「もっと勉強しておけばよかったな」という後悔だったり、学びへの欲(静岡県立大学国際関係学部・女・YH)/忍耐力、予定の逆算と妥協点の見極め(静岡大学工学部・男・みよかつ)/なんとかなるさ精神(静岡大学情報学部・女・わーこ)/自分で考える力(常葉大学外国語学部・女・おらたん)/卒業資格と先生との謎の友情(常葉大学造形学部・女・YS)/英論読解力(静岡大学工学部・男・SE)/今までほとんど興味のなかったことが好きになれた。(静岡文化芸術大学国際関係学部・女・S)/新たな知識。考え方の変化。先生とのコミュニケーション。(静岡英和学院大学保育学部・女・AS)/冊子(作品)、画を描く楽しさ、おばあちゃんの喜ぶ顔(静岡文化芸術大学デザイン学部・女・AU)/自分で考えて行動すること。報連相の大切さ(静岡大学農学部・男・かい)/先輩や先生からの信頼。知識。科学的な考え。研究に対する姿勢(静岡大学教育学部・男・サム)/段取力(静岡県立大学経営情報学部・女・スズ)/ゼミ内での結束力。(静岡英和学院大学・女・IK)/言葉の使い方を学んだ。基礎知識習得(東海大学海洋学部・男・MY)/ブラインドタッチ(静岡大学教育学部・男・ヒョコリキ)/その道の人との繋がり。同志(静岡大学教育学部・男・KO)/根気、色白の肌(夏の間、ずっと室内にいたため)(静岡県立大学経営情報学部・女・ST)/根性、徹夜できる体力(静岡大学教育学部・女・た)/多くの知識と、卒論を作る大変さと、その過程を知った経験と脂肪。(静岡大学工学部・男・もろこしタロー)/立ち向かう勇気、自信、粘り強さ、プレゼン力、専門知識、コミュニケーション能力(特に教授との)、センス、友人、主体性(静岡大学農学部・男・たんぽぽ)/制作戦争を共に乗り切ろうとする友達との、戦友のような気持ち。(静岡大学教育学部・女・フトアゴ)/ある程度の達成感と、電子マネーに対しての異常な反応(静岡文化芸術大学文化政策学部・女・りか)/勇気・友情・勝利(静岡大学教育学部・男・アルカトラズ)/実力、知識、友達、自信(常葉大学教育学部・女・SF)/知識と度胸(静岡大学教育学部・女・RS)/早く文書を書く力。「もうだめだ」をポジティブに捉えなおす力(静岡大学理学部・男・はっちゃん)/看護観(静岡県立大短期大学部・女・沖田)/自分の言葉を人にいかに伝えるかという力(常葉大学教育学部・女・KO)/どんな形であれ後世に努力を残せた自信(静岡大学工学部・男・ムークン)
▼こちらはクールな回答
卒業(静岡県立大学経営情報学部・男・てっかん)/卒業。会社の同期と卒論の辛さについて語り合えるということ。(静岡大学人文社会科学部・YN)/将来使い道のない複素数についての知識(静岡大学教育学部・男・GO)/単位(静岡大学人文社会科学部・男・YY)
▼なかにはマイナス意見も……リアルです。
ストレス(静岡大学教育学部・男・みたらし だんご)/忙しさ(静岡大学教育学部・男・たくみん)/結局は徒労感だけが残った。つまらぬ論文を書いたものだ(静岡大学人文社会科学部・男・RK)
【失ったもの】
時間とお金(多数の回答)/睡眠時間。精神の安定(静岡大学教育学部・男・みたらし だんご)/常識と諭吉(静岡大学教育学部・女・みぃみ)/視力(静岡文化芸術大学文化政策学部・女・KM)/数学が好きだという気持ち(静岡大学教育学部・男・GO)/遊ぶ時間(静岡大学教育学部・女・MS)/今までの自分(日本大学国際関係学部・男・づめ)/何もすることのない日(静岡県立大学食品栄養科学部・男・おおちゃん)/彼女(静岡大学理学部・男・はっちゃん)/健康とゆとり(静岡大学教育学部・男・あああ)/なあなあにしたがる気持ち(静岡大学教育学部・男・gerugeru)/朝起きて、夜寝る生活(静岡大学工学部・男・みよかつ)/若さかな?(成果報告とか発表練習とかでエナジードリンクの見ながら徹夜した回数が数知れず...)(静岡大学工学部・男・ムークン)/夏休みと冬休みの一部(静岡大学教育学部・男・FH)/恥じらい(静岡県立大学国際関係学部・男・SH)/大学時代。提出とともに、大学生活の終わりを感じた(静岡県立大学国際関係学部・女・YH)/体重(静岡大学人文社会科学部・女・むらせ)/準備とかしなくても大丈夫!という根拠のない余裕をもつ習慣。(静岡大学教育学部・女・M)/自分への期待(全く満足いくものができなかった。全く自分の思うほど掘り下げができていない。)(静岡英和学院大学人間社会学部・女・柴)/サークルの友達(静岡大学情報学部・女・N)
Q18 あなたは誰のために、なんのために卒業論文・卒業制作を行っていますか?
A.「自分のため」という回答が圧倒的に多かった(9割以上)!けれど「自分のため」と言っても人それぞれ。「卒業するため」や「知識を深めるため」「疑問を解消するため」「自己満足」などの回答がありました。「自分+○○のため」という意見も多く、○○にはお世話になった先生や、両親、研究を引き継ぐだろう後輩との回答が見られました!中には「日本のため」という人も!
Q19 最後に、あなたは伝説の卒業論文・卒業制作を知っていますか?
A 9割が「知らない」
・はい……6%
・いいえ……94%
「知らない」という声が圧倒的多数のなか、実はあなたの知らないところで「伝説」は生まれています。詳しくは静岡時代10月号P14~15をチェック!静岡県内大学伝説卒論6選!大学の先生に「伝説」の卒論・卒制とその誕生名場面をご紹介いただています!
◉編集部のひとこと
卒論は毎日徹夜が当たり前になるほど大学生活を一変させる。どこか高揚感がある。先輩が研究室にこもりっぱなしだったり、論文発表を見たり、先輩を通して卒論に必死になることに憧れる人も。卒論は手を抜くことも全力で取り組むこともできるもの。自分が「大学生」であることに対する姿勢が現れます。まさに大学時代の青春。誰もがかっこよくなれる瞬間なんです。
▶合わせて読みたい。編集部イチオシ記事!
・「君は“伝説”を知っているか?静岡県大学伝説卒論6選」(静岡時代10月号特集企画:p14〜15)
・「終わりは始まりの合図。卒業論文は“贈り物”だった」(静岡時代10月号特集インタビュー:p.17~19)
■静岡県大学マメ辞典
・静岡大学(静岡キャンパス、浜松キャンパス)
1949年に設置された国立大学。圧倒的に男子学生が多い工学部。女子生徒も増やそうと大学を挙げて奮闘中。
・静岡県立大学
1987年に静岡薬科大学、静岡女子大学、静岡女子短期大学を統合し、開学した公立大学。レンガ造りの校舎がとてもオシャレ。
・常葉大学(静岡キャンパス、瀬名キャンパス、富士キャンパス、浜松キャンパス)
1980年より設立された私立大学。2013年に常葉学園大学から常葉大学に改名。新たに法学部と健康科学部が誕生。
・静岡英和学院大学
2002年に静岡英和女学院短期大学と統合し開学。「ちびまる子ちゃん」の作者さくらももこさんは英和短大の卒業生。
・東海大学
1946年に開学した私立大学。一九六二年に海洋学部が静岡県に設置された。世界文化遺産、三保の松原近くに位置する。
・静岡福祉大学
2004年に開設された私立大学。福祉を中心に医療を学べる学科が多い。新たに「子ども未来学部」が設置される予定。
・静岡産業大学(藤枝キャンパス、磐田キャンパス)
1994年に静岡産業大学経営学部経営環境学科が開学された私立大学。のちに、国際情報学部が開学される。
・静岡理工科大学
1991年に設置された袋井市にある私立大学。理工学部と総合情報学部がある。小笠山総合運動公園エコパまで徒歩約15分!
・静岡文化芸術大学
2000年に開学した公立大学。2010年に私立大学から公立大学へ。留学生派遣・受入れや語学研修などが盛んな大学。
・浜松学院大学
2004年に開学した私立大学。県西部の大学で小学校・特別支援学校教諭一種免許を取得することができるのはここだけ!
・聖隸クリストファー大学
1992年に、聖隷クリストファー看護大学という名称で開学した私立大学。喫煙禁止。破ると退学を含む処分の対象になる。
・浜松医科大学
1974年に設置された国立大学。昨年の医師国家試験の合格率は98%と全国で六位。国立大学で二位という好成績を残す。
・日本大学三島キャンパス
1920年に設置された私立大学。国際関係学部、短期大学部の2学部ある。昨年度の時点で総卒業生数はなんと73104人
・順天堂大学三島キャンパス
医学校として歴史と伝統がある私立大学。三島市には保健看護学部があり、昨年度の看護師国家試験の合格率は100%!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◉お詫び
静岡時代10月号の内容(p8)に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。
(誤)「静岡県は25の大学・約180の学科がある」(p8/タイトル下)
↓
(正)「静岡県は23の大学・約180の学科がある」(p8/タイトル下)
読者の皆様、ならびに関係者のみなさまにご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Updated:2014年10月01日
文学に学ぶ「恋をする」とは?
いつの時代も「恋愛」を扱う文学作品や小説がある。当時の思想やその物語は、その時代の社会における意識を反映しているはず。「恋」はどのように解釈されてきたのでしょうか。近現代文学の専門家中村先生と書店を巡った。私たちの恋愛観は文学によってつくられていた!?
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
●中村ともえ先生(写真中央)
静岡大学 教育学部 准教授。専門分野は明治から現代にかけての近現代日本文学。今の考え方がどのような歴史のもとに作られてきたか、明治以降の小説や戯曲など文学の変遷を紐解く中で探求している。
●小池麻友:静岡県立大学3年(写真左) / 樫田那美紀:静岡大学3年(写真右)
●取材場所のご協力
戸田書店 〈静岡本店〉
〒420-0852
静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー2F・1F・BF
□HP→ http://todabooks.co.jp
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■恋愛という概念が生まれてからまだ100年
ーー私たちが時に楽しみ、時に苦しむ「恋愛」は小説や文学作品においてどのように描かれ、それは私たちの今日の恋愛にどういった影響を与えているのでしょうか。
(中村先生)そもそも日本語の「恋愛」という言葉自体が明治に始まる日本の近代化によって作り出された新しい言葉だと言われています。西洋から入ってきた「Love」という概念の翻訳語として、当時の日本人は「恋愛」という言葉を作りだしたんですね。もちろん「好き」という今のみなさんの恋愛感情に相当する気持ちは「恋愛」という言葉が登場する以前からあった感情でしょう。例えば江戸時代には男女の関係は「色」という言葉で表されていました。
しかし「色事」や「好色」というと、現在の「恋愛」とは少し違う気がします。今私たちが当たり前のように使い、普遍的なもののように感じている「恋愛」が一般に共有できる概念になったのは、この100年くらいのことなんですよ。
ーー恋愛という言葉や捉え方自体が、西洋からの刺激をきっかけとして生まれたものだったんですね。では、「恋愛」という概念は日本でどのように広まっていったのでしょうか?
(中村先生)「恋愛」という言葉のイメージを満たすことに大きな役割を果たしたのは小説です。例えば小杉天外によって書かれた『魔風恋風』(明治36年)は、主に男性が着用していた袴を着て髪にリボンを結び、自転車に乗り、勉学に勤しむ「ハイカラ」な女学生と、書生すなわち大学生との恋を描いた小説です。読売新聞に連載され人気を博したこの小説によって、明治以前は存在しなかった西洋流の教育を受けた学生同士のカップルが典型的な恋愛のイメージモデルとして定着していきます。
今でも「恋愛は学生や結婚前の20代の若者がするもの」というイメージが根強いのではないでしょうか。これも、明治以降の『魔風恋風』のような小説における恋愛の描かれ方が大きく影響を与えていると考えられます。つまり、小説を読まないという人も、小説によって形成されてきた恋愛のイメージを知らず知らずのうちに受け継いでいる面があるのです。
ーー確かに「大学生だから恋しなきゃ」と思う妙な焦りはあります。それもかつて文学によってつくりだされたものだとしたら驚きです。
(中村先生)明治以降の西洋との関わりの中で作られた新しい概念は、その時代から時を経た今にも通じているんですよね。けれど当時は、自由恋愛よりもお見合い結婚が主流だった時代。小説において、女学生のように西洋の文化に触れ、新しい恋愛観を持った女性が描かれるとき、その女性たちはしばしば不幸な運命を辿るよう描かれたのです。『魔風恋風』の女学生萩原初野も悲劇的な結末を迎え、恋愛を選んだ罰を受けます。夏目漱石の『虞美人草』(明治40年)の勝気なヒロイン藤尾を、漱石自身は「罰せられるべき女」として、批判的に描いています。しかし藤尾は読者の支持を得て人気を博します。たとえ悲劇的な結末を迎えたとしても、読者はその結末までの過程に描かれた新しい女性像や恋愛関係に魅力を感じ憧れの気持ちを持ったのではないでしょうか。
ーー確かに、私たちが恋愛をしている時、脳裏には「理想の恋人像」や「劇的な恋愛」への憧れがある気がします。とはいえ、恋愛小説のなかには非現実的なものもありますよね?
(中村先生)「恋愛小説」と一口に言ってもその視点や特徴は様々です。恋愛小説の一つに読者の共感を呼ぶものがあります。三島由紀夫の『潮騒』(昭和39年)は清らかで健康的な男女の非の打ちどころのない恋愛の形を描いた作品です。「わたしもこんな恋愛したい」と思わせるような小説はやはり支持されます。一方で、自分の日常とは明らかに切り離された「ありえないでしょ!」とつっこみたくなるような非現実的な恋愛を描いた作品もあります。
■共感をよぶ王道から現実離れした究極の愛まで
(中村先生)泉鏡花の『外科室』(明治28年)という作品は、たった一度すれ違っただけでお互いに一目惚れした男女が医師と患者の形で再会し、患者である女性は自分の秘密を口にすることを恐れて麻酔なしで手術に臨みます。女性の命はそこで絶え、男性もすぐにあとを追います。そんな嘘のように究極的で迷いのない恋愛を理想像として支持する読者もいるのでしょう。読者は、そんな現実離れした恋愛の形を小説を通して味わうこともできるんですね。読者が共感できる恋愛と、非現実的で自分とはかけ離れていると感じる恋愛、恋愛小説はそうした様々な恋愛模様を混ぜ合わせたグラデーションとして形成されているんです。
ーーこうして書店を歩くと恋愛をテーマとした作品の多さに驚きますが、それも各人の趣味趣向に応じた様々なタイプが描かれているんですね。最後に、どうして人は小説に恋愛というテーマを求めるのでしょうか。
(中村先生)恋をする人は誰しも「この気持ちは本当に恋なのか?」という疑問を持つと思うんです。そんな人は小説の中で描かれる恋愛に共感したり憧れたりする中で、自分の心情と小説とを照らし合わせて、その疑問を解消しようとするのではないでしょうか。それは決して文学に限った話ではなく、現代では漫画やドラマ、映画、歌などさまざまな文化が、同様の役割を受け継いでいると思います。「きゅんとする」という恋愛感情を表す今日の一般的な表現も、そのような現代の文化から生まれたものでしょう。でも、時代が変わっても、小説でしか表現できないことはあり、恋愛をテーマとした小説はこれからも読者に求められていくはず、そう思います。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
書籍紹介
■このお話をもっと深く掘り下げたいひとへ中村ともえ先生からのオススメ本!
『煩悶青年と女学生の文学誌̶̶「西洋」を読み替えて』平石典子. 新曜社.2012.
□今回の取材中に中村先生が取り上げた書籍のご紹介!
・『三四郎』.夏目漱石.新潮社 改版.1948
・『虞美人草』夏目漱石.新潮社 改版.1951
・『潮騒』三島由紀夫.新潮社 改版.2005
・『外科室』泉鏡花.岩波書店.1991
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
●話し手:中村ともえ先生
静岡大学 教育学部 准教授。専門分野は明治から現代にかけての近現代日本文学。今の考え方がどのような歴史のもとに作られてきたか、明治以降の小説や戯曲など文学の変遷を紐解く中で探求している。
●聞き手:
小池麻友:静岡県立大学3年 / 樫田那美紀:静岡大学3年
Updated:2014年08月18日
恋愛に学ぶ人間関係の極意とは?
「恋は盲目」といいますが、たしかに、自分と想い人だけの世界をつくってしまうことが「恋愛の怖さ」と関係があるのかもしれません。恋愛したが故に苦しんだり、辛い経験をしたことは誰にもあるはずでしょ。そこで今回は、人生の先輩でもあるパブ【マーブル】の望月さんに、体当たりで恋の悩みをぶつけてきました。人間関係を複雑にしてしまう恋だからこそ、その切り抜け方から恋愛にとどまらず人生を生きるヒントが浮かび上がるのかも。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
●望月真理子さん(写真左から2人目)
静岡市清水区にあるパブ「マーブル」を経営。20 代の頃にクラブで働きはじめ、独立してから約40 年が経つ。「私はみんなのお母さんだよ」と優しく、時にびしっと恋愛相談にのってくださいました。
●木下莉那/常葉大学4年(写真左) 小池麻友/静岡県立大学3年(写真右から2人目) 度會由貴/静岡大学3年(写真右)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■「うまく恋愛をする」って本当に難しい
本誌編集長小池(以下小池):「恋愛」は自分ひとりではどうにも悩んでしまったり、うまくいかないことがあると思うんです。自分と相手、その周辺、いろいろな人間や物事の関係性のなかで「うまく恋愛をする」って本当に難しいし、苦しいです。例えば、私の場合は忘れられない人がいることで悩んでいます。頭では、次の恋に進みたい、進まなきゃと思っているのに、できないまま時間だけが経とうとしています。友達にも「もういい加減にしなよ」と呆れられてしまって……。なんでこんなにも恋愛は苦しいんでしょう?こんなふうに悩んでいるのは私だけなんでしょうか?
望月さん:まず知ってほしいのは、みんな恋愛をして一人で悩んでる人が多いってこと。人に言わなくても、みんなあると思うの。わたしもいろいろな経験をしたし、こういうお店やっているから多くのお客さんの相談にのってきたわ。そのたびに私が言ってきたのは、あなたが一心に想っているその人とあなたは「道」が違うということ。忘れられないのはとってもいいことだよ。
でも、その「忘れられない」の理由が相手を恨みに思っているからっていう人もいるじゃん。恋愛って当事者しか分からないことだけど、相手と嫌なことがあってもそれをいつまでも引きずっていてはいけないと思うよ。そういう人は花が咲かないと思うの。私は「愛=花」だと思っていて、花を咲かす、つまりあなた自身の愛を咲かすには、相手を恨んじゃあいけない。「次の恋に進みたいけど相手を忘れられない」と思うんだったら、今の想いを捨てる必要はなくて、通る道が違うって割り切ればいいと思うの。国道一号線もある、旧東海道線もある、そうやってそれぞれの通る道が違えばすれ違っちゃうってことよ。
■「選ばれる」ためには自然体でいること
小池:いま、望月さんの仰ったことを聞いて、恨むという感情なのかわからないけれど、相手へのマイナスな感情があるのかなって気づきました。私は相手に迷惑かけたかなっていう罪悪感を少し持ってるんです。その罪悪感っていうマイナスな感情のせいで心に残ってしまっているのではないかと思うんです。
望月さん:それじゃあ花は咲かないよ。相手にも見る目、判断があるんだから仕方のないこと。だから恨ん
じゃあいけない。私の経験から言うとね、惚れるんじゃあなくて、「惚れられる人」、つまり選ばれる人にならなくちゃ。
小池:惚れられる人ですか?
望月さん:そう、それがいいと思うよ。自分で選ぼうとするから苦労するのよ。相手を追いかけて、背伸びするから疲れちゃう。
小池:確かにそれで悩んでいる人は大学生に限らず多いですよね。でも、相手を追いかけるリスクを承知で、自分から惚れたい、好きな人を見つけたいという人もいると思います。「愛されるより
も愛したい」みたいな。
望月さん:その場合も一緒で、選ばれる人にならないとって私は言うよ。結局好きな相手が選んでくれきゃ、実を結ばないんじゃないかな。これって恋愛に限らず就活にも共通するところがあると思うの。自分がどんなに強い想いを持っていたとしても相手が自分を選んでくれないと就職できないんだよ。
小池:恋愛も就活も相手ありきのことですもんね。選ばれるためにはどうしたらいいんでしょうか?
望月さん:それは自然体でいること。飾らない自分を好きになってくれる人がいると思うの。気取ったり、背伸びしたりして自分をいいように見せようとしないで、ありのままの存在でいることが「選ばれる」ための近道だと思うよ。自然体でいられるっていうのはあなたにとっても良きパートナーなんだと思うしね。
小池:頭では理解できるのですが、正直なところなかなか難しいです。
■結婚していたときに、好きな人ができたの
小池:ところで望月さんは40年近く、このパブ「マーブル」を一人で切り盛りしてこられたそうですね。お店の常連さんからは、「目鼻立ちがはっきりしていて、絶対モテたんじゃないかな」とお聞きしました。望月さんがどんな恋愛をしてこられたのか気になります。
望月さん:そう?随分私も恋愛はしてきたけど、自分からいいなって思う人はあんまりいなかったね。人に
想われていることのほうが多かったよ。その方が面白い。私にも忘れられない人がいるのよ。
小池:そうなんですか?詳しく教えてください!
望月さん:その人はとっても穏やかで、人間がいい人だったの。船の関係のお仕事をされていたから、2年に一回しか会えなかったんだけどね。惚れられて、それで私も好きだったんだけど、その時私はもう結婚していたの。プロポーズをされたけれど、私は夫とは別れられなかった。でもその方はずっと想っていてくれて、日本を離れるけど「待っててね」って言ってくれたから、私は6年間待った。好きだったけれど、自分も別れずにいたからそれじゃあ失礼だと思って、「あんたはあんたの道を行きなよ」って言ったよ。だから結局その人とは結婚しなかったんだよね。その後その人も結婚して、お店に来てくれたんだけど、「死んだら一緒になろう」って言うから「そうね」って。だから今でも心に「いい人」として残ってる。花咲くような恋愛だったよ。
小池:劇的な大恋愛をされていたんですね。「忘れられない」という気持ちがいい形で今も残っていることがうらやましいです。私もそんな素敵な出会いをしてみたいです。
■どうするかは自分の判断しかないわ
望月さん:出会いって他愛ないことだと思うけどね。今あなたが通っている大学だっていろんな土地で育った人が集まる場所。要するに人のつながりを創る場所なの。出会いを多く持つことが大事よ。もちろん、大学はそれだけじゃなくて、本来は学びに行くところってことも忘れちゃいけないよ。
小池:なるほど。積極的に人と関わりたいって思うけれど、例えば誰かを好きになったとき、その相手が自分にとって大切であればあるほど、迷惑をかけてしまったらどうしよう、嫌われたらどうしよう、って思ってなかなか動き出せない気がします。
望月さん:嫌われてもいいじゃない。そうはいってもその人の性格上割り切れる人、割り切れない人がいると思うけど。でも行動すればさ、良くも悪くもなにかしら相手の応答があるはず。その反応を見て自分でこの後どうすればいいか判断すればいいんじゃない?どうしたらいいかなんて本人にしか分からないの。どうするかは自分の判断しかないわ。
小池:たしかに、私は世間体や相手からどう見られるかということばかり気にして、自分の考えで動くというよりは無意識のうちに相手に合わせるようになっている気がします。
望月さん:そうやって自分が傷つくのを怖がっていたらなにもできないじゃない。「勝手にしやがれ」くらい思って、先へ先へ行かないと。恋愛にしろ仕事にしろさ、行動してみてなんか違うな、失敗だったかなって思ったら「道が違うんだな」って考えればいいじゃない。自分で胸叩いて、頑張れよって言ってきゃいいじゃん。その方がよっぽど清々しいわ。
小池:かっこいい!
望月さん:自分の人生は自分でつくっていかなければならないのよ。自分で判断して意思を示していかなくちゃ。
話し手:●望月真理子さん
静岡市清水区にあるパブ「マーブル」を経営。20 代の頃にクラブで働きはじめ、独立してから約40 年が経つ。「私はみんなのお母さんだよ」と優しく、時にびしっと恋愛相談にのってくださいました。
■ 望月さんへ会ってお話をしたい人へ パブ「マーブル」(静岡県静岡市清水区)
静岡県静岡市清水区旭町4- 21
☎ 054-351-1119
聞き手:
木下莉那/常葉大学4年
小池麻友/静岡県立大学3年
度會由貴/静岡大学3年
Updated:2014年07月17日
「学ぶって何ですか?」〜静岡英和学院大学 人間社会学部 古郡康人先生〜
私たち学生にとって大学生活を送るということは、イコール「学び」に直結しているわけですが。そもそも大学に入って"学ぶ"とは一体どういうことなのでしょうか。高校までの勉強が、大学に入るとどう変化するのか。今回は「文学」を専門とする静岡英和学院大学の古郡先生に、先生の高校時代から教職につくまでの過程。そして、専門に研究している森鴎外をきっかけに、「文学」とは、「学び」とは何か。を探っていきます。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
●古郡康人先生(写真右)
静岡英和学院大学人間社会学部 学部長
静岡県富士市出身。専門は日本近代文学。学生の頃に森鷗外を読み始める。
1971年当時、月に一冊配本が開始された『鷗外全集』を購読しはじめたのが研究のきっかけ。
●静岡英和学院大学2年/漆畑友紀(写真左)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■「森鷗外で行こうか。」が私の学問の出発点。
きっかけは、ほんの些細なことでいいんです。
——古郡先生は主に近代文学を専門とされていますが、そもそも「文学」という学問はどのようなものなのでしょうか?
「文学」は文学作品を研究の対象として扱います。森鷗外や夏目漱石などの近代文学から現代の作品まで、研究対象は幅が広いです。みなさんが文学作品に触れたとき、楽しい・哀しいなど感情の起伏が生まれることや、新しい発見をするような経験をしたことがあるでしょう?
文学はその発見に「なぜそのようになったのか」などという問題設定をし、作品をさらに深く読み込む研究をします。
日常会話を含む「言葉」によって成り立つ文学は、言語表現の中でも最も高度なものだと考えています。なぜなら、 例えば小説だと作者は登場人物の中で、あるいは登場人物とは別に、わざわざ語り手を設定し、語り手を通して物語を語っていきますよね。普段の読書のときにはあまり意識しないと思いますが、これらは非常に手が込んでいる高度な言語表現なんです。
少し文学からそれますが、私が思う学問とは、「思い込みは誰でもできるけど、その思い込みをできるだけ多くの人を納得させる真実へ近づかせること」と考えています。もちろん、一人一人の考えは沢山あってもいいものです。しかし、それらの考えを多くの人を「なるほど」と納得させることを目指すのが「学問」なのではないかと私は考えています。それぞれの人が持つ文学作品に対しての考えはそれでいいんだけど、もっとその文学作品を深く読むためには「こういう読み方もあるんじゃないか」と発見したい。大学の「文学」という学問を勉強して、それが発見できればいいんじゃないかと思っています。
私が文学を学問的にアプローチする際は、ただ単に作品を読んで「面白い!」という感想だけで済まさないようにしています。その作品から何が読み取れるのかを追求し、作品を読み解く「方法論」をみつけていくのが文学研究のひとつですね。
——先生は主に森鷗外を研究しているとおっしゃっていたのですが、森鷗外を研究しようとしたきっかけはなんだったのですか?
私が森鷗外を研究しようとしたのは、私が大学一年生のとき。『鷗外全集』が月に一巻ずつ発行されはじめた時期でした。『鷗外全集』は当時の価格が二千円でして、学生にとって二千円はかなりの出費でしたが全38巻ある『鷗外全集』を集めました。”どうせ研究するなら大物作家にしよう”といきごんでいたからですね。その考えと『鷗外全集』が発売される時期が重なったので、「鷗外で行こうか。」と、鴎外を研究することに決めました。学問のきっかけは、ほんのささいなことでいいんですよ(笑)
しかし鷗外を研究していくうちに、鷗外の人間性や日常の背後にある象徴的なものを知ることが出来、どんどんのめりこんでいきました。たとえば、鴎外自身の作品の中に、こんな話があります。「あるところへ宴会に行った。しかし予定よりも早く着いてしまい、一人で待っていたら料理屋の老女将がたくさんの豆を持ってきた。その日は節分で豆を撒く日だったので、老女将が「福は内 鬼は外」と豆を撒いた。その様子がとても生き生きとしていて、見ていてとても気持ちがよかった。一方、そのことをあとからやってきた宴会の主催者に伝えたら、「そうか、だったらもっと盛大にしてやろう!」と若い芸者衆を連れてきて、芸者衆みんなに豆まきをさせた。その様子をみても、まったく感動しなかった」。
はじめてこの作品を読んでみると、これのどこがいいのかちょっとわからないかもしれません。しかし、鷗外はニーチェの「芸術が最も深く感じられるときは、死の魔力がそれを支配したときにあるんだ」という言葉を引用しています。そう考えると、節分といった行事を充実させるのは若い人ではなく、老年の方なんだと作品から読み解くことができますよね。内容と形式というテーマを考えさせる仕掛けになっているんです。
鷗外はただ日常の些細な出来事を描いているのではなく、日常の些細な出来事の背後にある象徴的なものを描いているんだと気づいたとき、作者が森鷗外でなくてもこの作品は作品じたいとして優れているのだと気づくことができました。そういう発見を積み重ねることができるのは、とても楽しい作業なんですよ。
——「学問」と聞くと小難しい・カタいイメージが先行してしまいますが、かまえず、ほんのささいな入り方でもいいんですね。では他に、先生が研究に没頭できた理由はあるのでしょうか?
私の大学時代は、教員になることを考えていたわけではなく、先ほど言った通り森鷗外をはじめとしていろいろな本を読んでいました。ですが研究ということを意識したのは、尊敬できる先生に出会えたことが一番大きいかな。その先生はユニークな方でしたが、尊敬できる方だったなと。尊敬できる先生に出会えることは、大学生の特権だったと、大学生活を送ってそう思いました。
ーー恩師と出会えることはこの上ない喜びに繋がるかもしれませんね。大学は高校と違い自分の好きな学問が学べますよね。でも、「学ぶ」ことを考えてしまうと、大学生を続けていけるか、好きだったはずのものが嫌いになってしまうんじゃないかと不安があります。その不安の中で、学ぶことの意味を見い出すことができるのでしょうか?
そうですね。たとえば、大学生というと学部によって違いはありますが、まずは卒業論文を書かなければならなくなります。私は、卒業論文は研究者としての出発点に立つものだ思っているんです。実際に研究者になるならないは別にして、です。ある学者の方が、「自分が書いてきた論文の中で一番自信があるのは卒業論文だ」とおっしゃっていたように、卒業論文のためだけに一生懸命になる時って他にないですよね。
卒業論文のためだけに一生懸命になれるのは学生だけなのです。卒業論文を書くのは就活の時期と被っているので、卒業論文だけに!となることは中々難しいかと思うかもしれませんが、短い間だけど一つの対象に入れ込むことができる機会は、大学生のときしかないんじゃないかと思います。そして、それが自分にとっての自信に繋がるはずです。これだけは他の人には負けませんという自信です。それが自分にとって生きる糧になっていくはずです。それはすぐ役に立つことではないけれど、とても大事なことです。このことはどんな学問でも言えることなんですよ。
■文学は、作品の中で色んな人生が描かれている。ただそれだけですよね。
——確かに何十年後先のことなんてわかりっこないですね。でも私が、大学へ進学したのは、何十年の未来を見据えた上で、将来の夢と目標が明確にあり、それを叶えるために進学をしました。高校生の頃から私は将来の夢や目標は必ず持っていなければならないとずっと考えていたのですが夢や目標が固まっていなくても、大学へ進学してもいいのでしょうか?
確かに自分のやりたいこと、勉強したいことが決まっているのなら一番に力が付くんだろうと思います。そういうのは社会人学生の勉強に対する姿勢をみてみるとよくわかりますよね。大学に進学し、熱心に勉強する。自分のやりたいことのために勉強がしたいと決まっているから自分より年少の学生に混ざって進学してきていますよね。
しかし、18歳ぐらいで高校卒業してすぐ大学へ進学する方が社会人学生の方と同じような意識を持っている方が不自然のような気がしますね。じゃあ今の学生よりも昔の学生の方が夢や目標を持っていたかどうか、今も昔も個人差があって様々な学生が沢山いて、私はそれでいいと思います。
鷗外は「日本人は生きることを知っているだろうか」と問いかけています。どういう意味なのかと言うと、例えば高校生が高校を卒業して、大学へと進学して、その次には就職をして、と絶えず先の方に自分の人生があると思っているように、鷗外には見えたんでしょう。でも「今」がここにあるから人生はあるのであって「今」がなければ人生はないのです。なのに、絶えず夢をみて、先のことしか考えてないで今ある自分は本当の自分ではない。将来の自分こそが本当の自分なんだと信じて疑わない。こういう考えは、ちょっとおかしいのではないのかと思いますよね。
ーーなるほど。偉大なる作家さんがこうもおっしゃっていたとは驚きですし、なにより何十年先の自分を考えることは当たり前のことだと思っていました。たとえば高校生の進路決定などは将来を考えるひとつの大きな起点にあたると思うのですが、先生はどうだったんでしょうか?
私は高校時代バレーボール部に所属していて、そればかりやっていましたね。受験勉強はしていましたが、受験勉強のときに頑張れば、大学では好きなことが勉強できるんだろうと思っていたわけです。当時の私は自分の好きな勉強はなんなのかわからないけど、漠然と人生について考えようとしていました。人生ってなんだろうと色々と考えていくうちに、文学って色んな小説の中でも色んな人生が描かれていることに気付きました。
そういう、ささいな興味でしたから、大学へ進学した時も文学を研究する動機がまだ漠然としていました。人生を考えるなら哲学の方こそ専門だという考えもあるでしょうし。でも色んなことが有り得るわけだからと当時はそう思っていました。
しかし、学んでいくうちに好きな先生ができたり、勉強しながらこういう見方もあるのか、こんな見方もできるのか、と言う風に目指すべき道が不思議と開けてくるようになるんです。そのときはわからないかもしれないけれど、あとになって振り返ってみると、それには必然性があったと気付くことができるはず。
確かに高校生にとって、進路決定は自分の人生や目指す道を決めるひとつのターニングポイントです。でも、悩まないよりは悩んだ方がいい。なぜなら、自分のことや将来のことを考えているからこそ、悩みは大きくなるものですから。自分が精一杯努力している証だと私は思います。
——この先どうしよう、と焦れば焦るほど決断を早々に決めてしまいがちですが、そういう時だからこそ落ち着いて、自分の中で振り返って考えてみることが大事なんですね。
そうですね。それから、物事を狭く考えないことと、早いうちに自分の好き嫌いを決めつけないようにすることです。数学が苦手で、どうしても出来ない。と思っていても”嫌い”と思わないようにする。毛嫌いさえしなければ、いつ”好き”なものに変わるかわからないからです。そして、「好きこそ物の上手なれ」となれば、もうしめたものです。
せっかちに嫌いだと結論を出さないようにすることが、視野を広げたり、専門力を身につけることにつながっていくと思います。それから、基礎が大事だと思います。土台作りにおいて自分がいい加減にしているところがあったら、細かいとこまで目を光らせてしっかりとやることが大事ですよ。基礎がしっかりしていれば、後でぐーんと伸びます。(了)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
●語り手:
古郡康人先生
静岡英和学院大学人間社会学部 学部長
静岡県富士市出身。専門は日本近代文学。学生の頃に森鷗外を読み始める。
1971年当時、月に一冊配本が開始された『鷗外全集』を購読しはじめたのが研究のきっかけ。
●聞き手:
静岡英和学院大学2年/漆畑友紀
Updated:2014年06月23日
恋のメカニズムを教えて!〜脳科学から検証する、恋愛理論〜
「恋」や「恋愛」は、感覚的でよくわからない。理由があるにしても、どれも後付けな気がしてしまいます。論理的に「恋」を検証したら、私たちの身体の中では一体、何が起こっているのでしょうか。「恋」に科学的な視点を向けて、「人が何故恋愛をするのか」、理由を探っていきます。脳科学・神経科学の専門家である静岡理工科大学の奥村先生に、お話を伺いました。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
●奥村哲先生
静岡理工科大学 総合情報学部 人間情報デザイン学科客員准教授。研究分野は神経科学。大学で小鳥の脳と歌声の関連性を研究している。「研究している小鳥をもっと増やしたい」のだそう。
●小池麻友:静岡県立大学(写真右)/ 亀山春佳:静岡英和学院大学(写真左)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■「好き」は、出会って0.3秒で決まる
ーー奥村先生は神経科学を専門に研究されていますが、脳科学や神経行動学にみるとどうなったときに「好き」になったと言えるんですか?
(奥村先生)「好き」になるということは色々な研究から、出会って0.3秒ぐらいの中でびびっとくることが大切だといわれています。まず「びびっとくる」。そのあとから、好きだから、好感を持っているから、良く見えるということがあるのです。この「びびっとくる」時にはさまざまな、意味のある信号と意味のない信号、正直な信号と正直でない信号が働いているのです。
ーー早速もう分かりません。どういうことですか?
(奥村先生)正直なシグナルというのは、動物がもつ、よりよい子孫を残していこうとする本能にはたらきかけるものです。人間の場合でいうと、男性にとって第二次性徴で育った女性の胸はセクシーで、女性とっても男性の背中ががっしりしていたらセクシーに見える、というもの。例えば、一般的に若い女性のほうが人気がありますよね。それは妊娠確率の高い方がいいという本能的な理由も含まれているんです。ただヒトでは若い女性が特に好まれることもあるようです。でも、動物はちょっと違って一回子供を育てたことのあるメスの方が人気なこともあるんですよ。ワンシーズンちゃんと子育てを成功させたメスの方がいいんですね。
他にも、ハンディキャップ原理というものがあります。クジャクの尾があんなに大きく綺麗なのは、生きる上では必要のないものです。しかし、その不要な形質を持っていることが体力やなにがしかの資質の余剰分として異性に魅力的に見えているらしいんですよ。これを人間に当てはめると「シャープペンをくるくる回せる」とか「歌がうまい」とかといった、一見無駄な能力が魅力的にみえることがあるということにも、説明がつくかもしれませんね。
一方で、正直でないシグナルには人間にしかないシグナルもあります。例えば、ウソを言うこと。言葉を話す人間だけが獲得した、特別な能力です。だから「僕は君のことを大切にするんだ」と言葉だけは完璧でも、その気持ちが本当かどうか評価する能力が必要になってきます。口では何でも言えてしまいますからね。若いうちに色々と経験を積んでおくべきと言われますが、その能力を鍛えるのには必要かもしれませんね。ウソを見抜く能力が十分に発達していない人は不幸な結婚をするリスクが高いかもしれません。またヒトは文化をもつので、シグナルが多様化しています。その代表的な例がお金です。どれくらい自分にお金をかけてくれるか。お金によってもたらされる、生活の安定。それらもある種のシグナルとして働いているようです。
ーーシグナルを受け取り「好き」になったとき、私たちの脳ではいったい何が起こっているのでしょうか。
(奥村先生)「好き」という状態のときは、脳でオキシトシンという物質が働いていています。オキシトシンとは、愛着や信頼を増幅させる物質で、恋をしたとき、信頼の気持ちが高まるときに多く分泌されています。ものすごくオキシトシンの働きが強い人はすぐに他人を信じてしまって、騙されやすかったりします。ちなみに、動物にはものすごく近い種でも住んでいるところの違いで、乱婚や一夫一妻と分かれることがあるんですよ。ほとんど同じ脳ですが、オキシトシンの分泌量や受容体に違いがあるんです。ハタネズミという種では、オキシトシンの働きが強い種は、一夫一妻傾向が強くなっています。また、もしもこのオキシトシンを人に向かってスプレーで振りかけたとしたら、目の前の人を信じやすくなっちゃうかもしれない。究極の「惚れ薬」ともいえますよね。
ーー惚れ薬はつくれるんですね!
(奥村先生)はっきりいって、一目惚れはその人の人となりも分からないうちに好きになってしまうことです。「好き」になることでオキシトシンが分泌されて信頼が生まれるということであれば、そこには根拠のない信頼があることになります。実は、理想の人だから「好き」なのではなく、「好き」だから理想の人になるんです。
例えば、笑っているから楽しくなる、泣いているから悲しくなるといったことと同じです。だから「理想の人」というのは脳科学的にはほぼ後付けなんですよ。結婚をする理由は様々ですが、一目惚れという理由でお付き合いをはじめた夫婦の方が長持ちするというデータもあるくらいです。私たちの頭の中では好きになった人を無意識のうちに美化してしまうという、やさしい勘違いが起きているんですね。そうした勘違いも恋愛の初期には必要だと思います。最初の段階で愛着感を深めておけば、長い付き合いに繋がります。相手がいくらだらしない人だとしても、美化して盛り上がっている段階では意味がない。理想化されているから見ても何も思わないし、そもそも見えないんですよ。心理学的にも、人間は見たくないところは見えにくいのです。
■理屈で説明できない屁理屈で心が動く。その直感も侮れないもの
ーー「好き」は幻想なんでしょうか?恋を理屈で説明することはできないのでしょうか。
(奥村先生)たしかに「好き」になることは必ずしも理屈ではないということが分かってきました。言語を持たない動物のメスがオスを選ぶ根拠の説明は言語ではなかなかできませんからね。ダメ男ばかりを好きになっていく人もいますが、そんなものは言葉の論理ではなく感情的にしか説明できないんです。分析をすると理屈で考えたくなりますが、人生の多くのことは実は理屈ではないんです。逆の方向で理屈ではない情動がはたらく例としてはトラウマがあります。トラウマは、以前エレベーターに閉じ込められたことがあるから二度と乗りたくないと思うような気持ちです。頭のどこかでは、論理的にはもう二度と同じことが起こらないって分かっているくせに、エレベーターに二度と乗りたくないと思う。よっぽどのことですよね。論理で説明できない気持ち。それだけを比べたら、実は犬も人間もほとんど同じですね。
ーー犬も人間も同じ……。衝撃的な言葉です。自分自身で恋をコントロールすることはできないんですか?
(奥村先生)コントロールする必要があるんでしょうか。わざわざどうにかする必要はないと思いますね。恋ができるかどうかには、何人の人に出会えているかが重要だというデータがあります。びびっと来る時が出会いです。それでいいんですよ。もし過去の恋愛を引きずっていても、いつかびびってきて恋をするかもしれませんし、沢山の人と出会いをしていけば、相手からびびってくることもあるかもしれない。結局多くの人と出会いながら、そうなるときを待つしかないですね。「恋のはじまりは屁理屈なのがまっとう」です。そんなものです。理屈で説明できない屁理屈で心が動いてしまったら、それは恋の始まりとしてはとてもまっとうなんです。でも直感レベルの判断も実はなかなか侮れないことが分かってきています。自分の直感を信じて突き進むのも悪くはないと思いますよ。
◆このお話をもっと深く掘り下げたいひとへ奥村哲先生からのオススメ本!
『生物進化とハンディキャップ原理̶性選択と利他行動の謎を解く』アモツ ザハヴィ(他著). 白揚社. 2001.
●話し手:奥村哲先生
静岡理工科大学 総合情報学部 人間情報デザイン学科客員准教授。研究分野は神経科学。大学で小鳥の脳と歌声の関連性を研究している。「研究している小鳥をもっと増やしたい」のだそう。
●聞き手:
静岡県立大学3年/小池麻友
静岡英和学院大学4年/亀山春佳
Updated:2014年06月12日
知ることは舐めること「静岡の土、いただきます」
横にも縦にも長〜〜い静岡県。大井川と富士川で東部・中部・西部に分かれ、土も異なるそう。
「土が違えば味も違うんじゃないか!?」ということで、県内各地から集めた土をどんぶりに盛ってご紹介。そしてそれを味わうのが静岡時代編集部の精鋭三人!
座学じゃ決して得られない静岡の土の知られざる真実が見つかるかも…?
仕込みは十分!いざ実舐!
私たちが舐めます!

●樫田那美紀(写真中央)
静岡大学人文社会科学部3年。今号の静岡時代の編集長。今春、突然「静岡の土を舐めたい」と言い出した張本人。
●木下莉那(写真左)
常葉大学教育学部4年。天性のノリの良さをもつ静岡時代のムードメーカー。どちらかというと薄味派。
●野村和輝(写真右)
静岡大学人文社会科学部4年。静岡時代の男子代表。こういう汚れ役、いやビジュアル企画には欠かせない存在。天才。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
さて、これから舐める土は、4種類。
世界遺産に登録された富士山や観光名所が多い伊豆という静岡県東部に広がる「黒ボク土」、静岡県の山地に広がる「褐色森林土」、丘陵地に多い「赤黄色土」、川沿いの低地にある「グライ土」である。
ちなみに、土の採取は編集部員が手分けをして行った。入部ほやほやの新米編集部員はいきなり編集長から土(黒ボク土)の採取を命じられ、わけがわからないまま採取、初めて大学に土を持参し、授業を受けた。
副編集長も同様、「赤黄色土」を探しに母校まで原付を走らせ、散歩中のおじさんに「赤黄色土ありますか」と聞いて硬直させてしまったとか。某大学のド真ん中で土を掘るハメになった編集部員もいた。
さらに4種類の土のうち「グライ土」は、1メートル掘らないとお目にかかれないまさに「レア土」!。100均の手のひらサイズのスコップ片手に採取に臨んだ編集長は、とんだお笑いぐさである(もちろん農場の方は優しく対応してくださり、大きなスコップを貸してくれ、黙々と一緒に掘ってくださいました!)。
そんなちょっと悲哀のある土採集。果たしてその味とは?
編集長をはじめ、(編集長に強制的に指名された)実舐人員たちは、土を知ることはできるのか!?
悲喜こもごもの「土の実舐」。土壌学の専門家・南雲先生の解説とともにノンストップでお伝えします。

● 南雲 俊之先生
静岡大学農学部共生バイオサイエンス学科准教授。研究分野は土壌学と持続可能型農業科学。土壌保全を目的とし、水田土壌に集積したリンの有効利用等について主に研究されている。藤枝市にある農学部の所有する研究農場も研究拠点の一つだそう。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
〜はじめに。土の実舐、安全対策〜
土を電子レンジで殺菌します!

静岡県立大学食品栄養科学部の小池(静岡時代34号編集長)のアドバイスにより、平皿に広げてなるべく熱がいきわたるよう入念に殺菌。大体1分くらい。加熱しすぎると乾燥してパサパサになってしまい風味が落ちるのでご注意を。

ヴオーオン(普段使いの電子レンジのなかに土が……いや、雑念は捨てよ!)
※土の中には思わぬ雑菌や人体に良くない肥料などが混在している可能性があります。
良い子は真似しないでね。あと、レンジが予想以上に土の匂いに満たされます。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
その① 黒ボク土
ビコーズふじのくに、の代表格

樫田「見た目はなかなかホクホクしていて美味しそうじゃないですか!」木下「え~これなに?植物の根っこ?危険そう…」

まずは編集長・樫田から……(部室は近年に稀に見る静寂と緊張に包まれている)

………おおう。結構なお手前で。

ホワイトボードに各々味わいや気づきを書き留めていきます。「甘い」という木下と「苦い」という野村が真っ向対立!いったいどっち!?
● 土レビュー by 編集部
樫田 ★★★★★
粒子にバラエティ性があり、思い出せないけど…何かの味。深い風味です。
木下 ★★★★☆
食べてみると意外と甘い! 口に含むとすぐに溶けちゃう。もう食べちゃいたい!
野村 ★★★☆☆
薄い苦み。というかもう無味に近い。むしろもうなにも感じない。
野村が出だしから絶望オーラを出す一方で、木下は吐き出した土にホラーを感じてテンションMAX。
総合的に3人とも好評価。いい滑り出しです。
甘味、苦味、酸味を五段階評価した3人の味わい平均値→「甘:3 苦:2 酸:0」。
● 土の専門家・南雲先生のひとこと
「黒ボク土」は主に富士川以東の富士山麓~伊豆地域に分布します。磐田にも断片的に分布が確認されています。腐植物質が多く真っ黒の表層土壌を持つものから,腐植物質の集積が少なく褐色をしたものまで含まれます。火山放出物を材料に作られ,「アロフェン」など非晶質の鉄・アルミニウム鉱物を多く含み,そのためリン酸収着(吸着・沈殿)が起こりやすい土壌で,これが黒ボク特徴の定義にもなっています。一般的に,容積当たりの重量が小さく,透水性がよく保水性も良い土壌です。土壌pHが酸性であること,リン酸欠乏が起こりやすいこと等を除けば,畑作に向いています。
その② 褐色森林土
土壌界の青少年は、きなこ味……?

エニイウェア、な土。

さすが「土を舐めたい」といった編集長!引きつってますが笑ってます!

口直し必須
● 土レビュー by 編集部
樫田 ★★★☆☆
味わいはゼロ。どこかきなこの味に近い。粒子は細かく舌触りなめらか。
木下 ★★★☆☆
見た目は綺麗なのにしょっぱいし苦い。どこか未熟で危ない臭い…。
野村 ★☆☆☆☆
土の風味や匂いが一番強い。以上。(……なんか背中痛くなってきた)
編集部員小池「かっしー(樫田)が『土を飲み込まないで!』っていうのが飲み込めっていうフリにしか聞こえない」と漏らす。採取した張本人樫田はその土の出処を知っているからこそ妙な愛着を感じている模様。野村の背中の痛みの原因は考えないようにしたい。(ちゃんと治りました)
味わい平均値→「甘:1 苦:2 酸:1」
● 土の専門家・南雲先生のひとこと
狭義の褐色森林土は落葉広葉樹林下でできたものを指しますが、ここでは常緑広葉樹下でできるもの(黄褐色森林土)も含めておきます。つまり、日本は国土の2/3を森林が占めますが、その大部分はここでいう褐色森林土に該当するということです。
その③ 赤黄色土
「とろっとろ」な土。されど味なし!

三ヶ日みかんの影の立役者

編集長、泣かないで!

初めて木下の顔がゆがんだ!

ええと、野村くん……かえってきて
● 土レビュー by 編集部
樫田 ★★☆☆☆
口の中でとろける。粒子は荒め。…だんだん喉がいがいがしてきた。
木下 ☆☆☆☆☆
純度高くて、見た目は綺麗。でもかなり無味無臭。はっきり言って好きな味じゃない!
野村 ★☆☆☆☆
とろけすぎて危うく食べちゃいそうになっちゃった。歯にくっつく。
実食前、「赤黄色土」を採取した副編集長漆畑が登場。採取してくれた人の前でその土を悪くいうことをはばかられる…という妙な空気がながれました。しかし舐めてみればそんな意識はどこへやら。
まさかの目を見張るほどの低評価!!
味わい平均値→「甘:1 苦:2 酸:1」
● 土の専門家・南雲先生のひとこと
「赤黄色土」は,大井川以西に比較的多く分布しますが,静岡県下の台地や丘陵地上に広く見られます。静岡市内にも分布します。腐植物質の含有率が低く,土壌の色が比較的明るい黄色や赤いことが特徴で,この色が分類の基準になっています。この黄色や赤色は,土壌に含まれる鉄の酸化物,すなわち結晶化度のやや高い「ゲータイト」(黄色のもと)や結晶化度がさらに高い「ヘマタイト」(赤色のもと)に由来します。礫質のものから粘土質のものまで含みます。
その④ グライ土
その土、駿府城(周辺)にあり!

んんん!?編集長……、明らかに今までと毛色が違くないですか……?

編集長が直々に掘り出したグライ土。舐めるな危険信号をビシビシ感じます。樫田「この土が一番無添加だから!」

編集長・樫田、凛々しい面持ちで味わっております(たぶん)

臭いは……?野村「ワインのテイスティングもこんなかんじなのかな…」


ここまで一貫して低評価の野村くん。ラストオーダーのグライ土はいかに……

おや?
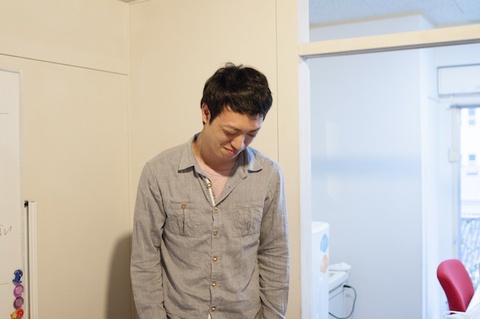
野村くん……?

野村ーーーーーーーーーーーー!
● 土レビュー by 編集部
樫田 ★★★★☆
最初は素っ気ない苦味がするんだけど、10秒舌で転がすと深い苦味がくる。
木下 ★★★☆☆
粘土の味がする(粘土を食べた経験なし)。もちもちして溶けない〜。
野村 ☆☆☆☆☆
粘り気が強い。舌に含んだ瞬間ビリビリする。不味い(白目)
最後に野村怒涛の低評価を決めました!攻撃的な容姿と予想を裏切る風味に編集部員惨敗。もちもちでネバネバ!土への概念を叩き壊された!
味わい平均値→「甘:0 苦:4 酸:2」
● 土の専門家・南雲先生のひとこと
グライ土は低地(沖積地)の土壌です。穴を掘って比較的浅い位置に「グライ特徴」をもつ土層がある土壌です。グライ特徴というのは,ほぼ1年を通して水が飽和状態で停滞するために,土壌に含まれる鉄の酸化物が還元反応(O2の制限された環境下で,土壌中の微生物が担います)を受けて,(Fe+++でなく)Fe++からなる化合物に変化することです。その結果、土層の色は灰色を基調として,青みを帯びていたり,緑みを帯びていたりします。静岡市内,それも駿河区から駿府城周辺までで工事現場を見かけたら,覗いてみてください。グライ特徴を持つ土壌が見られるかもしれません。
実食後
土を舐める道は険しい。時には喉、背中の痛みも伴う。しかしここで断言しよう。
「君は舐めてこそ初めて土を知る!」(by 本誌編集長・樫田那美紀)

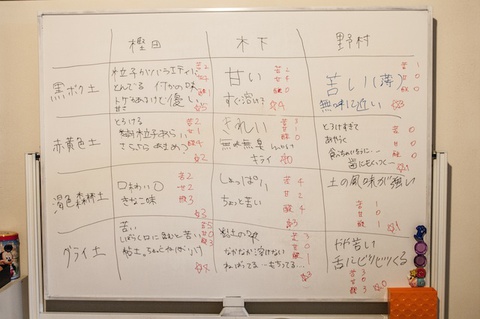
総合結果はこちら!(「褐色森林土」の字を間違えたのはご愛嬌)
Updated:2014年06月04日