編集室より
編集部日誌②~静岡時代6月号(Vol.35)~
『静岡時代』35号編集部日誌②〜副編集長の編集部レポート
皆さんこんにちは。
このたび、『静岡時代』6月号の副編集長を務めることになりました。静岡英和学院大学2年漆畑友紀です。
愛称はうるしーです。六月号は私が副編集長として初めて関わらせてもらう号です。
静岡時代の副編集長は編集長が直々に指名します。6月号編集長の樫田先輩(愛称:かっしーさん/以下、かっしーさん)に「うるしーなら一緒に土を舐めてくれると思って!」との理由で副編集長に任命された私。「え?……土?舐める??」。
当初は驚いた私ですが、編集長から「うるしーと一緒に作れてよかったよ!」と言ってもらえるように、読者の方に、「読んでよかった」「なんども読みたくなってしまう!」と思ってもらえるように、精進してまいります!
さて、6月号も入稿まであと2週間を切りました!編集部内では「〆切が近い……。恐ろしい!」と悲鳴があがっています。
ちなみに、『静岡時代』は4・6・10・12月と年に4回発行されております。そのため、6月号の制作期間は”2ヶ月”というタイトなスケジュール!連日PCに向かいながら6月号完成を目指しています。
目下、編集部員が取り組んでいる『静岡時代』6月号。みなさんにお届けする今回の特集は「土」です。「土」と言われ皆さんは「ん?土がどうしたの?」となるかもしれませんが、そんなあなたにクエスチョン!
「最近いつ土に触りましたか?」
この言葉が、編集長・樫田那美紀(静岡大学3年)の疑問であり特集の出発点です。編集長樫田の「土」に込める想いは、企画の打ち合わせや編集部会議を重ねながら、徐々に固まっていきました。
とある打ち合わせの日、編集長は言いました。「昔の時代は今の私達よりもたくさん土に触れあってきた。なのに今はアスファルトで埋められた道を歩く日々。幼いころは触れ合っていたはずなのに、いつの間にか私たちの生活は土と切り離されてしまっている気がする。土には微生物などといった沢山の命であふれていて、母なる大地と呼ばれるように、土は私達にとっていわば母のような存在。そこからこの企画が動きました」と、真剣なかっしーさん。特集では、土の専門家から土に常に触れ合っている人に取材を行い、先週、全ての取材が終わりました。土を様々な面で捉える方に話を聞き、かっしーさんは大喜びです。また、それをどう記事にするかでは悩んでます。ちなみに、「土」特集にたいする編集長直々のメッセージはこちら。
——私が今日大学へ向かう道も、食べた野菜も、使った器も、すべて土によって作られ、土によってそのものたらしめられています。だというのに、土を触ることも、見ることも、土を感じ語ることも私はできていない。私の歩く道が不自然なまでにアスファルトに塗り固められていることに気づいた時、幼い頃歩いた土剥き出しのあぜ道を想いました。
雄大な山々に豊かな海、健康的な土壌をもつ静岡県で育った人の多くは、かつては野原で遊んだり、泥にまみれた経験があるはず。つまり、私たちは土を知らないのではなく、かつては知っていた土を「忘れてしまっている」のです。
「静岡の土」に密接に触れ合う様々な立場の人の姿、考え、その精神を垣間見、そして私自身が土と向き合い触れ合う姿を見せることで、静岡の知られざる深層を発掘したい。夏の足音が聞こえる六月、思わず裸足で外に飛び出したくなってしまうような企画にしたいと考えています。
(静岡時代6月号:「静岡の土を舐めたい」企画書序文より抜粋)
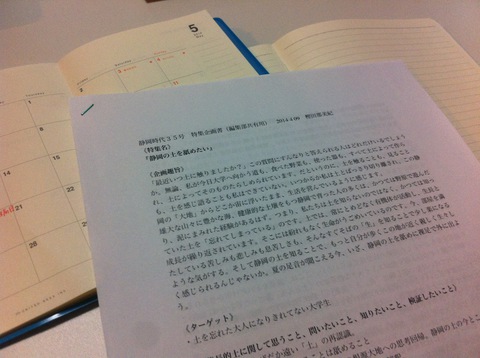

会議中の編集部員。特集について皆真剣に意見出し合ってます
編集長から「”土”をテーマに特集を組む」と言われた編集部一同。各々、「なぜ!?」と驚きを隠せない様子でした(なんたって前号の特集は”恋愛”。毎号編集長が変わる『静岡時代』ならではの妙味だったりします。→静岡時代4月号「静岡時代の恋愛論」 http://www.shizuokajidai.net こちらもぜひ!)。
しかし話が進むにつれ、編集部員たちからは”泥団子を作って遊んだりした”など、昔体験した「土」エピソードがたくさんでてきました。「なんだぁ。やっぱりみんな、土好きなんジャン」と、編集長の嬉しそうな声も。
編集部内では土=泥団子のイメージが多かったですが、編集長は地元の平野。私はさらさらの土です。なにもない、土があるだけの世界です(ひかないでください)。みなさんは、「土」にどんなイメージを持っているでしょうか? (コメント募集中!)
このように、毎回、静岡時代の企画のスタートは編集長の疑問を共有、編集部員の意見や自身のエピソードを話してもらいます。雑談に近いのですが、ひとりで考えがちになってしまう編集長が、外部から色んなアイデアを吸収する大事な時間になるんです。編集長は出てきた意見をメモしながら、全体のイメージを固めていきます。
(余談ですが私は泥団子作れませんでした。作っている様子をただひたすら眺めていた気がします)
さて、「土」といっても雑誌を作るにあたって沢山の壁にぶち当たっています。
・いかに「土」と「静岡県」を繋げられるか
・読者に「土」の存在を再認識してもらうには、どんな企画記事を制作すればよいか。
・特集の全体像は”真面目路線”で組むか、”真面目に馬鹿やっている”と思ってもらえるように組むのか……など
今回の企画タイトル「静岡の土を舐めたい」は一見キャッチーだけれど、読者である大学生は普段の生活において「土」そのものにそこまで関心が高いわけではありません。一見地味に見える土が実は主役級だった!と、読者のこれまでの価値観を変えてしまうような号にしたいです。
「土」から静岡県を知る。ここ静岡において、土とともに生きる風景や人、思想を取り上げ、土との向き合い方を学びたい。
ちなみに、今号では「直に土を舐める」企画を遂行しました!静岡県内には、黒ボク土や赤黄色土、褐色森林土など多様な土が分布しています(制作が進むにつれて、だんだん専門用語が飛び交うようになりました)。実際にそれらの土を採取に行き、編集長をはじめ3人の編集部員がいざ、「実舐」。合言葉は「知ることは舐めること」。どうやら“真面目一徹”からは離れたようですが、気になる結果は……。ふふふ、みなさんぜひお楽しみに。

とある打ち合わせの際の樫田編集長。凛々しい表情ですね。こうみえて、普段は癒しオーラ全開です。
樫田編集長は常に癒しオーラがでていて、歩く姿がとてもかわいいのです。そしてロックが大好き!というギャップ!(そんなロックが大好きなかっしーさんが副編集長を務めます12月号はこちらから読めます。)冗談を言うと笑いあったり、適度にツッコミをいれてくれます。私が冗談を言うと母性が垣間見えます。しかし!会議になると一変!凛々しい顔立ちに変わり、編集部員をビシバシと鍛えます(めちゃかっこいいです)。私を含め編集部員はそのオーラに圧倒します(……私にはオーラが茶色くみえます)。
樫田編集長は現在も、東・中・西部と果てしなく走りまわっています。6月号完成までを一生懸命指揮している樫田編集長を、私は支えていきたいと思います!
「土」をテーマに絶賛制作中の静岡時代編集部。編集長樫田と副編集長漆畑を筆頭に精進してまいりますので、みなさんご期待ください!
皆さんこんにちは。
このたび、『静岡時代』6月号の副編集長を務めることになりました。静岡英和学院大学2年漆畑友紀です。
愛称はうるしーです。六月号は私が副編集長として初めて関わらせてもらう号です。
静岡時代の副編集長は編集長が直々に指名します。6月号編集長の樫田先輩(愛称:かっしーさん/以下、かっしーさん)に「うるしーなら一緒に土を舐めてくれると思って!」との理由で副編集長に任命された私。「え?……土?舐める??」。
当初は驚いた私ですが、編集長から「うるしーと一緒に作れてよかったよ!」と言ってもらえるように、読者の方に、「読んでよかった」「なんども読みたくなってしまう!」と思ってもらえるように、精進してまいります!
さて、6月号も入稿まであと2週間を切りました!編集部内では「〆切が近い……。恐ろしい!」と悲鳴があがっています。
ちなみに、『静岡時代』は4・6・10・12月と年に4回発行されております。そのため、6月号の制作期間は”2ヶ月”というタイトなスケジュール!連日PCに向かいながら6月号完成を目指しています。
目下、編集部員が取り組んでいる『静岡時代』6月号。みなさんにお届けする今回の特集は「土」です。「土」と言われ皆さんは「ん?土がどうしたの?」となるかもしれませんが、そんなあなたにクエスチョン!
「最近いつ土に触りましたか?」
この言葉が、編集長・樫田那美紀(静岡大学3年)の疑問であり特集の出発点です。編集長樫田の「土」に込める想いは、企画の打ち合わせや編集部会議を重ねながら、徐々に固まっていきました。
とある打ち合わせの日、編集長は言いました。「昔の時代は今の私達よりもたくさん土に触れあってきた。なのに今はアスファルトで埋められた道を歩く日々。幼いころは触れ合っていたはずなのに、いつの間にか私たちの生活は土と切り離されてしまっている気がする。土には微生物などといった沢山の命であふれていて、母なる大地と呼ばれるように、土は私達にとっていわば母のような存在。そこからこの企画が動きました」と、真剣なかっしーさん。特集では、土の専門家から土に常に触れ合っている人に取材を行い、先週、全ての取材が終わりました。土を様々な面で捉える方に話を聞き、かっしーさんは大喜びです。また、それをどう記事にするかでは悩んでます。ちなみに、「土」特集にたいする編集長直々のメッセージはこちら。
——私が今日大学へ向かう道も、食べた野菜も、使った器も、すべて土によって作られ、土によってそのものたらしめられています。だというのに、土を触ることも、見ることも、土を感じ語ることも私はできていない。私の歩く道が不自然なまでにアスファルトに塗り固められていることに気づいた時、幼い頃歩いた土剥き出しのあぜ道を想いました。
雄大な山々に豊かな海、健康的な土壌をもつ静岡県で育った人の多くは、かつては野原で遊んだり、泥にまみれた経験があるはず。つまり、私たちは土を知らないのではなく、かつては知っていた土を「忘れてしまっている」のです。
「静岡の土」に密接に触れ合う様々な立場の人の姿、考え、その精神を垣間見、そして私自身が土と向き合い触れ合う姿を見せることで、静岡の知られざる深層を発掘したい。夏の足音が聞こえる六月、思わず裸足で外に飛び出したくなってしまうような企画にしたいと考えています。
(静岡時代6月号:「静岡の土を舐めたい」企画書序文より抜粋)
会議中の編集部員。特集について皆真剣に意見出し合ってます
編集長から「”土”をテーマに特集を組む」と言われた編集部一同。各々、「なぜ!?」と驚きを隠せない様子でした(なんたって前号の特集は”恋愛”。毎号編集長が変わる『静岡時代』ならではの妙味だったりします。→静岡時代4月号「静岡時代の恋愛論」 http://www.shizuokajidai.net こちらもぜひ!)。
しかし話が進むにつれ、編集部員たちからは”泥団子を作って遊んだりした”など、昔体験した「土」エピソードがたくさんでてきました。「なんだぁ。やっぱりみんな、土好きなんジャン」と、編集長の嬉しそうな声も。
編集部内では土=泥団子のイメージが多かったですが、編集長は地元の平野。私はさらさらの土です。なにもない、土があるだけの世界です(ひかないでください)。みなさんは、「土」にどんなイメージを持っているでしょうか? (コメント募集中!)
このように、毎回、静岡時代の企画のスタートは編集長の疑問を共有、編集部員の意見や自身のエピソードを話してもらいます。雑談に近いのですが、ひとりで考えがちになってしまう編集長が、外部から色んなアイデアを吸収する大事な時間になるんです。編集長は出てきた意見をメモしながら、全体のイメージを固めていきます。
(余談ですが私は泥団子作れませんでした。作っている様子をただひたすら眺めていた気がします)
さて、「土」といっても雑誌を作るにあたって沢山の壁にぶち当たっています。
・いかに「土」と「静岡県」を繋げられるか
・読者に「土」の存在を再認識してもらうには、どんな企画記事を制作すればよいか。
・特集の全体像は”真面目路線”で組むか、”真面目に馬鹿やっている”と思ってもらえるように組むのか……など
今回の企画タイトル「静岡の土を舐めたい」は一見キャッチーだけれど、読者である大学生は普段の生活において「土」そのものにそこまで関心が高いわけではありません。一見地味に見える土が実は主役級だった!と、読者のこれまでの価値観を変えてしまうような号にしたいです。
「土」から静岡県を知る。ここ静岡において、土とともに生きる風景や人、思想を取り上げ、土との向き合い方を学びたい。
ちなみに、今号では「直に土を舐める」企画を遂行しました!静岡県内には、黒ボク土や赤黄色土、褐色森林土など多様な土が分布しています(制作が進むにつれて、だんだん専門用語が飛び交うようになりました)。実際にそれらの土を採取に行き、編集長をはじめ3人の編集部員がいざ、「実舐」。合言葉は「知ることは舐めること」。どうやら“真面目一徹”からは離れたようですが、気になる結果は……。ふふふ、みなさんぜひお楽しみに。

とある打ち合わせの際の樫田編集長。凛々しい表情ですね。こうみえて、普段は癒しオーラ全開です。
樫田編集長は常に癒しオーラがでていて、歩く姿がとてもかわいいのです。そしてロックが大好き!というギャップ!(そんなロックが大好きなかっしーさんが副編集長を務めます12月号はこちらから読めます。)冗談を言うと笑いあったり、適度にツッコミをいれてくれます。私が冗談を言うと母性が垣間見えます。しかし!会議になると一変!凛々しい顔立ちに変わり、編集部員をビシバシと鍛えます(めちゃかっこいいです)。私を含め編集部員はそのオーラに圧倒します(……私にはオーラが茶色くみえます)。
樫田編集長は現在も、東・中・西部と果てしなく走りまわっています。6月号完成までを一生懸命指揮している樫田編集長を、私は支えていきたいと思います!
「土」をテーマに絶賛制作中の静岡時代編集部。編集長樫田と副編集長漆畑を筆頭に精進してまいりますので、みなさんご期待ください!
常葉大生による、静岡時代インターンシップ見聞録【2015】
祝!Facebook静岡未来が3周年を迎えました!!
【最新号】静岡時代6月号:発行のお知らせ!
【念願の初開催】全静岡県の大学生の祭典「第一回静岡県カレッジサミット」
編集部日誌:【制作】静岡時代4月号(vol.38)
静岡時代が「先生」に! 静岡時代の文章術講座〜裾野市の小学生と『裾野時代』発行!
祝!Facebook静岡未来が3周年を迎えました!!
【最新号】静岡時代6月号:発行のお知らせ!
【念願の初開催】全静岡県の大学生の祭典「第一回静岡県カレッジサミット」
編集部日誌:【制作】静岡時代4月号(vol.38)
静岡時代が「先生」に! 静岡時代の文章術講座〜裾野市の小学生と『裾野時代』発行!
Updated:2014年05月19日 編集室より
















