特集
恋のメカニズムを教えて!〜脳科学から検証する、恋愛理論〜
連続特集:「静岡時代の恋愛論」
「恋」や「恋愛」は、感覚的でよくわからない。理由があるにしても、どれも後付けな気がしてしまいます。論理的に「恋」を検証したら、私たちの身体の中では一体、何が起こっているのでしょうか。「恋」に科学的な視点を向けて、「人が何故恋愛をするのか」、理由を探っていきます。脳科学・神経科学の専門家である静岡理工科大学の奥村先生に、お話を伺いました。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
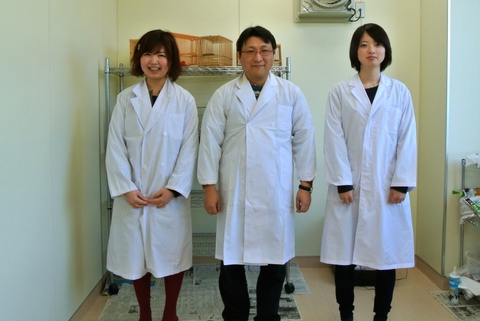
●奥村哲先生
静岡理工科大学 総合情報学部 人間情報デザイン学科客員准教授。研究分野は神経科学。大学で小鳥の脳と歌声の関連性を研究している。「研究している小鳥をもっと増やしたい」のだそう。
●小池麻友:静岡県立大学(写真右)/ 亀山春佳:静岡英和学院大学(写真左)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■「好き」は、出会って0.3秒で決まる
ーー奥村先生は神経科学を専門に研究されていますが、脳科学や神経行動学にみるとどうなったときに「好き」になったと言えるんですか?
(奥村先生)「好き」になるということは色々な研究から、出会って0.3秒ぐらいの中でびびっとくることが大切だといわれています。まず「びびっとくる」。そのあとから、好きだから、好感を持っているから、良く見えるということがあるのです。この「びびっとくる」時にはさまざまな、意味のある信号と意味のない信号、正直な信号と正直でない信号が働いているのです。
ーー早速もう分かりません。どういうことですか?
(奥村先生)正直なシグナルというのは、動物がもつ、よりよい子孫を残していこうとする本能にはたらきかけるものです。人間の場合でいうと、男性にとって第二次性徴で育った女性の胸はセクシーで、女性とっても男性の背中ががっしりしていたらセクシーに見える、というもの。例えば、一般的に若い女性のほうが人気がありますよね。それは妊娠確率の高い方がいいという本能的な理由も含まれているんです。ただヒトでは若い女性が特に好まれることもあるようです。でも、動物はちょっと違って一回子供を育てたことのあるメスの方が人気なこともあるんですよ。ワンシーズンちゃんと子育てを成功させたメスの方がいいんですね。
他にも、ハンディキャップ原理というものがあります。クジャクの尾があんなに大きく綺麗なのは、生きる上では必要のないものです。しかし、その不要な形質を持っていることが体力やなにがしかの資質の余剰分として異性に魅力的に見えているらしいんですよ。これを人間に当てはめると「シャープペンをくるくる回せる」とか「歌がうまい」とかといった、一見無駄な能力が魅力的にみえることがあるということにも、説明がつくかもしれませんね。
一方で、正直でないシグナルには人間にしかないシグナルもあります。例えば、ウソを言うこと。言葉を話す人間だけが獲得した、特別な能力です。だから「僕は君のことを大切にするんだ」と言葉だけは完璧でも、その気持ちが本当かどうか評価する能力が必要になってきます。口では何でも言えてしまいますからね。若いうちに色々と経験を積んでおくべきと言われますが、その能力を鍛えるのには必要かもしれませんね。ウソを見抜く能力が十分に発達していない人は不幸な結婚をするリスクが高いかもしれません。またヒトは文化をもつので、シグナルが多様化しています。その代表的な例がお金です。どれくらい自分にお金をかけてくれるか。お金によってもたらされる、生活の安定。それらもある種のシグナルとして働いているようです。

ーーシグナルを受け取り「好き」になったとき、私たちの脳ではいったい何が起こっているのでしょうか。
(奥村先生)「好き」という状態のときは、脳でオキシトシンという物質が働いていています。オキシトシンとは、愛着や信頼を増幅させる物質で、恋をしたとき、信頼の気持ちが高まるときに多く分泌されています。ものすごくオキシトシンの働きが強い人はすぐに他人を信じてしまって、騙されやすかったりします。ちなみに、動物にはものすごく近い種でも住んでいるところの違いで、乱婚や一夫一妻と分かれることがあるんですよ。ほとんど同じ脳ですが、オキシトシンの分泌量や受容体に違いがあるんです。ハタネズミという種では、オキシトシンの働きが強い種は、一夫一妻傾向が強くなっています。また、もしもこのオキシトシンを人に向かってスプレーで振りかけたとしたら、目の前の人を信じやすくなっちゃうかもしれない。究極の「惚れ薬」ともいえますよね。
ーー惚れ薬はつくれるんですね!
(奥村先生)はっきりいって、一目惚れはその人の人となりも分からないうちに好きになってしまうことです。「好き」になることでオキシトシンが分泌されて信頼が生まれるということであれば、そこには根拠のない信頼があることになります。実は、理想の人だから「好き」なのではなく、「好き」だから理想の人になるんです。
例えば、笑っているから楽しくなる、泣いているから悲しくなるといったことと同じです。だから「理想の人」というのは脳科学的にはほぼ後付けなんですよ。結婚をする理由は様々ですが、一目惚れという理由でお付き合いをはじめた夫婦の方が長持ちするというデータもあるくらいです。私たちの頭の中では好きになった人を無意識のうちに美化してしまうという、やさしい勘違いが起きているんですね。そうした勘違いも恋愛の初期には必要だと思います。最初の段階で愛着感を深めておけば、長い付き合いに繋がります。相手がいくらだらしない人だとしても、美化して盛り上がっている段階では意味がない。理想化されているから見ても何も思わないし、そもそも見えないんですよ。心理学的にも、人間は見たくないところは見えにくいのです。

■理屈で説明できない屁理屈で心が動く。その直感も侮れないもの
ーー「好き」は幻想なんでしょうか?恋を理屈で説明することはできないのでしょうか。
(奥村先生)たしかに「好き」になることは必ずしも理屈ではないということが分かってきました。言語を持たない動物のメスがオスを選ぶ根拠の説明は言語ではなかなかできませんからね。ダメ男ばかりを好きになっていく人もいますが、そんなものは言葉の論理ではなく感情的にしか説明できないんです。分析をすると理屈で考えたくなりますが、人生の多くのことは実は理屈ではないんです。逆の方向で理屈ではない情動がはたらく例としてはトラウマがあります。トラウマは、以前エレベーターに閉じ込められたことがあるから二度と乗りたくないと思うような気持ちです。頭のどこかでは、論理的にはもう二度と同じことが起こらないって分かっているくせに、エレベーターに二度と乗りたくないと思う。よっぽどのことですよね。論理で説明できない気持ち。それだけを比べたら、実は犬も人間もほとんど同じですね。
ーー犬も人間も同じ……。衝撃的な言葉です。自分自身で恋をコントロールすることはできないんですか?
(奥村先生)コントロールする必要があるんでしょうか。わざわざどうにかする必要はないと思いますね。恋ができるかどうかには、何人の人に出会えているかが重要だというデータがあります。びびっと来る時が出会いです。それでいいんですよ。もし過去の恋愛を引きずっていても、いつかびびってきて恋をするかもしれませんし、沢山の人と出会いをしていけば、相手からびびってくることもあるかもしれない。結局多くの人と出会いながら、そうなるときを待つしかないですね。「恋のはじまりは屁理屈なのがまっとう」です。そんなものです。理屈で説明できない屁理屈で心が動いてしまったら、それは恋の始まりとしてはとてもまっとうなんです。でも直感レベルの判断も実はなかなか侮れないことが分かってきています。自分の直感を信じて突き進むのも悪くはないと思いますよ。
◆このお話をもっと深く掘り下げたいひとへ奥村哲先生からのオススメ本!
『生物進化とハンディキャップ原理̶性選択と利他行動の謎を解く』アモツ ザハヴィ(他著). 白揚社. 2001.

●話し手:奥村哲先生
静岡理工科大学 総合情報学部 人間情報デザイン学科客員准教授。研究分野は神経科学。大学で小鳥の脳と歌声の関連性を研究している。「研究している小鳥をもっと増やしたい」のだそう。
●聞き手:
静岡県立大学3年/小池麻友
静岡英和学院大学4年/亀山春佳
「恋」や「恋愛」は、感覚的でよくわからない。理由があるにしても、どれも後付けな気がしてしまいます。論理的に「恋」を検証したら、私たちの身体の中では一体、何が起こっているのでしょうか。「恋」に科学的な視点を向けて、「人が何故恋愛をするのか」、理由を探っていきます。脳科学・神経科学の専門家である静岡理工科大学の奥村先生に、お話を伺いました。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
●奥村哲先生
静岡理工科大学 総合情報学部 人間情報デザイン学科客員准教授。研究分野は神経科学。大学で小鳥の脳と歌声の関連性を研究している。「研究している小鳥をもっと増やしたい」のだそう。
●小池麻友:静岡県立大学(写真右)/ 亀山春佳:静岡英和学院大学(写真左)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■「好き」は、出会って0.3秒で決まる
ーー奥村先生は神経科学を専門に研究されていますが、脳科学や神経行動学にみるとどうなったときに「好き」になったと言えるんですか?
(奥村先生)「好き」になるということは色々な研究から、出会って0.3秒ぐらいの中でびびっとくることが大切だといわれています。まず「びびっとくる」。そのあとから、好きだから、好感を持っているから、良く見えるということがあるのです。この「びびっとくる」時にはさまざまな、意味のある信号と意味のない信号、正直な信号と正直でない信号が働いているのです。
ーー早速もう分かりません。どういうことですか?
(奥村先生)正直なシグナルというのは、動物がもつ、よりよい子孫を残していこうとする本能にはたらきかけるものです。人間の場合でいうと、男性にとって第二次性徴で育った女性の胸はセクシーで、女性とっても男性の背中ががっしりしていたらセクシーに見える、というもの。例えば、一般的に若い女性のほうが人気がありますよね。それは妊娠確率の高い方がいいという本能的な理由も含まれているんです。ただヒトでは若い女性が特に好まれることもあるようです。でも、動物はちょっと違って一回子供を育てたことのあるメスの方が人気なこともあるんですよ。ワンシーズンちゃんと子育てを成功させたメスの方がいいんですね。
他にも、ハンディキャップ原理というものがあります。クジャクの尾があんなに大きく綺麗なのは、生きる上では必要のないものです。しかし、その不要な形質を持っていることが体力やなにがしかの資質の余剰分として異性に魅力的に見えているらしいんですよ。これを人間に当てはめると「シャープペンをくるくる回せる」とか「歌がうまい」とかといった、一見無駄な能力が魅力的にみえることがあるということにも、説明がつくかもしれませんね。
一方で、正直でないシグナルには人間にしかないシグナルもあります。例えば、ウソを言うこと。言葉を話す人間だけが獲得した、特別な能力です。だから「僕は君のことを大切にするんだ」と言葉だけは完璧でも、その気持ちが本当かどうか評価する能力が必要になってきます。口では何でも言えてしまいますからね。若いうちに色々と経験を積んでおくべきと言われますが、その能力を鍛えるのには必要かもしれませんね。ウソを見抜く能力が十分に発達していない人は不幸な結婚をするリスクが高いかもしれません。またヒトは文化をもつので、シグナルが多様化しています。その代表的な例がお金です。どれくらい自分にお金をかけてくれるか。お金によってもたらされる、生活の安定。それらもある種のシグナルとして働いているようです。
ーーシグナルを受け取り「好き」になったとき、私たちの脳ではいったい何が起こっているのでしょうか。
(奥村先生)「好き」という状態のときは、脳でオキシトシンという物質が働いていています。オキシトシンとは、愛着や信頼を増幅させる物質で、恋をしたとき、信頼の気持ちが高まるときに多く分泌されています。ものすごくオキシトシンの働きが強い人はすぐに他人を信じてしまって、騙されやすかったりします。ちなみに、動物にはものすごく近い種でも住んでいるところの違いで、乱婚や一夫一妻と分かれることがあるんですよ。ほとんど同じ脳ですが、オキシトシンの分泌量や受容体に違いがあるんです。ハタネズミという種では、オキシトシンの働きが強い種は、一夫一妻傾向が強くなっています。また、もしもこのオキシトシンを人に向かってスプレーで振りかけたとしたら、目の前の人を信じやすくなっちゃうかもしれない。究極の「惚れ薬」ともいえますよね。
ーー惚れ薬はつくれるんですね!
(奥村先生)はっきりいって、一目惚れはその人の人となりも分からないうちに好きになってしまうことです。「好き」になることでオキシトシンが分泌されて信頼が生まれるということであれば、そこには根拠のない信頼があることになります。実は、理想の人だから「好き」なのではなく、「好き」だから理想の人になるんです。
例えば、笑っているから楽しくなる、泣いているから悲しくなるといったことと同じです。だから「理想の人」というのは脳科学的にはほぼ後付けなんですよ。結婚をする理由は様々ですが、一目惚れという理由でお付き合いをはじめた夫婦の方が長持ちするというデータもあるくらいです。私たちの頭の中では好きになった人を無意識のうちに美化してしまうという、やさしい勘違いが起きているんですね。そうした勘違いも恋愛の初期には必要だと思います。最初の段階で愛着感を深めておけば、長い付き合いに繋がります。相手がいくらだらしない人だとしても、美化して盛り上がっている段階では意味がない。理想化されているから見ても何も思わないし、そもそも見えないんですよ。心理学的にも、人間は見たくないところは見えにくいのです。
■理屈で説明できない屁理屈で心が動く。その直感も侮れないもの
ーー「好き」は幻想なんでしょうか?恋を理屈で説明することはできないのでしょうか。
(奥村先生)たしかに「好き」になることは必ずしも理屈ではないということが分かってきました。言語を持たない動物のメスがオスを選ぶ根拠の説明は言語ではなかなかできませんからね。ダメ男ばかりを好きになっていく人もいますが、そんなものは言葉の論理ではなく感情的にしか説明できないんです。分析をすると理屈で考えたくなりますが、人生の多くのことは実は理屈ではないんです。逆の方向で理屈ではない情動がはたらく例としてはトラウマがあります。トラウマは、以前エレベーターに閉じ込められたことがあるから二度と乗りたくないと思うような気持ちです。頭のどこかでは、論理的にはもう二度と同じことが起こらないって分かっているくせに、エレベーターに二度と乗りたくないと思う。よっぽどのことですよね。論理で説明できない気持ち。それだけを比べたら、実は犬も人間もほとんど同じですね。
ーー犬も人間も同じ……。衝撃的な言葉です。自分自身で恋をコントロールすることはできないんですか?
(奥村先生)コントロールする必要があるんでしょうか。わざわざどうにかする必要はないと思いますね。恋ができるかどうかには、何人の人に出会えているかが重要だというデータがあります。びびっと来る時が出会いです。それでいいんですよ。もし過去の恋愛を引きずっていても、いつかびびってきて恋をするかもしれませんし、沢山の人と出会いをしていけば、相手からびびってくることもあるかもしれない。結局多くの人と出会いながら、そうなるときを待つしかないですね。「恋のはじまりは屁理屈なのがまっとう」です。そんなものです。理屈で説明できない屁理屈で心が動いてしまったら、それは恋の始まりとしてはとてもまっとうなんです。でも直感レベルの判断も実はなかなか侮れないことが分かってきています。自分の直感を信じて突き進むのも悪くはないと思いますよ。
◆このお話をもっと深く掘り下げたいひとへ奥村哲先生からのオススメ本!
『生物進化とハンディキャップ原理̶性選択と利他行動の謎を解く』アモツ ザハヴィ(他著). 白揚社. 2001.
●話し手:奥村哲先生
静岡理工科大学 総合情報学部 人間情報デザイン学科客員准教授。研究分野は神経科学。大学で小鳥の脳と歌声の関連性を研究している。「研究している小鳥をもっと増やしたい」のだそう。
●聞き手:
静岡県立大学3年/小池麻友
静岡英和学院大学4年/亀山春佳
新しい音楽の創り方〜静岡時代24号『静岡時代の、音楽論』より
今開かれる、静岡パンドラの箱!〜静岡時代12号『静岡魔界探訪』より
静岡時代を残す人【静岡県立中央図書館】〜静岡時代創刊10年記念号「静岡時代ベスト版」
禅問答のように難解な物語の紡ぎ方〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」より
文学が先か?音楽が先か?「音」から育てる物語〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」〜
使われるかもしれない“いつか”のためにアーカイブする〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」より
今開かれる、静岡パンドラの箱!〜静岡時代12号『静岡魔界探訪』より
静岡時代を残す人【静岡県立中央図書館】〜静岡時代創刊10年記念号「静岡時代ベスト版」
禅問答のように難解な物語の紡ぎ方〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」より
文学が先か?音楽が先か?「音」から育てる物語〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」〜
使われるかもしれない“いつか”のためにアーカイブする〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」より
Updated:2014年06月12日 特集


















