特集
文学が先か?音楽が先か?「音」から育てる物語〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」〜
物語の形は文学だけではない。例えば、音楽も音やフレーズに物語性を感じられる。文学も音楽も言語(音素)から発せられる点は同じだが、両者の物語性に関連性はあるのだろうか?日本文学の専門家 渡邊英理先生と指揮者 山下篤さんによる物語の構成要素徹底分析!
■長年、文学と音楽は手を携え物語を担ってきた
「祇園精舎の鐘の音、諸行無常の響きあり」から始まる平家物語の有名な冒頭がある。琵琶法師に代表される中世の語り物は語りながらもまずメロディーや節があり、楽器で伴奏を奏でるという音楽性を持っていた。近代以前は文学と音楽は融合していたのだ。
「日本の物語の豊穣なる一時期を支えたのは音楽と文学が融合したものではなかったか」と文学を専門とする渡邊英理先生は語る。今でこそ活版印刷技術の発展により活字メディアが浸透しているが、物語の起源は「声(音)」だ。人間の声帯が振動することで音が出る、言葉でもあり、原初的な楽器でもあった。文学と音楽は一つの未分化な状態で誕生し、そして「物語」を開花させたのだ。
文学と音楽が分かれたのは明治以降。西洋化と近代化によって、二つの間には、明確な境界線が引かれ、両者が融合し、大勢でライヴの様な形で享受する語り物のようなジャンルはマイナー化されてしまう事になる。かつては同じものから生まれ、分かれた文学と音楽が持つ物語の本質に迫った。(取材・文/寺島美夏)
▷文学の物語

◉渡邊 英理(わたなべ えり)先生
静岡大学人文社会科学部言語文化学科日本アジア言語文化コース准教授。
近現代日本語文学を専門とし、中上健次、崎山多美などの作品から地域をめぐる思想文学について研究している。
・もっと深く掘り下げたいひとへ渡邊英理先生がオススメする音楽性を感じる文学!『 不死』(『熊野集』より)中上健次
■文学とは言葉によって表現される時間芸術
Q1:文学と音楽の物語の構造の関係性
音楽と同じく文学もまた時間芸術です。言語は、時間の流れの中に置いてこそ表現可能なメディア。音素を順番に並べ組み合わせる事で初めて言葉となる。しかもその意味は、読み手が関わってはじめて発生します。読み手がいない時、文字は、白紙の上の黒い染みに過ぎない。物質としての文字に意味という息吹を与えるのが、読み手です。読み手は、単に物語を享受する消費者ではなく再創造者であり、物語の時間を動かす存在だと言えます。音楽に比べ文学は受け手の役割が大きいですね。作者が託した一つの意味だけではなく読み手自身が意味を作り出す。だからこそ、途中で時間を空けて物語を分割しても楽しむことができるのだと思います。

▲写真左:本企画編集長/河田弥歩(静岡大学4年) 写真右:執筆者/寺田美夏(静岡大学2年)
Q2:文学の物語の構成要素とは
先ほど述べた音素や文中の句読点に加え、受容のメディアそれ自体、つまり本の装丁や活字のフォント、頁の紙なども広い意味での構成要素だと言えます。また、読み手が意味を発生させるという点で、読書行為や読書空間もそうだ、と言えるかもしれません。
文学には複数の物語で構成される連作が存在します。中上健次の短編連作集のうち、『熊野集』は初めから連作として発表され、他方『化粧』は事後的に連作集にまとめられました。成立の経緯とは別に、いずれの連作集も、集すべてで大きな物語を構成しているようにも読めるし、また、個々の物語を独立したものとして楽しむこともできます。その解釈は読み手に委ねられます。言葉は、常に過去の引用によって成立します。そのため、新たに生み出され物語を、過去の物語に付け加えられた新しい一頁や一章として読むこともできますね。言葉で時間や空間を越えうる文学だからこそ可能なことだと思います。

Q3:物語としての文学の力
物語には両義的な力があると思います。文学の物語は、つねに読者を必要とし、読み手の読みたい、という欲望をつねに喚起しつづける必要があります。そのため物語は面白くあることが宿命づけられている。
昔話に超人や絶世の美女、富者や貧者、社会的弱者がしばしば登場しますが、これらは標準という基準から隔たりを作り、物語を面白くする仕掛けです。普通とは異なるものをよびこむ力は差別的です。その一方、物語には、虐げられた人々が現実では為し得ないことを成就させ、叶わぬ夢をすくい上げる働きもあります。いまある世界を唯一のものとしない想像力を、物語は手渡すのです(了)
▷音楽の物語

◉山下 篤(やました あつし)さん
上海音楽学院で管弦楽指揮と打楽器を学ぶ。中国、タイで打楽器奏者、指揮者として活躍した。
現在日本国内を始めアジアや北米で指揮者、打楽器奏者、解説者として活躍中。
・もっと深く掘り下げたいひとへ山下篤さんがオススメする物語性を感じる音楽!『 ニーベルングの指輪』ワーグナー
■楽章の間の無音も全体の物語を構成する
Q1:文学と音楽の物語の構造の関係性
音楽と文学は場面転換の構造が全く異なると思います。音楽は時間の流れと共に音符が流れていくため時間の芸術と言われています。例えば同じ交響曲ならば、作曲家は一楽章から四楽章まで連続して聴かれることを前提として作曲しています。一つの楽章の間の無音まで計算して曲が作られているので、CDなどで一楽章ごと切って聞いてしまうと物語性が伝わりにくく、感動が薄れてしまいます。でも文学は第一章と第二章を読むまでの間に何日も時間が空いても感動しますよね。音楽は途中で時間が空くと興ざめしてしまいますが、文学はそうではない。それは構造に大きな違いがあるからだと思います。

Q2:音楽の物語の構成要素とは
例えば第一楽章から第四楽章まで全く違う曲調であっても、それら全てで一つの物語を構成しています。曲にも起承転結があり、それは全て作曲家の手で計算されています。さらにその音楽が発せられる場所に大勢の観客がいるという、張りつめた空気感も合わさり、観客に心情の変化を与える。観客も構成要素の一つです。逆に音楽そのものが物語の構成要素になる場合もあります。作曲家のワーグナーは登場人物一人一人にテーマ曲をつけ、その音楽が流れるだけでその人物が観客の頭に浮かぶように刷り込む事で音楽を物語の構成要素として使いました。音楽全体で物語を表すこともあれば音楽が物語の一部にもなる、様々な形で物語を表現する事ができるのが音楽だと思います。

Q3:物語としての音楽の力
例えば高い音は緊張を表し、低い音は安堵を表す。長調は安心感を与え、短調は不安感を与える。それは原始人時代から培われてきたDNAによるものです。音楽は音の高低、和音、速さなどの組み合わせによって聴衆の中のDNAを上手に操作しています。だから音楽は人々に安らぎを与えたりリラックスさせることもできれば、緊張感を与えたり、拷問に使うことだってできるような大きな力を持っています。音楽はとても文化的なもののように思われがちですが、実は人間の本能に働きかけるとても動物的なものなんですよ(了)
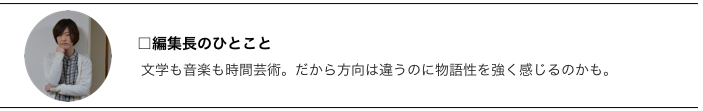
▼このインタビューが掲載されている、静岡時代最新号!▼
静岡県のすべての大学で配布中!(ほか、高校で配布・設置)
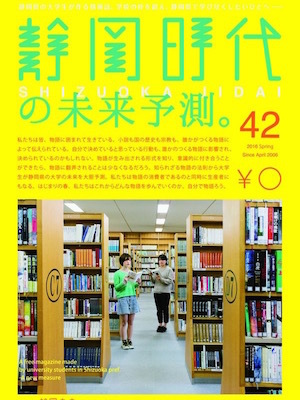
▷▷シリーズ第4回「人はどのように物語を紡いでいくのか」は、5/31(火)更新します!
■長年、文学と音楽は手を携え物語を担ってきた
「祇園精舎の鐘の音、諸行無常の響きあり」から始まる平家物語の有名な冒頭がある。琵琶法師に代表される中世の語り物は語りながらもまずメロディーや節があり、楽器で伴奏を奏でるという音楽性を持っていた。近代以前は文学と音楽は融合していたのだ。
「日本の物語の豊穣なる一時期を支えたのは音楽と文学が融合したものではなかったか」と文学を専門とする渡邊英理先生は語る。今でこそ活版印刷技術の発展により活字メディアが浸透しているが、物語の起源は「声(音)」だ。人間の声帯が振動することで音が出る、言葉でもあり、原初的な楽器でもあった。文学と音楽は一つの未分化な状態で誕生し、そして「物語」を開花させたのだ。
文学と音楽が分かれたのは明治以降。西洋化と近代化によって、二つの間には、明確な境界線が引かれ、両者が融合し、大勢でライヴの様な形で享受する語り物のようなジャンルはマイナー化されてしまう事になる。かつては同じものから生まれ、分かれた文学と音楽が持つ物語の本質に迫った。(取材・文/寺島美夏)
▷文学の物語

◉渡邊 英理(わたなべ えり)先生
静岡大学人文社会科学部言語文化学科日本アジア言語文化コース准教授。
近現代日本語文学を専門とし、中上健次、崎山多美などの作品から地域をめぐる思想文学について研究している。
・もっと深く掘り下げたいひとへ渡邊英理先生がオススメする音楽性を感じる文学!『 不死』(『熊野集』より)中上健次
■文学とは言葉によって表現される時間芸術
Q1:文学と音楽の物語の構造の関係性
音楽と同じく文学もまた時間芸術です。言語は、時間の流れの中に置いてこそ表現可能なメディア。音素を順番に並べ組み合わせる事で初めて言葉となる。しかもその意味は、読み手が関わってはじめて発生します。読み手がいない時、文字は、白紙の上の黒い染みに過ぎない。物質としての文字に意味という息吹を与えるのが、読み手です。読み手は、単に物語を享受する消費者ではなく再創造者であり、物語の時間を動かす存在だと言えます。音楽に比べ文学は受け手の役割が大きいですね。作者が託した一つの意味だけではなく読み手自身が意味を作り出す。だからこそ、途中で時間を空けて物語を分割しても楽しむことができるのだと思います。

▲写真左:本企画編集長/河田弥歩(静岡大学4年) 写真右:執筆者/寺田美夏(静岡大学2年)
Q2:文学の物語の構成要素とは
先ほど述べた音素や文中の句読点に加え、受容のメディアそれ自体、つまり本の装丁や活字のフォント、頁の紙なども広い意味での構成要素だと言えます。また、読み手が意味を発生させるという点で、読書行為や読書空間もそうだ、と言えるかもしれません。
文学には複数の物語で構成される連作が存在します。中上健次の短編連作集のうち、『熊野集』は初めから連作として発表され、他方『化粧』は事後的に連作集にまとめられました。成立の経緯とは別に、いずれの連作集も、集すべてで大きな物語を構成しているようにも読めるし、また、個々の物語を独立したものとして楽しむこともできます。その解釈は読み手に委ねられます。言葉は、常に過去の引用によって成立します。そのため、新たに生み出され物語を、過去の物語に付け加えられた新しい一頁や一章として読むこともできますね。言葉で時間や空間を越えうる文学だからこそ可能なことだと思います。

Q3:物語としての文学の力
物語には両義的な力があると思います。文学の物語は、つねに読者を必要とし、読み手の読みたい、という欲望をつねに喚起しつづける必要があります。そのため物語は面白くあることが宿命づけられている。
昔話に超人や絶世の美女、富者や貧者、社会的弱者がしばしば登場しますが、これらは標準という基準から隔たりを作り、物語を面白くする仕掛けです。普通とは異なるものをよびこむ力は差別的です。その一方、物語には、虐げられた人々が現実では為し得ないことを成就させ、叶わぬ夢をすくい上げる働きもあります。いまある世界を唯一のものとしない想像力を、物語は手渡すのです(了)
▷音楽の物語

◉山下 篤(やました あつし)さん
上海音楽学院で管弦楽指揮と打楽器を学ぶ。中国、タイで打楽器奏者、指揮者として活躍した。
現在日本国内を始めアジアや北米で指揮者、打楽器奏者、解説者として活躍中。
・もっと深く掘り下げたいひとへ山下篤さんがオススメする物語性を感じる音楽!『 ニーベルングの指輪』ワーグナー
■楽章の間の無音も全体の物語を構成する
Q1:文学と音楽の物語の構造の関係性
音楽と文学は場面転換の構造が全く異なると思います。音楽は時間の流れと共に音符が流れていくため時間の芸術と言われています。例えば同じ交響曲ならば、作曲家は一楽章から四楽章まで連続して聴かれることを前提として作曲しています。一つの楽章の間の無音まで計算して曲が作られているので、CDなどで一楽章ごと切って聞いてしまうと物語性が伝わりにくく、感動が薄れてしまいます。でも文学は第一章と第二章を読むまでの間に何日も時間が空いても感動しますよね。音楽は途中で時間が空くと興ざめしてしまいますが、文学はそうではない。それは構造に大きな違いがあるからだと思います。

Q2:音楽の物語の構成要素とは
例えば第一楽章から第四楽章まで全く違う曲調であっても、それら全てで一つの物語を構成しています。曲にも起承転結があり、それは全て作曲家の手で計算されています。さらにその音楽が発せられる場所に大勢の観客がいるという、張りつめた空気感も合わさり、観客に心情の変化を与える。観客も構成要素の一つです。逆に音楽そのものが物語の構成要素になる場合もあります。作曲家のワーグナーは登場人物一人一人にテーマ曲をつけ、その音楽が流れるだけでその人物が観客の頭に浮かぶように刷り込む事で音楽を物語の構成要素として使いました。音楽全体で物語を表すこともあれば音楽が物語の一部にもなる、様々な形で物語を表現する事ができるのが音楽だと思います。

Q3:物語としての音楽の力
例えば高い音は緊張を表し、低い音は安堵を表す。長調は安心感を与え、短調は不安感を与える。それは原始人時代から培われてきたDNAによるものです。音楽は音の高低、和音、速さなどの組み合わせによって聴衆の中のDNAを上手に操作しています。だから音楽は人々に安らぎを与えたりリラックスさせることもできれば、緊張感を与えたり、拷問に使うことだってできるような大きな力を持っています。音楽はとても文化的なもののように思われがちですが、実は人間の本能に働きかけるとても動物的なものなんですよ(了)
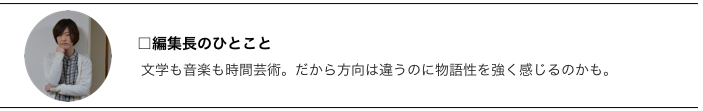
▼このインタビューが掲載されている、静岡時代最新号!▼
静岡県のすべての大学で配布中!(ほか、高校で配布・設置)
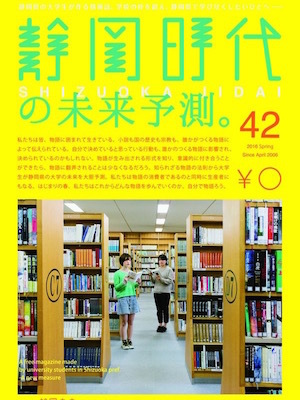
合わせて読みたい!【静岡時代の未来予測】バックナンバー
2016/05/09
人はみんな、意識的にも無意識的にも物語に縛られて生きています。昨日の出来事も、見た夢も、誰かに説明をしようとした時、それは「物語」という形でしか伝えられません。言語学を専門とする静岡大学人文社会科学部の堀博文先生は「そもそもある程度、複雑な世の中でないと物語は発達しない」と言います。
2016/05/17
人が考え、伝えるとき、それは物語の構造を孕んでいます。つまり、物語には何らかのメッセージが含まれているということです。古今東西、世の中には物語があふれているけれど、その土地土地に残された古い物語には、私たちが生きやすくなるような手がかりが隠されているのかもしれません。
▷▷シリーズ第4回「人はどのように物語を紡いでいくのか」は、5/31(火)更新します!
新しい音楽の創り方〜静岡時代24号『静岡時代の、音楽論』より
今開かれる、静岡パンドラの箱!〜静岡時代12号『静岡魔界探訪』より
静岡時代を残す人【静岡県立中央図書館】〜静岡時代創刊10年記念号「静岡時代ベスト版」
禅問答のように難解な物語の紡ぎ方〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」より
使われるかもしれない“いつか”のためにアーカイブする〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」より
なぜ人は物語るのか?〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」より
今開かれる、静岡パンドラの箱!〜静岡時代12号『静岡魔界探訪』より
静岡時代を残す人【静岡県立中央図書館】〜静岡時代創刊10年記念号「静岡時代ベスト版」
禅問答のように難解な物語の紡ぎ方〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」より
使われるかもしれない“いつか”のためにアーカイブする〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」より
なぜ人は物語るのか?〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」より
Updated:2016年05月24日 特集


















