特集
使われるかもしれない“いつか”のためにアーカイブする〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」より
人が考え、伝えるとき、それは物語の構造を孕んでいます。つまり、物語には何らかのメッセージが含まれているということです。古今東西、世の中には物語があふれているけれど、その土地土地に残された古い物語には、私たちが生きやすくなるような手がかりが隠されているのかもしれません。しかし、伝承文学を専門とする静岡文化芸術大学文化政策学部の二本松康宏先生は「そもそも物語における教訓は後付けだ」と言います。静岡県の古い物語の持つメッセージやその本質とは何なのでしょうか?

■二本松 康宏(にほんまつ やすひろ)先生〈写真:左〉
静岡文化芸術大学文化政策学部国際文化学科准教授。
「伝承文学と風景の中の文化」をテーマに実地調査を重視した研究を行う。年に一度、大久野島でうさぎに囲まれ休暇を過ごす大のうさぎ好き。
■河田 弥歩(かわた みづほ)〈写真:右奥〉
静岡大学 人文社会科学部3年。本企画編集長。
■田中 楓(たなか かえで)〈写真:右手前〉
静岡大学 人文社会科学部2年。
ーー昔話や伝説とも言われますが、そもそも「古い物語」の定義を教えて下さい。
(二本松先生)まず、「昔話」と「伝説」の違いから説明しましょう。昔話は物語の時代と場所を特定しません。だから「むかしむかし、あるところに」と語り出されます。伝説は時代や場所を特定します。なので、その伝説が伝えられる地域では、伝説が歴史的事実と混同されて伝えられる傾向があります。昔話は、どちらかというとおばあちゃんが囲炉裏の端で子どもたちに語って聞かせるイメージですね。だから女性によって家系的に伝承される傾向があります。伝説はその土地を舞台として土地に根付いて伝えられます。なので伝承者の多くは物知りのおじいさんで、「土地の古老」などと呼ばれる人たちです。一概には言えませんけどね。
また、昔話や伝説の他に「世間話」と呼ばれる分類もあります。それほど昔の話ではなく、近頃の出来事や自らの体験談、人から聞いた話などです。近年では「都市伝説」などとも言われます。学校の怪談なんかも世間話に属するものですね。神々の祭祀の由来を説く「神話」というのも一つの分類です。しかし、こうした分類はあくまでも学術上のことです。実際の語り手はそんな分類をいちいち意識してはいません。伝説的な昔話とか、神話と伝説の中間とか、いろいろありますよ。
ーーどういうことでしょうか?
(二本松先生)では例を一つ挙げてみましょう。私たちが刊行した『水窪のむかしばなし』という書籍に「上村の蛇婿入り」という話があります。若い娘のもとに正体不明の美しい男が夜毎に通ってくる。やがて娘は妊娠する。男の正体を突き止めるため男の衣の裾に糸を通した針を刺しておく。糸をたどってゆくと男の正体はなんと蛇だった」という話です。この話の元ネタは『古事記』にあり、三輪の大物主の神(蛇身)と活玉依姫の神婚の神話です。それが「むかしむかし、あるところに」となって昔話になりました。ところが、水窪では、蛇が通ったという娘の家系も蛇が沈んでいったという池も「そこだよ」と特定して伝わっています。こうなると分類は伝説です。神話だとか伝説だとか昔話だとか、そんな線引きはけっこう曖昧なんですよ。

▲『水窪のむかしばなし』上田沙来・内田ゆうき・野津彩綾・二本松康宏・福島愛生・山本理紗子.三弥井書店.2015

ーー同じ物語でもジャンルが違うと読み取れる事も変わってきますか?
(二本松先生)昔話というと、とかく何かの教訓や説教みたいなことが付いてきますが、そんなのは実は後付けですよ。もとからあったのはせいぜい「正直」と「親切」くらいなものです。昔話から何かを学ぼうとか、教訓を読み解こうなんて言っていると昔話の本質を見失ってしまいます。
ーーなるほど。では、先生が考える昔話の本質って何ですか?
(二本松先生)昔話の本質はたった一つ、「人の世の祝福」です。だから昔話は「めでたしめでたし」で終わるのです。いつかきっと幸せがやってくる。そう信じて、昔話は語り継がれるのです。
伝説の本質は「いまを生きる」ことです。いま、自分たちが暮らしている土地はどのようにして成り立ったのか?あの岩はなぜあそこにあるのか?あの山はなぜてっぺんが割れているのか?あの池はどうして……。いま自分たちが暮らす社会のはじまりを知りたい、伝えたいという思いが伝説を語り継ぎます。
例えば、浜松には「遠州大念仏」という郷土芸能があります。その由来は静大浜松キャンパスの近くの犀が崖(さいががけ)にあります。三方ヶ原の合戦に敗れた徳川家康が浜松城に逃げ込む。追撃してくる武田勢に対して、家康は犀が崖に白い布を掛け渡して橋に偽装する。武田勢は白い布を雪がかかった橋だと勘違いして次々と崖下に転落する。崖に落ちて亡くなった武田の兵たちの亡霊を慰めるために遠州大念仏が始まったと伝えられています。
しかし、これはあくまでも伝説です。ぜったいに歴史的事実ではありません。だいたい布の橋なんて一人が乗ったらそれだけで落ちますよ。それに気付かず次から次へと崖下に落ちてゆく武田軍なんて(笑)。そんな画期的な勝ち方をしたら家康は自慢げにあちこちに手紙を送ったりしますよ。でも残念ながらそういう記録を私は見たことがありません。

しかし、だから布橋伝説は歴史的事実ではない!!と一蹴してしまうのではありません。むしろ、そういう伝説がなぜ生成したのか?私の興味はそこにあります。それを風景のなかに探り、伝説の基層を読み解くのです。
第一に「犀が崖」という地名です。犀が崖の「犀」は「境」という意味です。この世とあの世の境にある「賽の河原」の「賽」も同じですね。境に祀られる神様は「塞ノ神」、サイノカミともサエノカミとも言います。つまり「犀が崖」はこの世とあの世の境なのです。第二に犀が崖は館山寺街道と姫街道の分岐点=辻にあります。辻も異界との境界と考えられました。第三には犀が崖が浜松城の北西にあたるという点。北西=戌亥は霊魂が去来する方位として畏れられていました。
また、「布橋」にも意味があります。富山の立山修験(芦峅寺)では白い布の橋を渡ることで疑似的な死と再生を体験する「布橋灌頂」という儀式があります。岐阜の白山修験(石徹白の白山中居権現)などにも布橋がありました。ひょっとしたら浜松の犀が崖でもかつて布橋灌頂のような疑死再生の儀礼が行われていたのかもしれません。そういう風景の中で犀が崖の布橋伝説が生成し、亡霊鎮魂の大念仏の由来譚として語り継がれてきたのです。
ーー物語から読み取れる土地との関係性は奥深いですね。ただ、こうした背景を探るのは大変な調査になりそうです。
(二本松先生)そうですね。例えていうならば、星の光を集めて太陽に挑むような作業です。着想から論文の完成までにはだいたい五年くらいかかります。長いのにると10年以上も調査を繰り返してようやく論文にできたものもあります。私が探しているのは「史実を超えた真実」です。
しかし、こんな研究は大学生には勧められません。学生はもっと短い期間で一定の成果を出さなければなりませんからね。まして四年生からの就活に備えるには、3年生の1年間が研究の正念場です。そこで、私のゼミでは浜松市の最奥部の水窪というところで昔話の採録調査に取り組んでいます。お年寄りたちに語っていただいた昔話や伝説を、語りのまま、方言のままに録音・記録し、解説も付けて書籍として出版しています。昨年は『水窪のむかしばなし』という書籍を出版しました。私とゼミの学生たちとの共著です。一般の書店でもAmazon.comでも買えます。今年も次の書籍(『みさくぼの民話』)が刊行される予定です。
語りのまま、方言のままに記録すること。学術的な解説を添えること。それを一般向けの書籍として刊行すること。そうすることで、私たちの書籍はアナログ・アーカイブとなります。「学問をもって世に問う」「学術をもって社会に貢献する」それが大学生の本質ではないでしょうか(了)
[取材・文/田中楓]


▼このインタビューが掲載されている、静岡時代最新号!▼
静岡県のすべての大学で配布中!(ほか、高校で配布・設置)
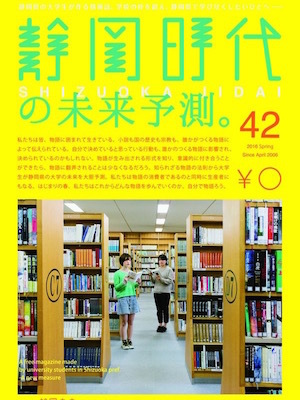
▷▷シリーズ第3回「音楽と文学は言語から生まれた二人姉妹?」は、5/24(火)更新します!

■二本松 康宏(にほんまつ やすひろ)先生〈写真:左〉
静岡文化芸術大学文化政策学部国際文化学科准教授。
「伝承文学と風景の中の文化」をテーマに実地調査を重視した研究を行う。年に一度、大久野島でうさぎに囲まれ休暇を過ごす大のうさぎ好き。
■河田 弥歩(かわた みづほ)〈写真:右奥〉
静岡大学 人文社会科学部3年。本企画編集長。
■田中 楓(たなか かえで)〈写真:右手前〉
静岡大学 人文社会科学部2年。
昔話、伝説、世間話……。物語は重なり合っている
ーー昔話や伝説とも言われますが、そもそも「古い物語」の定義を教えて下さい。
(二本松先生)まず、「昔話」と「伝説」の違いから説明しましょう。昔話は物語の時代と場所を特定しません。だから「むかしむかし、あるところに」と語り出されます。伝説は時代や場所を特定します。なので、その伝説が伝えられる地域では、伝説が歴史的事実と混同されて伝えられる傾向があります。昔話は、どちらかというとおばあちゃんが囲炉裏の端で子どもたちに語って聞かせるイメージですね。だから女性によって家系的に伝承される傾向があります。伝説はその土地を舞台として土地に根付いて伝えられます。なので伝承者の多くは物知りのおじいさんで、「土地の古老」などと呼ばれる人たちです。一概には言えませんけどね。
また、昔話や伝説の他に「世間話」と呼ばれる分類もあります。それほど昔の話ではなく、近頃の出来事や自らの体験談、人から聞いた話などです。近年では「都市伝説」などとも言われます。学校の怪談なんかも世間話に属するものですね。神々の祭祀の由来を説く「神話」というのも一つの分類です。しかし、こうした分類はあくまでも学術上のことです。実際の語り手はそんな分類をいちいち意識してはいません。伝説的な昔話とか、神話と伝説の中間とか、いろいろありますよ。
ーーどういうことでしょうか?
(二本松先生)では例を一つ挙げてみましょう。私たちが刊行した『水窪のむかしばなし』という書籍に「上村の蛇婿入り」という話があります。若い娘のもとに正体不明の美しい男が夜毎に通ってくる。やがて娘は妊娠する。男の正体を突き止めるため男の衣の裾に糸を通した針を刺しておく。糸をたどってゆくと男の正体はなんと蛇だった」という話です。この話の元ネタは『古事記』にあり、三輪の大物主の神(蛇身)と活玉依姫の神婚の神話です。それが「むかしむかし、あるところに」となって昔話になりました。ところが、水窪では、蛇が通ったという娘の家系も蛇が沈んでいったという池も「そこだよ」と特定して伝わっています。こうなると分類は伝説です。神話だとか伝説だとか昔話だとか、そんな線引きはけっこう曖昧なんですよ。

▲『水窪のむかしばなし』上田沙来・内田ゆうき・野津彩綾・二本松康宏・福島愛生・山本理紗子.三弥井書店.2015

どんな意図で物語が生まれたか。背景は今も足元に残されている
ーー同じ物語でもジャンルが違うと読み取れる事も変わってきますか?
(二本松先生)昔話というと、とかく何かの教訓や説教みたいなことが付いてきますが、そんなのは実は後付けですよ。もとからあったのはせいぜい「正直」と「親切」くらいなものです。昔話から何かを学ぼうとか、教訓を読み解こうなんて言っていると昔話の本質を見失ってしまいます。
ーーなるほど。では、先生が考える昔話の本質って何ですか?
(二本松先生)昔話の本質はたった一つ、「人の世の祝福」です。だから昔話は「めでたしめでたし」で終わるのです。いつかきっと幸せがやってくる。そう信じて、昔話は語り継がれるのです。
伝説の本質は「いまを生きる」ことです。いま、自分たちが暮らしている土地はどのようにして成り立ったのか?あの岩はなぜあそこにあるのか?あの山はなぜてっぺんが割れているのか?あの池はどうして……。いま自分たちが暮らす社会のはじまりを知りたい、伝えたいという思いが伝説を語り継ぎます。
例えば、浜松には「遠州大念仏」という郷土芸能があります。その由来は静大浜松キャンパスの近くの犀が崖(さいががけ)にあります。三方ヶ原の合戦に敗れた徳川家康が浜松城に逃げ込む。追撃してくる武田勢に対して、家康は犀が崖に白い布を掛け渡して橋に偽装する。武田勢は白い布を雪がかかった橋だと勘違いして次々と崖下に転落する。崖に落ちて亡くなった武田の兵たちの亡霊を慰めるために遠州大念仏が始まったと伝えられています。
しかし、これはあくまでも伝説です。ぜったいに歴史的事実ではありません。だいたい布の橋なんて一人が乗ったらそれだけで落ちますよ。それに気付かず次から次へと崖下に落ちてゆく武田軍なんて(笑)。そんな画期的な勝ち方をしたら家康は自慢げにあちこちに手紙を送ったりしますよ。でも残念ながらそういう記録を私は見たことがありません。

しかし、だから布橋伝説は歴史的事実ではない!!と一蹴してしまうのではありません。むしろ、そういう伝説がなぜ生成したのか?私の興味はそこにあります。それを風景のなかに探り、伝説の基層を読み解くのです。
第一に「犀が崖」という地名です。犀が崖の「犀」は「境」という意味です。この世とあの世の境にある「賽の河原」の「賽」も同じですね。境に祀られる神様は「塞ノ神」、サイノカミともサエノカミとも言います。つまり「犀が崖」はこの世とあの世の境なのです。第二に犀が崖は館山寺街道と姫街道の分岐点=辻にあります。辻も異界との境界と考えられました。第三には犀が崖が浜松城の北西にあたるという点。北西=戌亥は霊魂が去来する方位として畏れられていました。
また、「布橋」にも意味があります。富山の立山修験(芦峅寺)では白い布の橋を渡ることで疑似的な死と再生を体験する「布橋灌頂」という儀式があります。岐阜の白山修験(石徹白の白山中居権現)などにも布橋がありました。ひょっとしたら浜松の犀が崖でもかつて布橋灌頂のような疑死再生の儀礼が行われていたのかもしれません。そういう風景の中で犀が崖の布橋伝説が生成し、亡霊鎮魂の大念仏の由来譚として語り継がれてきたのです。
使われるかもしれない「いつか」のためにアーカイブする
ーー物語から読み取れる土地との関係性は奥深いですね。ただ、こうした背景を探るのは大変な調査になりそうです。
(二本松先生)そうですね。例えていうならば、星の光を集めて太陽に挑むような作業です。着想から論文の完成までにはだいたい五年くらいかかります。長いのにると10年以上も調査を繰り返してようやく論文にできたものもあります。私が探しているのは「史実を超えた真実」です。
しかし、こんな研究は大学生には勧められません。学生はもっと短い期間で一定の成果を出さなければなりませんからね。まして四年生からの就活に備えるには、3年生の1年間が研究の正念場です。そこで、私のゼミでは浜松市の最奥部の水窪というところで昔話の採録調査に取り組んでいます。お年寄りたちに語っていただいた昔話や伝説を、語りのまま、方言のままに録音・記録し、解説も付けて書籍として出版しています。昨年は『水窪のむかしばなし』という書籍を出版しました。私とゼミの学生たちとの共著です。一般の書店でもAmazon.comでも買えます。今年も次の書籍(『みさくぼの民話』)が刊行される予定です。
語りのまま、方言のままに記録すること。学術的な解説を添えること。それを一般向けの書籍として刊行すること。そうすることで、私たちの書籍はアナログ・アーカイブとなります。「学問をもって世に問う」「学術をもって社会に貢献する」それが大学生の本質ではないでしょうか(了)
[取材・文/田中楓]


▶︎もっと深く掘り下げたい人へ、二本松先生からのオススメの本
・半村良『戸隠隠伝説』.講談社文庫.1980.
▷このお話をもっと深く学びたい人へこの授業!
・「文学」(静岡文化芸術大学文化政策学部専門科目/二本松康宏先生)
・半村良『戸隠隠伝説』.講談社文庫.1980.
▷このお話をもっと深く学びたい人へこの授業!
・「文学」(静岡文化芸術大学文化政策学部専門科目/二本松康宏先生)
▼このインタビューが掲載されている、静岡時代最新号!▼
静岡県のすべての大学で配布中!(ほか、高校で配布・設置)
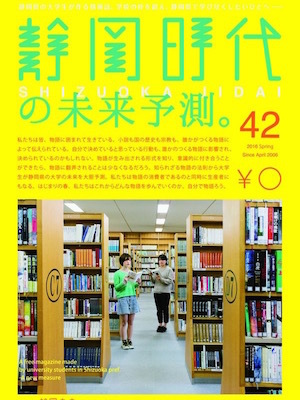
▷▷シリーズ第3回「音楽と文学は言語から生まれた二人姉妹?」は、5/24(火)更新します!
新しい音楽の創り方〜静岡時代24号『静岡時代の、音楽論』より
今開かれる、静岡パンドラの箱!〜静岡時代12号『静岡魔界探訪』より
静岡時代を残す人【静岡県立中央図書館】〜静岡時代創刊10年記念号「静岡時代ベスト版」
禅問答のように難解な物語の紡ぎ方〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」より
文学が先か?音楽が先か?「音」から育てる物語〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」〜
なぜ人は物語るのか?〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」より
今開かれる、静岡パンドラの箱!〜静岡時代12号『静岡魔界探訪』より
静岡時代を残す人【静岡県立中央図書館】〜静岡時代創刊10年記念号「静岡時代ベスト版」
禅問答のように難解な物語の紡ぎ方〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」より
文学が先か?音楽が先か?「音」から育てる物語〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」〜
なぜ人は物語るのか?〜静岡時代42号「静岡時代の未来予測」より
Updated:2016年05月17日 特集


















