キャンパス情報
せんせいの引き出し〜静岡大学理学部地球科学科:石橋秀巳先生
■静岡県内の大学の先生によるリレーコラム、「せんせいの引き出し」
表面6000℃以上、熔岩内部は1000℃以上、そんな熔岩を地質調査用の熔岩ハンマーを使ってすくい取ることを地球科学の研究者の間では「熔岩すくい」と呼ばれているらしい。今回は、主にマグマ・火山の研究をする静岡大学理学部地球科学科の石橋秀巳先生のコラムを紹介します。「地球科学の研究をしていると、地球のダイナミックな活動の現場に遭遇することがしばしばある」、その中でも石橋先生が最も印象深いと語る「熔岩すくい」を描写と石橋先生の茶目っ気たっぷりでお送りします。地球科学ってどんな学問?そんな方は必読!
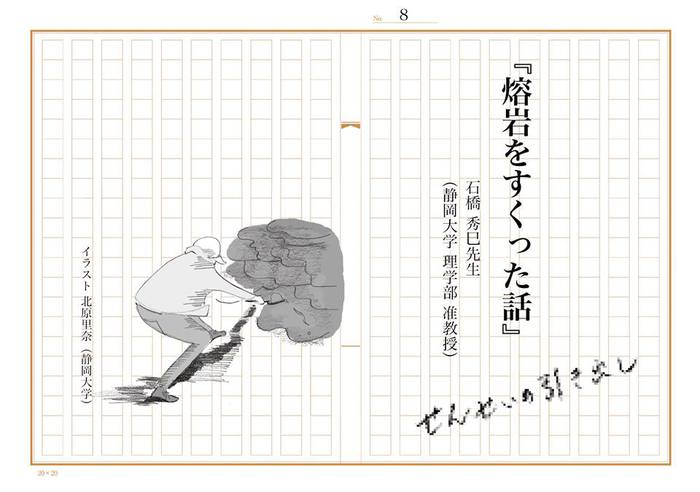
僕の専門分野は地球科学で、特にマグマ・火山の研究をしている。職業柄、火山に足を運ぶことも少なくないのだが、ここでは最も印象深かった「熔岩すくい」の思い出について語りたいと思う。舞台は米国ハワイ島である。
ハワイ島は、現在もキラウエア火山が活発な活動を続けている火山島であり、マグマ・火山研究者にとっての聖地といえる。ハワイ島が聖地たる所以として、ここでの研究が火山学・マグマ科学の発展に大きく貢献してきたことがあげられるが、もうひとつ大きな理由がある。この火山は穏やかに熔岩流を流す性質(ハワイ式噴火とよばれる)のため、他の火山では考えられない程の至近距離まで熔岩流に近づくことが可能な、世界でも稀な火山なのだ。そして、若いマグマ研究者が一度はやってみたいと思う「熔岩すくい」もここでできる。あこがれの「熔岩すくい」だが、ハワイ大学に短期留学していた数年前、ついに体験する機会を得た。
その頃は、前後数年間でも最も活動が低調な時期であり、熔岩の流れている領域は広大な熔岩原野の奥深くに限られていた。このため、車道の終点から数km以上、植生もほとんどない熔岩原野を歩いて、お目当ての熔岩流を探すこととなった(注:専門家の案内なしだと危険です)。目の前に広がるのは、見渡す限りの真っ黒な熔岩原野と青い空である。熔岩より立ち上がる噴気が遠くに見えるので、これを目印に歩き始めた。ふと足元に目を向けると、パホエホエとよばれるタイプの熔岩が「先刻まで流れていました」と言わんばかりの形を保って固まっている。その地形の生々しさを目の当たりにして気持ちが昂る。ところが、歩けど歩けどパホエホエ熔岩で、これが2時間以上も続くとさすがに飽きる。そして徒歩3時間、ようやく噴気の立ち上る目的地に辿り着いた。そこでは、ガラスの小欠片がピンピン音を立てて跳ねている不思議な光景を見られたが、残念ながら熱い熔岩流は見つからなかった。
ガッカリして帰り道を歩いていると、空気が突然変わった。真夏の球場のような、熱く息苦しい空気。そしてその先には、赤熱した熔岩がゆっくりと流れていた。表面でも600℃以上、熔岩内部は1000℃以上だろう。驚きと喜びが疲労感を打ち消す。その流れる様をしばらく観察していたが、やがて「熔岩すくい」を実行することとなった。地質調査用の鉄製ハンマーを使って熔岩をすくい取ることを、研究者の間で「熔岩すくい」とよぶ。液体状の熔岩にハンマーを突き刺し、ゆっくり引き上げると熔岩をすくうことができる。しかし、引き上げが速すぎると熔岩は流れ落ちてしまう。熔岩の放射熱のため、至近距離での作業はなかなかたいへんである。それでも失敗にめげず、放射熱を我慢して何度かトライし、こぶし大の熔岩をすくうことにようやく成功した。ひとつの夢を実現した瞬間であった。
地球科学の研究をしていると、地球のダイナミックな活動の現場に遭遇することがしばしばある。これは他では体験できない、この分野の大きな魅力のひとつだと思う。ところで、「熔岩すくい」で採取した熔岩だが、今も僕の机の引き出しの中に大事にしまってある。「引き出し」の話である〈了〉
表面6000℃以上、熔岩内部は1000℃以上、そんな熔岩を地質調査用の熔岩ハンマーを使ってすくい取ることを地球科学の研究者の間では「熔岩すくい」と呼ばれているらしい。今回は、主にマグマ・火山の研究をする静岡大学理学部地球科学科の石橋秀巳先生のコラムを紹介します。「地球科学の研究をしていると、地球のダイナミックな活動の現場に遭遇することがしばしばある」、その中でも石橋先生が最も印象深いと語る「熔岩すくい」を描写と石橋先生の茶目っ気たっぷりでお送りします。地球科学ってどんな学問?そんな方は必読!
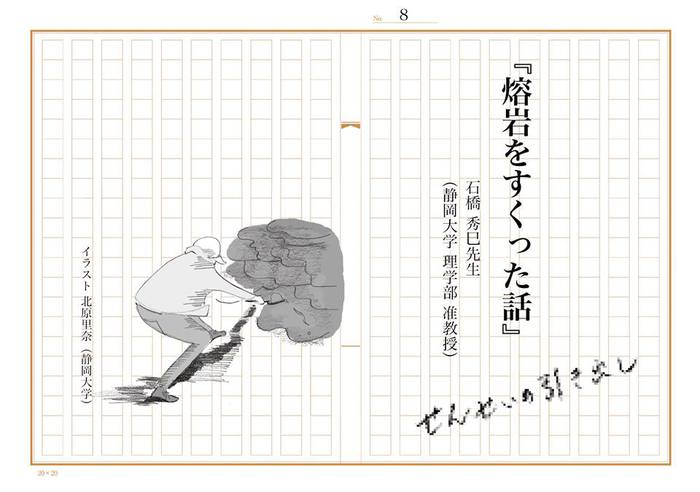
僕の専門分野は地球科学で、特にマグマ・火山の研究をしている。職業柄、火山に足を運ぶことも少なくないのだが、ここでは最も印象深かった「熔岩すくい」の思い出について語りたいと思う。舞台は米国ハワイ島である。
ハワイ島は、現在もキラウエア火山が活発な活動を続けている火山島であり、マグマ・火山研究者にとっての聖地といえる。ハワイ島が聖地たる所以として、ここでの研究が火山学・マグマ科学の発展に大きく貢献してきたことがあげられるが、もうひとつ大きな理由がある。この火山は穏やかに熔岩流を流す性質(ハワイ式噴火とよばれる)のため、他の火山では考えられない程の至近距離まで熔岩流に近づくことが可能な、世界でも稀な火山なのだ。そして、若いマグマ研究者が一度はやってみたいと思う「熔岩すくい」もここでできる。あこがれの「熔岩すくい」だが、ハワイ大学に短期留学していた数年前、ついに体験する機会を得た。
その頃は、前後数年間でも最も活動が低調な時期であり、熔岩の流れている領域は広大な熔岩原野の奥深くに限られていた。このため、車道の終点から数km以上、植生もほとんどない熔岩原野を歩いて、お目当ての熔岩流を探すこととなった(注:専門家の案内なしだと危険です)。目の前に広がるのは、見渡す限りの真っ黒な熔岩原野と青い空である。熔岩より立ち上がる噴気が遠くに見えるので、これを目印に歩き始めた。ふと足元に目を向けると、パホエホエとよばれるタイプの熔岩が「先刻まで流れていました」と言わんばかりの形を保って固まっている。その地形の生々しさを目の当たりにして気持ちが昂る。ところが、歩けど歩けどパホエホエ熔岩で、これが2時間以上も続くとさすがに飽きる。そして徒歩3時間、ようやく噴気の立ち上る目的地に辿り着いた。そこでは、ガラスの小欠片がピンピン音を立てて跳ねている不思議な光景を見られたが、残念ながら熱い熔岩流は見つからなかった。
ガッカリして帰り道を歩いていると、空気が突然変わった。真夏の球場のような、熱く息苦しい空気。そしてその先には、赤熱した熔岩がゆっくりと流れていた。表面でも600℃以上、熔岩内部は1000℃以上だろう。驚きと喜びが疲労感を打ち消す。その流れる様をしばらく観察していたが、やがて「熔岩すくい」を実行することとなった。地質調査用の鉄製ハンマーを使って熔岩をすくい取ることを、研究者の間で「熔岩すくい」とよぶ。液体状の熔岩にハンマーを突き刺し、ゆっくり引き上げると熔岩をすくうことができる。しかし、引き上げが速すぎると熔岩は流れ落ちてしまう。熔岩の放射熱のため、至近距離での作業はなかなかたいへんである。それでも失敗にめげず、放射熱を我慢して何度かトライし、こぶし大の熔岩をすくうことにようやく成功した。ひとつの夢を実現した瞬間であった。
地球科学の研究をしていると、地球のダイナミックな活動の現場に遭遇することがしばしばある。これは他では体験できない、この分野の大きな魅力のひとつだと思う。ところで、「熔岩すくい」で採取した熔岩だが、今も僕の机の引き出しの中に大事にしまってある。「引き出し」の話である〈了〉
◉石橋 秀巳(いしばし ひでみ)先生
静岡大学理学部地球科学科・准教授。徳島県生まれ。
九州大学理学部卒、同大学大学院理学府地球惑星科学専攻博士後期課程修了。博士(理学)。専門分野は地球科学(岩石学・火山学・マグマ科学)。主にマグマの物性や形成過程・火山噴火プロセス等について研究している。
■静岡大学理学部Webサイト→ http://www.sci.shizuoka.ac.jp
静岡大学理学部地球科学科・准教授。徳島県生まれ。
九州大学理学部卒、同大学大学院理学府地球惑星科学専攻博士後期課程修了。博士(理学)。専門分野は地球科学(岩石学・火山学・マグマ科学)。主にマグマの物性や形成過程・火山噴火プロセス等について研究している。
■静岡大学理学部Webサイト→ http://www.sci.shizuoka.ac.jp
【2016年】静岡県内大学の夏季オープンキャンパス情報!
「長男は結婚相手に不向き?」恋愛相談by学術〜静岡文化芸術大学 森山一郎先生
せんせいの引き出し〜静岡県立大学薬学部実践薬学分野:並木徳之先生
せんせいの引き出し〜静岡大学人文社会科学部 平野雅彦先生〜
せんせいの引き出し〜浜松学院大学現代コミュニケーション学部 土倉英志先生〜
SNAP from campus〜浜松ホトニクス株式会社〜
「長男は結婚相手に不向き?」恋愛相談by学術〜静岡文化芸術大学 森山一郎先生
せんせいの引き出し〜静岡県立大学薬学部実践薬学分野:並木徳之先生
せんせいの引き出し〜静岡大学人文社会科学部 平野雅彦先生〜
せんせいの引き出し〜浜松学院大学現代コミュニケーション学部 土倉英志先生〜
SNAP from campus〜浜松ホトニクス株式会社〜
Updated:2016年07月21日 キャンパス情報

















