静岡の街から
ハタチの社会見学〜株式会社 佐藤園〜
ハタチの社会見学(8)
■株式会社 佐藤園にやってきた!

【徳川家康公への献上茶 本山地区のお茶づくり】
静岡茶発祥の地として八百年の歴史をもつ本山地区でお茶を作り続ける株 式会社佐藤園。この地区は標高が高い山間に位置し、朝夕の寒暖差が大きく、更には美しい川が流れ、霧がかかるため、茶栽培に最適な環境が整っています。厳しい環境で育つお茶は香り高く、 飲むと「ほっ」と一息つけます。
そんなお茶を生み出す佐藤園の始まりは一軒の茶農家でした。創業から、栽培・ 収穫・製茶・仕上げ・販売までの全てを自社で手掛けています。今回はほんのりお茶の香りが漂う工場で、収穫から仕上げの工程に密着しました。







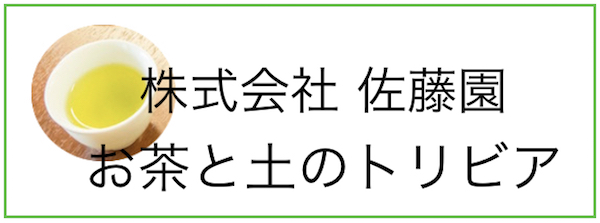

佐藤園のお茶は、800 件を越える全国の生産農家がお茶の品質を競う全 国茶品評会で10 年連続入賞しています。高品質なお茶の秘訣は、お茶作りで使用される土に隠されています。お茶の葉は土から養分を吸って成長します。本山地区は綺麗な川・水捌けの良さという好条件が揃っており、良質な土に恵まれています。また、滋養豊かな土で作ったこだわりの肥料も、 全国でも誇れるお茶作りの秘訣になっています。







800年の歴史をもつ本山地区は、かつて日本国内有数の茶産地でした。しかし、国内需要が低下し、手頃な価格でお茶を購入できる今、お茶を専業とする農家がお茶だけで生計を立てるのは難しい時代と言えます。日本茶の歴史が終わろうとしているのです。農家の数の減少とともに、日本一であった茶産業の衰退化を何とかして阻止する必要があります。「日本一の茶産地である静岡を復活させたい」。その思いで、佐藤園とともに十年間お茶を作り続けてきました。
今年は新たな取り組みとして、抹茶をつくりはじめました。お菓子など抹茶を利用した加工品がありますよね? 国内外でそうした抹茶の需要が高まっているのです。本山の茶葉は他に比べて葉が柔らかく、色も濃く鮮やかなため、抹茶製造に適しています。今後は 本山茶をはじめとした静岡茶を海外に 向けても発信しようと考えています。
佐藤園は創業以来、「地域に必要とされる企業であること」という理念を持ち続けています。世の中が必要としている、「美味しい」お茶を届けたいんです。モノづくりは作り手の思いがはっきりと表れます。お茶づくりも一分一秒手抜きできません。50年先に、「本山のお茶ってすごいよね」と皆さんに思っていただける産地にすることが私の夢です。
■マルカブ佐藤製茶株式会社
森山 幸男さん
マルカブ佐藤製茶株式会社 常務取締役 製茶部部長。
日本茶インストラクター。お茶づくりに携わり続けて46年。農林大臣賞を受賞した時に娘さんが書いてくれた、「お父さんがお茶のオリ ンピックで金メダルをとりました。」という作文は今でも宝物。
住所 : 静岡県静岡市葵区大原 1057
HP:http://www.satoen.co.jp
◎お茶カフェ:9時 30 分〜 17 時営業 (火曜定休・季節により変更有)

10 年連続で全国茶品評会で好成績を残しているにも関わらず、現状に甘んじることなく常に挑戦し続ける佐藤園の姿に刺激を受けました。
一度は衰退しかけた静岡のお茶文化を佐藤園が中心となり、再び全国に静岡茶の素晴らしさを知ってもらえる日が来るのではないかと期待に胸が躍ります。ひとつの事を突きつめた森山さんの顔がとても輝いて見えました。最近は急須を使ってお茶を飲む機会が減ってしまいました。ほっと一息つきたい時は佐藤園が運営するお茶カフェで豊かな緑に囲まれながらお茶を飲むのもいいですね。
■株式会社 佐藤園にやってきた!
【徳川家康公への献上茶 本山地区のお茶づくり】
静岡茶発祥の地として八百年の歴史をもつ本山地区でお茶を作り続ける株 式会社佐藤園。この地区は標高が高い山間に位置し、朝夕の寒暖差が大きく、更には美しい川が流れ、霧がかかるため、茶栽培に最適な環境が整っています。厳しい環境で育つお茶は香り高く、 飲むと「ほっ」と一息つけます。
そんなお茶を生み出す佐藤園の始まりは一軒の茶農家でした。創業から、栽培・ 収穫・製茶・仕上げ・販売までの全てを自社で手掛けています。今回はほんのりお茶の香りが漂う工場で、収穫から仕上げの工程に密着しました。
[取材・執筆:加藤佑里子(静岡大学)]
[取材・撮影:寺島美夏(静岡大学) 山口奈那子(常葉大学)]
佐藤園の工場内へ!
▽
▽

まずは、工場近くにある自社管理茶園で茶葉(生葉)を収穫。
現在、およそ10種のお茶の葉を育てています。
現在、およそ10種のお茶の葉を育てています。
▽
▽

右の建物が荒茶工場で、左が仕上げ工場。
まずは収穫した生葉を蒸し、乾燥させ荒茶(原料茶)にしていきます。
まずは収穫した生葉を蒸し、乾燥させ荒茶(原料茶)にしていきます。
▽
▽
収穫した生葉の一時保管場所。
茶葉の色合いや香味などの鮮度を保つため、風や水蒸気をあてることで湿度を調節します。
また、急速冷却することで香りを維持します。
茶葉の色合いや香味などの鮮度を保つため、風や水蒸気をあてることで湿度を調節します。
また、急速冷却することで香りを維持します。
▽
▽

茶葉を蒸す前に、摘採時に交じった枝などをふるいにかけ取り除きます。
さらに、別の装置でPM2.5や花粉も吸い取ります。
さらに、別の装置でPM2.5や花粉も吸い取ります。
▽
▽

茶葉を攪拌させながら蒸気で蒸します。
茶葉の色を保たせながら青臭さを除去。装置は綿密に計算されたオーダーメイドです!
茶葉の色を保たせながら青臭さを除去。装置は綿密に計算されたオーダーメイドです!
▽
▽
蒸した茶葉を乾燥させます。
風量や回転数を5段階に分けて乾燥させることで、深みのあるお茶になります。
風量や回転数を5段階に分けて乾燥させることで、深みのあるお茶になります。
▽
▽
この機械で乾燥機を制御しています。
しかし、その日の茶葉や気候にあわせた微調整は、人の手で行われます。
しかし、その日の茶葉や気候にあわせた微調整は、人の手で行われます。
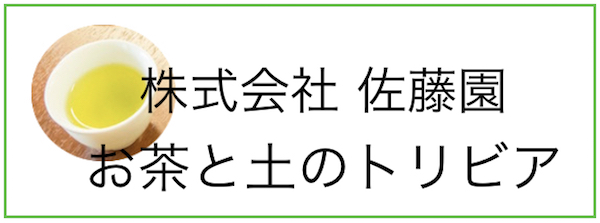

佐藤園のお茶は、800 件を越える全国の生産農家がお茶の品質を競う全 国茶品評会で10 年連続入賞しています。高品質なお茶の秘訣は、お茶作りで使用される土に隠されています。お茶の葉は土から養分を吸って成長します。本山地区は綺麗な川・水捌けの良さという好条件が揃っており、良質な土に恵まれています。また、滋養豊かな土で作ったこだわりの肥料も、 全国でも誇れるお茶作りの秘訣になっています。
▽
▽
錘で茶葉に圧力を加えながら揉んでいきます。
含有成分を浸出しやすくることで葉と茎で異なる水分量を均一化します。
含有成分を浸出しやすくることで葉と茎で異なる水分量を均一化します。
▽
▽
攪拌によりできた細かい茶葉のかたまりを動かしながらほぐしていきます。
手揉みでいう「より切り」にあたります。
手揉みでいう「より切り」にあたります。
▽
▽

含水率を8〜9%にし、茶葉をまっすぐな形に整えます。
その後、さらに乾燥させ、含水率を5〜6%にし、冷蔵庫で保管します。
その後、さらに乾燥させ、含水率を5〜6%にし、冷蔵庫で保管します。
▽
▽
仕上げ工場に移ります。
余分な粉や茎を取り除き、大小さまざまな状態の茶葉を分けて切断し、整えていきます。
余分な粉や茎を取り除き、大小さまざまな状態の茶葉を分けて切断し、整えていきます。
▽
▽
大・中・小に分けられた茶葉を別々に火入れ乾燥させます。
こうして乾燥の程度に偏りなく、香ばしい香味をつけられます。
こうして乾燥の程度に偏りなく、香ばしい香味をつけられます。
▽
▽
茶畑でうまれた美味しさを、そのまま閉じ込めて出荷します。
製茶工場に隣接するお茶カフェでは、芯蒸し茶や茶羊かんも味わえます。
ちなみに、茶羊かんの工場見学もできますよ!
製茶工場に隣接するお茶カフェでは、芯蒸し茶や茶羊かんも味わえます。
ちなみに、茶羊かんの工場見学もできますよ!
社会見学インタビュー:佐藤園 製茶部部長/森山幸男さん

本山からはじめる 静岡茶ブランディング
800年の歴史をもつ本山地区は、かつて日本国内有数の茶産地でした。しかし、国内需要が低下し、手頃な価格でお茶を購入できる今、お茶を専業とする農家がお茶だけで生計を立てるのは難しい時代と言えます。日本茶の歴史が終わろうとしているのです。農家の数の減少とともに、日本一であった茶産業の衰退化を何とかして阻止する必要があります。「日本一の茶産地である静岡を復活させたい」。その思いで、佐藤園とともに十年間お茶を作り続けてきました。
今年は新たな取り組みとして、抹茶をつくりはじめました。お菓子など抹茶を利用した加工品がありますよね? 国内外でそうした抹茶の需要が高まっているのです。本山の茶葉は他に比べて葉が柔らかく、色も濃く鮮やかなため、抹茶製造に適しています。今後は 本山茶をはじめとした静岡茶を海外に 向けても発信しようと考えています。
佐藤園は創業以来、「地域に必要とされる企業であること」という理念を持ち続けています。世の中が必要としている、「美味しい」お茶を届けたいんです。モノづくりは作り手の思いがはっきりと表れます。お茶づくりも一分一秒手抜きできません。50年先に、「本山のお茶ってすごいよね」と皆さんに思っていただける産地にすることが私の夢です。
■マルカブ佐藤製茶株式会社
森山 幸男さん
マルカブ佐藤製茶株式会社 常務取締役 製茶部部長。
日本茶インストラクター。お茶づくりに携わり続けて46年。農林大臣賞を受賞した時に娘さんが書いてくれた、「お父さんがお茶のオリ ンピックで金メダルをとりました。」という作文は今でも宝物。
住所 : 静岡県静岡市葵区大原 1057
HP:http://www.satoen.co.jp
◎お茶カフェ:9時 30 分〜 17 時営業 (火曜定休・季節により変更有)
取材後記:加藤佑里子(静岡大学)

10 年連続で全国茶品評会で好成績を残しているにも関わらず、現状に甘んじることなく常に挑戦し続ける佐藤園の姿に刺激を受けました。
一度は衰退しかけた静岡のお茶文化を佐藤園が中心となり、再び全国に静岡茶の素晴らしさを知ってもらえる日が来るのではないかと期待に胸が躍ります。ひとつの事を突きつめた森山さんの顔がとても輝いて見えました。最近は急須を使ってお茶を飲む機会が減ってしまいました。ほっと一息つきたい時は佐藤園が運営するお茶カフェで豊かな緑に囲まれながらお茶を飲むのもいいですね。
もう一度歩きたくなる、「エッシャーの世界」〜静岡市美術館〜
働く私の静岡時代〜株式会社 サンロフト〜
JR三島駅〜日本大学三島キャンパス〜極私的、古地図研究会
働く私の静岡時代〜株式会社江﨑新聞店〜
働く私の静岡時代〜まちと人をつなぐ情報流通企業 株式会社しずおかオンライン〜
働く私の静岡時代〜まちと人をつなぐ情報流通企業 株式会社しずおかオンライン〜
働く私の静岡時代〜株式会社 サンロフト〜
JR三島駅〜日本大学三島キャンパス〜極私的、古地図研究会
働く私の静岡時代〜株式会社江﨑新聞店〜
働く私の静岡時代〜まちと人をつなぐ情報流通企業 株式会社しずおかオンライン〜
働く私の静岡時代〜まちと人をつなぐ情報流通企業 株式会社しずおかオンライン〜
Updated:2016年01月06日 静岡の街から


















