静岡の街から
ハタチの社会見学〜株式会社 大村屋酒造場〜
ハタチの社会見学(4)
■株式会社 大村屋酒造場にやってきた!
〜歴史に恵まれた土地で、歴史深い日本酒を伝える〜

もともと静岡県は良質な水に恵まれ、日本酒をつくるには最適の土地。そのなかでも特に大井川流域の水は、水量が豊富でやわらかな水なのだそう。創業1832年の大村屋酒造場は、その大井川の伏流水を使って、11月〜4月の間、酒造りをしています。看板商品は純米大吟醸「おんな泣かせ」と純米「若竹 鬼ころし」。これらは30年ほど前から海外輸出されるようになり、今では生産量の3分の1が計16カ国で親しまれています。今回はそんな大村屋酒造場の日本酒が静岡だけではなく、世界中で愛される理由に迫ります!
[取材・撮影・執筆:小泉夏葉(静岡大学3年)]
[取材・撮影:小池麻友(静岡県立大学4年)]
■『日本酒を、これからの日本に残していくために!』
◉株式会社 大村屋酒造場
杜氏 日比野哲さん

人口減少に伴い、日本酒を飲む人が減っています。そうした背景もあり、私たちは海外展開も行っています。実は世界的にみるとお米から造られるお酒は、海外の安価な原料で造られるものが多いです。その中で価格の高い日本酒を広めるためには、良いものを造っていかねばならないのです。良質なお酒を造るために最もこだわっている工程が「洗い」。酒造りは米を割らないためや、道具に臭いや雑菌がつかないために、洗う作業が多いです。「洗いにはじまり、洗いにおわる」と言うように、「洗い」がしっかりしていてこそ、素材が活きてきます。また、酒造りは朝四時から夜中まで行われるので、人の輪が肝心。人が変わるとお酒の味も変わるほどです。
最近では日本酒の魅力を知ってもらうために「島田の食材と地酒を楽しむ会」など日本酒と接してもらう機会を設けています。大学生にも日本酒の正しい情報とおいしさを知ってもらいたいので、試飲会を開けたらなあと思っています。日本酒は飲み過ぎは禁物ですが、人との付き合いがしやすくなるし、何よりおいしい。私たちはそんなおいしい日本酒を大井川の伏流水、静岡酵母、そして静岡県産のお米を使って造っています。この土地があってこその「地酒」。これからも地元の人に愛される地酒をつくっていきたいですね。

(1)社会見学スタート!

▲お酒の原料であるお米の保管場所から見学させていただきました。保管しているお米は6割が静岡県産です。酒米の王様「山田錦」や静岡県が開発した「誉富士」がありました。

(2)精米

▲精米機でお米を磨きます。酒米は普段食べるお米よりも大粒なのが特徴。中央にデンプンが少なく、白い不透明な部分(心白)があります。
(3)糠の分類

▲精米で出た糠を赤糠、中糠、白糠に分類します。糠は、発酵させて茶畑の肥料にしたり、米菓の原料にしたりと無駄がありません。
(4)美味しさの鍵

▲お酒といっても、8割以上が水。大村屋酒造場では大井川の伏流水を井戸からひいています。この水を、竹炭でろ過し、仕込み水で使います。
(5)蒸し

▲大釜でお米を50分程度蒸していきます。樹脂製の疑似米を敷いた状態で蒸すことで、べたつきを防ぎ、さらっと蒸すことができます。
(6)もとつくり

▲水、蒸米、米こうじ、酵母をいれて発酵させると「酒母(または酛)」が完成。静岡で発見された静岡酵母のみを使用しています。
(7)発酵

▲手作業で全体にこうじエキスを行き渡らせます。

▲ぷくぷくとしているのは酵母がはたらき発酵している証拠。バナナのような香りがしました。
(8)三段仕込み

▲酒母やお米などを3回に分けて仕込む「3段仕込み」。室町時代から続く伝統の技です。発酵が進み、炭酸ガスが充満しているので顔をいれると気を失ってしまうのだそう!
(9)種こうじ=もやし

▲蒸米に3日間かけてこうじ菌を生やし、乾かします。種こうじを「もやし」と呼ぶそうで、漫画「もやしもん」の由来も実はここから。
(10)醪(もろみ)

▲3段仕込みした醪中ではこうじによる糠化、酵母による発酵が行われます。20〜30日間ほどかけてじっくり発酵させます。人がすっぽり入ってしまうくらい大きなタンクです。
(11)温度管理

▲タンク内は発酵時に発せられる熱で温度がどんどん上昇。そのため、中にこの管を入れ冷水を循環させて温度を管理します。
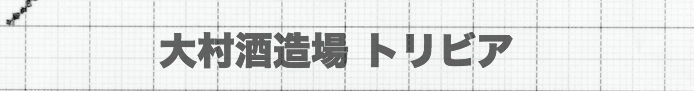

酒屋や酒蔵の屋根にぶら下がっているクス玉のようなものを皆さんも一度は見かけたことがあるのではないでしょうか。みなさんはこれが何か分かりますか?
実はこれ、酒林 ( あるい は杉玉 ) と呼ばれるもので、丸みを帯びているのは神様を表しており、青々としたものは「新しいお酒が出来たよ」という印なのだそうです。また、吊るしたては綺麗な緑色なのですが、月日が経つにつれて茶色く枯れていきます。これは新酒の熟成度を表す一つの目印になっています。
(12)圧搾

▲発酵が終わった醪がタンクから送られ板の並んだしぼり機で搾られます。板と板の間からは甘酒の原料である、酒粕がとれます。
(13)原酒

▲酒粕が搾り取られたあとの原酒が集められています。中を覗くと色は透き通っており、とてもフルーティーな香りが漂っていました。
(14)完成!

▲出来上がったお酒は瓶に注がれて完成。大村屋酒造場の瓶はラベルの種類も豊富です!細部までこだわりぬかれた日本酒が多くの人々のもとへ届けられます。

■見学を終えて……

酒母がぶくぶくと発酵している工程では「生き物みたい!」と思わず声をあげてしまいました。酒米は粒の周りが磨かれ、4〜7割しかお酒にならないと聞いたときは 「もったいない!」と思いましたが、そうすることで麹菌や 酵母が活発に働き、良いお酒ができること、さらには除かれた糠も余すことなく使って いることを知り、職人魂を感じました。また、同じ温度 45 度のお酒でも、50 度まで温めてから45度にするのと、そのまま45度に温めたものでは味わいが違うらしいのです。日本酒はなんて奥深いんだ!ハタチになったら、両親と一緒に日本酒を楽しみたいです。[取材・文/小泉夏葉]
■株式会社 大村屋酒造場にやってきた!
〜歴史に恵まれた土地で、歴史深い日本酒を伝える〜

もともと静岡県は良質な水に恵まれ、日本酒をつくるには最適の土地。そのなかでも特に大井川流域の水は、水量が豊富でやわらかな水なのだそう。創業1832年の大村屋酒造場は、その大井川の伏流水を使って、11月〜4月の間、酒造りをしています。看板商品は純米大吟醸「おんな泣かせ」と純米「若竹 鬼ころし」。これらは30年ほど前から海外輸出されるようになり、今では生産量の3分の1が計16カ国で親しまれています。今回はそんな大村屋酒造場の日本酒が静岡だけではなく、世界中で愛される理由に迫ります!
[取材・撮影・執筆:小泉夏葉(静岡大学3年)]
[取材・撮影:小池麻友(静岡県立大学4年)]
■『日本酒を、これからの日本に残していくために!』
◉株式会社 大村屋酒造場
杜氏 日比野哲さん

人口減少に伴い、日本酒を飲む人が減っています。そうした背景もあり、私たちは海外展開も行っています。実は世界的にみるとお米から造られるお酒は、海外の安価な原料で造られるものが多いです。その中で価格の高い日本酒を広めるためには、良いものを造っていかねばならないのです。良質なお酒を造るために最もこだわっている工程が「洗い」。酒造りは米を割らないためや、道具に臭いや雑菌がつかないために、洗う作業が多いです。「洗いにはじまり、洗いにおわる」と言うように、「洗い」がしっかりしていてこそ、素材が活きてきます。また、酒造りは朝四時から夜中まで行われるので、人の輪が肝心。人が変わるとお酒の味も変わるほどです。
最近では日本酒の魅力を知ってもらうために「島田の食材と地酒を楽しむ会」など日本酒と接してもらう機会を設けています。大学生にも日本酒の正しい情報とおいしさを知ってもらいたいので、試飲会を開けたらなあと思っています。日本酒は飲み過ぎは禁物ですが、人との付き合いがしやすくなるし、何よりおいしい。私たちはそんなおいしい日本酒を大井川の伏流水、静岡酵母、そして静岡県産のお米を使って造っています。この土地があってこその「地酒」。これからも地元の人に愛される地酒をつくっていきたいですね。
日比野哲さん
株式会社 大村屋酒造場の杜氏。静岡大学農学部卒業。
学生時代は「日本酒友の会」をつくり、美味しいお酒を探求していたそうです。静岡大学と共同で日本酒「 静大育ち」を製造。島田、藤枝、焼津のお酒ははずれが無いのだとか !
住所:静岡県 島田市本通 1 丁目 1‒8
電話:0547‒ 36‒2444
株式会社 大村屋酒造場の杜氏。静岡大学農学部卒業。
学生時代は「日本酒友の会」をつくり、美味しいお酒を探求していたそうです。静岡大学と共同で日本酒「 静大育ち」を製造。島田、藤枝、焼津のお酒ははずれが無いのだとか !
住所:静岡県 島田市本通 1 丁目 1‒8
電話:0547‒ 36‒2444

(1)社会見学スタート!
▲お酒の原料であるお米の保管場所から見学させていただきました。保管しているお米は6割が静岡県産です。酒米の王様「山田錦」や静岡県が開発した「誉富士」がありました。

▽
▽
▽
(2)精米
▲精米機でお米を磨きます。酒米は普段食べるお米よりも大粒なのが特徴。中央にデンプンが少なく、白い不透明な部分(心白)があります。
▽
▽
▽
(3)糠の分類

▲精米で出た糠を赤糠、中糠、白糠に分類します。糠は、発酵させて茶畑の肥料にしたり、米菓の原料にしたりと無駄がありません。
▽
▽
▽
(4)美味しさの鍵
▲お酒といっても、8割以上が水。大村屋酒造場では大井川の伏流水を井戸からひいています。この水を、竹炭でろ過し、仕込み水で使います。
▽
▽
▽
(5)蒸し
▲大釜でお米を50分程度蒸していきます。樹脂製の疑似米を敷いた状態で蒸すことで、べたつきを防ぎ、さらっと蒸すことができます。
▽
▽
▽
(6)もとつくり

▲水、蒸米、米こうじ、酵母をいれて発酵させると「酒母(または酛)」が完成。静岡で発見された静岡酵母のみを使用しています。
▽
▽
▽
(7)発酵

▲手作業で全体にこうじエキスを行き渡らせます。

▲ぷくぷくとしているのは酵母がはたらき発酵している証拠。バナナのような香りがしました。
▽
▽
▽
(8)三段仕込み

▲酒母やお米などを3回に分けて仕込む「3段仕込み」。室町時代から続く伝統の技です。発酵が進み、炭酸ガスが充満しているので顔をいれると気を失ってしまうのだそう!
▽
▽
▽
(9)種こうじ=もやし
▲蒸米に3日間かけてこうじ菌を生やし、乾かします。種こうじを「もやし」と呼ぶそうで、漫画「もやしもん」の由来も実はここから。
▽
▽
▽
(10)醪(もろみ)

▲3段仕込みした醪中ではこうじによる糠化、酵母による発酵が行われます。20〜30日間ほどかけてじっくり発酵させます。人がすっぽり入ってしまうくらい大きなタンクです。
▽
▽
▽
(11)温度管理

▲タンク内は発酵時に発せられる熱で温度がどんどん上昇。そのため、中にこの管を入れ冷水を循環させて温度を管理します。
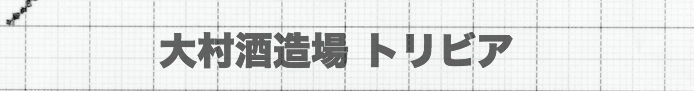

酒屋や酒蔵の屋根にぶら下がっているクス玉のようなものを皆さんも一度は見かけたことがあるのではないでしょうか。みなさんはこれが何か分かりますか?
実はこれ、酒林 ( あるい は杉玉 ) と呼ばれるもので、丸みを帯びているのは神様を表しており、青々としたものは「新しいお酒が出来たよ」という印なのだそうです。また、吊るしたては綺麗な緑色なのですが、月日が経つにつれて茶色く枯れていきます。これは新酒の熟成度を表す一つの目印になっています。
▽
▽
▽
(12)圧搾

▲発酵が終わった醪がタンクから送られ板の並んだしぼり機で搾られます。板と板の間からは甘酒の原料である、酒粕がとれます。
▽
▽
▽
(13)原酒

▲酒粕が搾り取られたあとの原酒が集められています。中を覗くと色は透き通っており、とてもフルーティーな香りが漂っていました。
▽
▽
▽
(14)完成!

▲出来上がったお酒は瓶に注がれて完成。大村屋酒造場の瓶はラベルの種類も豊富です!細部までこだわりぬかれた日本酒が多くの人々のもとへ届けられます。

■見学を終えて……

酒母がぶくぶくと発酵している工程では「生き物みたい!」と思わず声をあげてしまいました。酒米は粒の周りが磨かれ、4〜7割しかお酒にならないと聞いたときは 「もったいない!」と思いましたが、そうすることで麹菌や 酵母が活発に働き、良いお酒ができること、さらには除かれた糠も余すことなく使って いることを知り、職人魂を感じました。また、同じ温度 45 度のお酒でも、50 度まで温めてから45度にするのと、そのまま45度に温めたものでは味わいが違うらしいのです。日本酒はなんて奥深いんだ!ハタチになったら、両親と一緒に日本酒を楽しみたいです。[取材・文/小泉夏葉]
もう一度歩きたくなる、「エッシャーの世界」〜静岡市美術館〜
働く私の静岡時代〜株式会社 サンロフト〜
JR三島駅〜日本大学三島キャンパス〜極私的、古地図研究会
働く私の静岡時代〜株式会社江﨑新聞店〜
働く私の静岡時代〜まちと人をつなぐ情報流通企業 株式会社しずおかオンライン〜
働く私の静岡時代〜まちと人をつなぐ情報流通企業 株式会社しずおかオンライン〜
働く私の静岡時代〜株式会社 サンロフト〜
JR三島駅〜日本大学三島キャンパス〜極私的、古地図研究会
働く私の静岡時代〜株式会社江﨑新聞店〜
働く私の静岡時代〜まちと人をつなぐ情報流通企業 株式会社しずおかオンライン〜
働く私の静岡時代〜まちと人をつなぐ情報流通企業 株式会社しずおかオンライン〜
Updated:2015年08月13日 静岡の街から


















