静岡の街から
静大・太田隆之先生に聞く!今や全国に広まる”街バル現象”の実態とは?!
静岡市の中心街。いわゆる”おまち”と呼ばれる場所で、来月11月9日(土)に酒好き、美味しいもの好き垂涎のイベントが開かれます!その名は”静岡おまちバル(BAR)”。昨今、本イベントのような「街バル」というグルメイベントが全国に広まっています。関西生まれの「街バル」は、食べ歩き・飲み歩きと銘打ちながらその触手を伸ばしてきたのです。それは今や地域の自治体や商店街・飲食店街のまちおこし事業として成り立つまでに。
しかしそれは一体、なぜなんでしょか?そこまで人をひきつける理由とは?
今回、その疑問について御教授願ったのは、静岡大学で地域政策を研究している太田隆之先生。学生は、”静岡おまちバル”の学生実行委員ひとりである、同大学の高村理沙さん。彼女が、"静岡おまちバル"を代表して、「街バル」の実態を調査してきました!!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●太田隆之先生(写真左)
静岡大学人文社会科学部経済学科准教授。専門分野は地域政策で、地域における環境資源の自治的管理とそれを前提とした持続可能な社会実現のための地域政策を研究。お酒はかなり弱いが、飲むことは嫌いではないとのこと。年齢を重ねるごとに甘いお酒がダメになってきたのだとか。最近はもっぱらビールや焼酎をたしなむ。
●高村理沙さん(写真右)
静岡大学人文社会科学部経済学科3年。太田ゼミに所属。専攻は地域活性化。ゼミのテーマに商店街を扱っています。静岡おまちバルでは、実行員会のイベントステージ企画に携わっており、他の参加学生のまとめ役的存在。皆でわいわい集まって飲むお酒が好き、とのこと。
"静岡おまちバル"のHPはこちらから→ http://www.omachibar.com
また、当日ボランティアも募集中!
募集要項はこちら→https://docs.google.com/file/d/0B_U_B3xdOKj8OU5fbDhjZUlJa00/edit?usp=sharing
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
街バルの意義は、まちと自分自身の関係をみつめなおすきっかけにある。
——“静岡おまちバル”は今年で5回目を迎え、私はその実行委員としてイベントの企画・運営に携わっています。その中でわかったことのひとつが、いわゆる”街バル”が全国各地で多様化され、認知されているということ。しかも、ここ2、3年で爆発的に広まったことです。そんな短期間で、これほどまで地域の人たちに受け入れられる街バル。一体なにが、その要因となっているのでしょうか?
(太田先生)静岡県に限らず、「街バル」が全国に広まっているという背景にはひとつ、【中心都市の空洞化】があると思います。この現象は、ここ10年〜16年ほど言われ続けてきているんですね。その状況を改善しようと政策も行われてきましたが、厳しい状況が続いているところは少なからずあります。例えば静岡市では、旧清水市の中心市街地も活性化基本計画の対象になっています。そして2009年にその事業が実施されていますが、状況はなかなか変化していません。
そういう意味で、中心市街地・中心商店街空洞化という課題は今も解決していないという事実があり、多方面で「どうするか」と議論されている状況なのです。
その状況の中で、政府は市民目線の取り組みも求めています。街バルのキッカケ自体は、ヨーロッパの”バル”をモデルにしていますよね。それは比較的取り組みやすいもの、またそれなりの成果をあげている事例があることから、商店街・飲食店の方たちが自分たちで何かできることのひとつとして、街バルのようなイベントは適当なのではないでしょうか。
また商店街や飲食店街は偏在するものなので、同じような資源を持ち、そして同じ問題に直面していると考えられます。ですのである意味、商店同士、そして商店街の組合同士で取り組みやすい、「やっていこう」という意志でまとまりやすい面を持つイベントと言えるでしょう。反面、主体が多くなると組織化の難しさや中心市街地空洞の深刻さなど大変な部分もありますが、これらの背景によって、街バルは段々と全国各地へ広がっていったのではないでしょうか。

——お話を聞くと、ひとつのバルを運営するだけでも大規模になるな、という印象を受けたのですが、ある程度お金がないと出来ないものなのでしょうか?
(太田先生)うーん、考えどころですね。実際は、自治体によって補助金を出しているところもあります。しかし必ずしも、ある程度の大きなお金や補助金などがないと出来ないというわけではありません。本来、商店街・飲食店街として成り立っていたり、盛り上がっていたりするならば、お金はそんなに必要ありませんよね。よほど大規模な整備や派手なPRなどを行う時にはお金を使うこともありますが、多くは口コミで広まったりしながら、賑わっていくものですし。
——“広まる”といえば、街バルは北海道の函館ではじまり、大阪で話題になったのですが、土地柄というか、地域性の関係はあるのでしょうか?
(太田先生)そうですね。例えば地元密着型というか地元が好きな人が多い場所は、うまくイベントや取り組みの設計をすれば、人にウケるということはあると思います。例えば大阪は食文化も多様なので、潜在的な資源が多く、身の丈に合う取り組み方や街バルの本質をよく知っているのではないでしょうか?
——“街バル”は【中心市街地空洞化】の改善のための重要なポストなんですね。しかし、市街地活性化のためのイベントや取り組みは他にも多くありますが、その中で街バルの必要性はどの程度あるのでしょうか?
(太田先生)正直なところ、商店街や飲食店街が成り立っている状況があれば、本来は街バル自体なくても構わないとも思います。ただ、それは街バルイベントが不必要というわけではありません。なぜならさきほど言った、地域の良さや地域が直面している課題を知るためのひとつのきっかけになるからです。今回のイベントでいえば、お店を訪れるリピーターの確保のためにとか、飲食店の経営とも関わって行うという目的がある場合は、それは中心市街地空洞化の深刻さを示しているとも考えます。実際、街バルのモデルとなったヨーロッパでは、こういうイベントを開かなくても街には人が集まり、賑わいをみせていますよね。
その現状の中で街バルが必要であるのであれば、それは落ち込んでいる状況を打開したり、中心商店街側を奮起させることがポイントになります。お店に自助努力を促す側面や街中に人を呼び込むインセンティブという意味では必要な要素なんですね。街の活性化におけるひとつの導入の位置づけというのが街バルに対する僕自身の見方なので、参加する人たちはより良いお店やより美味しいものを食べにいく意識を持っていくのが良いのではないでしょうか。
店側も自慢の資源を積極的に示すことで、店と客の関係が構築されることはもちろん、地域の良い所を互いに確認し合うことができます。全体の取り組みを通じて、お互いに街のことを考えるきっかけにするのが大事。ですので、様々な地域でおこなわれてる街バルイベントの意義は、まちと自分自身の関係を見つめ直す機会といえますね。

——それでは、街バルによって静岡県に暮らす私たちとまちも、そういう関係性でつながっていくのでしょうか?
(太田先生)そうですね。今回行われる”静岡おまちバル”は静岡市内で開催されますが、まちの良さを再確認することを意図してやっている側面がありますよね。実は、静岡市の中心市街地は他の地域と比べると経済活動が良好な状況にあるんです。ですので、より中心市街地が活性化するために、地元の良さを店と客が互いに知り合い新しい発見をする、もしくは改めて地産地消の食材の美味しさやメニューの良さを感じる機会になります。
また、静岡市自体は広い商圏を持っています。静岡市の商圏に含まれると考えられる地域を含めて、商圏の維持に繋がる可能性があります。”静岡おまちバル”など、中心市街地の活性化によって、浜松や三島など静岡県内の他の地域でも刺激を与えうる機会になるのではないでしょうか。
僕の個人的な印象ですが、静岡県民の方たちは地元愛を強く持っている傾向にあると思うので、そこで暮らしている人たちも高い意志を持っていると考えています。ただ、経済状況の動向によって中心市街地の状況も変動すると、地元から離れていってしまう人たちがいるのも事実です。自分たちの暮らすまちの良さって、実はたいしたことないんじゃないか?と。
そういう状況が認められる中では、地元の良さを再認識するとともに、自分たちの周りのどこに課題があるのか、皆が共有する機会になってくれればいいですね。成功体験や成果を示すことが出来れば、次の活性化策や次のまちづくりに繋がっていきます。それは例えば、ひとつのイベントの先を考えるのではなくて、もっと広い視野で先をみていくことです。静岡県・市をどうしていくか、という話に、県政だけでなく県民も積極的に参加するような機会に繋がっていくことが望ましいですね。
"継続は力なり"。静岡のまちは、きっとレベルアップしていきます
——少し話は変わりますが、今回の”静岡おまちバル”では静岡県内の学生や20代の若い世代にも参加してほしいという想いがあります。何かと打ち上げやお酒を飲む機会が多くなる私たち世代と静岡おまちバルの相性が気になるのですが。
(太田先生)街バル自体「地元の商店街にこんな店がある」、「地元の食材や地酒が楽しめる」という紹介になるし、学生の参加を促すということでは魅力は十分にあると思います。ただ、例えば今回のイベントに参加するためのチケットの値段や、頼めるメニューの品数を考えると、若い世代にとっては参加する際の障壁になるかもしれません。価格に関しては、皆より上の世代の人たちにとってはたいしたことがない値段かもしれないし、それで美味しい物が食べられればOKという満足感は得られるかもしれません。しかし、20代前半の若い人たちにとってはどうかな?価格設定が参加のためのハードルになっていませんか?
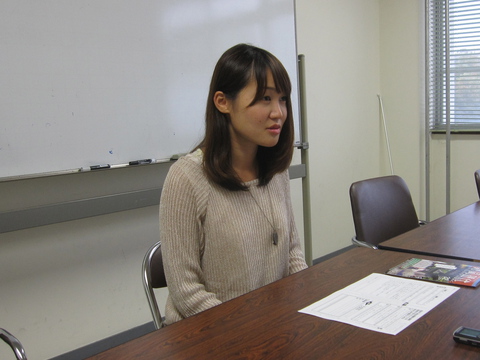
——正直「ちょっと高いかも」と感じる部分があります……。
(太田先生)学生や若い世代をターゲットにするためには、対「若い世代」のための手段を考えることも必要なのではないでしょうか。例えば、学生割など特別枠を設けて価格を下げたり、出されるメニューを増やしたりとかね。若者も静岡のお酒を飲んでみましょう、ということも前面に出してもいいかもしれません。飲食店や商店が、そして街を知ることへのイントロダクションのようにすれば、若い世代への掴みも変わってきます。ただ、若い世代の人たちにとっては、イベント自体に、訪れたことのない店やそこでの味を楽しめる魅力が十分に揃っているので、参加して新しい発見をするキッカケになると思います。あとは社会人の先輩や自分たちより上の世代の仲間といえる人に誘ってもらって連れて行ってもらうことも、参加しやすくなるひとつの手段ではないかな?
——なるほど。今後の”静岡おまちバル”を続けていく上では、各世代のニーズにそいながら企画・運営を考えていくのもひとつの手段ですね。では今後、静岡おまちバルによって、静岡のまちに何かしらの変化は起こるのでしょうか?
(太田先生)イベントの開催自体を主目的にするのではなく、これをキッカケにして静岡のまちの方向性を考えるということであれば変化の兆しは見られると思います。さしあたっては、こういうイベントを続けていくことが大事です。ただ注意したいのが、”イベントをやる”ということに重きを置いてしまうと、経済状況等に変化が起きたときにそれまでの活動の意味がなくなってしまうことです。変化というのは、例えばお店側には、「バルがあるときは盛り上がるけれどそれ以外の時は元に戻ってしまう、もしくはそれほど変化がない」という状況になる可能性があるということ。静岡のまちの活性化という、本来の意味や目的とは違ってきてしまうんですね。
ですので、店側にとっては常時新しいメニューの提供、良い物をよりよくしていくなどのイノベーションを促す機会であり、僕たち静岡県民は自然に街中に足を運ぶような状況を生み出していく。また、”静岡おまちバル”のイベントがスタートしてそれほど長い時間が経っているわけではないので、毎年開催する度に、何かしらの効果があることをお互いに認識することも大事ですね。
あとは、行政に頼らないことも重要です。先ほど触れましたが、例えば埼玉県のように9千万くらいの補助金を出している事例もありますが、僕はそれだとあまり意味がないと思っています。どうしても、補助金が出ればやる・出なけれなやらない、という状況が生まれる可能性が排除できないからです。だから、まず自分たちでできることをやっていく。それは背伸びしてできること以上のことを無理をしてでもやるということや、市民の政治参加につなげていくという別次元といえることを目指すという意味ではなく、イベントの開催側や参加する客側も楽しみながら、まちの良さやそこが抱えている課題を感じながら次の行動につなげていくのがいいと思います。

青葉通りのおでん横町や両替町など、飲み屋の多い静岡のおまち。去年の静岡おまちバルでは多くの人が飲み歩き、はしご酒を楽しみました。
自分の足で静岡のおまちを巡り、美味しいお酒や食べ物に出会える日。
——それでは最後に、太田先生の専門分野からみた、”静岡おまちバルの魅力”を教えてください。
(太田先生)そうですね。僕が面白いと思ったのは食べ歩きや飲み歩きなど、いわゆる「はしご酒」で人を動かし、回遊させる機会を作っている、かつ、参加店全部を回れるわけではなく自分でいくつか選択させるというのはとても興味深かったです。
——はい。静岡おまちバルでは、広場に屋台を出店するような他のグルメイベント等とは 違い、自分で足を運んでもらうという一番の目的があるんです。
(太田先生)それは、人を招いて動かすこと自体が難しくなっているという現状を考えたときに、その制度設計は良い意味でお店間の競争を促していることになるんです。例えば、七間町や鷹匠は続々と新しい店ができているっていう部分で競争があります。常に刺激的なものを中心街・商店街に提示しているんですね。
公共経済学では「足による投票」という議論があります。これは居住する地域について多くの選択肢がある中で地域政策の実施状況等から行先を1つ選択し、人々がそこに行くことがその地域の評価を示すという議論ですが、“静岡おまちバル“には参加者のお店の選択が参加店の評価につながるというところが面白い取り組み方だと思いました。お店側も客のニーズを意識して店自慢の逸品を出すということは、トータルでいえばそれだけ静岡に美味しい物があるというのを示すということに繋がりますよね。また、イベントの中で人とのコミュニケーションや付き合いが広がることも良いことです。
あとは、静岡おまちバル参加者は地元の人が多いですよね。インタビューのはじめに、地元愛の強い人が多く集まる場所はイベントの取り組み方によって成果があるという話をしたけれど、そういう意味では、”静岡おまちバル”は成功しているのではないでしょうか。地元の資源も一生懸命使っていますしね。まずは地に足をついた、本来のあるべきバルを追求しているのが、静岡おまちバルの魅力だと思います

●太田隆之先生
静岡大学人文社会科学部経済学科准教授。専門分野は地域政策で、地域における環境資源の自治的管理とそれを前提とした持続可能な社会実現のための地域政策を研究。お酒はかなり弱いが、飲むことは嫌いではないとのこと。年齢を重ねるごとに甘いお酒がダメになってきたのだとか。最近はもっぱらビールや焼酎をたしなむ。
●高村理沙さん
静岡大学人文社会科学部経済学科3年。太田ゼミに所属。専攻は地域活性化。ゼミのテーマに商店街を扱っています。静岡おまちバルでは、実行員会のイベントステージ企画に携わっており、他の参加学生のまとめ役的存在。皆でわいわい集まって飲むお酒が好き、とのこと。
しかしそれは一体、なぜなんでしょか?そこまで人をひきつける理由とは?
今回、その疑問について御教授願ったのは、静岡大学で地域政策を研究している太田隆之先生。学生は、”静岡おまちバル”の学生実行委員ひとりである、同大学の高村理沙さん。彼女が、"静岡おまちバル"を代表して、「街バル」の実態を調査してきました!!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

●太田隆之先生(写真左)
静岡大学人文社会科学部経済学科准教授。専門分野は地域政策で、地域における環境資源の自治的管理とそれを前提とした持続可能な社会実現のための地域政策を研究。お酒はかなり弱いが、飲むことは嫌いではないとのこと。年齢を重ねるごとに甘いお酒がダメになってきたのだとか。最近はもっぱらビールや焼酎をたしなむ。
●高村理沙さん(写真右)
静岡大学人文社会科学部経済学科3年。太田ゼミに所属。専攻は地域活性化。ゼミのテーマに商店街を扱っています。静岡おまちバルでは、実行員会のイベントステージ企画に携わっており、他の参加学生のまとめ役的存在。皆でわいわい集まって飲むお酒が好き、とのこと。
"静岡おまちバル"のHPはこちらから→ http://www.omachibar.com
また、当日ボランティアも募集中!
募集要項はこちら→https://docs.google.com/file/d/0B_U_B3xdOKj8OU5fbDhjZUlJa00/edit?usp=sharing
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
街バルの意義は、まちと自分自身の関係をみつめなおすきっかけにある。
——“静岡おまちバル”は今年で5回目を迎え、私はその実行委員としてイベントの企画・運営に携わっています。その中でわかったことのひとつが、いわゆる”街バル”が全国各地で多様化され、認知されているということ。しかも、ここ2、3年で爆発的に広まったことです。そんな短期間で、これほどまで地域の人たちに受け入れられる街バル。一体なにが、その要因となっているのでしょうか?
(太田先生)静岡県に限らず、「街バル」が全国に広まっているという背景にはひとつ、【中心都市の空洞化】があると思います。この現象は、ここ10年〜16年ほど言われ続けてきているんですね。その状況を改善しようと政策も行われてきましたが、厳しい状況が続いているところは少なからずあります。例えば静岡市では、旧清水市の中心市街地も活性化基本計画の対象になっています。そして2009年にその事業が実施されていますが、状況はなかなか変化していません。
そういう意味で、中心市街地・中心商店街空洞化という課題は今も解決していないという事実があり、多方面で「どうするか」と議論されている状況なのです。
その状況の中で、政府は市民目線の取り組みも求めています。街バルのキッカケ自体は、ヨーロッパの”バル”をモデルにしていますよね。それは比較的取り組みやすいもの、またそれなりの成果をあげている事例があることから、商店街・飲食店の方たちが自分たちで何かできることのひとつとして、街バルのようなイベントは適当なのではないでしょうか。
また商店街や飲食店街は偏在するものなので、同じような資源を持ち、そして同じ問題に直面していると考えられます。ですのである意味、商店同士、そして商店街の組合同士で取り組みやすい、「やっていこう」という意志でまとまりやすい面を持つイベントと言えるでしょう。反面、主体が多くなると組織化の難しさや中心市街地空洞の深刻さなど大変な部分もありますが、これらの背景によって、街バルは段々と全国各地へ広がっていったのではないでしょうか。

——お話を聞くと、ひとつのバルを運営するだけでも大規模になるな、という印象を受けたのですが、ある程度お金がないと出来ないものなのでしょうか?
(太田先生)うーん、考えどころですね。実際は、自治体によって補助金を出しているところもあります。しかし必ずしも、ある程度の大きなお金や補助金などがないと出来ないというわけではありません。本来、商店街・飲食店街として成り立っていたり、盛り上がっていたりするならば、お金はそんなに必要ありませんよね。よほど大規模な整備や派手なPRなどを行う時にはお金を使うこともありますが、多くは口コミで広まったりしながら、賑わっていくものですし。
——“広まる”といえば、街バルは北海道の函館ではじまり、大阪で話題になったのですが、土地柄というか、地域性の関係はあるのでしょうか?
(太田先生)そうですね。例えば地元密着型というか地元が好きな人が多い場所は、うまくイベントや取り組みの設計をすれば、人にウケるということはあると思います。例えば大阪は食文化も多様なので、潜在的な資源が多く、身の丈に合う取り組み方や街バルの本質をよく知っているのではないでしょうか?
——“街バル”は【中心市街地空洞化】の改善のための重要なポストなんですね。しかし、市街地活性化のためのイベントや取り組みは他にも多くありますが、その中で街バルの必要性はどの程度あるのでしょうか?
(太田先生)正直なところ、商店街や飲食店街が成り立っている状況があれば、本来は街バル自体なくても構わないとも思います。ただ、それは街バルイベントが不必要というわけではありません。なぜならさきほど言った、地域の良さや地域が直面している課題を知るためのひとつのきっかけになるからです。今回のイベントでいえば、お店を訪れるリピーターの確保のためにとか、飲食店の経営とも関わって行うという目的がある場合は、それは中心市街地空洞化の深刻さを示しているとも考えます。実際、街バルのモデルとなったヨーロッパでは、こういうイベントを開かなくても街には人が集まり、賑わいをみせていますよね。
その現状の中で街バルが必要であるのであれば、それは落ち込んでいる状況を打開したり、中心商店街側を奮起させることがポイントになります。お店に自助努力を促す側面や街中に人を呼び込むインセンティブという意味では必要な要素なんですね。街の活性化におけるひとつの導入の位置づけというのが街バルに対する僕自身の見方なので、参加する人たちはより良いお店やより美味しいものを食べにいく意識を持っていくのが良いのではないでしょうか。
店側も自慢の資源を積極的に示すことで、店と客の関係が構築されることはもちろん、地域の良い所を互いに確認し合うことができます。全体の取り組みを通じて、お互いに街のことを考えるきっかけにするのが大事。ですので、様々な地域でおこなわれてる街バルイベントの意義は、まちと自分自身の関係を見つめ直す機会といえますね。

——それでは、街バルによって静岡県に暮らす私たちとまちも、そういう関係性でつながっていくのでしょうか?
(太田先生)そうですね。今回行われる”静岡おまちバル”は静岡市内で開催されますが、まちの良さを再確認することを意図してやっている側面がありますよね。実は、静岡市の中心市街地は他の地域と比べると経済活動が良好な状況にあるんです。ですので、より中心市街地が活性化するために、地元の良さを店と客が互いに知り合い新しい発見をする、もしくは改めて地産地消の食材の美味しさやメニューの良さを感じる機会になります。
また、静岡市自体は広い商圏を持っています。静岡市の商圏に含まれると考えられる地域を含めて、商圏の維持に繋がる可能性があります。”静岡おまちバル”など、中心市街地の活性化によって、浜松や三島など静岡県内の他の地域でも刺激を与えうる機会になるのではないでしょうか。
僕の個人的な印象ですが、静岡県民の方たちは地元愛を強く持っている傾向にあると思うので、そこで暮らしている人たちも高い意志を持っていると考えています。ただ、経済状況の動向によって中心市街地の状況も変動すると、地元から離れていってしまう人たちがいるのも事実です。自分たちの暮らすまちの良さって、実はたいしたことないんじゃないか?と。
そういう状況が認められる中では、地元の良さを再認識するとともに、自分たちの周りのどこに課題があるのか、皆が共有する機会になってくれればいいですね。成功体験や成果を示すことが出来れば、次の活性化策や次のまちづくりに繋がっていきます。それは例えば、ひとつのイベントの先を考えるのではなくて、もっと広い視野で先をみていくことです。静岡県・市をどうしていくか、という話に、県政だけでなく県民も積極的に参加するような機会に繋がっていくことが望ましいですね。
"継続は力なり"。静岡のまちは、きっとレベルアップしていきます
——少し話は変わりますが、今回の”静岡おまちバル”では静岡県内の学生や20代の若い世代にも参加してほしいという想いがあります。何かと打ち上げやお酒を飲む機会が多くなる私たち世代と静岡おまちバルの相性が気になるのですが。
(太田先生)街バル自体「地元の商店街にこんな店がある」、「地元の食材や地酒が楽しめる」という紹介になるし、学生の参加を促すということでは魅力は十分にあると思います。ただ、例えば今回のイベントに参加するためのチケットの値段や、頼めるメニューの品数を考えると、若い世代にとっては参加する際の障壁になるかもしれません。価格に関しては、皆より上の世代の人たちにとってはたいしたことがない値段かもしれないし、それで美味しい物が食べられればOKという満足感は得られるかもしれません。しかし、20代前半の若い人たちにとってはどうかな?価格設定が参加のためのハードルになっていませんか?
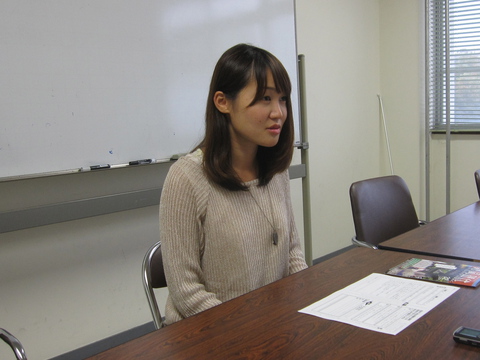
——正直「ちょっと高いかも」と感じる部分があります……。
(太田先生)学生や若い世代をターゲットにするためには、対「若い世代」のための手段を考えることも必要なのではないでしょうか。例えば、学生割など特別枠を設けて価格を下げたり、出されるメニューを増やしたりとかね。若者も静岡のお酒を飲んでみましょう、ということも前面に出してもいいかもしれません。飲食店や商店が、そして街を知ることへのイントロダクションのようにすれば、若い世代への掴みも変わってきます。ただ、若い世代の人たちにとっては、イベント自体に、訪れたことのない店やそこでの味を楽しめる魅力が十分に揃っているので、参加して新しい発見をするキッカケになると思います。あとは社会人の先輩や自分たちより上の世代の仲間といえる人に誘ってもらって連れて行ってもらうことも、参加しやすくなるひとつの手段ではないかな?
——なるほど。今後の”静岡おまちバル”を続けていく上では、各世代のニーズにそいながら企画・運営を考えていくのもひとつの手段ですね。では今後、静岡おまちバルによって、静岡のまちに何かしらの変化は起こるのでしょうか?
(太田先生)イベントの開催自体を主目的にするのではなく、これをキッカケにして静岡のまちの方向性を考えるということであれば変化の兆しは見られると思います。さしあたっては、こういうイベントを続けていくことが大事です。ただ注意したいのが、”イベントをやる”ということに重きを置いてしまうと、経済状況等に変化が起きたときにそれまでの活動の意味がなくなってしまうことです。変化というのは、例えばお店側には、「バルがあるときは盛り上がるけれどそれ以外の時は元に戻ってしまう、もしくはそれほど変化がない」という状況になる可能性があるということ。静岡のまちの活性化という、本来の意味や目的とは違ってきてしまうんですね。
ですので、店側にとっては常時新しいメニューの提供、良い物をよりよくしていくなどのイノベーションを促す機会であり、僕たち静岡県民は自然に街中に足を運ぶような状況を生み出していく。また、”静岡おまちバル”のイベントがスタートしてそれほど長い時間が経っているわけではないので、毎年開催する度に、何かしらの効果があることをお互いに認識することも大事ですね。
あとは、行政に頼らないことも重要です。先ほど触れましたが、例えば埼玉県のように9千万くらいの補助金を出している事例もありますが、僕はそれだとあまり意味がないと思っています。どうしても、補助金が出ればやる・出なけれなやらない、という状況が生まれる可能性が排除できないからです。だから、まず自分たちでできることをやっていく。それは背伸びしてできること以上のことを無理をしてでもやるということや、市民の政治参加につなげていくという別次元といえることを目指すという意味ではなく、イベントの開催側や参加する客側も楽しみながら、まちの良さやそこが抱えている課題を感じながら次の行動につなげていくのがいいと思います。

青葉通りのおでん横町や両替町など、飲み屋の多い静岡のおまち。去年の静岡おまちバルでは多くの人が飲み歩き、はしご酒を楽しみました。
自分の足で静岡のおまちを巡り、美味しいお酒や食べ物に出会える日。
——それでは最後に、太田先生の専門分野からみた、”静岡おまちバルの魅力”を教えてください。
(太田先生)そうですね。僕が面白いと思ったのは食べ歩きや飲み歩きなど、いわゆる「はしご酒」で人を動かし、回遊させる機会を作っている、かつ、参加店全部を回れるわけではなく自分でいくつか選択させるというのはとても興味深かったです。
——はい。静岡おまちバルでは、広場に屋台を出店するような他のグルメイベント等とは 違い、自分で足を運んでもらうという一番の目的があるんです。
(太田先生)それは、人を招いて動かすこと自体が難しくなっているという現状を考えたときに、その制度設計は良い意味でお店間の競争を促していることになるんです。例えば、七間町や鷹匠は続々と新しい店ができているっていう部分で競争があります。常に刺激的なものを中心街・商店街に提示しているんですね。
公共経済学では「足による投票」という議論があります。これは居住する地域について多くの選択肢がある中で地域政策の実施状況等から行先を1つ選択し、人々がそこに行くことがその地域の評価を示すという議論ですが、“静岡おまちバル“には参加者のお店の選択が参加店の評価につながるというところが面白い取り組み方だと思いました。お店側も客のニーズを意識して店自慢の逸品を出すということは、トータルでいえばそれだけ静岡に美味しい物があるというのを示すということに繋がりますよね。また、イベントの中で人とのコミュニケーションや付き合いが広がることも良いことです。
あとは、静岡おまちバル参加者は地元の人が多いですよね。インタビューのはじめに、地元愛の強い人が多く集まる場所はイベントの取り組み方によって成果があるという話をしたけれど、そういう意味では、”静岡おまちバル”は成功しているのではないでしょうか。地元の資源も一生懸命使っていますしね。まずは地に足をついた、本来のあるべきバルを追求しているのが、静岡おまちバルの魅力だと思います

●太田隆之先生
静岡大学人文社会科学部経済学科准教授。専門分野は地域政策で、地域における環境資源の自治的管理とそれを前提とした持続可能な社会実現のための地域政策を研究。お酒はかなり弱いが、飲むことは嫌いではないとのこと。年齢を重ねるごとに甘いお酒がダメになってきたのだとか。最近はもっぱらビールや焼酎をたしなむ。
●高村理沙さん
静岡大学人文社会科学部経済学科3年。太田ゼミに所属。専攻は地域活性化。ゼミのテーマに商店街を扱っています。静岡おまちバルでは、実行員会のイベントステージ企画に携わっており、他の参加学生のまとめ役的存在。皆でわいわい集まって飲むお酒が好き、とのこと。
もう一度歩きたくなる、「エッシャーの世界」〜静岡市美術館〜
働く私の静岡時代〜株式会社 サンロフト〜
JR三島駅〜日本大学三島キャンパス〜極私的、古地図研究会
働く私の静岡時代〜株式会社江﨑新聞店〜
働く私の静岡時代〜まちと人をつなぐ情報流通企業 株式会社しずおかオンライン〜
働く私の静岡時代〜まちと人をつなぐ情報流通企業 株式会社しずおかオンライン〜
働く私の静岡時代〜株式会社 サンロフト〜
JR三島駅〜日本大学三島キャンパス〜極私的、古地図研究会
働く私の静岡時代〜株式会社江﨑新聞店〜
働く私の静岡時代〜まちと人をつなぐ情報流通企業 株式会社しずおかオンライン〜
働く私の静岡時代〜まちと人をつなぐ情報流通企業 株式会社しずおかオンライン〜
Updated:2013年10月30日 静岡の街から


















